


ルーベンスはイタリアで、ルネッサンス後期やマニエリスムの芸術などを学び、かのマントヴァ公の、宮廷画家ともなりました。マントヴァは、この「神話と植物の物語」シリーズの〈北イタリア紀行―Vol.4〉で訪れましたが、芸術が擁護されて、絢爛たる文化の花咲いた、誇り高き都市です。
その、ドラマティックな構図、やや誇張気味とも思われる壮大な表現。
彼の評判は高く、膨大な数の作品を描きました。バロック時代を代表する画家のひとりとして名声を得ます。
さらに外交官としても活躍していたというのですから、なんというエネルギッシュな生涯でしょうか。
いっぽうこの時代のアントワープは、圧政に苦しめられました。さらに、ペストの流行もありました。
ルーベンスも、友人や愛する妻をペストで失います。その悲しみから、外交官の仕事に忙しく出かけた、といわれます。それでも、62歳で没するまでの仕事を見ると、やはり常人とは思えないですね。



ルーベンスの家や聖母大聖堂からほど近い場所には、すばらしい教会芸術に飾られた、美術館ともいえるような教会が並びます。じっさい、かつて教会は、美術館だったともいえますね。
そのなかには、彼がファサード(建築の正面デザイン)の装飾を手掛けた教会や、彼のお墓のある教会もあります。





散策しながら、ユニークなデザインで話題の博物館、MAS(Museum Aan de Stroom)へ向かいましょう。
この建物はかつての港の一角にあり、ここも古い建物や新しい建物が、混在する地区です。港沿いの作業場の装飾でさえ、優美な曲線がかわいらしい。
心を向けて手をかけた細部には、仕事をすることの喜びや誇りも宿ります。




アントワープの街の名前が、〈手〉にまつわることをVol.9で記しましたが、MASの建物の壁には、銀色の〈手〉のオブジェが、なんと、およそ3000個埋め込まれているそう。
Mでは、ブリュッセルのオメガング(Ommegang、中世からの、伝統的な祭礼の行列)を描いた17世紀の絵画や、デッサンなども見られます。
そういえばオメガングの起源は、Vol.3でご紹介したように、1348年にヴィジョンを見た少女が、聖母子像をもってブリュッセルに到着したことでした。
それは、このアントワープから出発した旅でした。
博物館は民俗学的な資料展示が多いので、まさに古代から現代までを旅することのできる場所です。
土地に根ざした民族独自の感受性と、あまねくさまざまな民族に共有される感覚の、両方どちらにも物語があります。それぞれに普遍的で、力強い。
ここからあらたに、広い世界へ、旅の夢も広がっていきますね。
ちょうど、〈生と死〉をテーマにした展示を見られましたが、それは人類を地球規模でみつめる大きな視点。
それにしても、民俗芸術の呪術の力は強烈で、目を奪われます。
そして、ときにユーモラス。これも生きるうえで、とても大切なことですね。



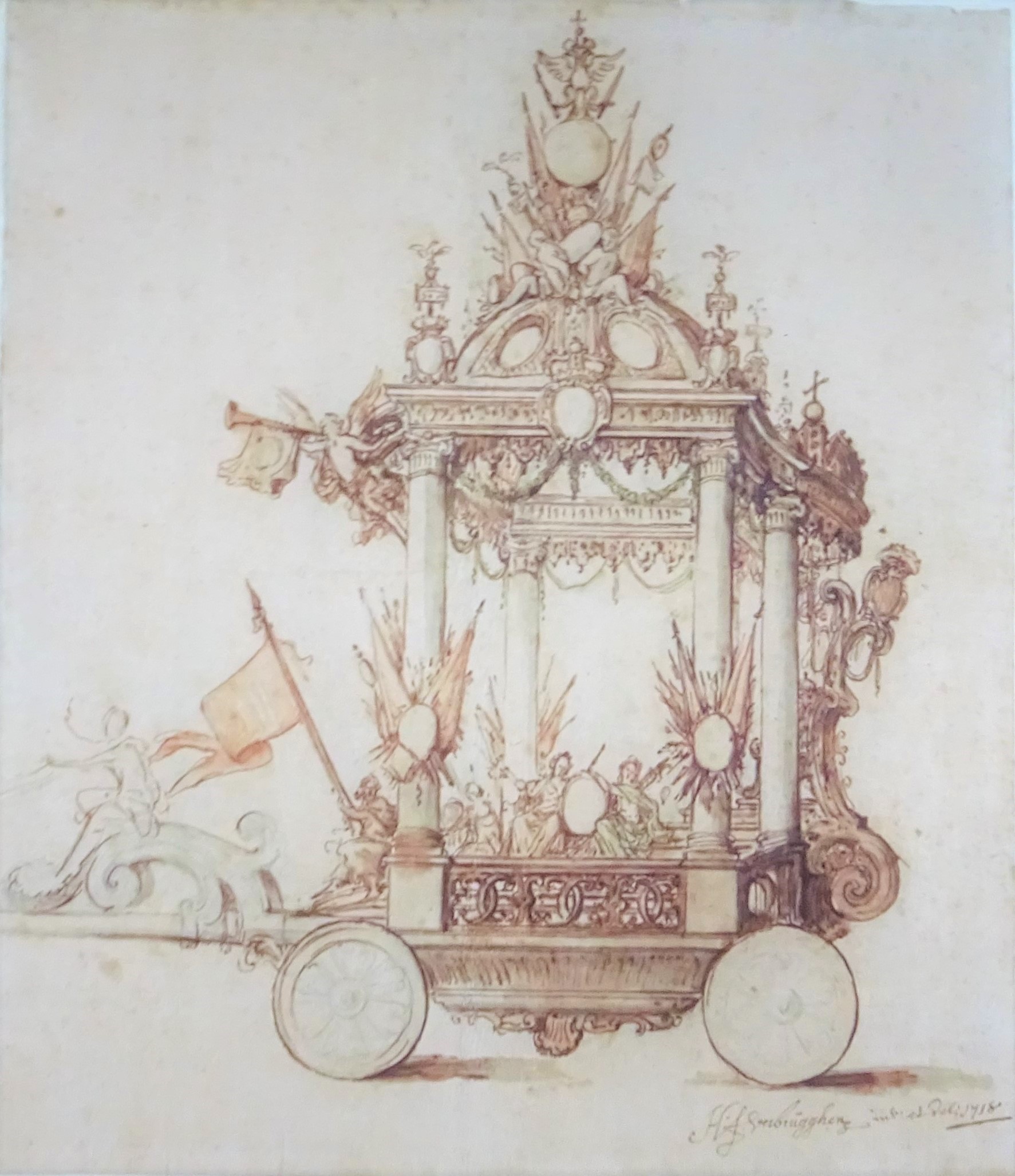




そう、〈生と死〉。
北欧神話では、神々はついに、運命〈ラグナロク〉(Ragnarøk)を迎えます。
神々の世界に、巨人たちが押し寄せる。
彼らが虹の橋ビフレストを越えるとき、橋は震えて、ついに轟音とともに砕けてしまった。
虹の橋の見張り番ヘイムダルは、一行が迫ってくるのを見ると、角笛ギャラルホルンを高く吹き鳴らす。
角笛の音に、すべての神々は集った。
神々は武器を身につけた。
そして、ヴァルハラのすべての死んだ勇者たちとともに、神々の王オーディン(Óðinn)を先頭にして、ヴィーグリーズの野に出陣した。
グングニルの槍をとって、オーディンは巨大な怪物狼に立ち向かう。が、狼は、神を吞み込んでしまった。
つぎの瞬間、オーディンと巨人の間に生まれたヴィーザル(Víðarr)は、母から与えられた強い靴で、狼の顎に足をかけ、その口を引き裂いて狼を倒す。
戦いの神、雷の神トール(Þórr)はその間ずっと、大地をぐるりと取り巻く巨大なミッドガルド蛇と戦っていた。トールは相手に致命傷を与えたが、この怪物の吐きかけた毒のために、その勝利のあとで倒れてしまった。
別の場所では、もはや神々の敵となったロキ(Loki)と、虹の橋の番人ヘイムダル(Heimdall)
が、互いに相手に致命傷を与えあっていた。
炎の巨人スルト(Surtr)は、神々と巨人や怪物の戦いの果てに、炬火(こか)を大地に投げ放つ。
いまや全世界は、火炎に包まれて燃えあがった。
「太陽は暗く、大地は海に沈み、きらめく星は天から落ちる。
煙と火は猛威をふるい、火炎は天をなめる」
(「巫女の予言」、谷口幸男訳『エッダ―古代北欧歌謡集』、新潮社)
ときがたった。
炎は消え落ちた。
そして、すべてが静まりかえったとき、青々とした大地が、海中からふたたび浮きあがってきた。
太陽は狼に呑み込まれたが、新たに生まれた太陽の娘が、母親の軌道を回りはじめる。
野には、さまざまな花が咲きみだれ、さまざまな果実もなった。
山からは滝が流れ落ち、鷲は空のうえ高く飛んで、輪を描く。
この激しい騒乱のあとに、生き残った神々もいた。
オーディンとトールの息子たちが、無傷で現れた。
ヤドリギで射られて死んだバルドル(Baldr)も、定めのとおり、死の国から戻ってきた。
しばらくすると、森の奥に隠れていた、リーヴ(Lif)とリーヴスラシル(Lífþrasir)が姿を現す。
やがて、この2人から新しい種族がふえて、地上を満たしていく…。
「種 撒かぬまま
畑は 実を 結ばん。
不幸という不幸は ことごとく 改まらん。
(中略)
そして 二人の兄弟の
息子らは 住む、
広大なる 風の世界に。
(中略)
そこには 罪なき
人々が 住み、
とこしえに
幸いを 享受せん。」
(尾崎和彦著『北欧神話 宇宙論の基礎構造』、白凰社)





「わたしたちはどこへ行くのか」、画家ゴーギャンはそう問いかけた。
楽園へ、向かいたいですね

乾 ゆうこ
ライター
ホリスティックハーバルセラピスト。大学時代に花椿編集室に在籍し、「ザ・ギンザ・アートスペース」(当時の名称)キュレーターを経て、ライター・エディターとして活動。故・三宅菊子氏のもと『フィガロ・ジャポン』『家庭画報』などでアート・映画・カルチャーを中心に担当。出産を機に伝統療法や自然療法を学び、植物の力に圧倒される。「北イタリア植物紀行(全4回)」「アイルランドから〜ケルト植物紀行」(ともに『クレアボー』フレグランス・ジャーナル社)など執筆。生活の木(表参道校)ではクラスを開催。
https://www.instagram.com/nadia_laakea/
















