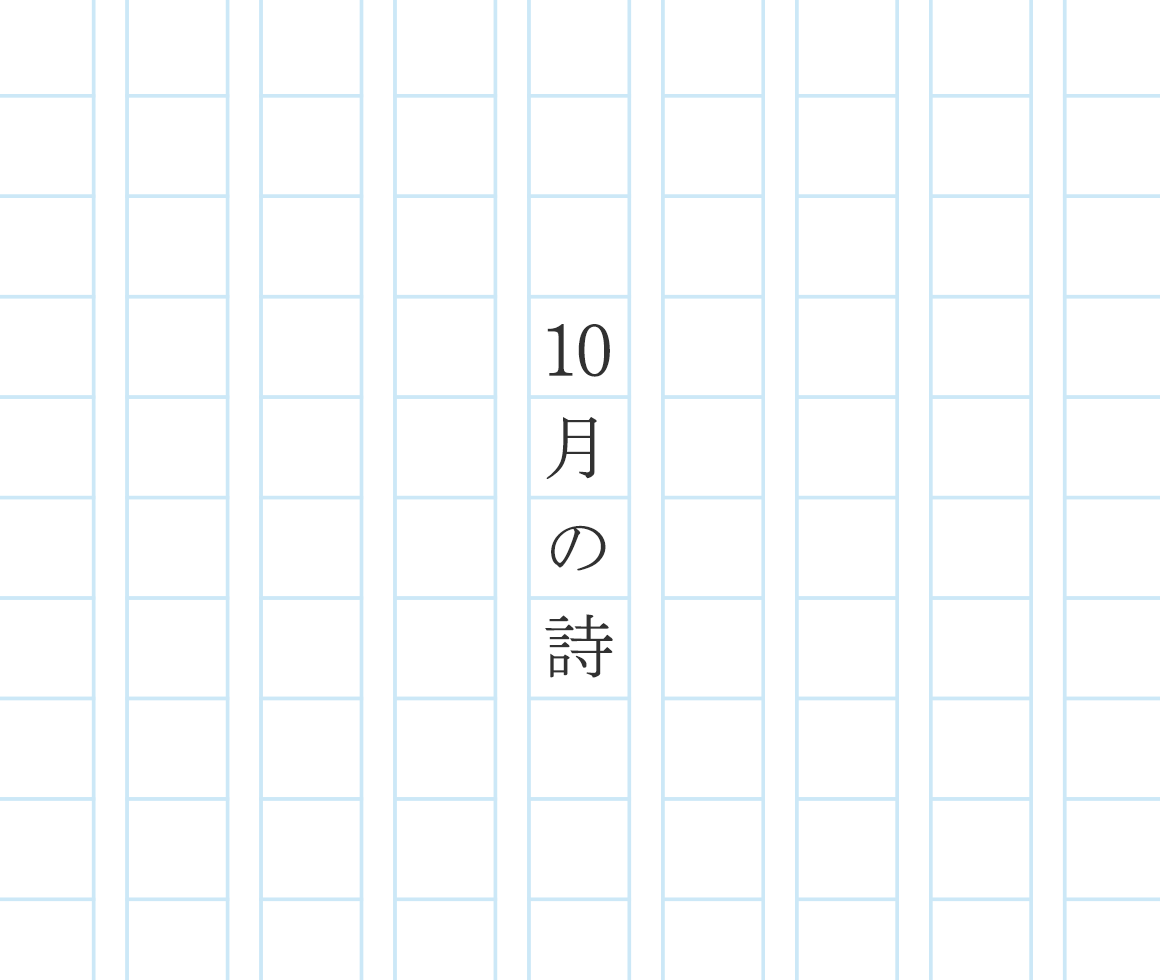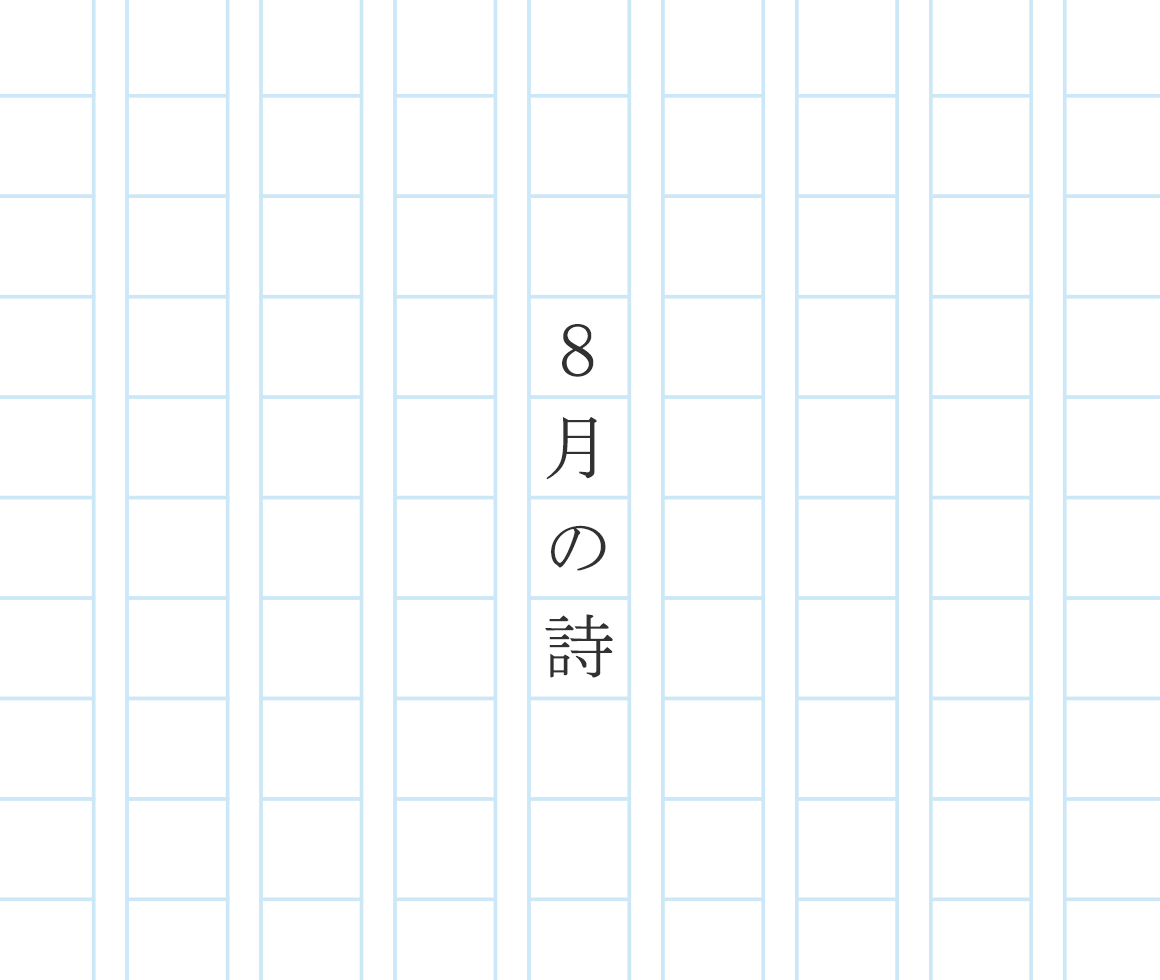子犬のことは七度まで。神田川沿いの公園のことは四度まで。かき氷は三度、あさ顔のことは二度までなら書いていいと、あなたが言った記憶をたよりに、生まれたてのチョコを抱く。チョコはちいさくて・やわらかくて・得体のしれない、なまの夏のにおい。すこしもこぼさないように、手のひらでつつむと時間はゆりかごのようにゆれた。おそらく、チョコもすこしだけゆれた。ゆれているあいだに地球は終わってしまって、わたしとチョコはゆいいつ、あのうす桃色の家にとり残されていた。チョコは気づいていないようで、音もたてず両手のなかにいた。そのときにきこえた、夕焼け小焼けのかすかなずれについては、一度だけなら書いていいだろうか。
選評/穂村 弘
回数の不思議
「子犬のことは七度まで。」という謎めいた冒頭から惹きつけられる。「チョコ」とは「仔犬」の名前なのだろう。「神田川沿いの公園のことは四度まで。かき氷は三度、あさ顔のことは二度までなら」と、その夏のさまざまな出来事について、「書いていい」とされる回数が決まっているのはどうしてか。それを伝えた「あなた」はどうなったのだろう。その人はもう「わたし」の「記憶」の中にしかいないのかもしれない。おそらくはそのせいで、この詩の「あなた」はなんとなく神様めいたオーラを放っている。
遠い昔、神様は人間に向かって云ったのだろう。「命は一度まで」と。その日から私たちは与えられたただ一度きりの命を生きることになった。「あなた」に与えられたさまざまな回数たちは、今も「記憶」の中にあって「わたし」の心を縛っている。でも、その時、教えられなかったことはどうなのか。その後の出来事については、「あなた」に訊くことはできない。「わたし」自身で決めなくてはならない。「わたし」も「生まれたてのチョコ」も命の回数は一度。二人で一緒に聞いた「夕焼け小焼けのかすかなずれ」も「一度だけ」だ。