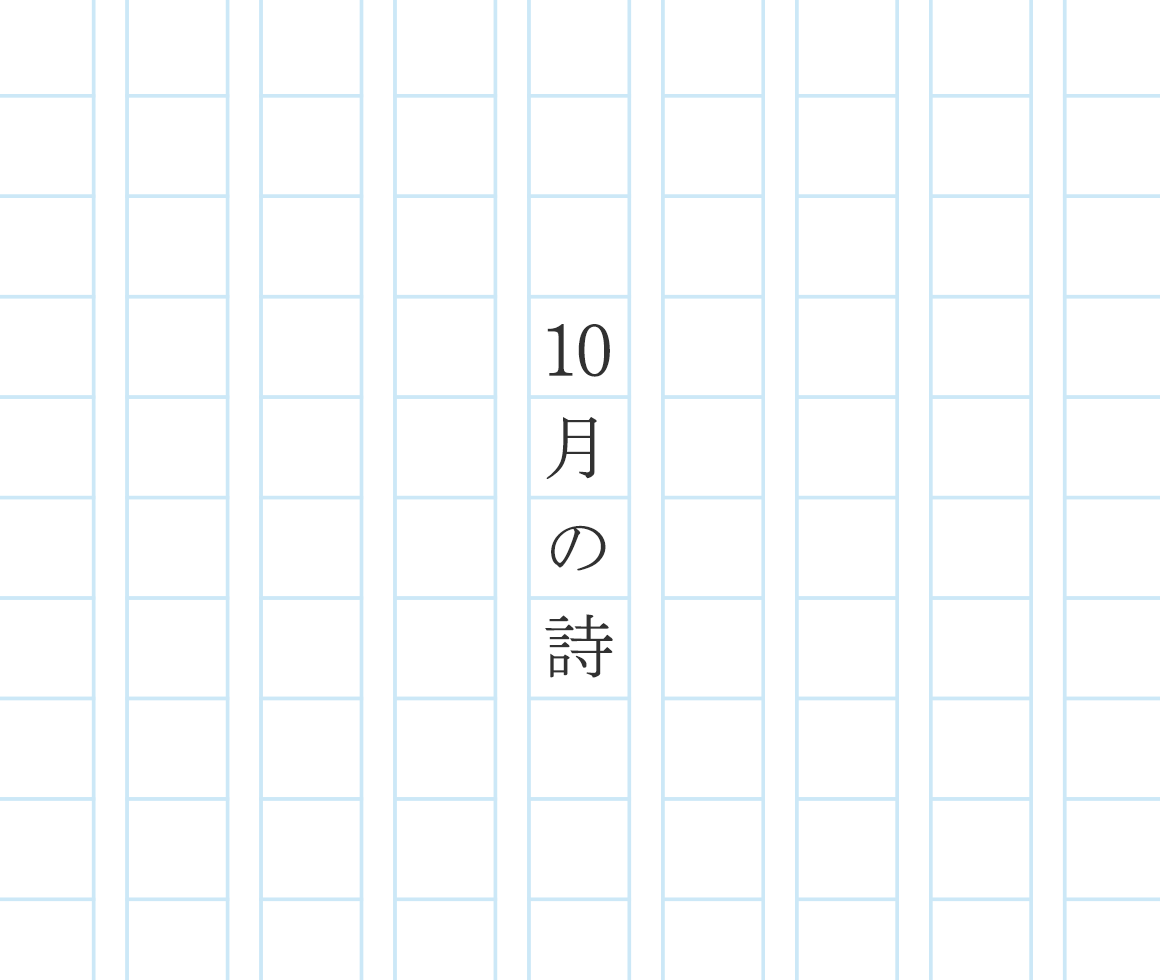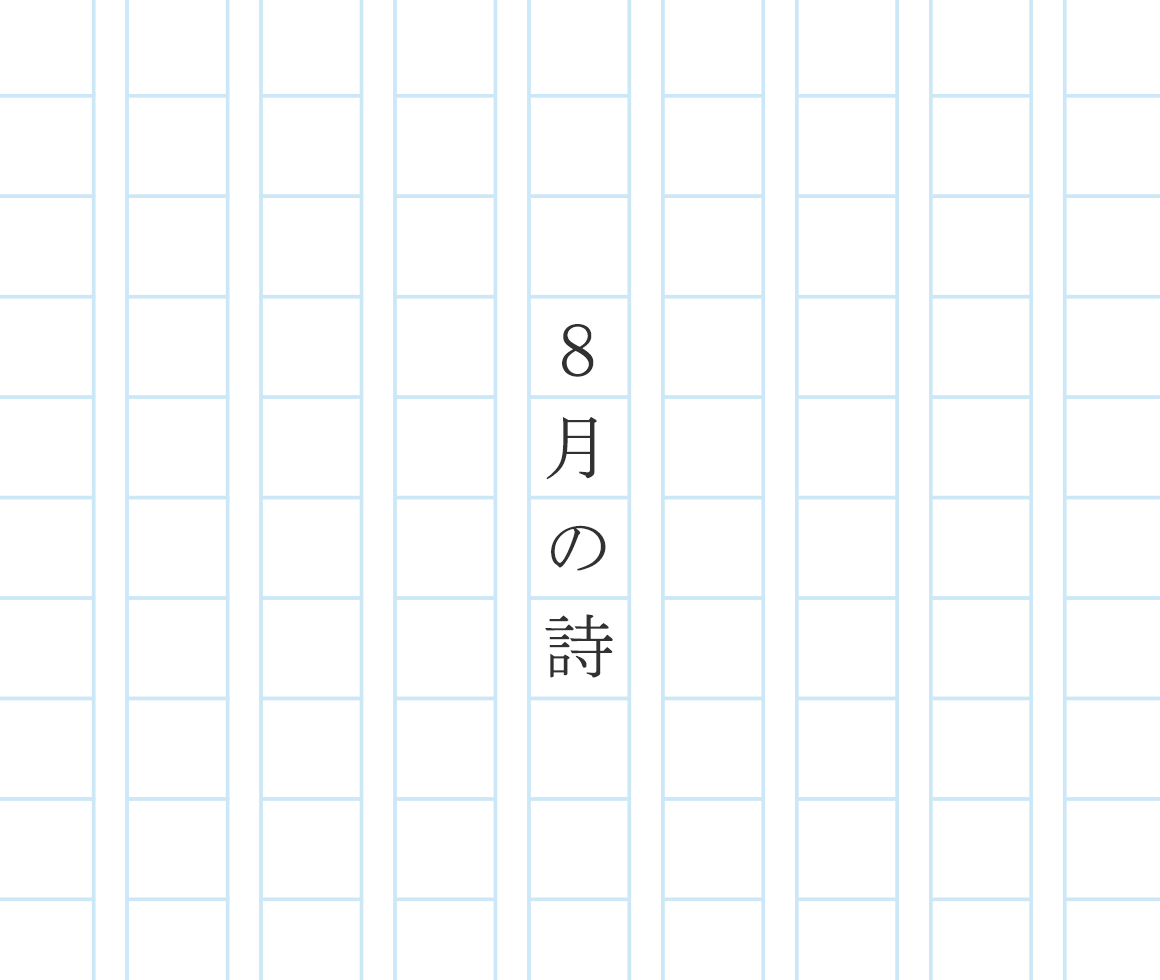騒々しい箱庭。
交わるほどに、まとわりつく皮膚。
隣のベランダにはびこるナスタチウムが
非常板をくぐって
わたしの日盛りを覆いつくそうとする。
上室に住む人の吸い殻が醜くねじ折れて
ベランダの手摺にのっている。
フィルターについた黒いタールの円が
一日の染みとなって脳内にこびりつく。
管理人の電話番号を探すうちにどうでもよくなる。
どうでもいいことばかりじゃないか。
その時チャイムが大きく鳴り
(こんな音量設定にしたかといぶかりながら出ると)
インターフォンの四角いディスプレイに
中型のケリーブルー・テリアが映っていた。
まなこが長い毛で覆われている。
ランタナだった。
欲しくて買ってもらったのに
高校生になり自分のことにかまけて
散歩も洗毛もしなくなって
毛玉だらけになったランタナだった。
共働きの両親は犬の面倒をみず
結局知人に引き取られた。
年齢を考えれば生きているはずのないランタナ。
ランタナを駅前の雑踏で知人に引き渡した。
大きめの空き段ボールに入れて。
ランタナの眼を見ることなく知人の後姿を見送った。
そのランタナが
十年も前に実家を出たわたしのマンションに来ている。
おそるおそる扉をひらくと
ランタナは快活に飛び込んできた。
饐えた汗の匂いが小さな風になって脇腹をすり抜けた。
その日から。
ランタナは甲斐甲斐しくわたしの世話を焼く。
仕事から帰ると風呂が沸いていて
簡単な食事が用意されている。
寝具は清潔に整えられ
部屋もこざっぱりと片付いている。
うたた寝するわたしにランタナは毛布をかけてくれる。
いつもランタナの眼は毛で覆われ
表情がわからない。
わたしを、恨んでいるのだろうに。
日に日にランタナの想いを知りたくなり
ランタナの眼をみたいと思うが
ランタナの眼は常に毛玉だらけの体毛に覆われている。
ランタナが横になったとき
そっと瞼に被さった毛をよけようとしたが
ランタナは急に起き上がって激しく頭を振った。
眼を。見せてはくれない。
あの日。わたしが見なかった眼。
ランタナはわたしを見ていたのか。
ランタナが突然姿を消した。
見なかった眼だけがここに残った。
夏の日盛り。
隣のナスタチウムがベランダを侵食する。
開け放した窓に上室から副流煙が流れ込む。
肺いっぱいに煙を吸って
ナスタチウムを摘み取った。
思いついたようにわたしは
自分の目に触れた。
失くなっているような気がしたのだ。
選評/穂村 弘
命の塊
「わたし」の現状はいいものではないらしい。日常生活のユーザーとして、不満を抱いているのだろう。だから、窓口である「管理人」に電話でクレームをつけようとする。でも、それさえも途中で「どうでもよくなる」ほど、うんざりしている。
そんな「わたし」の元へ、幻の犬がやってくる。「年齢を考えれば生きているはずのないランタナ」だ。その昔、「わたし」に見捨てられた恨みを晴らしに来たわけではない。むしろ逆。「ランタナ」は仇を恩で返すかのように「わたし」に親切にしてくれる。「うたた寝するわたしにランタナは毛布をかけてくれる」なんて、想像すると素敵な光景だ。でも、どうしてそんなに優しいのか。不思議だ。「わたし」の論理では「ランタナの想い」は計れない。その「眼」が見えない。
そんな「ランタナ」が、突然姿を消した後、「わたし」の中で何かが変わる。自分は日常生活のユーザーではない。「わたし」はなんのユーザーでもない。ただ、生きることの当事者であり、めちゃくちゃな命の塊だ。