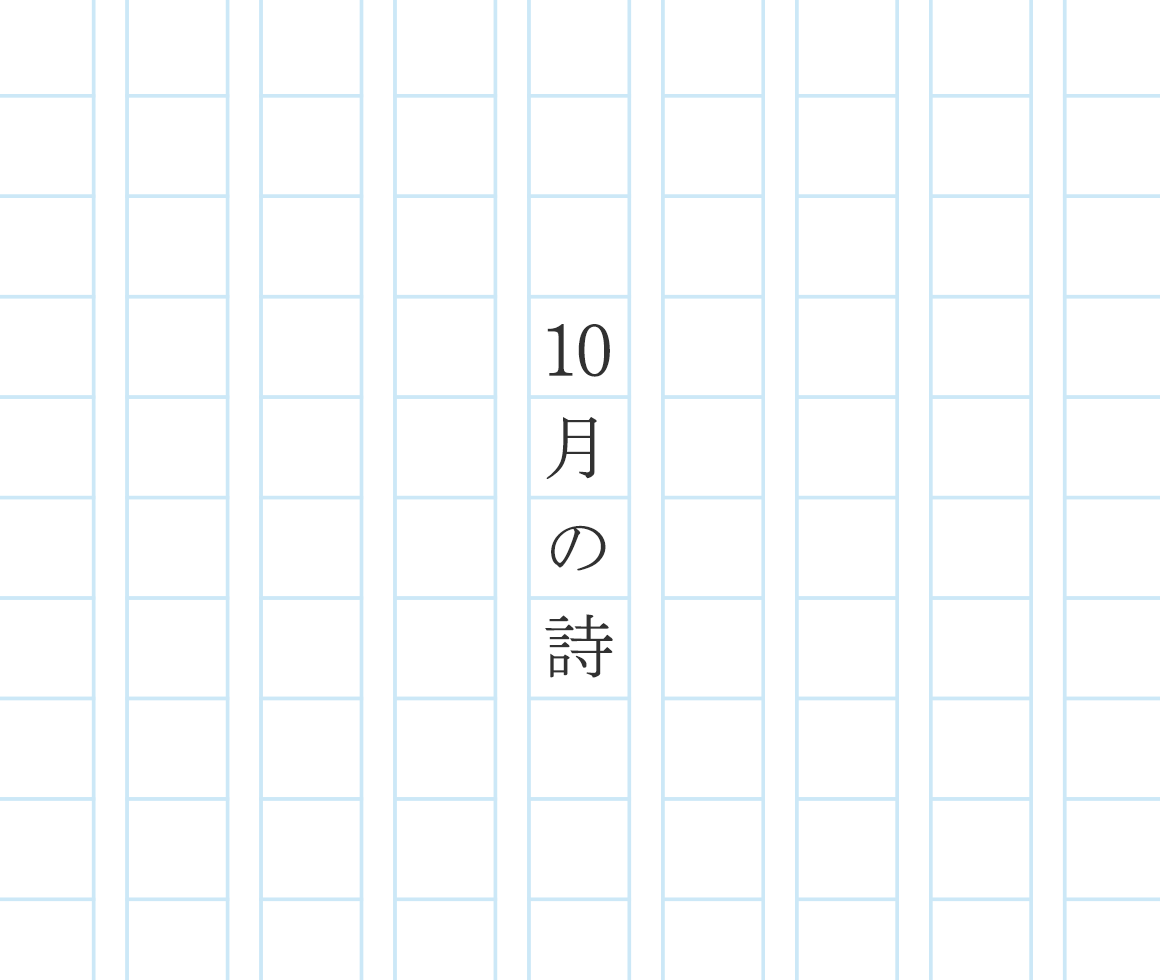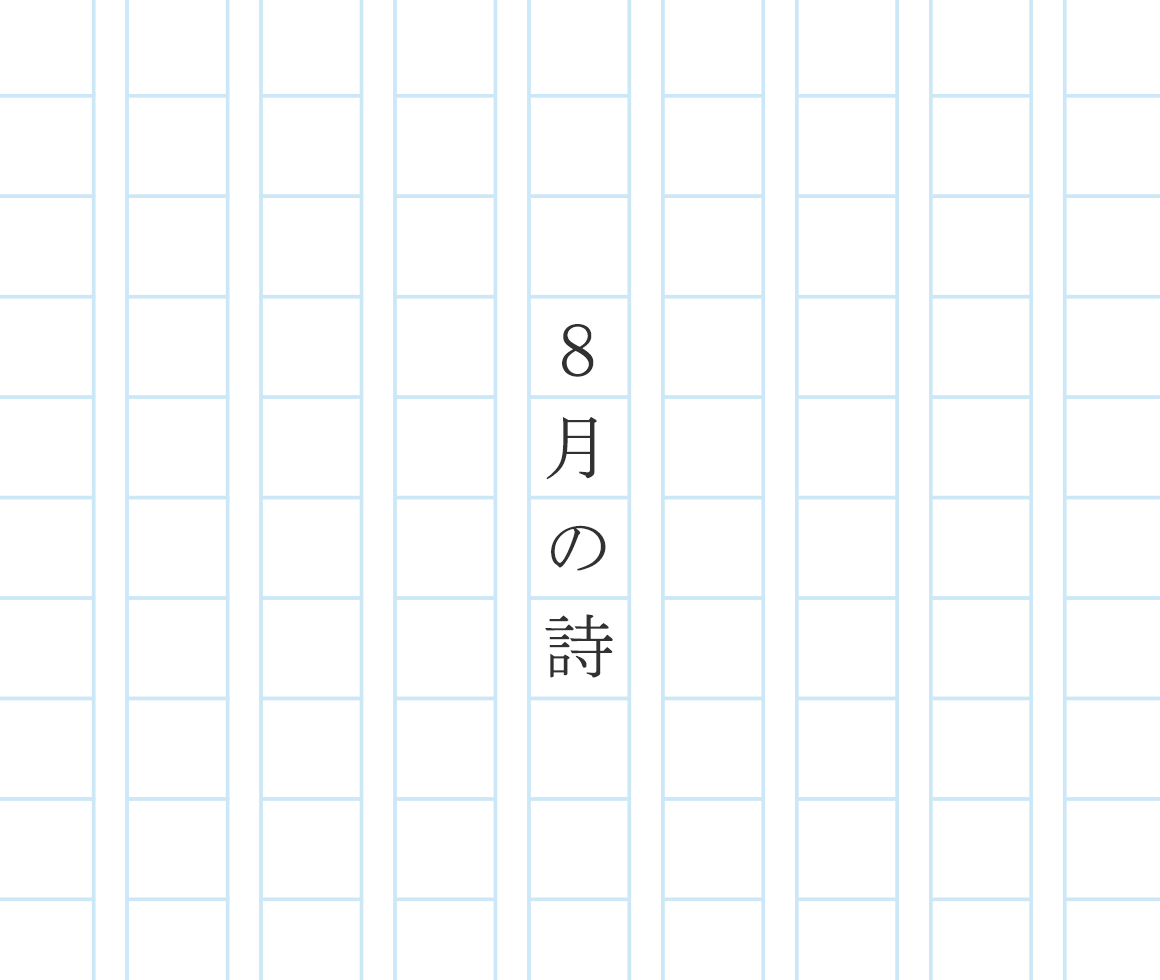顔くらい大きなプラタナスの葉が色褪せて地面に落ちると、熱されたアスファルトがこんがりと焼き上げてゆく。
くるりと茶色く巻き上がっているのを選んで靴裏で踏むと、ポテトチップスよりも香ばしい音がはぜた。
拭いきれない夏と予感される秋で満杯だ。
派手な予告に魅せられているうちに始まっていた映画みたいに見逃してしまうよ、始まりの始まり。
気の抜けたサイダーと山盛りのポップコーン。
ポップコーンひと粒
つまんで口に入れるとカップの中に
ひと粒分のとうめい
噛み砕いて飲み下して、嵩を減らさないと。
踏みしめるごとにわずかずつ空は高くなる。もっとずっと、高くできる。
十分に高くなったらそのとき流れ込んでくる、
秋だ。
選評/大崎清夏
愉快&軽快な直喩が次々に飛びだして、楽しみながら書いていることが伝わってきた。ポテトチップスもポップコーンも手軽につまめるお菓子で、ここではそのパリッとした空気のような軽さが、空気が軽く乾くことで秋を肌に感じることの、アナロジーになっている。締めくくり、ぽんと弾けるような「秋だ。」への一行空きも、効いている。
ただ、映画の比喩がポップコーンという言葉を引き出すための手段としてしか機能しておらず、比喩の取捨選択が整理しきれていないのが惜しい。映画館の暗さと、この詩が描こうとしている秋の(もちろん屋外の)明るさや空気の軽さや乾きとは、対比というには甘く、あまりうまく噛みあっていないように思う。
けれども、ポップコーンのあった場所に、ひと粒食べるごとに空間が生まれていくという発想には、美しさがある。「嵩」が減るほど空が高くなるというイメージもいい。どこまでも空気の軽みを追求して、あともうひといき推敲できたら、ものすごくさっぱりと清潔に乾いた秋が、やってきそうな気がする。