私が林央子さんの本を初めて手にしたのはおそらく2012年。東日本大震災がきっかけでドイツの高校に編入してからというもの、毎日胃薬を手放せず自分の殻の中に縮こまっていたあの頃。ティーンエイジャーの私に、後にたぐり寄せることとなる編集という技術を、最初に鮮やかに提示してくれたのが『拡張するファッション』(林央子著)だった。
あれからおおよそ10年の間に私は日本の美大に入学し、入学直後から卒業まで自分で創刊したインディペンデントマガジン『HIGH(er)magazine』の制作に勤しんだ。そして今、その延長線上で立ち上げたHUGという会社で編集やプロデュースなどの仕事をしている。
コロナウィルスによって世界が激変し、仕事をする上での人とのコミュニケーションや、長らく着手できていない個人の制作についてぼんやりと悩んでいるとき、林さんが10年ぶりに新しい本を出されるという情報をTwitterで目にした。私にとって一大ニュースだった。まるで推しのカムバみたいだと胸を躍らせながら、本のタイトルを見て、「やられたァ!」と思った。まさに、今の私に必要な本だと確信したのだ。

『つくる理由』
このシンプルなことばの奥に、林さんとアーティストたちとの間に流れる時間、そして個々が過ごした孤独な時間が、みずみずしく生きている。
この本では、林さんが10年の歳月をかけて見つめ、そしてその活動を伝えようとした「つくる行為」をするアーティストやファッションデザイナーたちの物語が丁寧に束ねられている。この本に出てくるどのつくり手も、「生活」をしながらものづくりをしているのだ。
そんなのあたりまえのことだと思うかもしれないが、東京で広告の世界に片足を突っ込んでいる私からすると、ここでは多くの人がまるで「生活」と「仕事」をするのは別のふたつの人格であると思って過ごしているような気がする。代理店の人と打ち合わせをすれば「ずっと徹夜続きなんですよ」とまるで抜け殻のようだったり、多様性を謳った「革新的な」広告を打ち出すクリエイターが私生活では差別的な発言をしていたりする。どうしてこう、ちぐはぐなんだろう。人も、物も、情報も異様なスピードで入れ替わる消費活動のレールの上にいると、自分にとって本当に大切なことは何なのか、簡単に見えなくなってしまうみたいだ。そして、私も違和感を覚え ながらもその渦の中から完全には抜け出せずにいる。
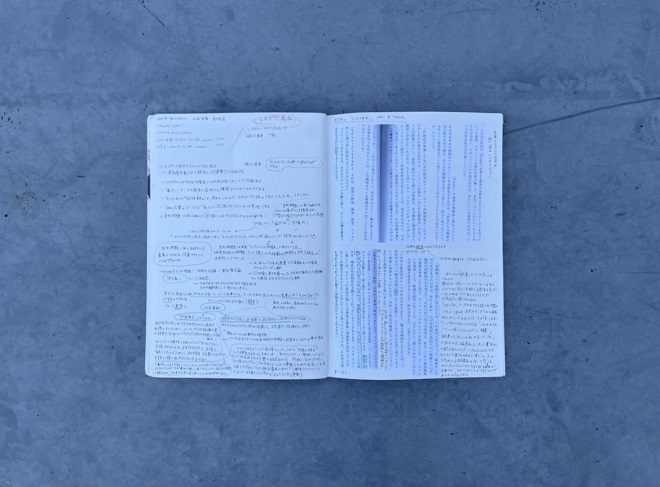
林さんの世界を見つめるまなざしは、穏やかでありながら、強い。震災や新型感染症の拡大、そのほかのさまざまな日々の不安ごとにゆらぎ、迷いながらも「見つめる」をやめず、つくり手の声に耳を傾け続けること。それは今の世の中で求められるスピードや数字、わかりやすいラベリングを跳ねのける、静かな反逆の姿勢だと私は捉えている。革命を起こすアクションが、必ずしも派手とは限らない。
先日、学生時代から私のヘアカットをしてくれている美容師のKさんに取材をする機会があった。そこで彼が言っていたことがとても印象的だったので、ぜひここに残しておきたいと思う。
まだKさんがサロンでアシスタントをしていた頃、「ヘアメイクを学ぶために海外に行きたい」と店長に相談するものの、「まずは美容師として力をつけたほうがいい」と反対されてしまう。それから何年もの間、仕事にもお客さんにも真摯に向き合ってきたKさんは、あるとき「変わらずそこにいることの価値」に気がついたそうだ。目まぐるしく変化する東京の街で、変わらずそこにいて、お客さんを迎え入れること。それは自分にとって、人生に大きな変化をもたらすことよりも価値のあることなのではないだろうか、と。何をした、何を成し遂げたかを自分で気軽に発信できるようになった今、やらなかったことや選ばなかった人生について考えることは滅多にないと思う。6年間も髪を切ってもらいながら初めて見えたKさんの姿に、私は小さな衝撃を受けた。
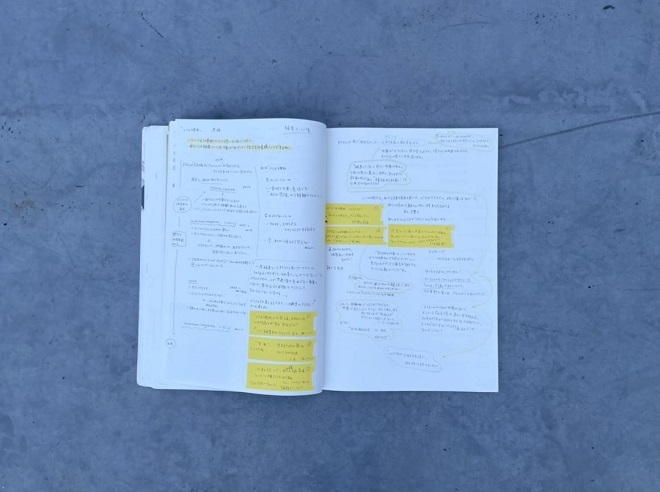
私は学生時代からなんとなく自分のことを「編集者」と名乗ってきたが、いつもそうすることに自信をもてないでいた。自分でマガジンを作っているとはいえ、どこかの編集部でノウハウを教わったこともない。編集者によって、仕事の定義もそれぞれだったりする。クライアントに怒られるのが編集者の仕事、と言ってる人を見かけたことがあるが、それは私からすると編集の仕事をしながら遭遇する一場面にすぎないと思う。
『つくる理由』の第3章、「形あるものをつくらない」では、アーティスト田村友一郎さんの編集的感覚について紹介し ている流れで、林さんご自身が編集という技術について言及されている箇所がある。
「一度編集という技術を身につけた人は、その後もずっと、編集をしながら生きることになる。何かと何か、人が共通項を見出さない事象をつなげ、意外な切断面をとりだして、それらをつないで見せる。私も二〇代で雑誌編集の技術を体得した人間で、ファッションデザイナーを取材しても、アーティストを取材しても、映画の試写に行っても、ふだんなら一緒にされることのない人や話題を出会わせることで、何かが言えた、と思うことがある。」(『つくる理由』より)
「編集者」と名乗ることに気が引ける私の自意識をふきとばしてくれたのがこのテキストだ。もう今後は肩書きを聞かれて「プ、プロデューサーです」とごにょごにょ答えることもなくなるだろう。
興奮のあまりインスタグラムに『つくる理由』の写真をアップしたところ、林さんご本人からDMをいただいた(こういう時は都合よく、SNSよありがとうと思う)。いくつかやりとりを交わすなかで、これまた一生胸に刻んでおきたいことばを林さんが贈ってくださった。
「いろいろな仕事からくる思いがあったときに、自分には編集という広場があったという気づきは素晴らしいですよね。」
今、またやっと自分のマガジンの制作を始めた。ほんの少しずつだけど、またあの感覚が戻ってきている。日本語で文章を書けることがとにかく嬉しかったあの頃とは、また違ったものがつくれる気がする。
私から見える、そして見えないあなたとの対話が私のものづくりの原点であり、これからもそうあり続けるだろう。
編集という広場へようこそ、そしておかえりなさい。

(Hey world, I’m haru and I’m an editor 😉)

haru.
編集者/モデル
『HIGH(er)magazine』編集長。1995年仙台市生まれ。東京藝術大学美術学部先端芸術表現科在学中。10代の6年間をドイツで過ごし、さまざまなカルチャーに慣れ親しむ。2015年『HIGH(er)magazine』を立ち上げる。ファッションやカルチャーだけでなく、政治やフェミニズムについてなど率直な記事が話題を呼び、ファッションブランドとのコラボレーションも行う。
https://www.instagram.com/hahaharu777/
http://hahaharu777.thebase.in
















