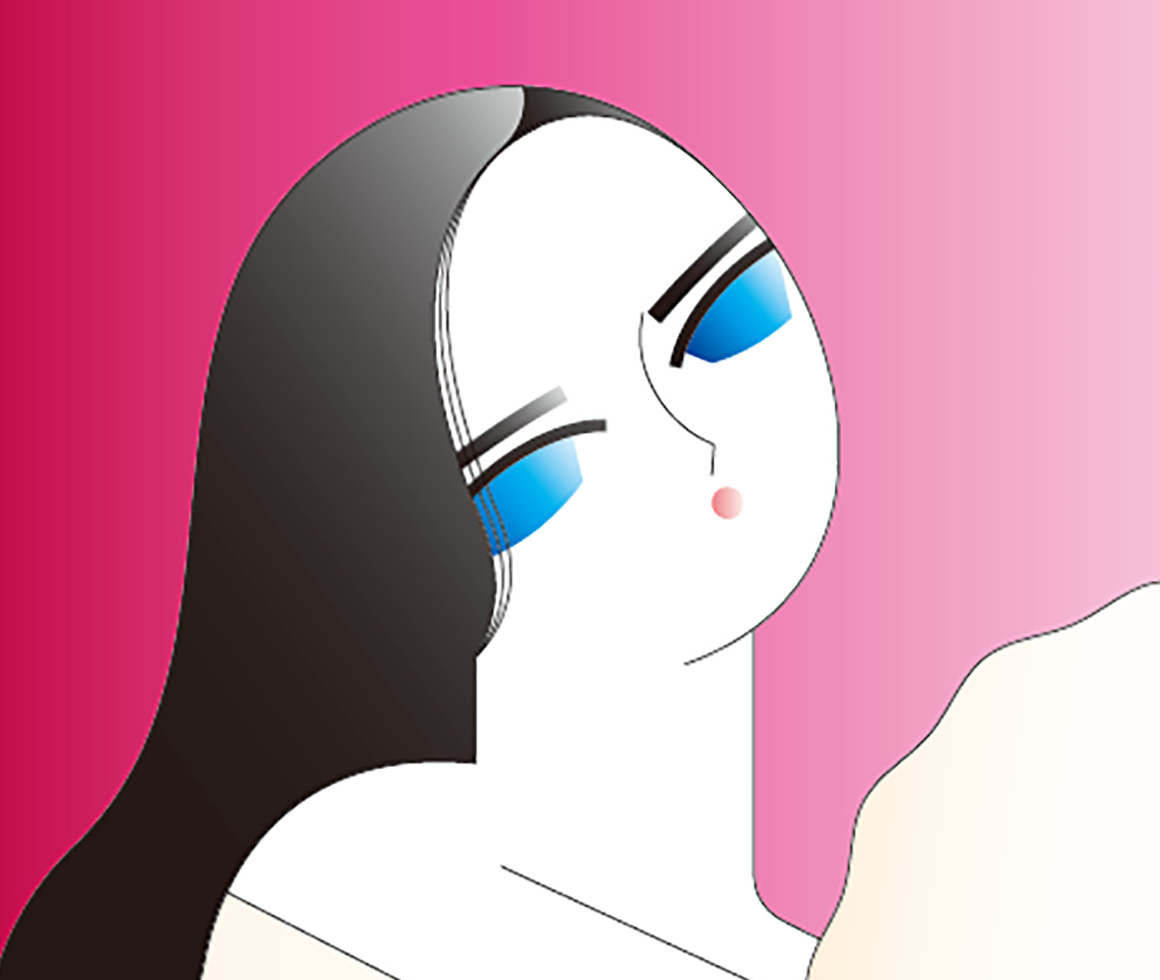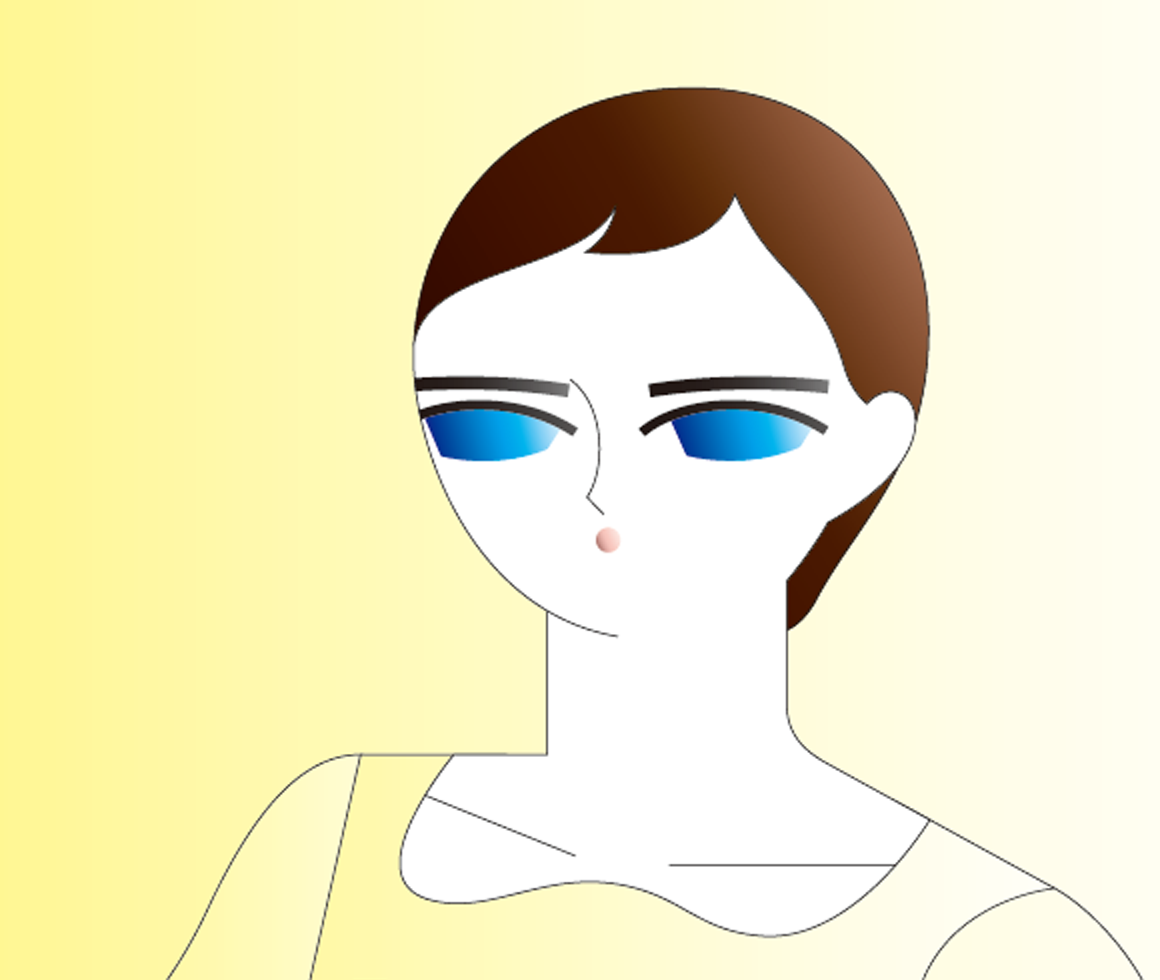映画史に名を残す名シリーズ『猿の惑星』も、21世紀版リメイクを立て続けた後、恐らくもうしばらくは新作が出ないだろうと思うのだけれど、よくある事で、遺伝子というか亡霊というか、想像だにしなかったタイミングと場所で、失ったものの面影に遭遇する。といった事はどなたも経験があるのではないだろうか?
曰くAV(エッチなほう)を見ていたら、女優さんが高校時代の同級生、しかも男子にそっくりだと気がついてしまい、慄然とした。曰く、今まで付き合った事のないタイプだ、とフレッシュに思っていた彼女(や彼氏)が、付き合ってみたら、過去に別れた彼女(や彼氏)と、何かがーーー例えば、政治についての考え方や、キスする時の身体のこわばり方や、パフェの食べ方、等々ーーー瓜二つで、慄然とした。
と、慄然とした例ばかりになってしまったけれども、それは今回、慄然とした経験報告だからなのだが、それよりも何よりも今回、断固として断っておきたいのだが、ワタシは女性の、特に顔の美醜について書いているのではない、という事だ。先に書いてしまうが、チンパンジーそっくりのエマ・ワトソンは、率直に言ってものすごく可愛い。彼女のフィルモグラフィーの中でも極点的な可愛さだと思う。
という訳でディズニー映画『美女と野獣』の話だ。先日、仕事の要請によって、シネコンに足を運んだ。
エマ・ワトソンは、言うまでもなく「ハリー・ポッター」のシリーズで魔法学校の女生徒として、実質上のヒロインを演じ続け、シリーズ終了後も最も順風満帆のキャリアを重ねている女優だけれども、コーカソイドというかアングロサクソンというか、白人一般の特徴として、顔にシワが多い。
ロリコン大国であるわが国では、蛇蝎のごとく忌み嫌われる顔シワだが、文化はなんだってそうだ。海外では悪点にはならない(逆に「高すぎる鼻」が醜いとされ、美容整形で削ったりする。という話は、どなたもご存知だろう)。とはいえ、彼女のそれは一種の大サーヴィスでもあって、ワタシはシネコンの椅子に座り、キャラメルポップコーンを頬張りながら「うおー。チンパンジーみてえ! かっわいー!」と興奮してしまった。
と、途中だが、過去「猿に似ている」「シワが多い」と虐められた経験がある読者にワタシは言いたい。トラウマの痛みはよく分かるが、だからこそあえて言いたい。動植物や魚類や爬虫類、とにかく、生物の何かに似ている事は、美しさの証拠だ。ワタシはよく深海魚とか犬とか言われるが、そんな事はともかく、「何にも似ていない、どう見ても人間にしか見えない顔」というのは、かなり忌まわしい筈だ。
さらに言えば、我々人類が、白菜やクジラやフクロウ、などと比べた時、それが猿である可能性は最も高い。何せ「類人猿」というぐらいなのだから。そして、シワは男女問わずセクシーであるに決まっている(海外では禿頭がセクシー。というのはどなたもご存知であろう)。
そして、わが国が前述の通りロリコンのガラパゴスだとしても、ディズニー映画のお姫様役となれば若々しくて美しくあらねばならない事は地球規模のミッションである。今回エマ・ワトソンがCGによるビューティーレタッチを使わなかった事は、彼女が極右的なナチュラリストである、とか、ディズニーが世界的に顔シワを愛でるように文化的な操作をしている、とかいった面倒な理由ではないだろう。単に、欧米では顔シワというものが、プリンセスにあってはならぬもの、ではない。という事の証明に過ぎない。
と、我ながら周到すぎるかなと思うほどのエクスキューズを済ませてから言うが、『美女と野獣』のエマ・ワトソンは、『猿の惑星』の特殊メイクにギリギリで隣接するほどにはチンパンジーに似ている。そして再び、超可愛いのである。
しかし、今回の論点はそこではない。エマのチンパンジー似はきっかけに過ぎない。
ジャン・コクトーを映画史上のオリジン(原作は18世紀に出版されている)とする『美女と野獣』のコンセプトはシンプルで「人の美醜は、表面ではなく、内面である。それを理解できる人間こそが愛を理解できる」というものだ。コクトー版(46年フランス公開。実質上の戦前よ。因みに第二次世界大戦ということですが)の野獣役である、世紀の美男子ジャン・マレーは、もう笑ってしまうほど、毛皮の仮面というか、着ぐるみみたいな状態で「醜い野獣」を演じ、ラストに魔法が解け、「もともとは美男子だった王子様」に戻る。
しかーし、最新のディズニー版では、野獣が全然、いや、「ぜんっぜん!」と書いたほうが適切なほど、醜くない。「何かひげの濃い白人だったら、このぐらいの人いるよね」程度の特殊メイクなのだ。
何せ、私の隣に座ったOLさん(恐らく)は、劇中ボロ泣きしていたのに、ラスト、魔法が解けて「美青年」に戻った王子様の姿を見て、隣席のご友人に「ねえ、戻らなかったほうがよくない?(くすくす)」とおっしゃったのだからして。
という訳で、ディズニー版の『美女と野獣』は、チンパンジーに似たプリンセスと、野獣というにはハンサムすぎるプリンスによって、「外見の美しさと内面の美しさは、そもそも意味が違う。そして、崇高なのは内面の美しさなのだ」というテーマが、液状化の形で無意味になっているのである。つまり、映画はテーマを打ち出すもの、とする限り、失敗作なのだ(全体的に見ると、ミュージカルクラシックのリヴァイヴァル運動として大傑作だけれども)。
だが、映画は日めくり格言カレンダーではない。もっと複雑で恐ろしいものなのである。既にコクトー版からして「美醜って、思っているより複雑でしょう? 醜いと思っているものが美しく思えたり、美しいと思っているものが禍々しかったりと、容易に反転してしまう。人間の感覚って、フェティッシュで、怖いわよね」というフランスの悪魔のささやきが込められているのだ。
最新版は、この悪魔のささやきを、逆転的に突破している。よく言えば「映画に映っているものは全部美しい=誰だって美しくなれるよ」といったポジティヴであり、悪く言えば、同じ効果が、人間理解に関して、非常に狭くて小さい解釈に押し込めようとしている。「スクリーンに映っているものはみんな美しい=スクリーンに映っていないものは、みんな美しくない」とばかりに(これは「液晶モニターに写っている写真はみんな美しい」というインスタグラム文化と直結している)。
人間理解が狭っくるしい世の中は、言うまでもなくファシズムを準備する世の中である。「『美女と野獣』のエマ・ワトソンはチンパンジーそっくり」「『美女と野獣』は『猿の惑星』とのマッシュアップ。つうか、『猿の惑星』には『美女と野獣』と同様のテーマが内包されている」と言い放つ勇気だけが、エッセイストという仕事を、お気軽なネット日記書きから、筆を握る責任をもつ文筆家に高めるのだ。全然そんなことないんだけどね。ふっふっふっふ。

菊地 成孔
音楽家/文筆家
1963年生まれの音楽家/文筆家/大学講師。音楽家としてはソングライティング/アレンジ/バンドリーダー/プロデュースをこなすサキソフォン奏者/シンガー/キーボーディスト/ラッパーであり、文筆家としてはエッセイストであり、音楽批評、映画批評、モード批評、格闘技批評を執筆。ラジオパースナリティやDJ、テレビ番組等々の出演も多数。2013年、個人事務所株式会社ビュロー菊地を設立。
http://www.kikuchinaruyoshi.net/
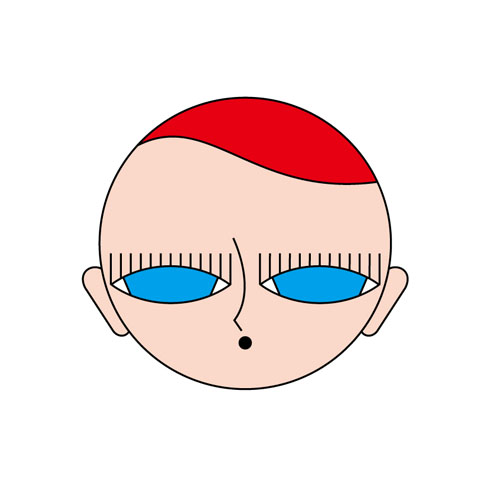
瓜生 太郎
イラストレーター
東京都在住。ファッションをテーマに女性を描くことを得意とし、シンボルマークのような図形的描写とシンプルな色使いが特徴。主な仕事に、銀座三越ウインドウディスプレイや表参道ヒルズシーズンヴィジュアルなどがある。
http://tarouryu.com/