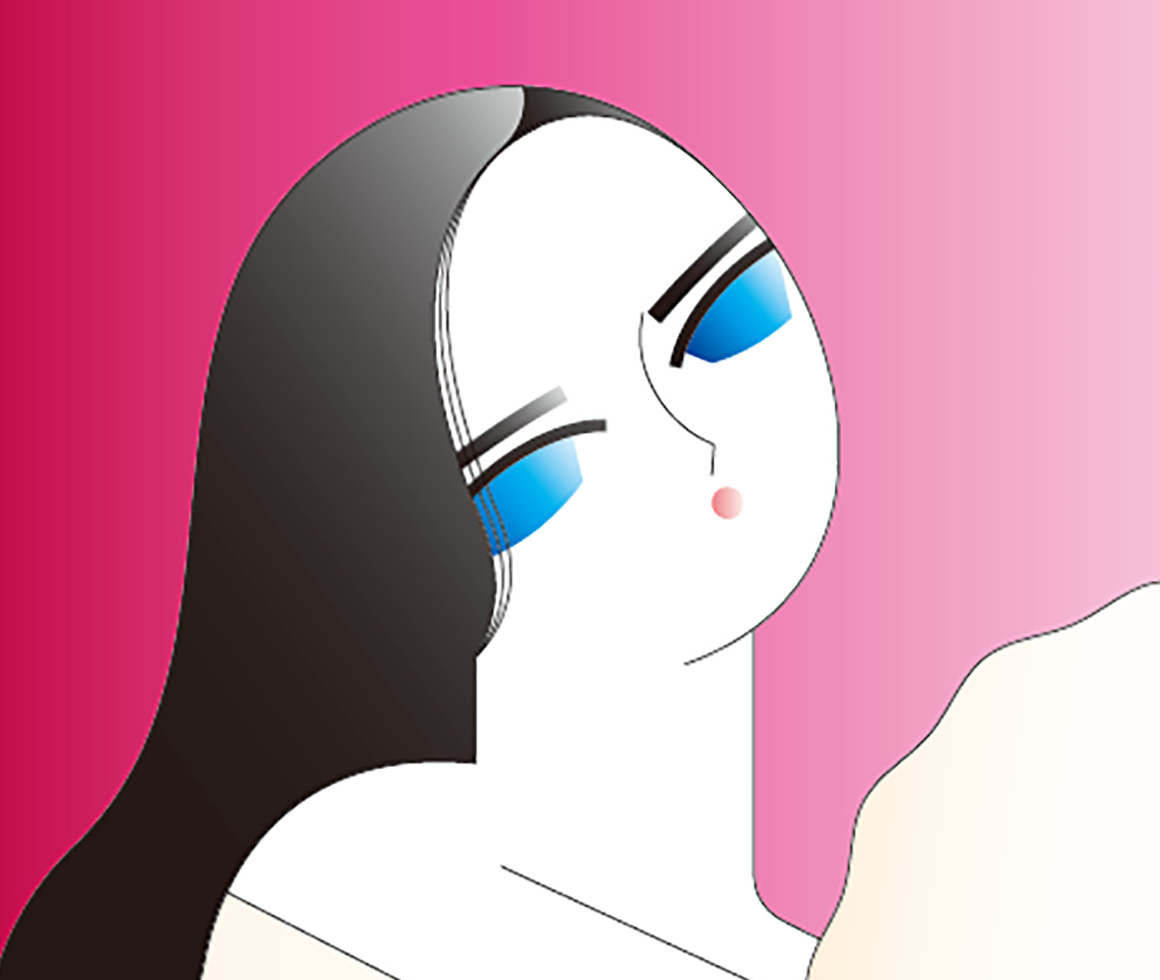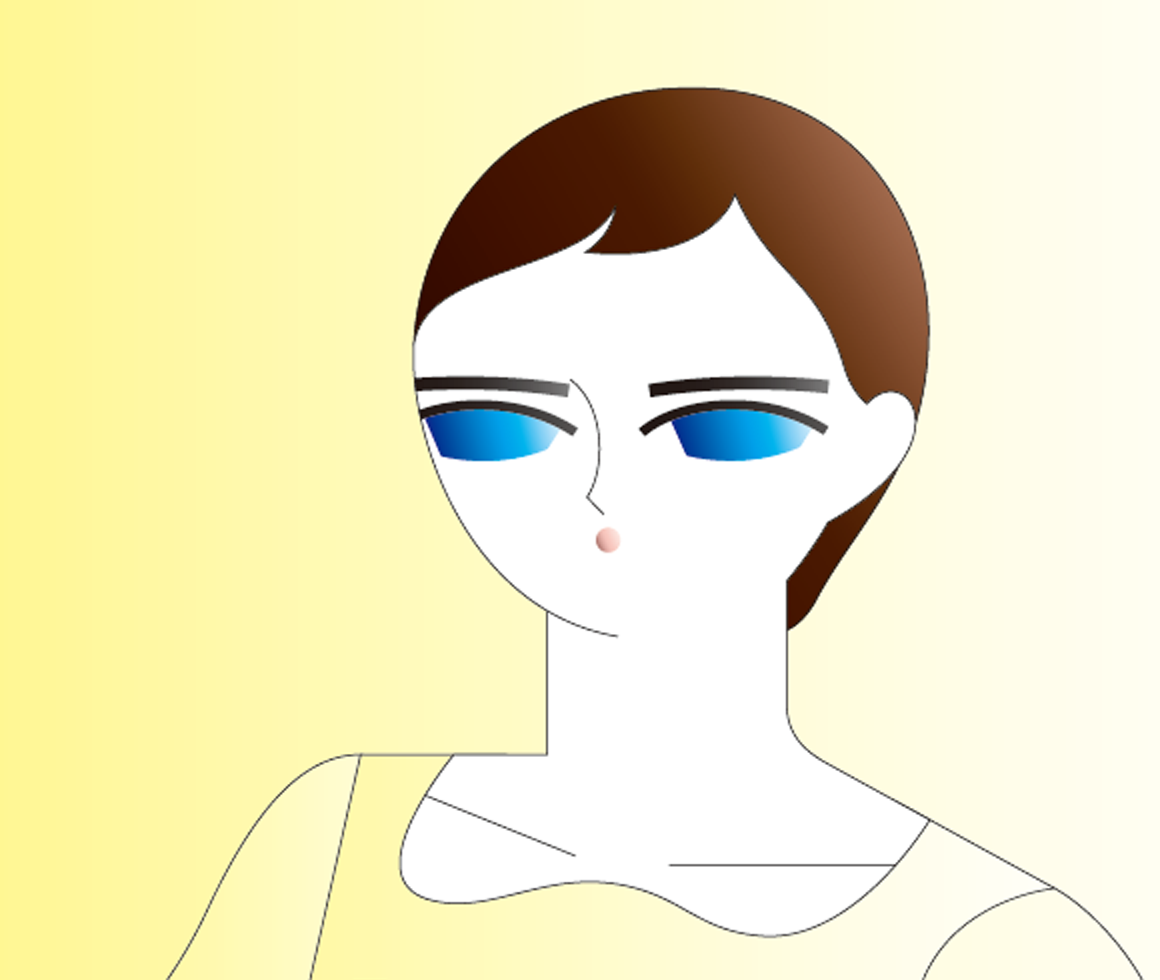この原稿を書いている私の仕事は、な、な、な、なんと音楽プロデューサーである。この連載の愛読者の方は、俄には信じられないかも知れないが、よくテレビとかで見るでしょう。でっかい録音スタジオがあって、若いバンドが演奏している。エンジニアのコンソールのちょっと後ろにプロデューサーズ・チェアがあって、私はそこに座って難しい顔をしているのである。しつこいようだが、信じられないでしょう。自分でも信じられない。スタジオは銀座、しかも歌舞伎座の裏の一等地ですよ。レコード会社はSONYである。私は、この連載を書いている最中、連載がこれしかない薄給のエッセイストのような気分に自分を持っていっている。我々は自己像のコスプレをして生きているのだ。
しかも、パソコンに向かって仕事をしているふりをして、株やゲームをしている駄目な会社の駄目な社員のようなマネをしているのである。生まれてから一度も堅気になった事がないので、そんな会社や社員が今の我が国にまだ存在しているのかどうかすら知らないが。
「そんなあ、ダメな会社員じゃあるまいし、音楽プロデューサーがそんな事して大丈夫なんですか? 数分おきに判断を仰がれるんじゃないの? 今のどうでした? とか言われて」
そう、仰る通りである。しかもバンドはまだ20代が多い新人だ。一回録音が終わる度に不安そうに私を見つめる。全員の視線を感じながら、私は腕組みをして「そうだなあ、全体のノリは良いんだけど、サビ前のベースが半拍ズレてるから、修正した方が良い。あ、いいよいいよこっちでエンジニアがやるから。それよりテイク2行こう。みんな少しリラックスして」とか言っちゃって。
特にヴォーカルの女の子には、父性と慈愛に満ちつつも、厳しい表情は崩さず(鉛筆なんか持っちゃって)
「このサビの部分ね」
「はい」
「今、どんな気持ちで歌ってる?」
「……」
「好きな人の事を考えながら?」
「……はい。っていうかあ、揺れてます正直。音程の事とか、リズムの事を考え始めちゃうと」
「それじゃカラオケじゃない。上手いカラオケでリスナーは感動するかな? リスナーは君の友達じゃないだろ」
「……はい」
「(背中をぽんぽん叩きながら)技術の事は忘れよう。君は技術がない子じゃない。だけどいつもブースに入ると技術の事を気にしだすのは(あえて目は見ないで)失恋の痛手から逃げようとしてるからだ」
「……」
「楽しもう。切ない気持ちもね」
「はい」
なーんつって、大変に忙しいわけだ。プロデューサーというのは。
大韓民国の、アイドルグループとかの現場ならば。或いは、タイムマシンに乗って、1970年代の東京の、ロックバンドのレコーディングの現場まで飛べればね。
現在の我が国の、特に、ちゃんと演奏するバンドというのは、もう、体育会みたいに練習しているし、PCの普及によって、どんな若いバンドマンも、自分の演奏をデジタルコンテンツとして客観的に把握できる耳を持っている。20世紀的なプロデューサーというのは不要な職業として消えるだろう。
だって、こうやって原稿書いている間に、どんどん現場は進み、バンドはエンジニアと直接波形編集(修正)の自己申告をし、バンドをやる事で、友情と人生の喜びに満ちて、とても仲良しで、ぜんぜん揉めないし、エナジードリンクやコンビニのパンやお菓子でいつまででもレコーディングを楽しむのだ。プロデューサーが「今日の出前どこにするう?」とか言って、スタジオにある出前用紙の束を読み上げたりしていた90年代が懐かしい。
ここまで書いて、メンバーもスタッフも誰も私の事を気にもかけない。原稿はもうそろそろ終わるが(もう、まったくドキドキしていないし、特に面白い事も書けそうにないので)、レコーディングはあと5時間は続く。8世紀までは、指揮者というのはボートのオールぐらいあるでっかい木の棒を、リズムに合わせて床に、餅つきのように打ち付ける仕事だったのである。それが、あの、ちっちゃい上品な棒に替わって、今やクラシック音楽でさえ、現場によっては指揮者はいらないと言われている。そして誰もがPCを使ったエッセイストになった。この私のように。背徳感を返してくれよコンピューター。

菊地 成孔
音楽家/文筆家
1963年生まれの音楽家/文筆家/大学講師。音楽家としてはソングライティング/アレンジ/バンドリーダー/プロデュースをこなすサキソフォン奏者/シンガー/キーボーディスト/ラッパーであり、文筆家としてはエッセイストであり、音楽批評、映画批評、モード批評、格闘技批評を執筆。ラジオパースナリティやDJ、テレビ番組等々の出演も多数。2013年、個人事務所株式会社ビュロー菊地を設立。
http://www.kikuchinaruyoshi.net/
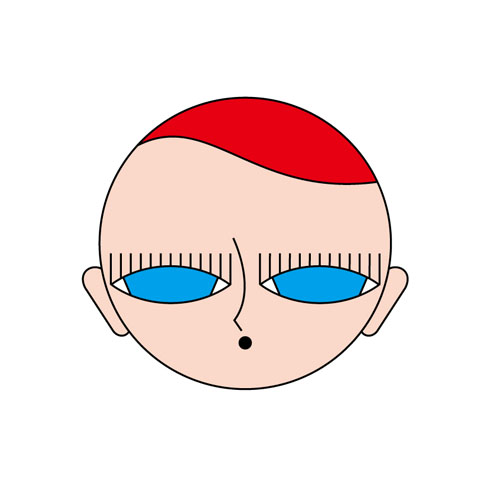
瓜生 太郎
イラストレーター
東京都在住。ファッションをテーマに女性を描くことを得意とし、シンボルマークのような図形的描写とシンプルな色使いが特徴。主な仕事に、銀座三越ウインドウディスプレイや表参道ヒルズシーズンヴィジュアルなどがある。
http://tarouryu.com/