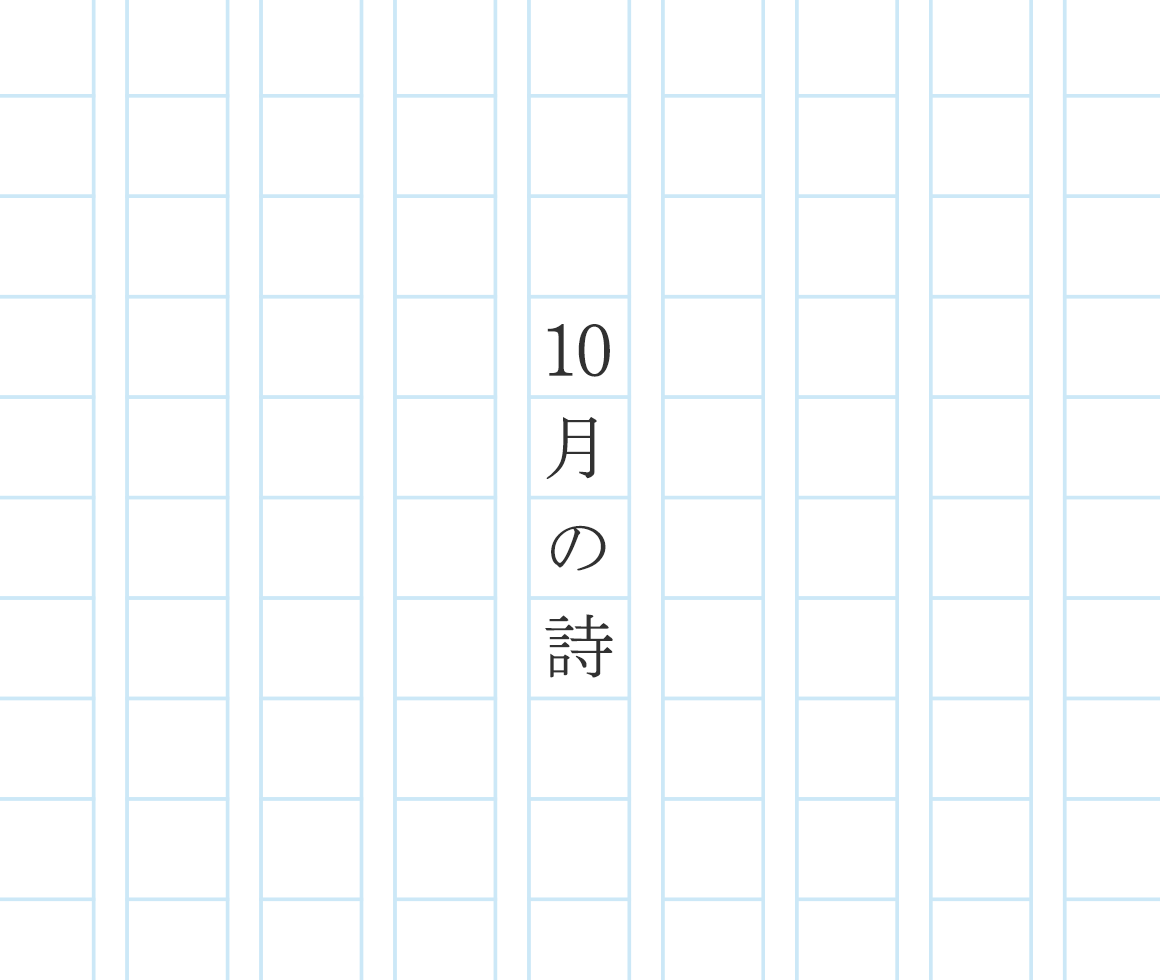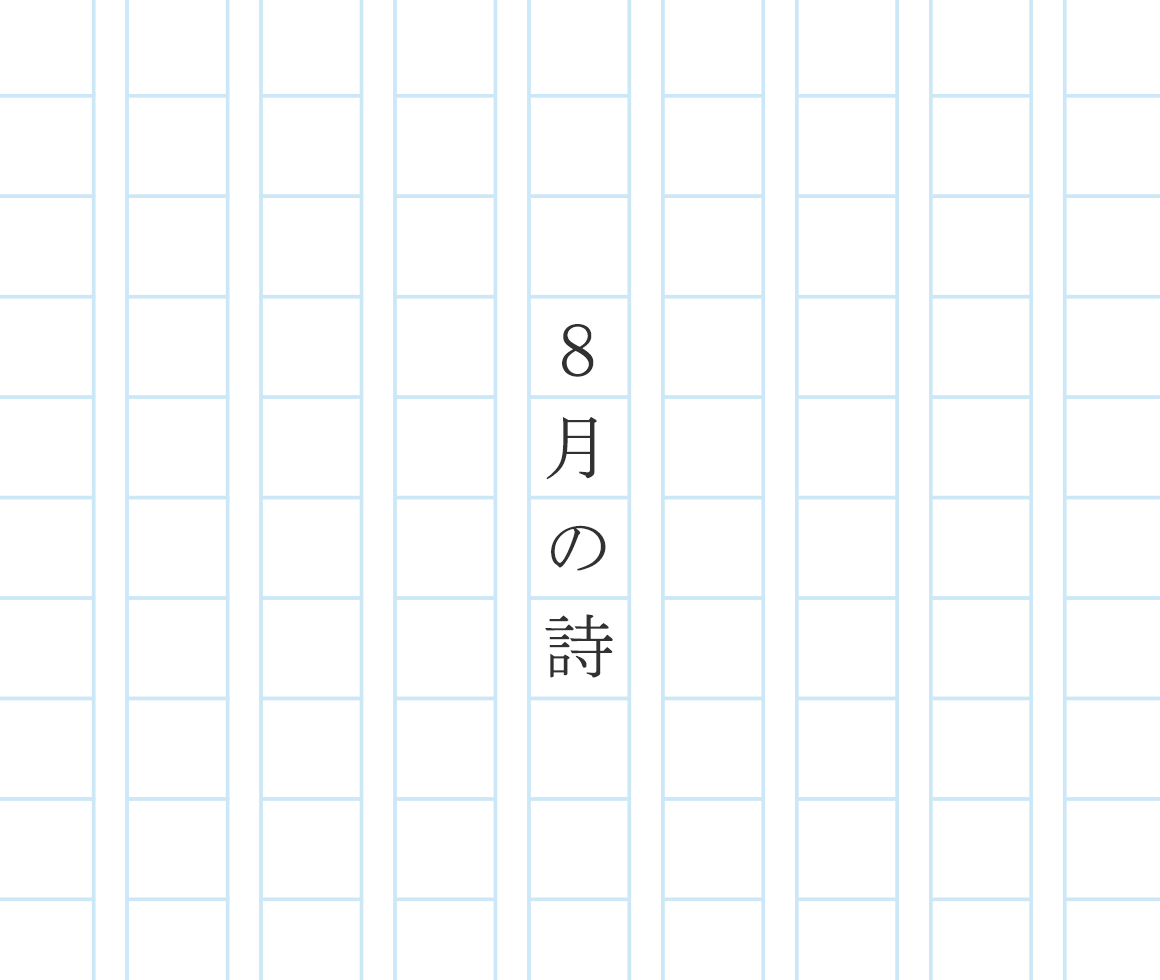お別れまでには長い待ち時間がある
ある男性はピザトーストを注文し、
ある女性はサンドイッチを催促する
少年が両親にパフェをねだっている
湯気の立つ珈琲が運ばれる
窓から差し込む光が眩しい
誰もカーテンを閉めようとはしなかった
みんな生きようとしていた
選評/大崎清夏
火葬場の喫茶店なら私も入ったことがあるのに、火葬場の喫茶店の、あの中途半端な時間のことを、こんなふうに詩にすることができるとは思わなかった。
息子や姪や孫でなく、男性や女性や少年として描かれた人々は、そこにあるはずのしがらみのようなものから、お別れを待つ間のひととき、解放されている。メニューにはややこしいものはなく、とてもシンプルに「待つ時間」が提供されている。珈琲の湯気が、どこにも書かれていない火葬場の煙と、珈琲を注文した人の体温を、同時に連想させる。一行ごとの情報が鮮やかで、ばちっばちっと構図が決まっていて、潔い。
ひとつの死を受けいれるために集まる人間は生きていて、食べることも、光を浴びることも、生きるためのことだ。強さを感じるのに、力みのない、落ち着いたいい詩だと思う。読んでいる私まで素直な気持ちになって、そうだな、生きよう、と思った。