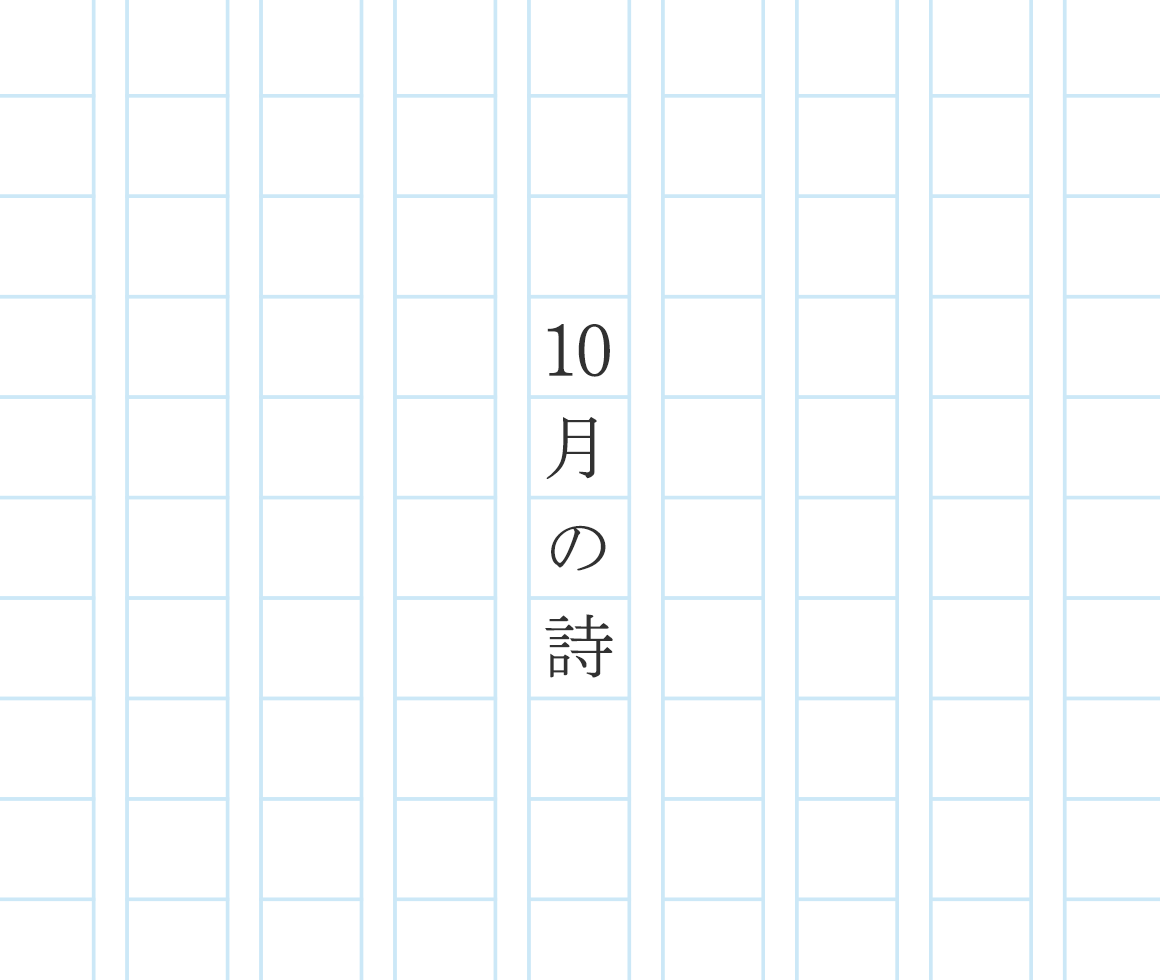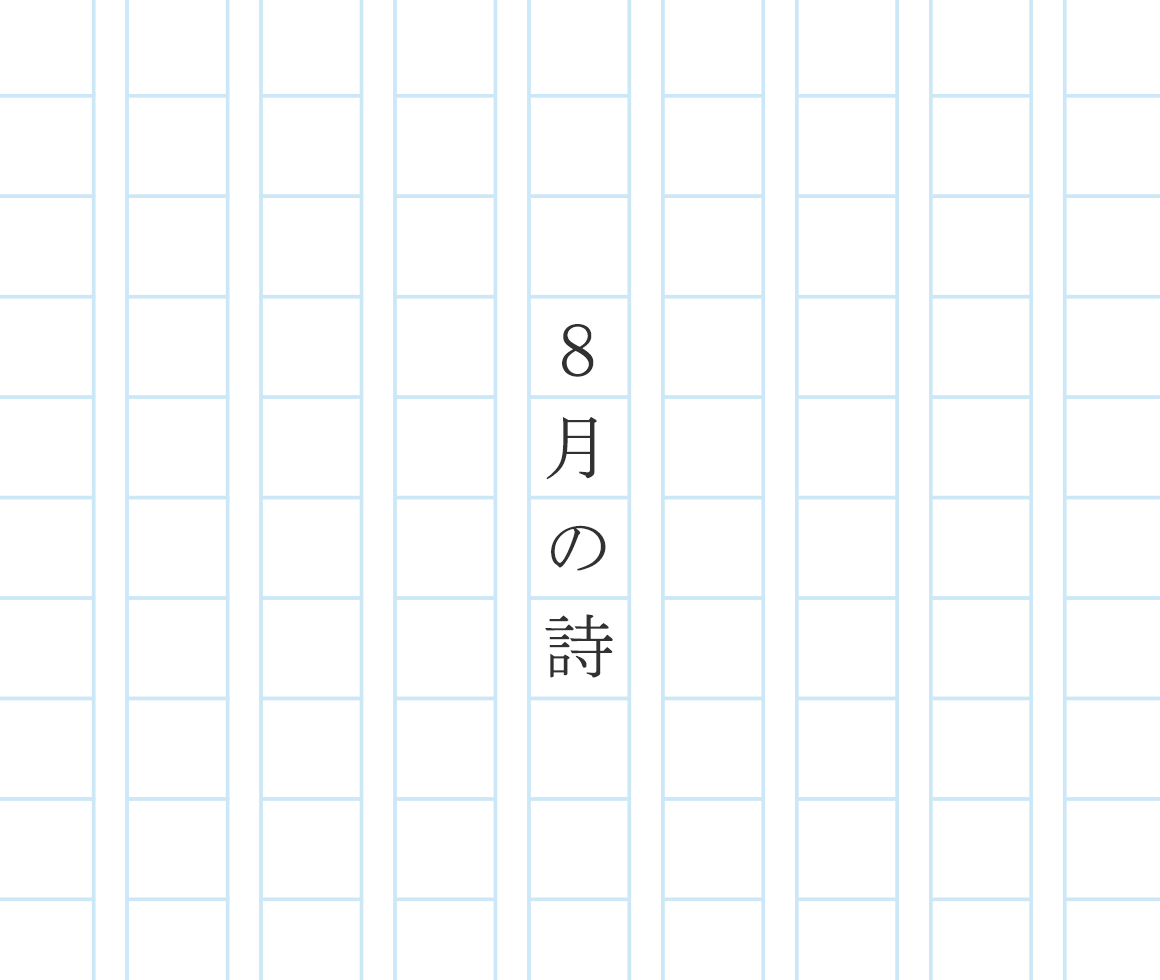牧場に羊を見に行きましたら
どうしてか
近くにいた誰かが、
柵の向こうの羊たちの群れに向かって
私の名前を
力いっぱい呼びました
(まぁ、ありふれた名前ですから)
そうしたら、子羊が
めぇー、と大きく鳴きました
これはびっくり
あらあら、私
そんなところにもいたのですか
不意の呼び声に
力強く応える、命
これはひとつ、私も
めぇーと、
鳴いてみることにいたしましょう
どこにでもいる
私という羊たちと、一緒に
ここにいますと
いつでも良い返事ができるように
選評/文月悠光
「名前」という記号は、「私」をかけがえのない存在として世界に繋ぎとめてくれる。名前を呼んでくれる他者がいるから「私」に気づく。誰かが私の名前を発音するとき、その響きが鼓膜を震わせ、私に名前を刻み込む。けれど、不思議に思う。その音が「私」を意味することを、いつ、どうやって私は知ったのだろう?
この詩の語り手は、かなり風変わりだ。〈まぁ、ありふれた名前ですから〉とドライな姿勢を見せつつ、子羊の力強い応答に〈あらあら、私/そんなところにもいたのですか〉とおどけたように驚いてみせる。子羊の応答にならおうとさえする。〈私という羊たちと、一緒に/ここにいいますと〉返事ができるように。それが救いであるかのように。
本作では、命の力強さの前で、名前の匿名性が揺らいでいる。「私」のかけがえのなさよりも、「〈どこにでもいる〉私」に価値が置かれているようだ。私たちは皆、柵に守られた羊なのかもしれない。誰かが〈力いっぱい〉呼んでくれるのを待ち焦がれる、群れているくせにどこか寂しい羊たち。いつでも呼び交わすことができるのに、決定的に孤独なのだ。まるでSNSのタイムラインみたい。
かけがえのない存在は、それがいつか失われてしまうことを考えると、果てしなく怖いものだ。私たちは「どこにでもいる」と「どこにもいない」の狭間で惑う。だから〈ここにいますと〉一緒に、精いっぱいに鳴いてみせよう。