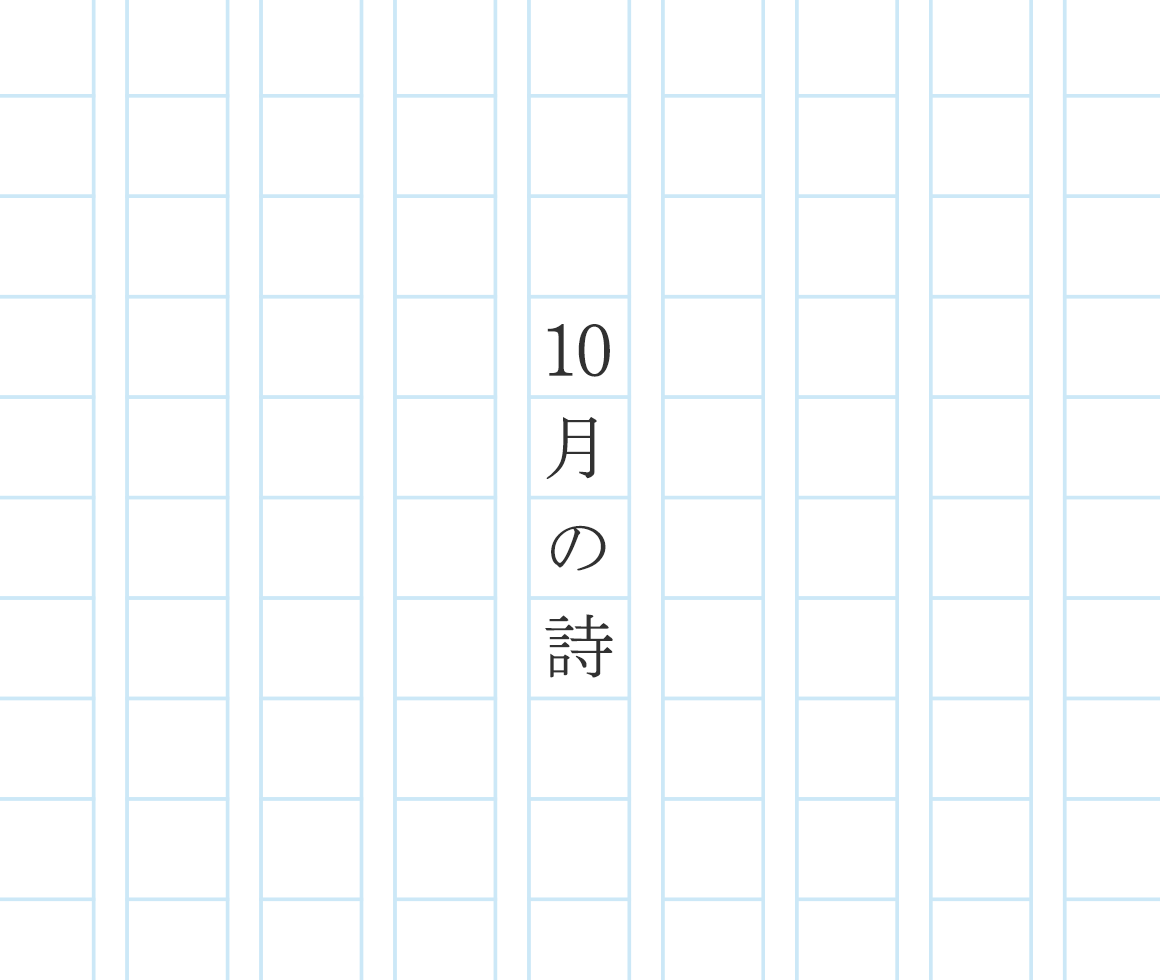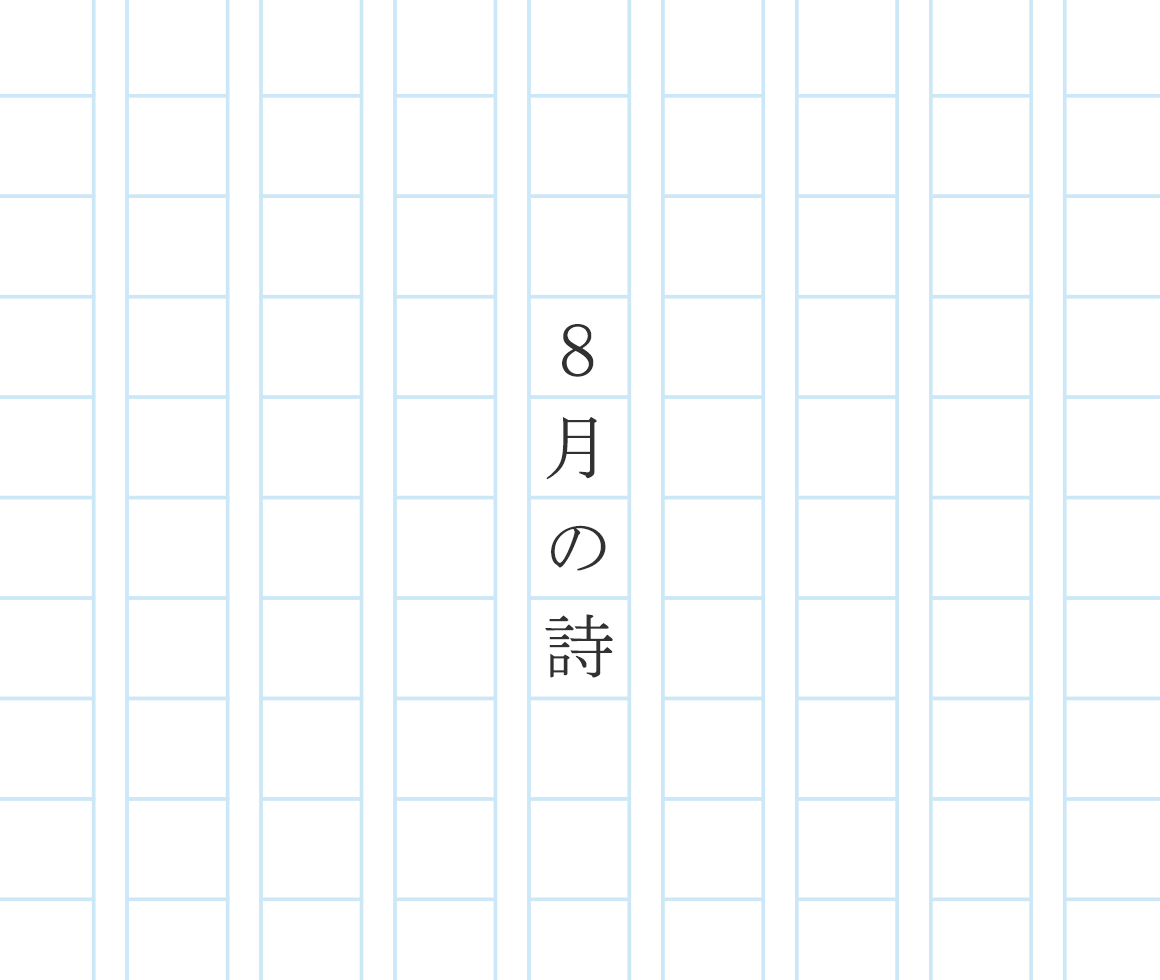包丁の先を初夏が研ぐ
青菜を鮮やかに切る
パーフェクト
冷蔵庫にあるだけのもの
空腹でもそうでもない足りる
種子の根は花の色を思案している
時おり水をやる 忘れずに
夏休みに読んだ
水色の小説をこちらにたぐり寄せる
思えば遠くなってしまった日と人を
透明な空の向こう側に感じた
と思えば
意外なほど近く そばにいたり
扇風機の風が
氷を急がせて
グラスの水滴に夏がいた
宿った種子を枯らさずに
水やりは忘れずに
土のにおいがかたむく
月日の中にひそやかに埋めておいた種子の
膨らんでゆく皮の張りを
指先で撫でている
実家の畑に這っている
かぼちゃの花が好きだ
選評/暁方ミセイ
魅力的な点がいくつも散りばめられている詩です。まず、出だしの、爽やかなスピード感。「初夏が研ぐ」という言葉が、水で洗った新鮮な青菜の切れる感触を見事に表現していると思いました。「種子の根は花の色を思案している」という一文にも心惹かれます。まるで、種が自分自身を思い出そうとしているよう。
お腹の空き具合に見合うだけの料理を手際よく作り、食べるという生活の匂いの最中で、詩は、ふと空を彷徨うように思いを浮遊させます。しかし、最後にはちゃんと土に、自分の肉体であるとさえ言えるかもしれない「実家の畑」の「かぼちゃの花」に帰ってくる(でも詩として素敵な飛躍をしている)のも、よい終わり方だなあと思いました。
謎めいている点にも、おもしろさがあります。「意外なほど近く そばにいたり」というのは、どういうことなのでしょう。秘密をほのめかす行でも、あるいはそのまんま、懐かしい人たちも案外ご近所に住んでいる、という意味でも、何だかいいなあ。あらゆるものはちゃんと存在していて、手放しても、力強く、在り続けるのです。健やかなあたたかさを感じる詩だと思いました。