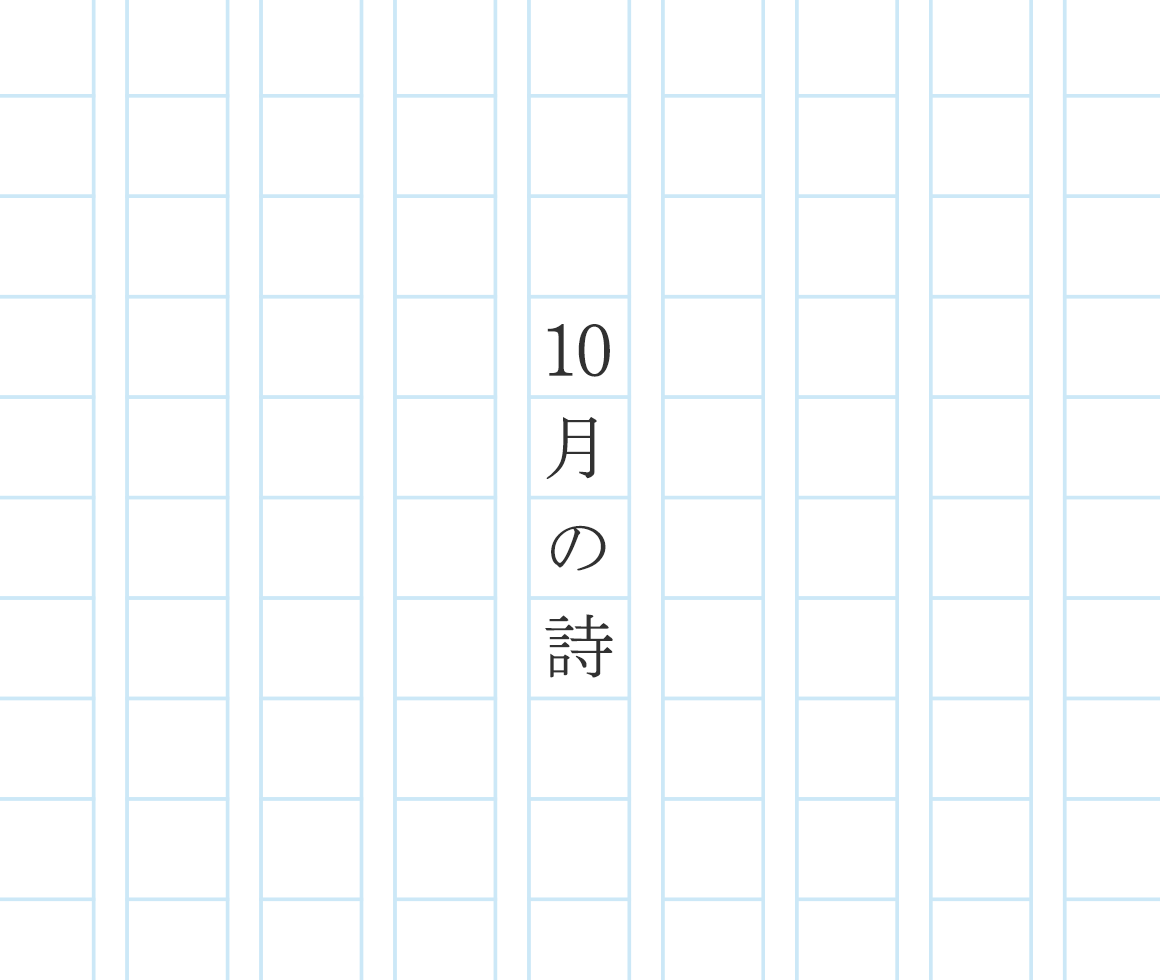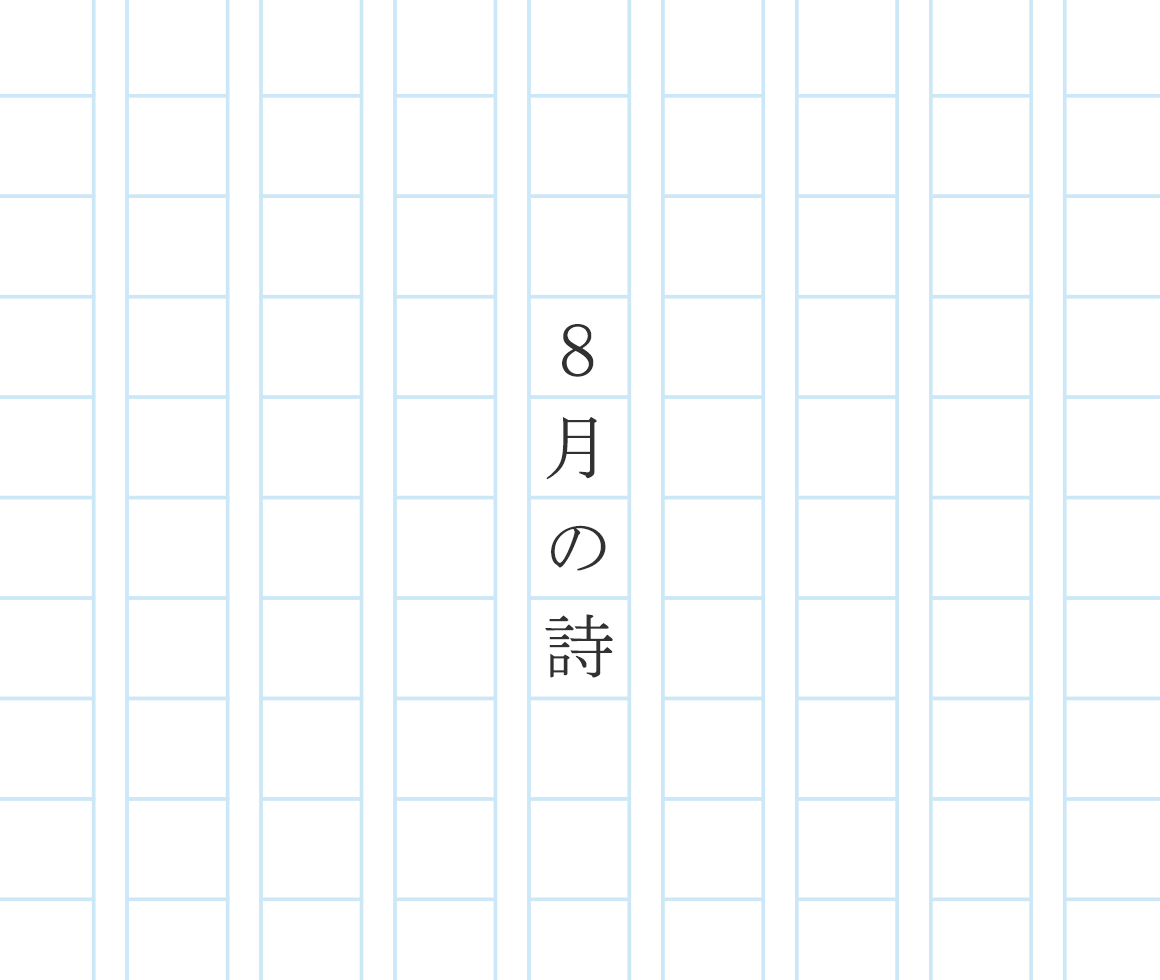幼いころ
「貝殻を耳にあてると海の中の音が聞こえる」と
おしえてもらったことがある
空っぽの貝殻を耳にあてると
わたしはよく海の中の生活を想像した
夢みた
そこから
どんな魚が行き来しているのかをよく見ていたし
誰も見たことのない海の生き物もみんな知っていた
自分の手からも貝と同じ音が聞こえると気がついたのは
10年も20年もあとのことだった
大雨の日
ひとりぼっち
広い海辺を歩いていると
今ならあの海に
もどれるような気がした
あたたかい波が足にふれる
手を耳においてわたしは海の中の夢をみる
選評/暁方ミセイ
「私の耳は貝のから 海の響をなつかしむ」(「耳」ジャン・コクトー著、『月下の一群』新潮社に収録)。堀口大學が訳した、ジャン・コクトーの有名な詩を思い出す作品です。堀口自身も本歌取りの詩を作っているように、多くのオマージュが存在する題材だと思いますが、柏原さんの作品はどうでしょうか。
貝殻に耳をあてて、海の中の生活を夢みていた詩の主人公は、ずっと後で、自分の手のひらからも海の音が聞こえることに気づきます。そして大雨の日、ひとりぼっちで海辺を歩いて、足に触れる波をあたたかいと感じます。
コクトーの「耳」は、まず耳と貝殻という視覚的な面白さがあり、その貝殻が思い出す潮騒が再び耳を呼び戻し、聴覚的にも読者を楽しませる詩です。堀口大學の「母の声」は、耳の奥の三半規管を巻貝に見立て、失われた記憶を尋ねる詩。では柏原さんの「海の中の夢をみる」はというと、まるで全身が貝になってしまったようです。「あの海」は、自らの血潮の中にあるのです。それは目の前に広がる海から、大昔生き物が細胞で囲って、飛び地になってしまった海です。
自然体で書かれているけれど、今ここで生きていることに深く潜っていく、佳作だと思いました。