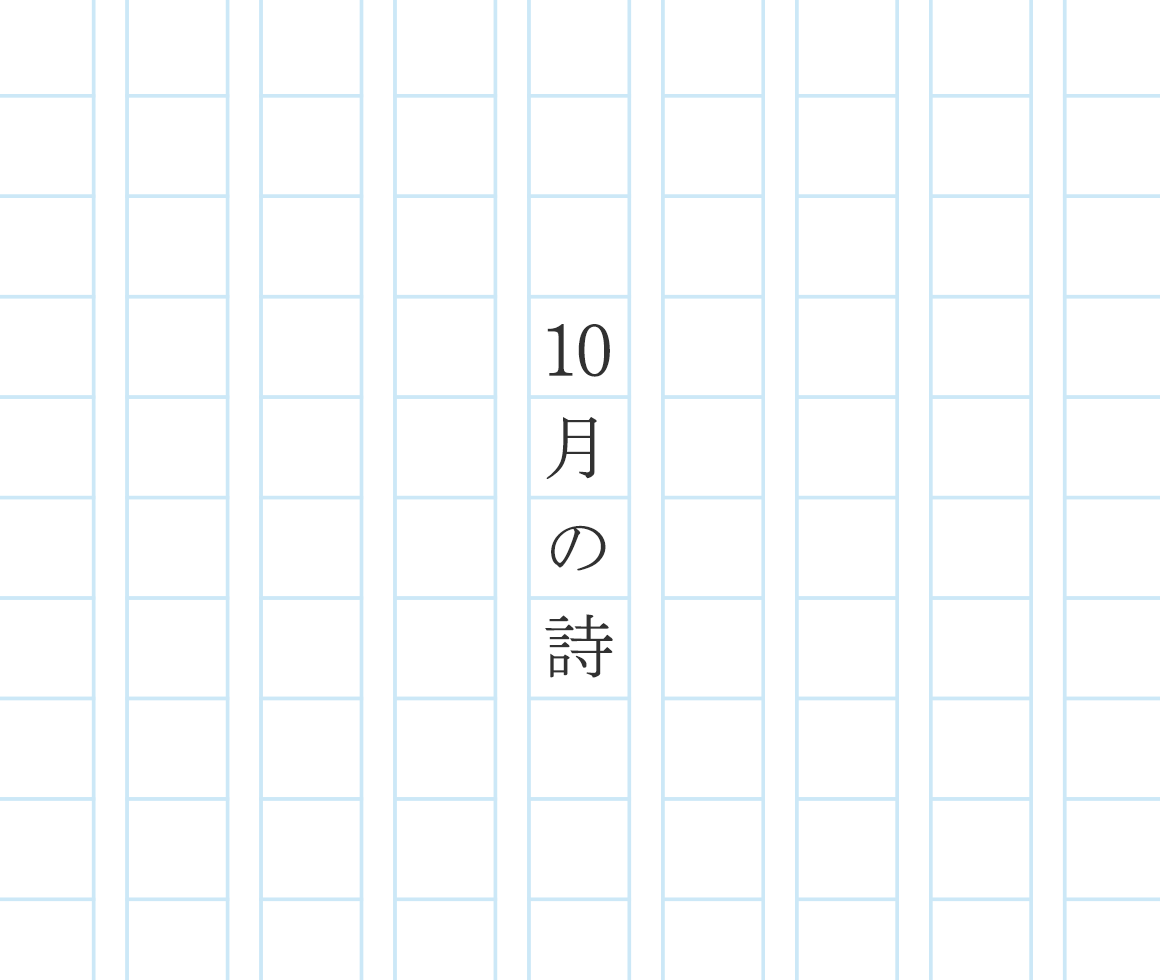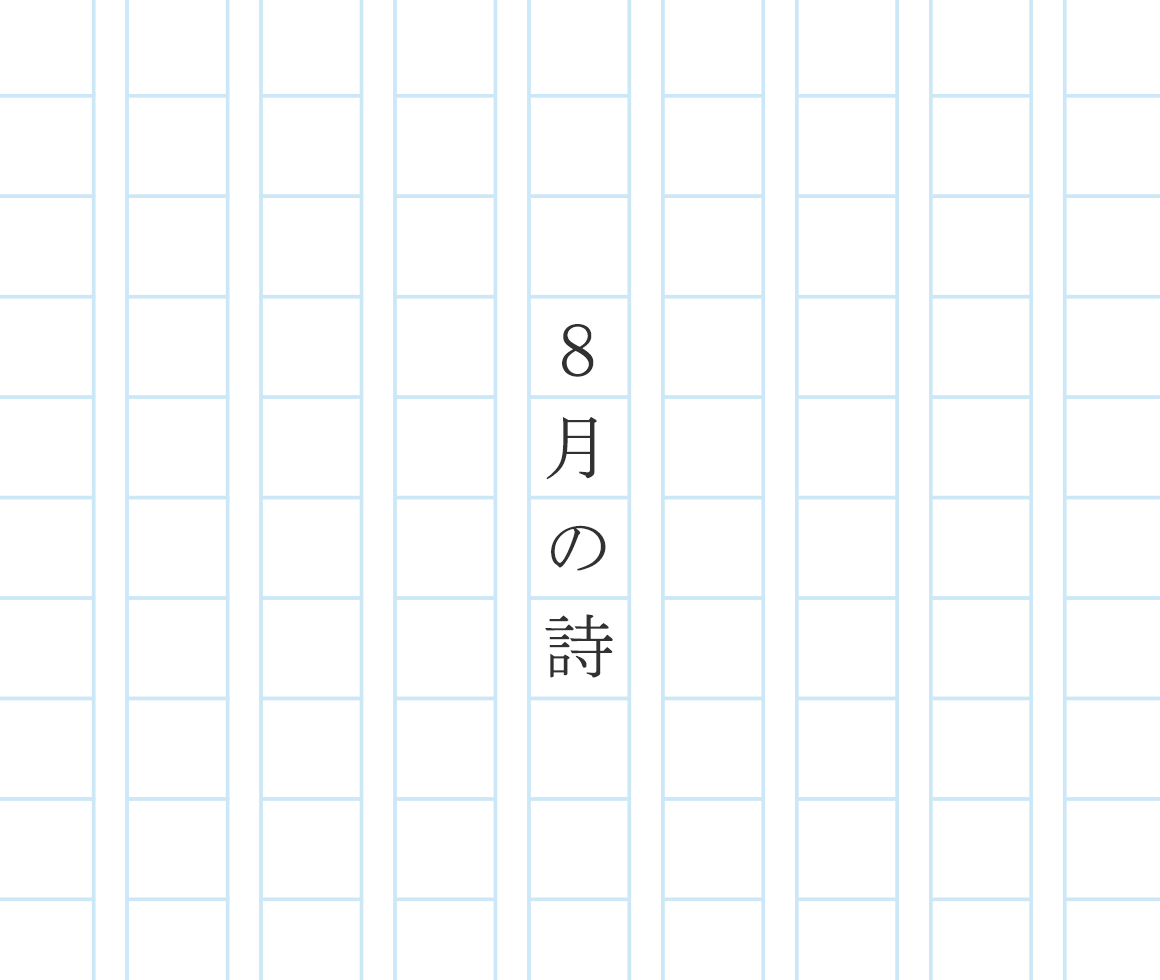お昼に急いでつめこんだ
たったひとつのおにぎりで
動かしていた身体が
みしみしと鳴りガタガタ軋み
一瞬めまいがして気づく
160センチあるこの身体を
たったひとつのおにぎりで
操縦していたのだ
無理もないと冷静になる
夕方のコックピットはもぬけの殻
働けど 働けど
楽にはならず埋もれてゆく
生きているだけ
最近はとくに
生きているだけでなんか痛いし
同世代のかがやき
ギラついた野望
あわれみを孕むまなざし
自意識過剰と雑に片付けられる
物事の多さに落ち込む
(彼氏いないの)
(紹介しようか)
(結婚はまだか)
(産むならいま)
(あきらめるな)
( )
多様性はどうやら
わたしの星までは届かない
夜になって泣く
子どものように泣く
子どもだった頃のこと
わたしは誰よりも覚えている
おなかがすいた 悔しい
生きているだけなのに
生きている
この可笑しさはなんなんだ
もういい明日は
おいしいランチを食べる
ひとりで好きなものを食べる
ご褒美でもなんでもない
ただ食べたいから食べるのだ
わたしだけは
わたしを肯定し続ける
がんばれも大丈夫も
わたしがわたしにだけ使える言葉であれ
とかそんなことを考えて
ただ生きてゆるやかに終わるその日まで
好きなものを食べる
おいしいと言って食べる
涙が出ても食べる
この悔しさはわたしのもの
明日も明後日も動いてくれよ
たのむぜわたし
選評/大崎清夏
たったひとつのおにぎりで済ませるランチは、楽にならない日々をぎりぎり「操縦」していくための節約なのだろう。まだまだ多様性に不寛容な社会の中、「わたし」はさまざまな抑圧の言葉に蹂躙される日々を堪えている。「生きているだけでなんか痛いし」の一行に、切っ先の鋭いものでえぐられるような気がした。
二連目の「働けど 働けど」は、石川啄木「はたらけど はたらけど猶 わが生活(くらし) 楽にならざり ぢつと手を見る」への目配せだろうか。啄木は実際はあまり働いていなかったと言われるけれど、「わたしの星」には粛々と労働があり、「おなかがすいた 悔しい」にも「生きている/この可笑しさはなんなんだ」にも、誰に向けたらいいのかわからないふつふつとした怒りが宿っている。これは二十一世紀のプロレタリア詩だ。
怒りがふっきれる最終連が清々しい。抑圧に対して反駁の呪詛を投げ返すのでなく、「がんばれも大丈夫も/わたしがわたしにだけ使える言葉であれ」という祈りをこんな芯のある詩行にまとめたことに、作者の強さを感じた。「わたし」はかっこいい。ドラマ『カルテット』に出てくる言葉を贈りたい。「泣きながらご飯食べたことある人は、生きていけます」。