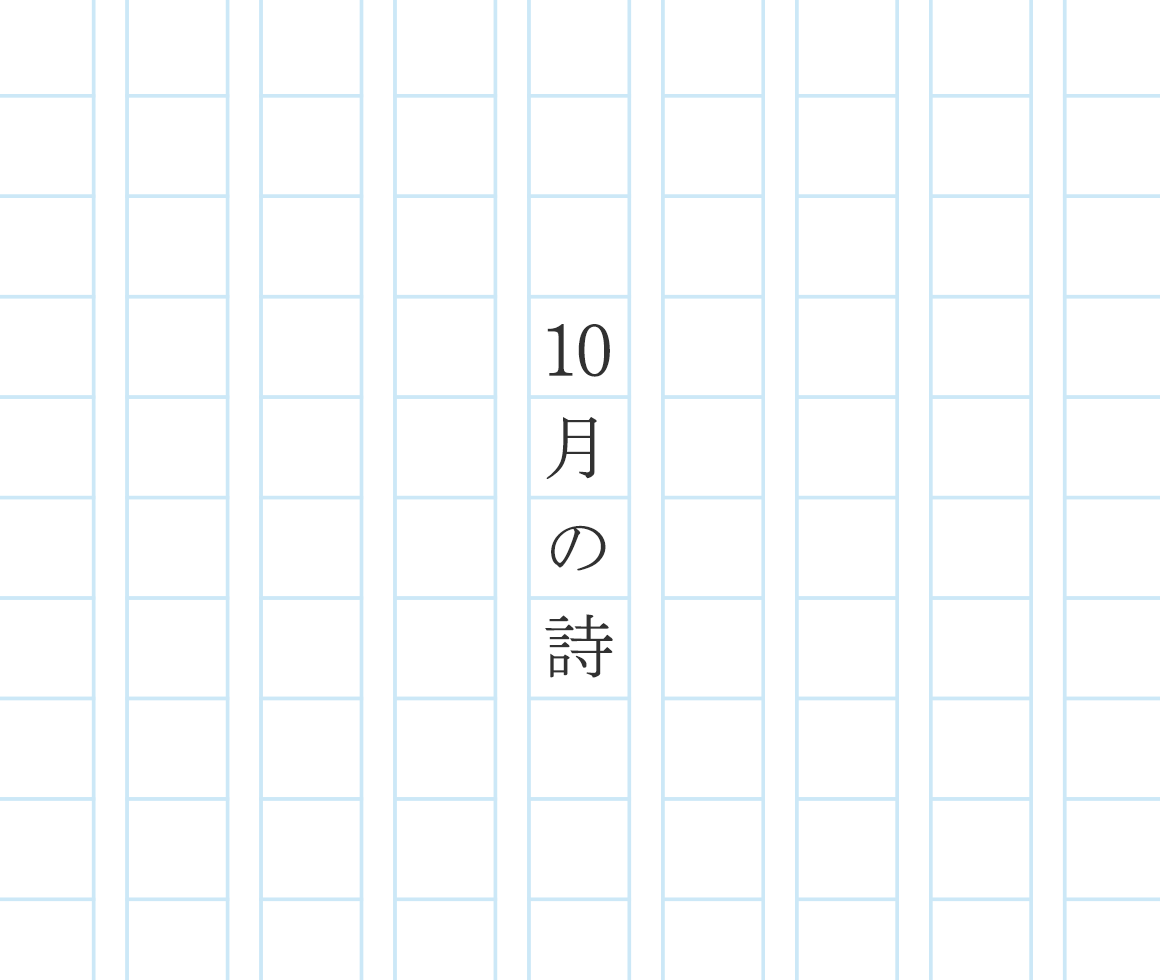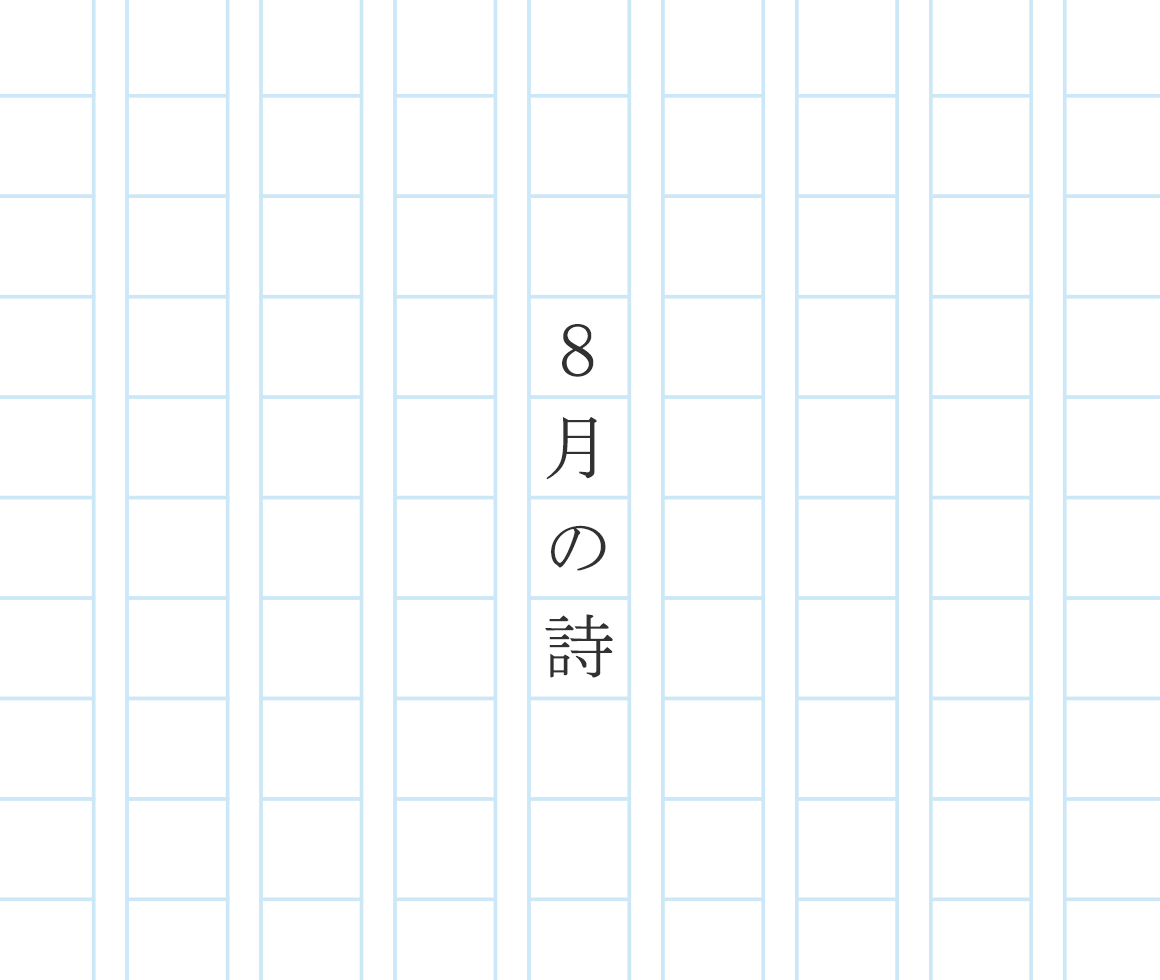ふと 胸を突かれるのは
通り過ぎる自転車のかごの中に
ねぎが入っているのを見たとき
キャンバスみたいなお化粧のお姉さんも
ネクタイの曲がったお兄さんも
柄と柄のコーディネートが光るおばさまも
ねぎを買った人は みんな同じように
その先端を かごから飛び出させたまま
不恰好な姿勢のまま ぎこちなく駆け抜けていく
どこか滑稽で 垢抜けていなくて
でも だからこそ
新緑の頃を思わせる
あの鮮やかな緑が視界を横切るたび
今この時も 世界が回り続けていることを知る
ねぎがあるなら まだ大丈夫
ねぎがあるなら まだまだやれる
そんな想いを抱きながら
わたしは 気がつけば今日も街角で
わたしだけのねぎを 探し求めている
選評/大崎清夏
最近、どうでもいいことの美しさの価値が、高騰し続けていると感じる。ここ数年ずっと、今年に入ってさらに。「ねぎ」を読んで、どうでもいいことの美しさを描いた詩の傑作をいろいろと読み返したくなった。たとえば、ウィリアム・カーロス・ウィリアムズの「This Is Just To Say」。ヴィスワヴァ・シンボルスカの「一九七三年五月一六日」。山之口獏の「湯気」。小津夜景の『漢詩の手帖 いつかたこぶねになる日』には、どうでもいいことの美しさを描いた漢詩がたくさん紹介されていて、たのしい。
「ねぎ」にはどことなく、漢詩的な洗練を感じる。日常の土台となるものの手触りが、観念的にならずに、ねぎのあの、圧倒的にどうでもいい姿に結実している。この主題なら、俳句や短歌のような定型詩にしても、いい作品になりそうだ。でも、京さんは行分けの自由詩にした。自転車が目の前を通り過ぎる一瞬が行ごとにゆっくりと重ねられるから、そのかごに刺さったねぎのぴんと伸びた背筋が、「不格好な姿勢」と対比されながら、スローモーションで輝く。
「わたしだけのねぎ」とはもちろん、食べるためのねぎではなく、詩の瞬間としてのねぎだろう。探されているのは、生活の軸になる詩=ねぎなのだ。……いい詩だなあ。