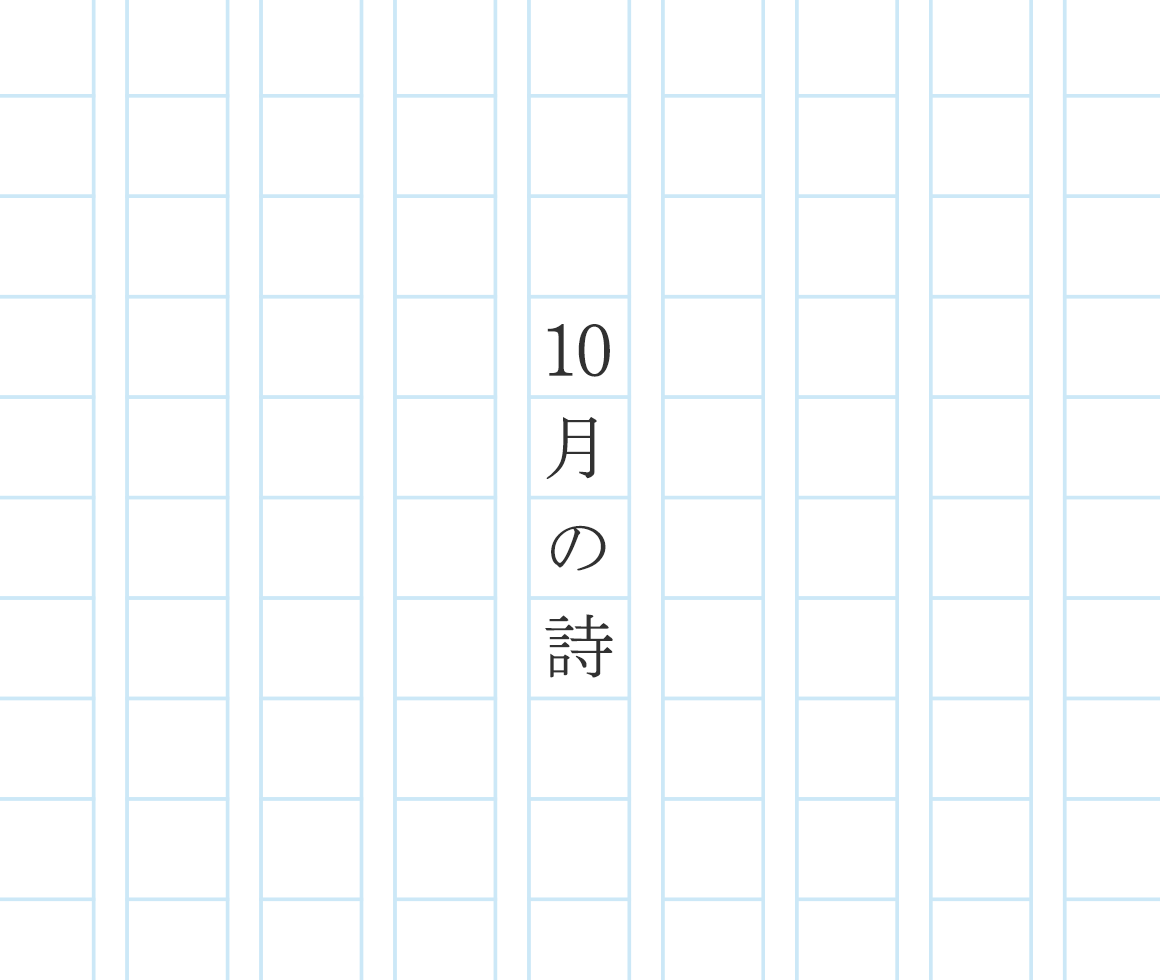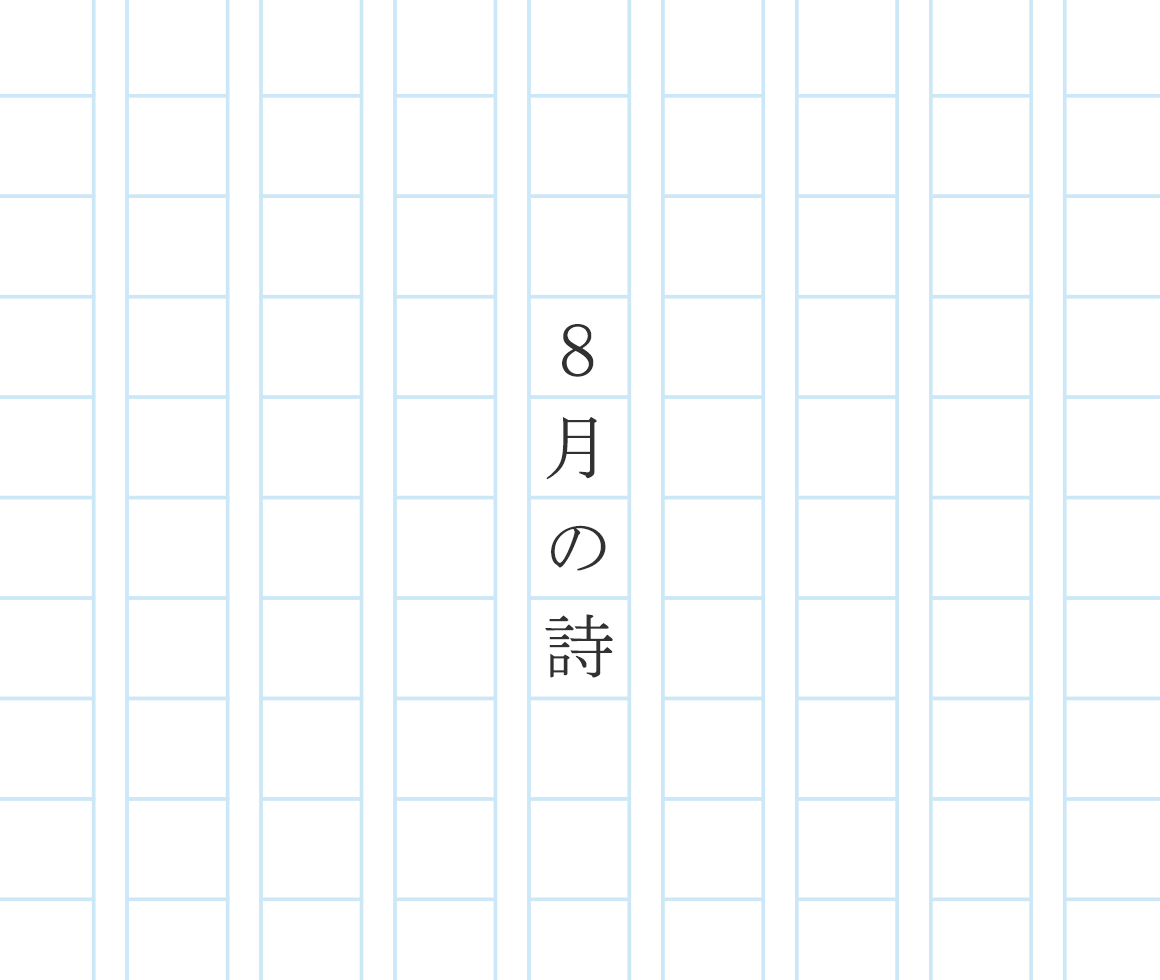エレベータが昇っていく
透明な貝殻が耳にかぶさり
水晶と水晶体が入れ替わり
やわらかな嘴が生えて
細かな鱗が全身をおおった
感覚がすべて遠のいていく
エレベータは二十一階で止まった
完成したわたしたちは今日もはたらく
選評/大崎清夏
変身は、混雑したエレベータの静寂のなかで、誰も微動だにせぬまま、成し遂げられる。十階、二十階と垂直にギュンギュン上昇するエレベータが、SF映画に登場するカプセルさながら、変身の舞台になる。エレベータが上がっていくときって、なんかみんな上を見ますよね。ヒーローが飛びたつ瞬間みたいに。
でもこれは、平凡な人生を送る人がヒーローに変身してたたかう物語というわけではなさそうだ。嘴や鱗は、感覚を遮断するための武装。「完成したわたしたち」は、むしろ何か人間らしいものを麻痺させて、ぞろぞろとエレベータを降り、たたかうかわりに「はたらく」。美しいパーツを身につけて、ありえないものに変身しているのに、この詩ぜんたいが無感情で、淡々とそれをこなしているところが妙にリアルで、平凡で、読む人をそっとぞっとさせる。ぞっとさせる力がある詩なのだ。
オフィスビルの二十一階で「わたしたち」がしている仕事は何だろう。たくさん並んだデスクの前で、大勢の人がそれぞれの画面に向かっている光景が浮かぶ。透明な貝殻はヘッドセット、水晶はパソコン?……と比喩の可能性を考えながら「水晶」を検索してみたら、「水晶発振子」という言葉に行き当たった。