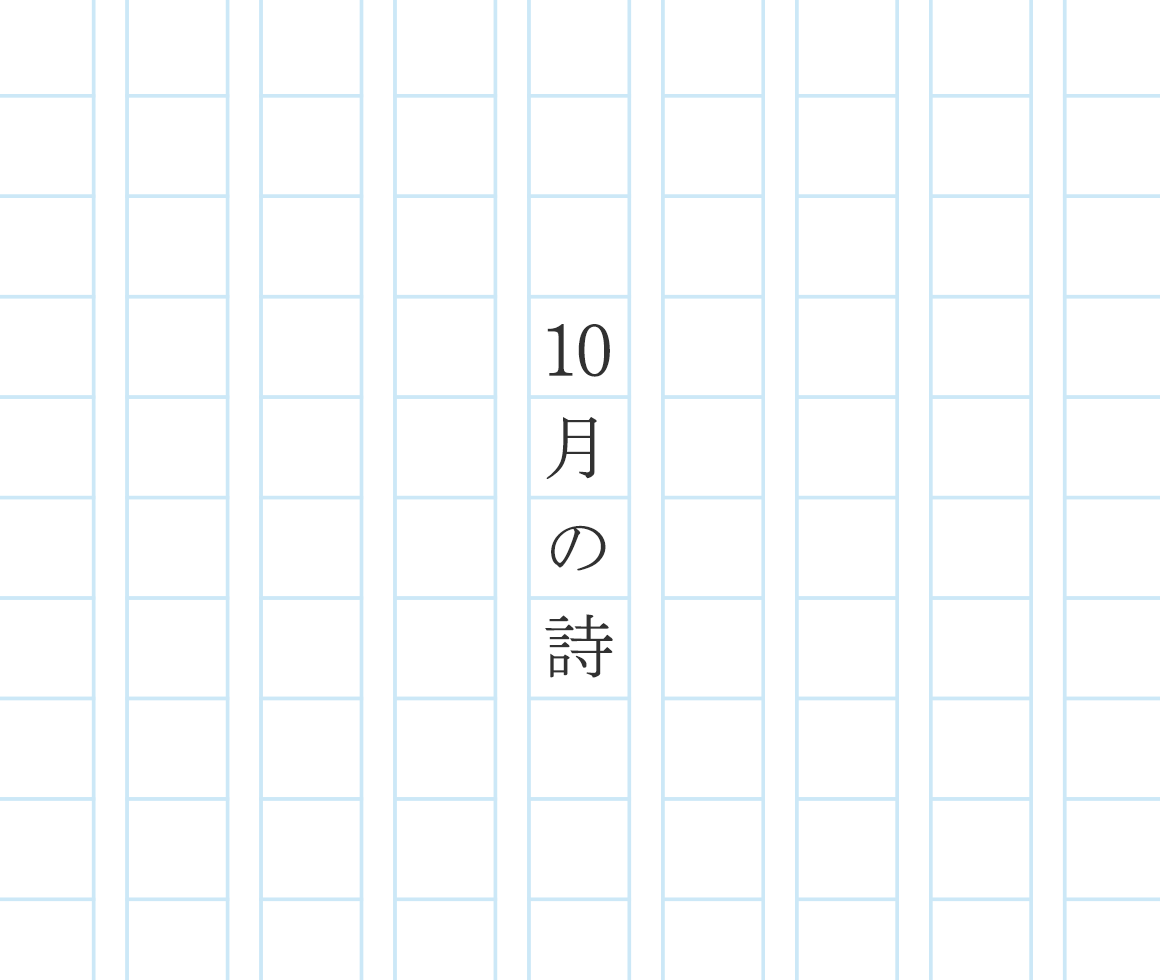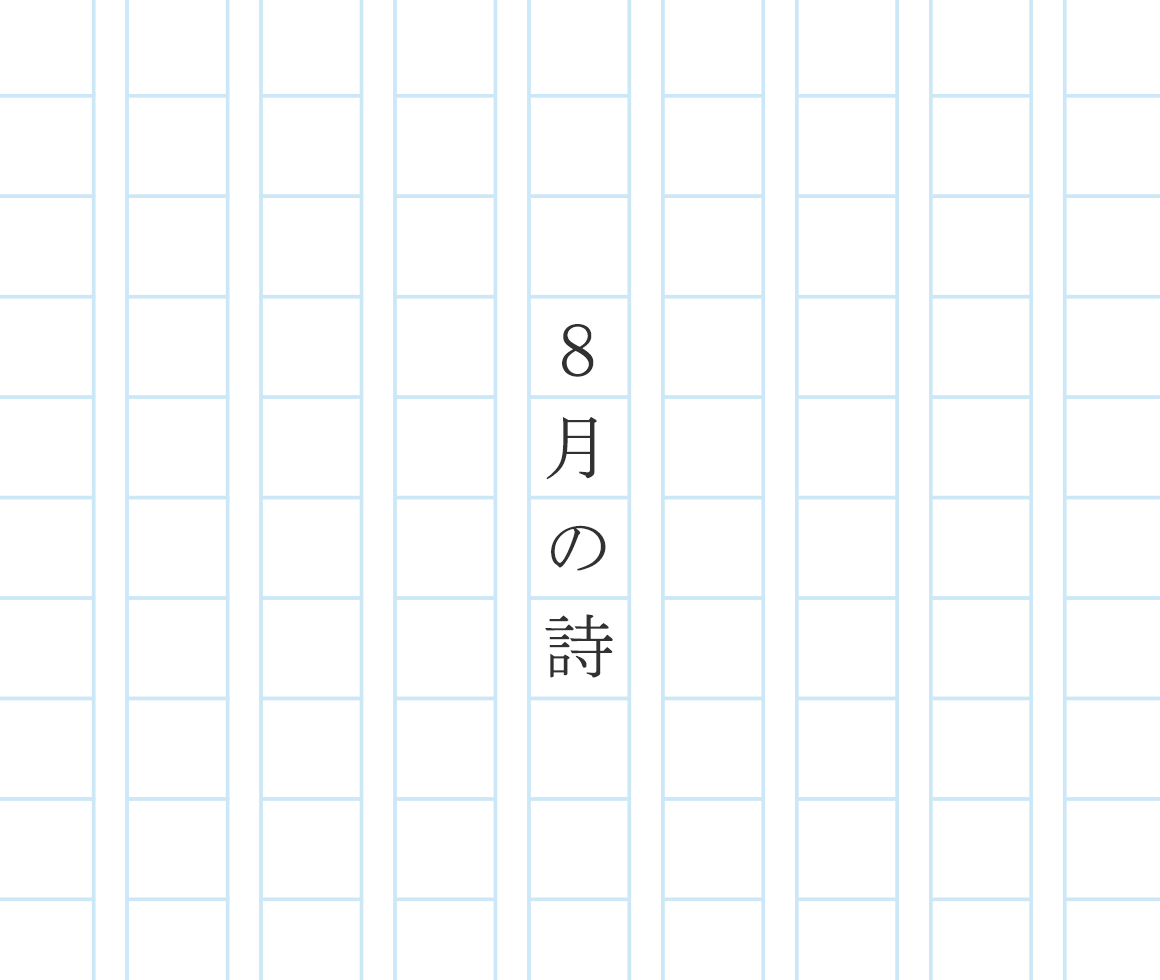家事が嫌いだ
風呂掃除も煮炊きもゴミ捨ても同じ
取りかかるだけで憂鬱が寄せてきて
肩がじっとり重たくなる
だれかが両手を置いているみたいに
これは
霊だ
わたしの憂鬱ではない
霊が 自分の憂鬱を
わたしのものに見せかけているのだ
霊は主婦だ
名前を月子という
月子は三十三歳
夫の同僚に安産型といわれたことがある
月子は賢い
古い野菜の捨て際をよく知っている
がたがたしない道をよく知っている
会釈のタイミングをよく知っている
家に帰ってくる
靴を脱ぐ
荷物を置く
なまものを冷蔵庫に入れる
ここではじめて電気を点ける
ソファの上にタオルが積み重なっている
地獄だ
と月子は思う
月子は地獄のこともよく知っている
それはしじみの砂抜きであったり
座布団を正円に並べることであったりする
そんなことには特に詳しい月子である
月子はほとんどの家事を憎んでいるが
洗濯だけは少し好きだ
中でも干すのが好きだ
しかしそれは錯覚であり
単に上方へ手を伸ばすのが好きなだけだった
かごから洗濯物を引き抜く
ぱんぱんと叩いてしわを伸ばす
手を伸ばして洗濯ばさみでとめる
かごから洗濯物を引き抜く
ぱんぱんと叩いてしわを伸ばす
襟首をハンガーに通す
手を伸ばして物干し竿にかける
月子はみんなに奥畑さんと呼ばれている
かつては奥畑さんではなかったが
いまはみんなが奥畑さんと呼ぶ
だが地獄は月子のものであって
奥畑さんのものではない
奥畑さんのものにしてたまるかと月子は思う
かごから洗濯物を引き抜く
ぱんぱんと叩いてしわを伸ばす
手を伸ばして物干し竿にかぶせる
大きい方の洗濯ばさみでとめる
月子は歌がうまい
とくにオペラがうまい
しかし月子は賢い
歌い出したいからといって
歌い出していいわけではないと知っている
いちばん危ないのが洗濯物を干すときだ
上を向くと歌い出したくなるのを
月子はいつもこらえている
かごから洗濯物を引き抜く
ぱんぱんと叩いてしわを伸ばす
わたしが上方へ手を伸ばすとき
わたしの喉の底を
知らない歌が
引っ掻く
月子は
呼ぶ声がするとかならず答える
それが奥畑さぁーんであろうと
ひいちゃんママーっであろうと
おかあさぁーんであろうと
奥さぁーんであろうと
宮本さぁーんであろうと
おまえーっであろうと
月子ははあいと言って行く
それが月子の使命であるなんてことは
まして喜びであるなんてことは
月子は考えたことがない
月子
わたしは家事が嫌いだ
風呂掃除も煮炊きもゴミ捨ても憎い
油も泡も水もみんな憎い
タオルの端と端をつまんで
指先であわせるなんて考えられない
壁からは四方くまなく甲高い音がして
さっきわたしが磨いた蛇口が光をみらみらぶつけてくる
わたしは月子をくり返し呼ぶ
月子
月子
月子
月子は 歌い出す前に死ぬつもりでいる
それでいて
九十五歳くらいまで生きるつもりでいる
選評/穂村弘
「家事が嫌いだ」という一行目から、するすると読み出せる。「霊だ」で笑ってしまう。霊なんだ。「霊は主婦だ」がまた可笑しい。そうなんだ。「夫の同僚に安産型といわれたことがある」「ここではじめて電気を点ける」「大きい方の洗濯ばさみでとめる」といった細部に小さな意外性とリアリティがある。「だが地獄は月子のものであって/奥畑さんのものではない」に批評性を感じる。改行のタイミングや繰り返しの使い方が巧みで、それらが魅力的なリズムを作り出しながら、ラストに向かってテンションが高まってゆく。「月子」という名前にはなんとなく、帰りそこねたかぐや姫のイメージがある。「呼ぶ声がするとかならず答える」のに、自分の「歌」は「こらえている」のか。「壁からは四方くまなく甲高い音がして/さっきわたしが磨いた蛇口が光をみらみらぶつけてくる」の危うさに惹かれる。「みらみら」が怖い。張り詰めたテンションは「わたしは月子をくり返し呼ぶ/月子月子月子」で最高に達する。たぶん、「わたし」は「主婦」ではないのだろう。