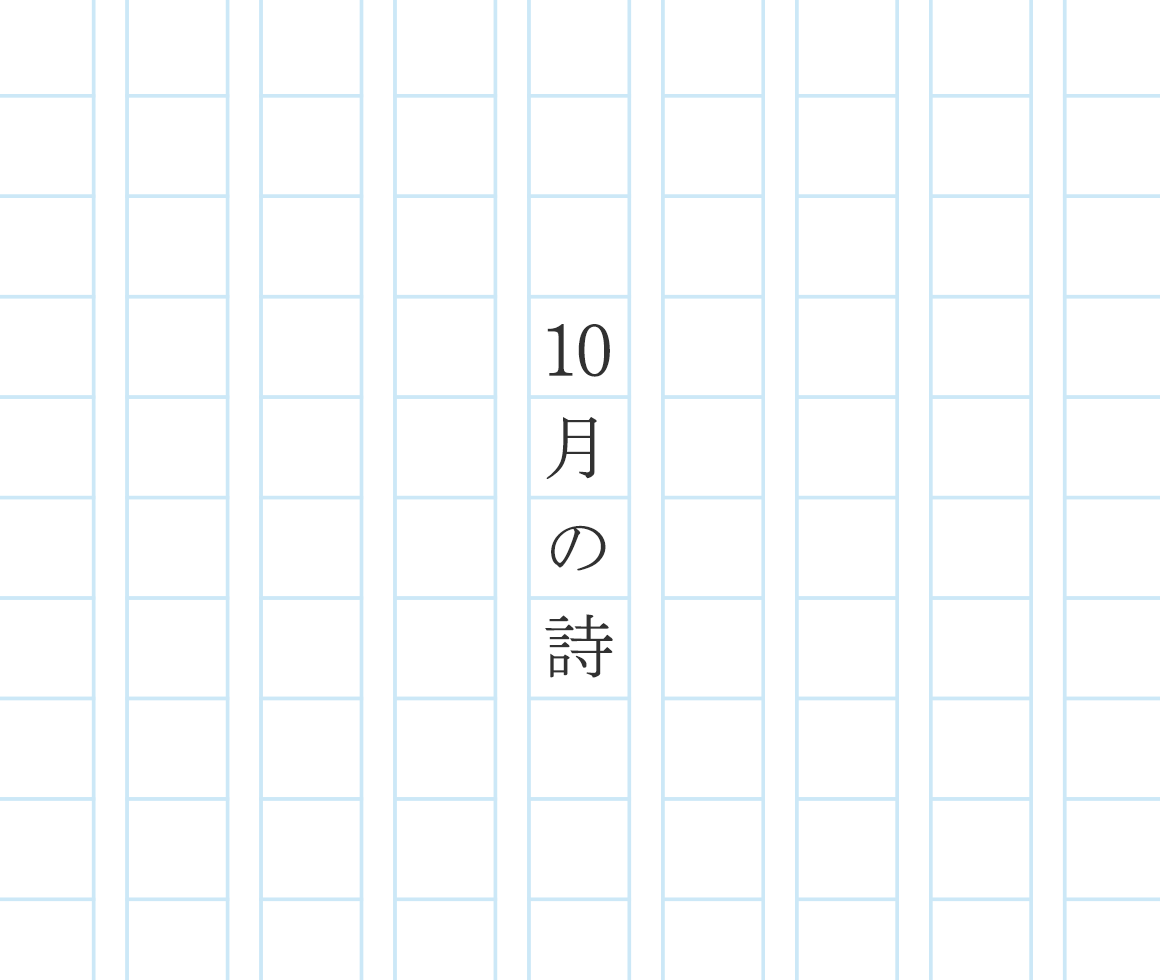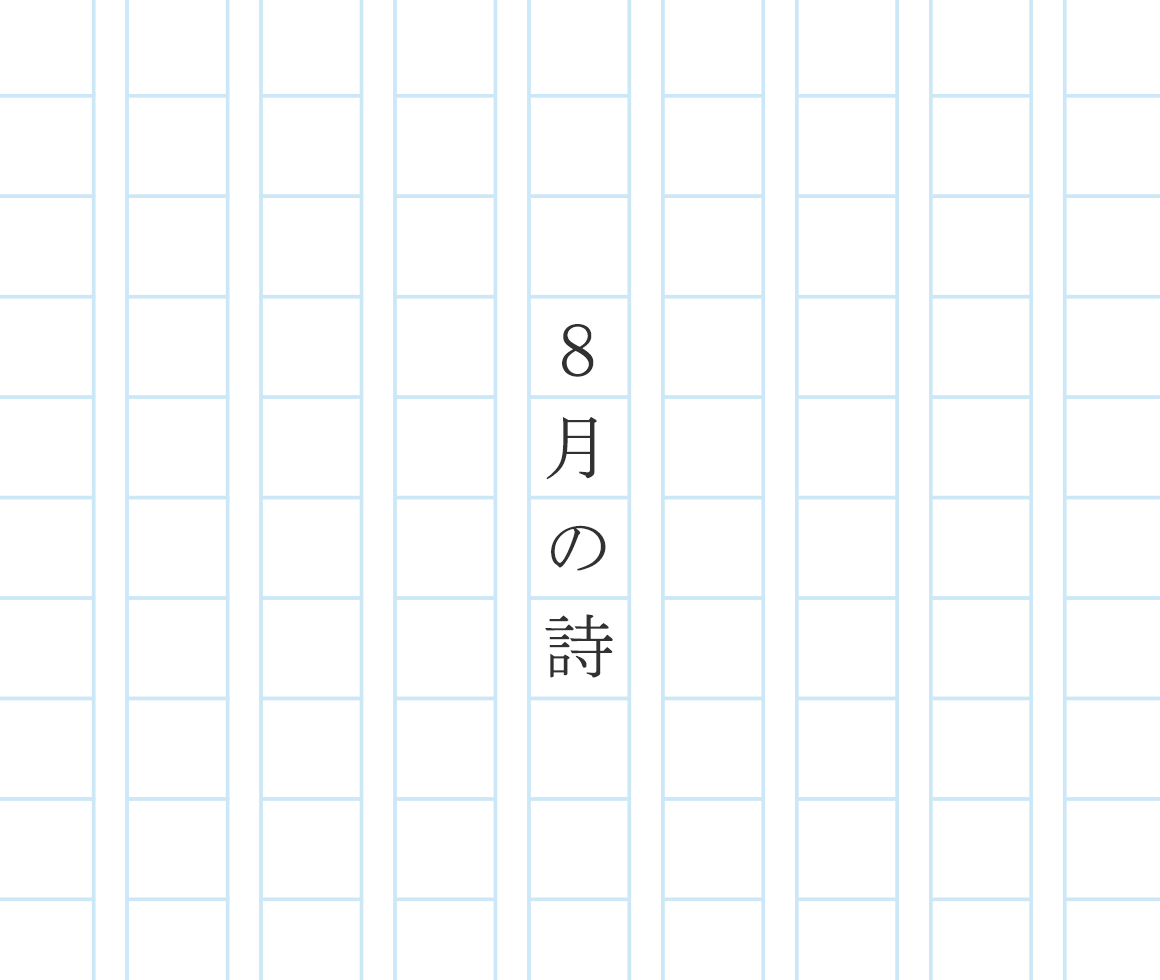ウェブ花椿の連載「今月の詩」で昨年から選考委員を務める、歌人の穂村弘さんが5月にデビュー歌集の新装版を、詩人の大崎清夏さんが新詩集を刊行されました。1年に1度、選考会でお会いするお二人が、短歌について、詩について、そして「今月の詩」についていろいろお話しくださいました。
時間を経て読む作品
大崎清夏(以下、大崎) 穂村さんの31年前のデビュー歌集『シンジケート』の新装版、ヒグチユウコさんの絵がすごく可愛いし、ページの途中にキャンディの包み紙が挟まれてあるのも面白いですね。
穂村弘(以下、穂村) ありがとうございます。自分にとってすごく大切な本だし、その気持ちを汲んでくれる人と思って装幀は名久井直子さんにお願いしたら、夢のようにきれいな本にしてくれました。
大崎 今回通読してみて、ロマンチックな歌より怖さや怒りが感じられる歌のほうが刺さったんです。一番怖いと思ったのは、〈恐ろしいのは鉄棒をいつまでもいつまでも回り続ける子供〉。子供も怖いし、それを見つめて短歌にする穂村さんも怖い。
穂村 ああ。ただ、もうそれを書いた頃とは別人ですよ。いや、コアのところは変わっていないから、味覚の変化とかに近いのかな。好きな食べ物って自然に変わるでしょう? その変化って抗うものでもないし、抗おうとしても抗えない。そうした変化は1日2日や1年2年では分からないけれど、31年経つとはっきり可視化されますね。
大崎 31年前、私は7歳でした。
穂村 わぁ、でも、生まれてはいたんですね。最近は当時まだ生まれてなかった人と仕事することも多いから(笑)。『シンジケート』には今はもう使わないことばもたくさん出てくるでしょう? 受話器とか毟(むし)るタイプのプルトップとか。〈カルピス飲むと白くておろおろした変なものが口から出る〉という現象も、今のカルピスは進化して澱が出ないから、何かのメタファーだと思われそう(笑)。それと、今だったら倫理的にNGな歌もある。当時も駄目だと分かってあえて書いてるんだけど、今は敢えて書くということ自体が通用しないから。でも、迷った末に今回は手を入れずに出すことにしました。
大崎 詩や短歌の世界にもポリコレの波はありますよね。私は人間をふたり出すとき、男女でも男男でも女女でも入れ替えて読めるように書くことが多い。でもそれはポリコレを意識して変わったのではなく、もともと中性的に描くのが好きだったんです。なるべく幅広い読者に届け、という気持ちがあって。
穂村 なるほど。

大崎さんの最新詩集『踊る自由』(左右社)
詩を書くこと、歌を書くこと
穂村 大崎さんは何歳から詩を書き始めているんですか。
大崎 投稿を始めたのは27歳くらいです。学生のときは小説家になろうと思っていたんですけれど難しくて書けなくて、卒業後も小説の破片みたいなものをごにょごにょ弄んでて。27歳のときに友達が伊藤比呂美さんの詩の朗読に連れていってくれて、そこで「はー、これだー」って。ほどなく伊藤さんが「ユリイカ」の詩の選者になられたので、ここに送るしかない、となりました。
穂村 「これだー」と思ったのは言語化するとどういうこと?
大崎 「声なんだ」って思ったんです。リズムがあるってこういうことなんだ、韻文ってこういうことなんだ、って。
穂村 大崎さんの詩って物語的な雰囲気があるから、小説を書いていたと聞いて腑に落ちました。でもやっぱり詩なんだよね。新刊詩集の『踊る自由』の「みや子の話」の〈いつか津波が到達した辺りで〉という表現は通常の文脈だと過去のことだけど、ここでは未来の可能性も拓かれるような言葉の揺れというか、普通とは違った時間の多層性が感じられます。また、「渋谷、二〇二一」の、路上でサムギョプサルの店の男の子に店の名刺を渡された時の〈渡しながら、私の手にピリ辛新しょうがの小袋があるのを見て/男の子はにやっと笑ってました。〉は、小説の一節としても読めるけれど、より印象が鮮烈ですよね。
大崎 その部分に言及していただけるの、すごく嬉しいです。
穂村 表面は客引きという行為でありつつ、利害関係とはまた違うコミュニケーションというか、すごく魂が接近した瞬間になっている。その次のページの、コンビニで肉まんを食べるところの〈デラックスとかじゃない、普通の肉まん。〉も、デラックスだったら付記する意味があるけれど反転している。やっぱり普通の散文よりもエッジイに思えます。
大崎 今挙げていただいたところは、全部実際にあったことを書いた箇所なんですよ。短歌アイに発見された気がしました(笑)。穂村さんの歌論集『短歌の友人』に〈棒立ちのポエジー〉ということばが出てきますよね。それを見て、短歌の世界と現代詩の世界の近さを感じたんです。私が書き始めた頃、詩の世界の人たちが修辞をつきつめて展開していく流れがあったけれど、私にはそれが全然面白いと思えなくて。あくまでも手持ちの貧しい言葉から出発することでしか、自分の詩は書けないと感じていたので。
穂村 短歌の世界で大崎さんの世代の人たちが出てきた頃、最初は「フラット」って言われていたのね。そのフラットに見えたものが、実はことばを精緻に微細に動かすための原点みたいなものだと判明してきたのがここ15年くらい。それまでめっちゃ味の濃いものを良しとしていたから、味が淡すぎるように見えただけなんだよね。堀川正美の有名な詩の一節に「時代は感受性に運命をもたらす」ってあるけれど、今はそれが骨身にしみて感じられます。『シンジケート』を出した頃は欲望への肯定感があって、世界の資源は無限で取り合っても誰も困らないという感覚だった。でも、すべての資源が有限だっていう世界に生まれてきた世代は対人関係に対するフェアネスが全然違う。全員が乗っている方舟の中で勝手なことしたら未来が死ぬんだよっていう、そうした倫理観がある時から強烈になった。
大崎 私が「ユリイカ」の新人賞に選ばれた頃に震災があって、それからずっと災害が起き続けている中で書いている感覚があります。自分が息をするためにはどんな表現が必要なのか、ずっと探っている感じがありますね。
穂村 一方で、詩と短歌は違うなと思うこともあります。『踊る自由』の最初の三篇を読むと、最初の詩は読点を打ちそうな部分が一字空きになっていて、唯一〈私はただ、〉のところだけ読点がある。次の詩は句点はいっぱいあるけど読点がない。次は句読点はあるけれど改行がない。僕は詩によってそういうふうに変わることの必然性が充分には分からないんだけど、詩人同士は「それぞれの勝手でしょ」という感じで、そういう話をしている気配がない。
大崎 全然してないです(笑)。
穂村 歌人同士は一字空きの話とかよくするんです。互いに分からないと落ち着かない。僕は詩人たちがそういう話をしていなさそうなことが不満で、詩人たちがそれを不満と思っていないらしいことも不満なんだけど(笑)。
大崎 私は、その都度、声にしたときのリズムを一番落とし込める句読点を選んでいる気がします。〈ただ、〉は、そこでギアの変化を感じてほしいところ。語気がすこしだけ強くなるイメージです。
穂村 改行については?
大崎 私の場合は一行ずつカット割りする気持ちかな。映画の絵コンテみたいに、この一行で見せたいのはこういう動き、と。『踊る自由』では編集者さんもいろいろアイデアを出してくださって、改行なしの散文詩でも詩ごとに1行の長さを変えて、全体のリズムを多様にしました。そうすると文体もいろんな踊りを踊っているように見えるので。
穂村 『踊る自由』は大島依提亜さんの装幀もすごくいいですね。カバーのタイトルからしてちょっと文字がずれていて踊っているみたい。
大崎 ありがとうございます。


傑作を待っている!
穂村 詩って難しいものっていう印象になりがちですよね。もっと自由に読めばいいんだけど、多くの読者はひとつひとつの短歌や詩に解説がないとやっぱり不安みたい。でも、書き手は自分の詩集に解説をつけることには抵抗がある。だから、全員がアンソロジーを編むといいですね。自分が好きな詩を選んで解説を書く。そういう意味では僕たちが選んでいる「花椿」の詩の紹介は一種のアンソロジーみたいになってますね。選評といいつつ、読み筋を提示しているから。
大崎 責任を持って「私はこう読みました」ということを書いて、その中で疑問点や甘い部分を指摘するようにしています。
穂村 応募作を見ていると、すごくレベルが高いのに、ラストが惜しいものが多いよね。自分の文脈を信じ切れずに、着地で突然一般論が出てきたりする。そこまでの文脈だと「もう朝は来ない」という感じなのに、突然「明日も朝が来る」みたいになってねじれちゃっている。
大崎 そうなんですよね。もうひとつ私が気になるのは、社会の動きとか世間で言われていることを詩のことばに変換しただけのもの。他人のことばを再現しているだけだから、一見うまくできているけれど、スカスカしているというパターンがありますね。
穂村 あと1年選考を担当するけど、目も覚めるような傑作に出会いたいですね。世界の色が変わるような。そういう妄想をしちゃう(笑)。
大崎 そんな名作に出合えたら、私たちもハッピーですよね。

2021年8月31日17:00まで、
「今月の詩」の発展企画として、第4回「心にのこった詩はどの詩ですか?」を実施中です。
2020年7月~2021年に6月にご紹介した12篇の詩から、心にのこったお気に入りの1篇を選んでいただき、ご投票ください!
詩が読者のみなさまの身近な「ことば」になりますように。
投票はこちらからどうぞ
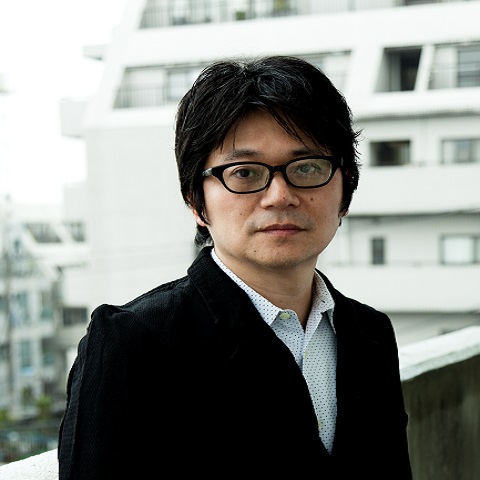
穂村 弘
歌人
1962年北海道生まれ。90年、第一歌集『シンジケート』を刊行。2008年『短歌の友人』で伊藤整文学賞を受賞。同年、石井陽子とのコラボレーションであるメディアアート作品『火よ、さわれるの』でアルス・エレクトロニカインタラクティブ部門栄誉賞を獲得。17年『鳥肌が』で講談社エッセイ賞、翌年『水中翼船炎上中』で若山牧水賞を受賞。歌集、エッセイ、評論、絵本、翻訳など多数。月刊誌『花椿』(12年~15年)での対談連載「穂村弘の、こんなところで。」もKADOKAWAより刊行された。

大崎 清夏
詩人
1982年神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部卒。詩集『指差すことができない』で中原中也賞受賞。著書に詩集『踊る自由』(左右社)、『新しい住みか』(青土社)、絵本『うみの いいもの たからもの』(山口マオ・絵/福音館書店)など。他ジャンルとのコラボレーションも多数手がける。2019年ロッテルダム国際詩祭招聘。女子美術大学非常勤講師。(撮影:黒川ひろみ)
https://osakisayaka.com/

瀧井朝世
ライター
作家インタビュー、書評を主に執筆。著書に『偏愛読書トライアングル』(新潮社)、『あの人とあの本の話』(小学館)、『ほんのよもやま話 作家対談集』(文藝春秋)。監修に岩崎書店「恋の絵本」シリーズ。穂村弘『穂村弘の、こんなところで。』(KADOKAWA)の構成・文を担当。