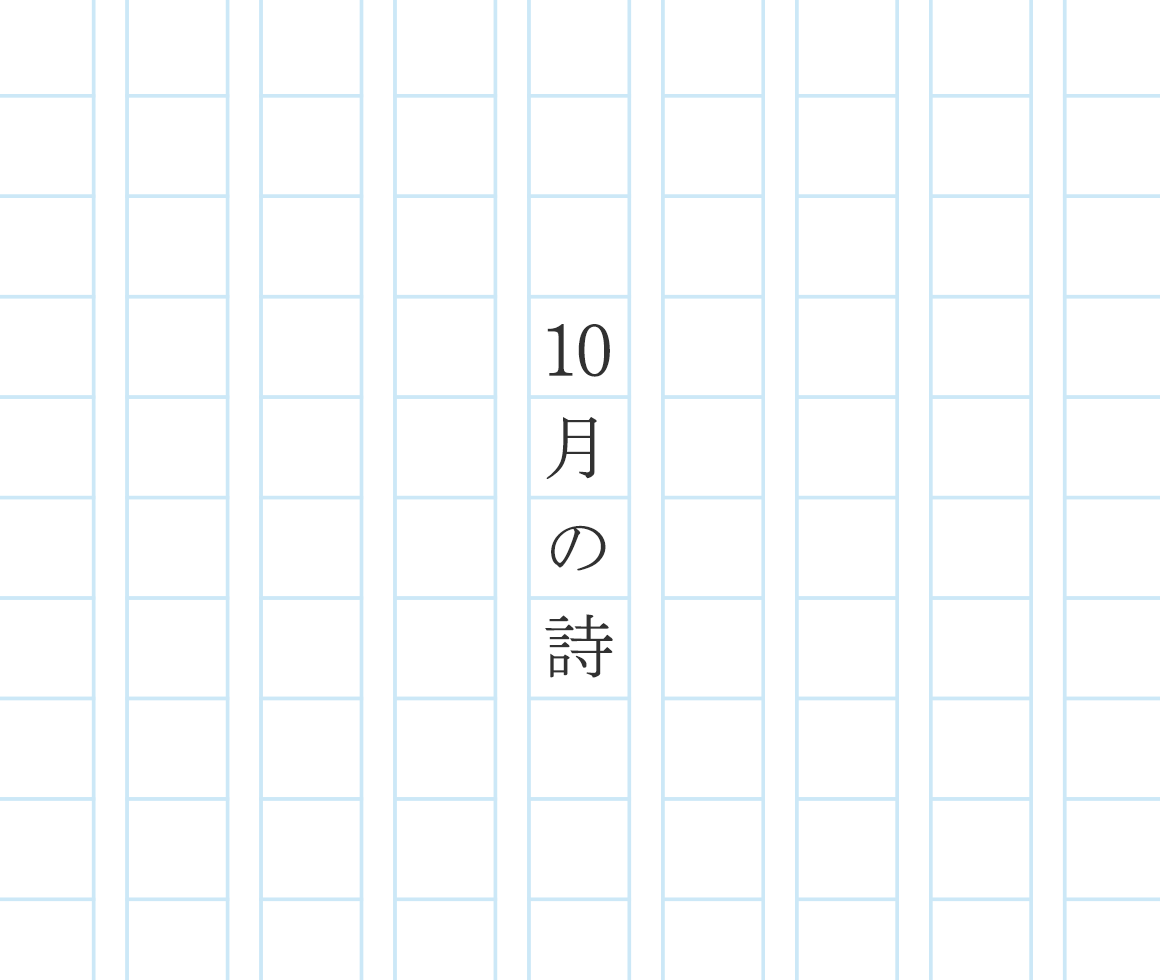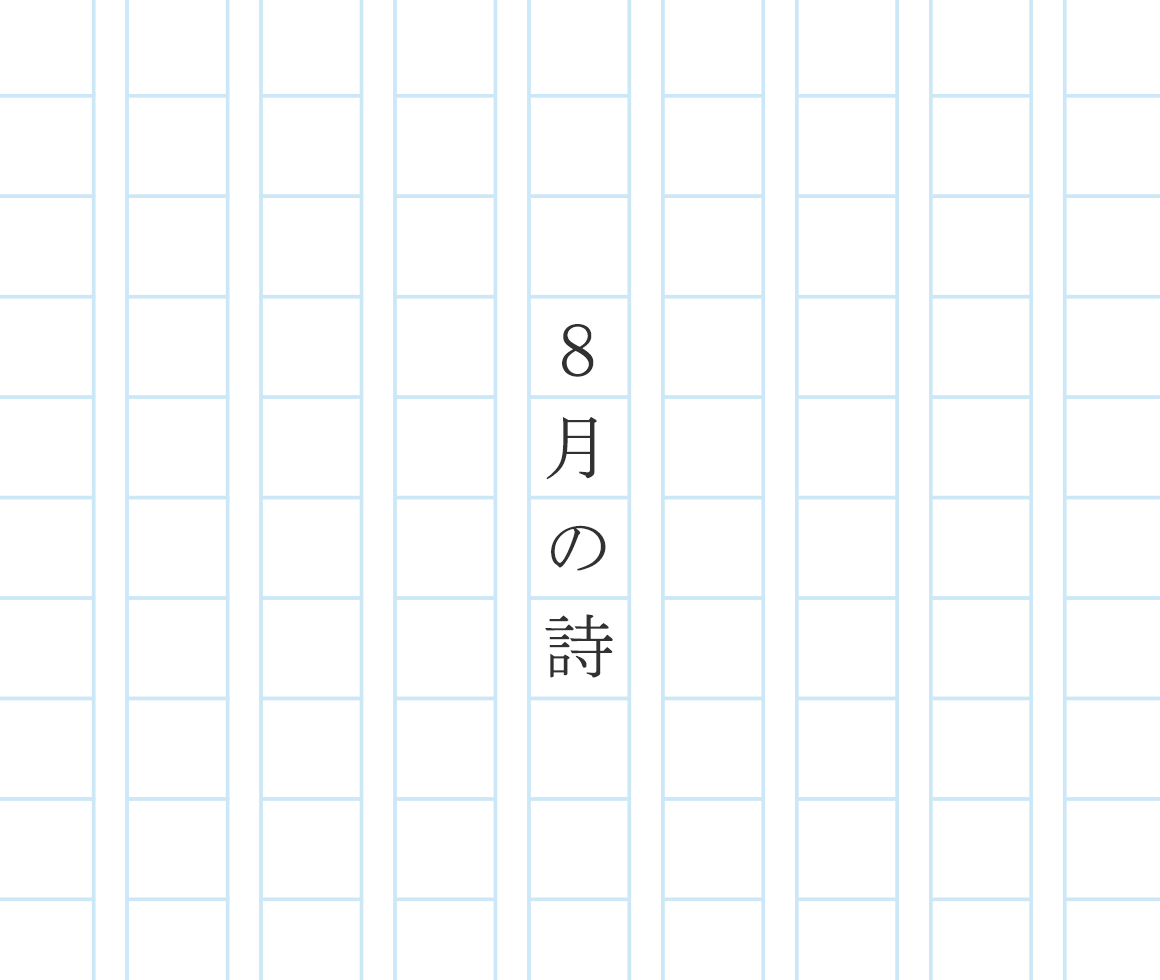父が階段を降りてきた
過去いくつもの太陽の匂いがしみ込んだ
ガーゼケットから顔を出す
床がきしむ音があって二拍すると
トイレのドアが開く
変わっていない
起きていることがバレないように
ゆっくりと寝返りを打つ
昨年からはじめた一人暮らしの部屋で
かたく目をつぶりながら
「ここは実家だ」
と念じてみる
そうすると二段ベットの柵や
隙間から光が差す重い雨戸が浮かんできた
水が流れる音がして
スリッパが擦れる音
換気扇を回すスイッチの音
回転をはじめる音
電気を消す音
開けるときは乱暴なのに
閉めるときは丁寧なドアの音
ひとつ咳払いをして
足音が三拍
洗面所のシャワーの蛇口で手を洗う
父がこの家を買って生活していく中で
手に入れた動作たち
私はそのすべてを覚えている
安堵感で手のひらがじんわりと熱くなり
ぺちゃんこの枕に押し付けた
父はそのまま階段を昇っていった
もう一度寝るのなら
まだ朝は来ない
再び静寂に秒針の音が響き
私は自分の身体を抱きしめるように
丸まって目を閉じた
選評/大崎清夏
夜中に起き出し、階段を下りて用を足す父と、その音を布団の中で聞いている私。淡々とした描写に、べたべたしない父娘の距離が丁寧に掬いとられている。娘である私が聞き取っているのは、長年繰り返されてきた父との暮らしのリズムが奏でる安定感や安心感だ。「二拍すると/トイレのドアが開く」「足音が三拍」。そのリズムの合間で「一人暮らし」や「二段ベッド」の数字がもっと大きな時間の推移を刻み、しれっとやっているけれど、これがしっかり裏拍として効いている。
第一連が実家の記憶だったと判る第二連では父の面影はすうっと遠ざかり、代わりに私の一人暮らしの部屋と実家の部屋が布団の中で重なる(実家を出て一人暮らしをしたことのある人なら誰にでも、身に覚えのある感覚じゃないだろうか)。三連目では音に付随した意味が順序立てて並べられ、父の動作や空気感がまた生々しくこちらに近づく。最終段落には「父はそのまま階段を昇っていった」とあり、うっすら死の匂いがして、父の存在がまたふっと遠くなる。時間の遠近感覚を狂わせるリズムの力にいつのまにか引きこまれて、そういえば人間は誰でもひとりぼっちなんだった、と思い出してしまった。