
90s in Hanatsubaki
2019.07.29
第9回 ガーリーカルチャーからスーザン・チャンチオロに出会う
文/林 央子
写真/細倉 真弓
以前、アート欄に定期的に執筆していた『GINZA』というファッション雑誌から久しぶりに連絡があって、インタビューを受けた。「一生ものの、本と映画と音楽とアート。」という新しいコラムに呼んで頂いたのだ。自分にとって「一生もの」は何かな? と考えるとき、映画や音楽はすこし考えて決めたけれど、アートについて迷いはなかった。スーザン・チャンチオロ。1996年秋にニューヨークへ取材に行き、『花椿』97年2月号の特集「ニューヨークのニューな部分」に登場してもらった人だ。当時は、新進ファッションデザイナーだった彼女も、2017年にはニューヨークのホイットニー・ビエンナーレの招待作家となり、所属ギャラリーもきまって、今ではしっかりと現代アートのシーンを軸足に活躍するようになった。長くファッションとアートの両方の世界にいて仕事をしてきて、領域を越境している人特有の不定形な魅力もあり、また苦労もたくさんあったと思うのだが、彼女はずっと、私にとっては、生粋のアーティストというべき存在だった。

「私にとってはアーティスト」という人が、私のまわりにはいっぱいいるな、ということに最近、気がついている。とくに90年代の、私がその後仕事をしていくうえで重要な人たちに出会って行く段階で、とても魅力を感じた存在というのはほぼ全員が、いわゆる"現代アート"の分野でアーティストとして活躍している人ではなかった。けれども、その人ならではの独創性、自由を愛する心、ジャンルを超えたボーダレスな活躍ぶりなど、「どう考えてもアーティストにしか思えない、私にとっては」という人たちと、『花椿』の仕事を通して何人も出会っていった。マイク・ミルズ、エレン・フライス、そしてスーザン・チャンチオロなど。
なかでもスーザンとの出会いと、その後彼女とした仕事は『花椿』を軸に展開していった。だから、ぜひこの連載に書いてみたいと思う。まずは出会いの前の編集部の状況や、90年代半ばごろの自分の関心事について振り返ってみたい。
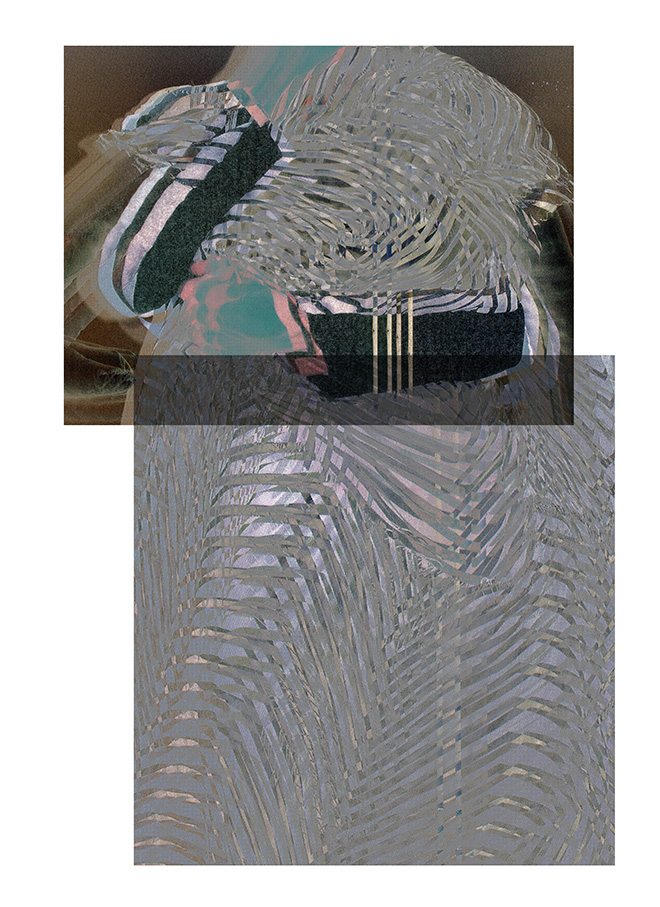
スーザンと出会いのきっかけには、90年代に私が興味をもった、ガーリー・カルチャーがあった、と言えると思う。『花椿』95年9月号のインタビュー欄で、ソフィア・コッポラを取材したころのエピソードに遡ってみよう。当時私は、海外の雑誌を読んでは面白かった記事を編集部内で報告する役割を担っていた。ある日、そこで見つけたのが、X-girlというブランドを、ソニック・ユースのキム・ゴードンがはじめた、という記事。X-girlのことは『Vogue』や『Harper’s Bazaar』から『Interview』などのカルチャー誌、ほかにも若者むけの音楽雑誌まであらゆる媒体に記事をみつけることができた。キム・ゴードンが所属していたソニック・ユースというバンド(1981-2011)は、80年代にはオルタナティブ・シーンの知る人ぞ知る存在だったが、90年に彼らがメジャーのゲフィン・レコードに移籍して初のアルバム『Goo』を発売したころから、さまざまなメディアで名前を見かける存在になっていた。私が『花椿』でソフィア・コッポラのインタビューページをつくることが出来たのも、ソフィアとキム・ゴードンの2人がX-girlのファッションショーのために、川崎のクラブチッタに来日したからだった(キム・ゴードンもその機会に『花椿』の「萬有対談」で後藤繁雄さんに取材していただいた)。キム・ゴードンはその取材の場で、これから注目するべき若い女性アーティストを惜しみなく紹介してくれたのだが、彼女は普段から雑誌などでも同様のコメントをしているようで、とくに90年代のアイコンでもあった(のちに自死してしまう)ミュージシャン、Nirvanaのカート・コヴァーンは、まさにソニック・ユースのサーストン・ムーアとキム・ゴードンによって紹介されて、瞬く間にスターになっていった存在だった。
キム・ゴードンが目をつけた人に間違いはない。そういう信頼のある人だった。事実、私はソニック・ユースのかなり昔の白黒のミュージック・ビデオで、まだ誰も話題にしていなかったころのソフィア・コッポラを観た記憶がある。ミュージシャン(ビースティ・ボーイズのマイクD)が運営に参加していたスケートボート・カルチャー・シーンのファッションブランド、X-largeの女の子版ができるからやらないか、という声がキム・ゴードンにかかったとき、キムがソフィア・コッポラをファッションショーのプロデューサーに招いた、という経緯も興味をひいた。そして、いろいろな記事をしらべていくとほかにも、たくさんの気になる固有名詞がでてきた。マイク・ミルズ、クロエ・セヴィニー 、リタ・アッカーマンetc.。ソフィア・コッポラは93年のX-girlのファーストショーに関わったあと、自分でもファッションブランドを立ち上げる、と言って95年に、ミルクフェドをはじめていた。
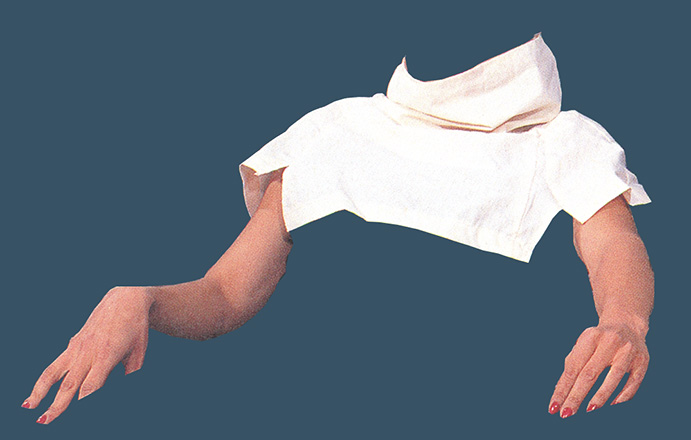
キム・ゴードンやソフィア・コッポラのスピーディーな動きに象徴されていたものは、D.I.Y.の精神だった。フォロワー数が多いから、有名人だからブランドも簡単に始められる、などという感覚では全くなかった。やってみたいと思ったなら、人にどうこういわれるより前にやってしまおう、という、自分軸で生きて行く女性たちの格好良さがあった。そしてそんな彼女たちの姿勢への憧れが、当時のガーリー・カルチャーを引っ張っていた。私もそのうちのひとりで、ソフィア・コッポラがLAで構えていたミルクフェドの事務所(ソフィア・コッポラと友人で同僚のステファニー・ハイマンがたった2人でやっていた、マンションブランドの規模のオフィスだった)まで、雑誌をつくっている友達と一緒に取材しに行ってしまう、という行動力を発揮したくらい、そのカルチャーの流れが気になっていた。もちろんそこまで行ったのは、当時の『花椿』の仕事とは無関係で、休みを利用しての趣味の旅といったところだったのだが。
そんな90年代半ばの私の活動は、時に『花椿』の誌面に足跡を残すことができたけれど、最初のうちはとくに、『花椿』では記事をつくることができず、もっぱら同世代の友達と顔をあわせる部活で本当に好きなことをする、という感じで、友達の林文浩さんが手がけた『DUNE』というファッション誌に、ガーリー・カルチャーについてのコラムを書かせてもらったりしていた。そのうちに林文浩さんと、X-girlの周辺にいたことをきっかけに『花椿』でも取材した結果、とても尊敬と興味を抱いた人物であるマイク・ミルズから、「ニューヨークにすごくおすすめなファッションデザイナーが現れたよ! ぜひ取材するといいよ!」と言われた。それが、スーザン・チャンチオロだったのだ。
『花椿』とアメリカン・カルチャーの距離
スーザン・チャンチオロと出会いの号になった97年2月号の『花椿』は、私がはじめて企画した特集を誌面で実現できた号だ。入社9年目にして初めて自分の企画が通るというのは、編集以外の仕事ならよくある話かもしれない。けれども編集の世界ではそうではないはずだ。当時私のまわりには20代ですでに編集長をやっていた同世代がたくさんいて、自分の思うままに企画を組む自由を得ているようだった。もちろん制約などもあったのかもしれないが、私にはそう見えていて、自分が面白いと思うことに堂々と誌面をさける彼らのことがいつも羨ましかった。
『花椿』は90年代に大きな変化を迎えていた。私が入社したころの編集長であり、1960年代以来長年『花椿』に所属していて、長い間実質的な編集長を担ってきた平山景子さんにかわって、やはり『花椿』に在籍が長かった小俣千宜さんが編集長になって、93年4月号から誌面リニューアルを行っていた。ADはかわらず仲條正義さんだったから、外からはどう見えたのかはわからないけれど、編集部という雑誌の内側にいた自分にとっては、それはとても大きな変化だった。というのも、小俣さんはファッションを見ない立場の人だったから。編集長を退いてからも平山さんはファッション・ディレクターの立場で『花椿』にかかわっていた。平山さんは長らくパリコレに通い続けてきた人だったし、そのパリコレ出張中に平山さんが築かれてきた人脈は、『花椿』の屋台骨になって、その質をしっかりと支えていた。小俣さんが編集長になって、パリコレ出張に私も連れて行ってもらうようになると、ヨーローッパは個人への信用からすべてが始まる社会なんだということを知り、日本とは全く違う社会のしくみを垣間みた気がしたものだった。それだけ平山さんが個人への信頼によって築いてきた世界は、大きかったと思う。
とはいえ私たちで『花椿』をつくっていかなくては。という立場になって思い知ったことは、自分の個人的な興味と、媒体が提示する世界には距離がある、ということだった。当時の私が興味をもったのはストリートファッションで、『花椿』はパリコレのモードを報道していた。都市でいえばパリとロンドンの動向を追いかけるのが『花椿』だったが、私は当時LAから発信されていたユースカルチャーやオルタナティブ・シーンに興味があって、そこからたどり着いたキム・ゴードンやソフィア・コッポラ、マイク・ミルズといった人たちの活動に興味をもっていた。

そこに「モード」があれば、『花椿』でもそれほど苦労しなくても、取材の対象になったかもしれなかった。けれども、そこにあったのはより消費に近いファッションであり、ジャンルを乗り越えて活躍しようとしているD.I.Y.的な個人の姿だった。当時、ずっとキム・ゴードン、ソフィア・コッポラ、マイク・ミルズと言っていた私に対して、「なんで林さんはそんなにアメリカに興味があるの?」というのが編集部の空気だったと思う。それは職場の常識からいったら、かなり的外れなことで、突拍子もないことだった。けれども、時代の勢いというものがある。97年、あの古くさいパリの街にコレットというセレクトショップが生まれた。ハイモードと同時にスニーカーや音楽、日本の雑誌や写真集も扱い、アーティストの本も扱うと同時に、注目の新しいファッションも扱うというブティックで、開店当時バイヤーのサラは「パリにはオルタナティブ・シーンのレコードを買える場所がないからつくりたかったの」と言っていた。
SNS時代を迎え、コレットが2017年末に閉店した今、こんな記事がどう読まれるのかはわからないけれど、「その時代その時代のあたり前や、新しいものはどんどんくつがえされていくし、変わっていく」ことの例証として受けとめてもらえたらいいのかな、と思う。このように、90年代後半には、アメリカから出てくるカルチャーシーンに注目することは世間的にはそれほど逸脱的なことではなかったと思うけれど、モード志向でありヨーロッパ志向だった『花椿』においては、周囲の人たちに熱心に働きかけ、説得しないと実現できないことであった、ということだ。Instagramで即座に外国の人とつながっていく今は、カルチャーマップを国別に意識することなど、あまりなくなったのかもしれないけれど。
(次回につづく)

林 央子
編集者
1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)
http://nakakobooks.seesaa.net/
https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓
写真家
東京/京都在住
触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。
http://hosokuramayumi.com
















