
90s in Hanatsubaki
2022.03.14
第20回 マルタン・マルジェラと『花椿』の90年代 ―脱構築とは何か? その2
文/林 央子
写真/細倉真弓
1993年からパリコレに行くようになると、日本にいてパリコレのファッションだと思っていた文化は新規なファッションであって、その奥にはそれほど素早く変化はしないモードの世界が広がっていることを、私は察知した。当時の日本人は、海外の新しいファッションの話題にも好奇心いっぱいに反応していたけど、そうしたファッションへの興味は、世界においてはむしろ例外的なのかもしれなかった。けれども、なかには人と違うことを恐れない姿勢をファッションにもたらした、稀有な存在もいた。際立っていたのは、82年にパリコレにデビューしたコム デ ギャルソンと、88年秋からパリコレに参画していたマルタン マルジェラだった。彼らの仕事はよく”脱構築”と評されたが、それを平易な言葉で置き換えれば「人と違うことを恐れない」姿勢だったのではないかと思う。

パリコレに行き始める前の私にとってマルタン マルジェラは、「イン・ファッション」の編集会議や『花椿』の記事で見聞きするだけの存在だった。当時、渋谷にはパルコの手前にシードという先端的なファッションブランドを扱うビル(現在は無印良品がテナントになっている)があって、その2階に、うすぐらい照明のもとで、エッジーなインポートブランドの服が限られた点数、セレクトされたものが吊り下がっていた。マルタン マルジェラはダラーンとした暗い感じの服で、そのチープな素材感からすると信じられないくらい高価な値段がタグについていた。「どうして?」と思いはしても、先輩編集者の、普段は古着やパリでしか買えないイリエを粋に着こなしていることの多い渡辺さんが時々マルジェラを着ているのを見て、「だからきっと、格好良い服ということなんだろう」と考えるようにしていた。編集長だった平山さんは、着ている服のブランドが一目瞭然なのは嫌だといって、いつもパリのお友達の入江末男さんがデザインするイリエの服がワードローブだった。平山さんは初期から、メルカさんも大絶賛の、もとジャン=ポール・ゴルチェのアシスタントだった(故に正統的なパリモードのつくり手としての実力があるとみなされる)マルジェラを評価していたけれど、自分で着るようになったのは、編集長職をはなれてファッションディレクターと名乗るようになってからだったと思う。
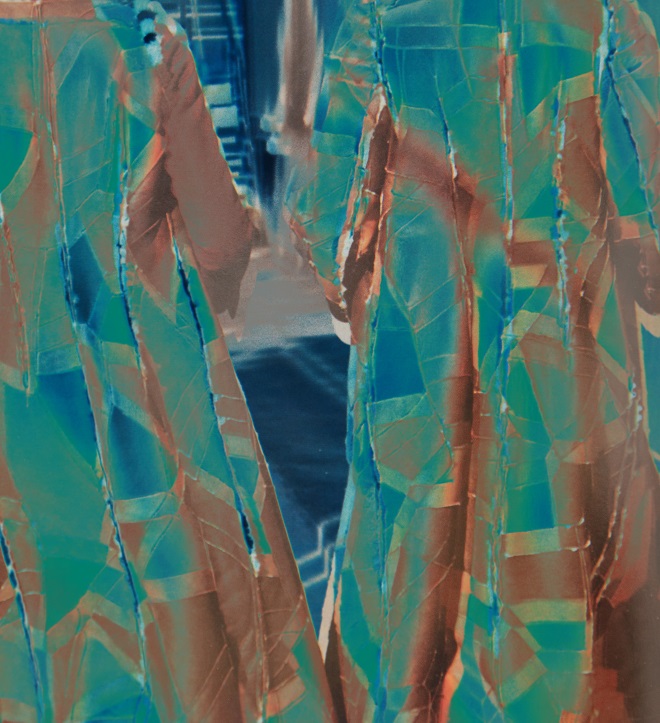
最近見た映画『マルジェラが語る “マルタン・マルジェラ”』*(脚注参照)によって、このブランドのヒストリーをより明快に、デザイナーの説明から知る機会を得た。わたしが初めてパリコレに行った93年10月は、マルタン マルジェラがデビュー5年目を迎えており、時期としては最初無名だったこのブランドの人気が急速に上昇し、発表当初は理解されなかったデビュー当時からのくるぶし丈のロングシルエットのコピーが出回って、その現象がデザイナーを悩ませていた時期にあたったようだ。そこで、過去のコレクションをすべてグレーに染め直してタグに発表年を刻印し、ファッションショーは行わず展示会とフロアショーという形式でプレスやバイヤーを招く、という形での新作発表を行っていた。はじめて体験するマルタン マルジェラの新作発表会場にいたモデルたちは、素人の業界関係者などだった。後々、私がパリコレ出張のたびに出会っていく編集者やカメラマン、ファッションデザイナーなどから「私、あのときのマルジェラモデルだったの」という話を、聞くことになっていく。『Purple』(当時はまだ創刊したばかりで、『Purple Prose』と名乗っていた)編集長のエレン・フライスも、このシーズンのモデルをつとめていた。デザイナーによってスタイリングされ、生身の女性たちの身体によって着られた服は、店にダラリと吊り下げられた服とは違い、マルタン マルジェラという未知な謎めいたブランドの魅力を、説得力をもって伝えていた。
マルジェラの発表では驚かされることがたくさんあったけど、その時私が驚いたことの一つは、ファッションショーに代わるそのシーズン唯一の発表の場であった展示会場の去り際に、メゾンのスタッフが「気に入った写真を選んで」と、マリナ・ファウストやアンダース・エドストロームが撮影した写真の入った箱を差し出されたことだった。
ショーを行えば、そのショーでキャットウォークを歩くモデルを正位置から撮るカメラマン席が決められており、そこで撮られたカットが世界に伝播するというファッション業界の定石があった。しかし、このときのマルジェラのようにショーを行わないという型破りな見せ方においては、メゾン側が何も手を打たなければ、どこでどんな瞬間を報道用に撮られてしまうかは、わからないことになる。そこで先手をうって、招待された記者がメモ的に撮るのは自由だけど、誌面に露出する際には自分たちが用意したイメージを使ってくださいね、という方法をとることにしたのだろう。こうした「個別ルール」もパリコレで発信されることが普通だったから、日本ではなかなか顔をあわせられないメゾンのプレスやデザイナーと、顔をつきあわせて信頼関係を構築することが、パリコレ期間中の両者にとって重要なことだった。SNSが登場したことによって、こうした情報伝達の仕組みは世界的に更新されていくのだが。

こういう、新規のファッションブランドとして、メディアとの付き合い方を構築する上でかつてない行為を行うときも、マルジェラのスタッフがそう申し出るときの態度は、あくまでフレンドリーだった。写真の選択肢をたくさん取り揃えておいて、そのなかから「あなたの好きなものを選んで」というように、判断を記者や媒体に任せた。その瞬間、メゾンがすでにレールをしいたイメージからしか選べないという不自由を、記者自身が数点選択するという行為によって逆転させ、報道する側も主体性を発揮できるという機会を与えられた感覚があった。そうした細かい気配りによって、プレスも知らず知らずのうちに、マルタン・マルジェラという、いわばパリコレの掟破りの共犯者になっていた。
映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、ファッションのシステムのなかで、その内側にいながらちょっとした行為で、先例とは違う選択をして、結果システムを変革した。それが90年代マルタン・マルジェラの「脱構築」だった、ということも再認識させてくれた。たとえば、白い空間をめぐるエピソード。彼がブランドを始めた当時、ファッションブランドのプレスルームといえばコンクリートの壁に黒い家具、というのがお決まりだった。それを変えたくて、家具や壁だけでなく「全部白く塗る」ことにした、という話。パソコンも、電話機も、そこにあるもの全部が白い布で覆われるか、白いペンキで塗られた。スタッフの制服も白い作業着だった。白、白、白。徹底してどこもかしこも塗り尽くす、覆い尽くすという行為によって、そこには一種不思議な風景が立ち現れていた。映画の冒頭でマルタンが語る、シュール・レアリスムへの傾倒が、その実践の背後にはあったかもしれない。シュール・レアリスムは彼の出身地であるベルギーから生まれた美術運動である。

映画では、マルタンの肉声で、82年にパリコレデビューしたコム デ ギャルソンへの興奮が語られていた。コム デ ギャルソンのパリコレへの登場によって「かつての憧れの対象は全部過去になった。未来が現れた。ショールームや店舗やカタログが変わった。そういう変化はモデルの雰囲気や歩き方にまで及んだ。強烈だったよ」とマルタンの肉声が語っていた。80年代前半にコム デ ギャルソンがパリコレを舞台に行ったファッションへの変革への姿勢を、80年代後半にデビューしたマルタン マルジェラは受け継いで、さらなる変革を重ねていった。その両者の脱構築の背後には、連綿と続くファッションという文化があって、そこに対する異議申し立てや別の方法論の模索が行われていたのだった。
それはファッション雑誌や女性誌に対して『花椿』が行ってきた変革への姿勢と似ていたのではないだろうか? 当時は月刊誌とはいえ、40数ページしかない薄い冊子であった『花椿』は、女性誌というものの要素と徹底的に向き合い、それを別なやり方で解釈して実践していたように思える。女性誌にお決まりの要素といえば、たとえばファッション、それだけでなく旅や食の話題、などがある。その最新情報を追いかけるのがファッション誌かもしれないが、『花椿』はそこに歴史という深みを加えることで、情報の量ではなく情報の質で差別化していたのではないか。たとえば、20世紀前半の歴史上に生きたヨーロッパの女性たちの、当時にしたら相当思い切った行為である旅とその人生を綴った海野弘さんの「旅をする女」。フランスのワインとチーズと食のルポルタージュを自分の足と舌と手で記し、食の本場から発信したパリ在住の増井和子さんによる「ワイン&キュイジーヌ」。シネマに関してはフランス人のダニエル・エイマンがヌーヴェル・ヴァーグのみならず90年代に新興してきたアジア映画やイラン映画の動向を定期的にレポートしていた。とくに80年代から90年代にかけての『花椿』の変遷をふりかえると、「女性誌を脱構築していたのが『花椿』だった」、ということができるのではないかと思う。
言うまでもないかもしれないがこの映画は、現役中は、プレスの前に姿を表さないデザイナーでい続けたことで、ミステリアスなデザイナーだといわれたマルタンが、はじめて自分の肉声でブランド創世記から退役までを語ったことで知られた映画。88年秋に89年春夏コレクションでデビューし、90年代の生き生きとした実験的行為を重ねたのち、資金難からディーゼル社に買収された2000年代の混迷を経て08年、20周年のファッションショー終了後、スタッフに告げずに引退するまでが回顧された。この記事を書いていた21年秋、パリの美術館Lafayette Anticipationsで現代アートのアーティストとして個展を開催。引退後初めての公的な活動として、注目を集めた。

林 央子
編集者
1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)
http://nakakobooks.seesaa.net/
https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓
写真家
東京/京都在住
触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。
http://hosokuramayumi.com
















