
90s in Hanatsubaki
2022.06.30
第22回 最終章 物質文化を超えて。時代の変化のきざしを、ファッションから見つける その2
文/林 央子
写真/細倉真弓
先日、 今年の正月から企画をあたためてきた、トークイベントのシリーズ第一回を行った。これは、昨年私が出版した、インタビューを集めた本『つくる理由』で提案した、一人ひとりが暮らしのなかで「ものをつくる」ことの意義を、ゲストとともに再考するトークの企画だ。一回目に迎えたゲストは、ニット作家の保里尚美さんだった。彼女は広島で編み物教室をしながら、企画展での展示販売と、受注したセーターを編むことで生活している。
保里さんは一昨年前に、やはり私が翻訳して出版した『エレンの日記』というエレン・フライスのエッセイ集を愛読していて 、Twitterで彼女が本の感想をつぶやいてくれているのを私が見つけて、SNS上で言葉をかわしていた。昨年末には、彼女の『働くセーター』をきっかけに大規模なブックフェアが無印良品の京都のお店で開催されていて、そこで保里さんが『つくる理由』と『エレンの日記』を、おすすめの本として紹介してくださっていたことを友人を介して知り、またSNS上のやりとりが始まった。そこから、なんと元日に、保里さんが送ってくださった、仕事着としてのシンプルなセーターやベストの編み方を紹介する本をつくった保里さんご自身の本『働くセーター』が届いた。それを開いたことをきっかけに、これまで『花椿』での試行錯誤にはじまって、そこを離れてからも、私がエレンの文章を翻訳したり、エレンとともにさまざまな活動をしてきたことの延長線に、というかその最前線の活動に、保里さんの、手編みのセーターのレシピ本を位置付けることができると、直感的に理解したことからの、イベントだった。
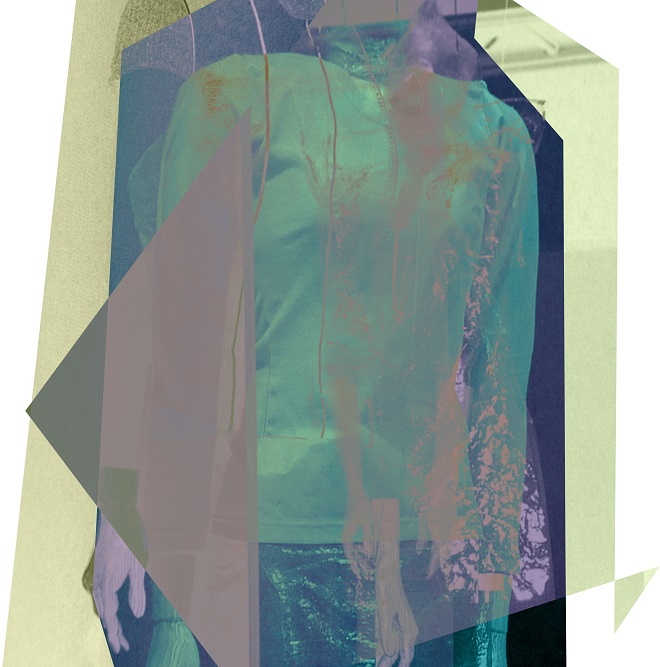
広島に住む保里さんと、東京にくらす私と、愛知県から東京に引っ越してきたばかりでカフェを制作準備中でイベント企画者の熊谷さんが3人で、それぞれの場所からズームでつながり、発信するイベントは、90分間話終わるまでが、互いを知るための時間に費やされ、お互いに慣れてきたころに、イベントが終わった。話し切らないこともたくさんあったけれど、お互いに頭に浮かんだことをぽつり、ぽつりとSNS上で発言してきた一週間の後半に、保里さんが見つけ出して紹介してくれたのが、2008年『暮しの手帖』夏号の巻頭特集「服とわたしの物語」という記事だった。書いているのはエレン・フライスで、企画・編集構成は私。保里さんがエレンと私の仕事に出会ったのが、今から約15年前に私が企画したこのページだったことを、トークの後思い出した、ということをSNSに書いてくれていた。
エレンがワードローブの中でお気に入りの服をセレクトし、自宅の空間でその服を友人のレティシアに撮影してもらう。小さい情報欄としてではなく、一ページに服が一点と、エレンの縦書きの文章で見開きを構成する、というつくりの15ページ特集だった。私が資生堂『花椿』編集室を2001年に離れて、フリーになってからパリコレに行きはじめた時、マレ地区にあるエレンのアパートに泊めてもらう、ということをしていた。全行程だと一週間ほど長さになるから、最初の数日間だけ泊まって、その後はアパートホテルを借りて。その後2003年には息子が生まれたので、以前のようにパリコレに行くことが難しくなった。行けなくなって懐かしいと思うのは、ファッションショーの場ではなく、マレ地区にある、青いペンキがぬられた重い木製のドアを押して中庭に入る、大きな古い共同住宅の2階にあるエレンの部屋だった。彼女はこの場所を、身寄りのないジュエリーデザイナーの男性から遺産として譲り受けたということだった。

特集を掲載した『暮しの手帖』は、私が子供のころ70年代に母が定期購読していたから、私も子供時代に読んでいた雑誌だった。第二次大戦後に創刊され、暮らしについて実直に考え、有用な情報を提供することが目的の媒体で、それゆえに広告を掲載しない編集方針を貫いていたから、いわゆるファッションというイメージから一番遠い場所にあるような長寿の女性誌だといえるだろう。「暮し」という誌名の古い仮名遣いからも長い月日を感じるその媒体が、リニューアルを必要とする時代になり、一族会社に招かれた新しい編集長が私を指名してくれて、仕事をし始めたのが2007年末だった。最初に頼まれたのは、イギリス人の女性ファッションデザイナーをインタビューして執筆する仕事で、その次に私は自分が考えた編集企画を提案する場を与えられた。そこで提案したいくつかの企画案を「連載にしませんか?」と誘われて「暮らしの風景」という6ページ連載が34号から始まっていた時期だ 。
子どものころから読んでいた雑誌に参加して、ページをつくることができるというのは大きな喜びであり、期待もいっぱいあった。私だからこそできるのは何だろう? と考えたときに、『花椿』の仕事のなかで取り組んでいた、ファッションのルポルタージュということが頭に浮かんだ。エレンも、私も、パリコレの場を通して出会い、そこで関係を培ってきたということができる。フランス、そしてパリといえばそもそもファッション文化を育んできた土地柄である。その街に生まれて育ったパリジェンヌのエレンが、ファッションをどう見ているか。私が『花椿』というメディアで工夫しながらパリコレのレポートを書くことはあっても、自分らしさをまげることのないエレンが普通のファッション情報記事を書くとはとても思えなかった。でも、彼女の自宅のなかで、彼女の大好きな服についてなら、書いてくれるのではないか? 私もそれを読んでみたい。ポリシーがある人の確固とした声だからこそ、聞いてみたいと思う時がある。世の中に先が見通せない不安が広がって、混沌が溢れる時などだ。
エレンはここで、コズミック ワンダーのドレスやスーザン・チャンチオロのスカートなどお気に入りの服を紹介したが、なかにマルタン マルジェラのセーターが1点含まれていた。その紹介文は、一時期惚れ込んだマルタン マルジェラへの感情が、数年前に終わってしまったことから始まっている。「少しずつ、マルジェラの新作はかつてのそれの青ざめたコピーとなり、自分自身のパロディーとなった」「マルジェラの変貌について責任があるのは、金銭にむしばまれた時代とファッション界だ。今日、成功しそれでいて成功による影響に抵抗することは、不可能に近い」とエレンは書いた。最後は、「私はマルタン マルジェラの服のほとんどを売ってしまった」とある。この『暮しの手帖』夏号のエレンのエッセイが出たあと、迎えた秋のパリコレを舞台に、マルタン・マルジェラの突然の引退劇が起こった。
雑誌から一人の人間が離れ、そしてまた別の雑誌と出会い、その場所だからこそできるブランド批判を含む記事を企画して、友人の力を得て15ページにわたる事「服とわたしの物語」が生まれた。そこに書かれていたことは、広島でその雑誌を手にとった保里さんも認めるように、多くの人の心に強く響いた。さらには、その雑誌が日本の書店に並んだ数ヶ月後に、パリでマルタン・マルジェラが誰にも告げずに引退した。さらには、その頃から日本でも世界でも続々と、インターネットの台頭により紙の雑誌の存続が難しくなり、次々とおなじみの雑誌の数々、『ハイ・ファッション』や『流行通信』、『スタジオ・ボイス』などが廃刊や休刊になっていった。

保里さんが 見つけ出してくれた15年前の『暮しの手帖』は、自宅に2冊あった。かなり久しぶりにそのページを開いて読んでみると、最近自分で企画したゲリラ的な『ハンカチ文集』の制作が思い起こされた。今世の中で起こっていることに反応し、編集という技術を通して、自分の表現したい世界を形にする。それは自分がずっとやってきた雑誌編集ということだったのではないか。私の場合、個人雑誌の『here and there』以外では、編集長の座についたことがない。それが幸いして、雑誌媒体という社会的な要素のある「器」に、自分のアイデアを鋭く差し込むことで、人の印象にのこるものをつくる、という技術が体得でき、またそれをさまざまに応用することができてきたのではないかと思う。
『ハンカチ文集』では、映画の公開とそれにまつわるプロモーション活動という、 雑誌をつくっていると身近な場所で日常的に展開されている、試写に行くことや映画についてのコメントを書く行為を、アーティストの友達をさそって一緒にハンカチをつくるという形でやってみる、ということをしている。4年前にソフィア・コッポラの映画『ビガイルド 欲望のめざめ』のときに初めてやって、今年はアマリア・ウルマンの初監督映画『エル プラネタ』公開時に二度目の展開を行った。情報が集まってくるタイミングに、メディアとはまた違った角度で利用して、面白いことをやってみよう、と提案するものだ。

こうした、日常身近にあるものを別な形に利用できないかな? という面白いアイデアを考えることが、私は好きだ。雑誌もハンカチも、私たちの生活の身近にあるものだ(もはや、紙の雑誌はそうではないかもしれないけれど)。そうしたところから、自分たちの生活を、ちょっと変えてみることの提案なのだが、ライターとしての私がすることといえば、試写にいくためや執筆行為のために集める情報を、友人と共有したり彼らを誘ってみるという、簡単なことにすぎない。もちろん、私のいる業種はちょっと特別だといえるかもしれないが、行為自体は応用可能で、自分が詳しく知っていることを誰かに教えてあげたり、自分が知らなくて困っていることを人に聞いてみる、ということでしかない。それを気軽に行うことで、「もっと一人ひとりが生きやすくなるんじゃない?」という提案でもあると思っている。
次回につづく。

林 央子
編集者
1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)
http://nakakobooks.seesaa.net/
https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓
写真家
東京/京都在住
触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。
http://hosokuramayumi.com
















