
90s in Hanatsubaki
2022.01.21
第18回 『花椿』とは何だったか? その3:パリコレと私
文/林 央子
写真/細倉真弓
前回記事はこちらからどうぞ。
年二回のパリコレ取材は重労働だった。ファッションショーは1時間遅れが普通だし、ルーブル地下のメイン会場から、さまざまなデザイナーが外に出て自分の理想とする会場を選び取っていたから、ファッションショーの期間は一日中移動が大変だった。人気のデザイナーのショーであれば見たい人が大勢いて競争になるけれど、デザイナーがみんな、大規模な会場を借りるとは限らない。たとえばヘルムート ラングは90年代半ば、3区のrue comminesにある会場で毎回ショーを行っていたけど、たいして大きな会場ではないからいつも、ショーの前後には車道にも人があふれて、ヒヤヒヤさせられた。日本だったら安全性が疑問視されたり、許可がおりずに実現できないのではないだろうか、と思えるショー会場もたくさんあった。
ネットでショーが配信されるようになる前のことだ。日本もデザイナーズブランドのブームが訪れた80年代以降、新しいデザイナーがパリコレで話題をよぶと、必ずといっていほど、日本人が主要な顧客になった。ジャン=ポール ゴルチェも、ロンドンからキャリアをスタートさせたヴィヴィアン ウェストウッドもそうだった。それでも、パリコレ会場で日本人のバイヤーやジャーナリストに与えられる席は末席だった。ショーのあと、平山さんがいつも同行しているお仲間たちとファッションショー談義になった。彼女たちが「素晴らしい」というモードのよさが、私には全然わからないことがよくあった。もちろん例外もあって、マルタン マルジェラや、コム デ ギャルソンには感動した。けれども、パリコレのショーの数はとても多く、そのような実験精神にみちたエキサイティングなショーばかりではなかった。いつの世も、どのジャンルでも、人と違うことをするのは、勇気がいることなのだ。

社内では、「パリコレに連れて行ってもらえるなんて」という羨望の眼差しもあったし、なにより、贅沢をしているんじゃないかという誤解をうけることもあった。でも、パリコレに行くにつれて、反動のように渋谷の街でみる日本人の若い男女のストリートファッションに夢中になっていく私がいた。渋谷系といわれる音楽が90年代初頭からブームになって、日本人のバントの音楽をファッショナブルなものとして、日本人の若者が聴くようになっていた。これは新しい現象だった。それまでの時代は、おしゃれな若者が聴くのは洋楽だと決まっていたからだった。音楽の聴き方が変わってくると、日本人ミュージシャンが被写体になった写真を見ることになり、日本人にとって日本人が憧れの対象になる流れが自然に出来上がっていた。並行して1989年に創刊された『CUTiE』など、岡崎京子の漫画にインスパイアされたような、日本人の女の子を表紙にした、新しいタイプのファッション誌も登場していた。この勢いを無視して、「パリのモード」だけを信奉し続けることが、時代にそぐわないのではないかと私は思っていた。
ファッションが文化になるまで
そんな思いは、編集部のなかでは異質なものだった。平山さんはつねにパリ・モードこそ最も見るべきものとしていたし、仲條さんや小俣さんにとってみても、ストリートファッションの台頭は受け入れ難いものだったと思う。わたしは編集会議などではよく、モードとカルチャーを一体視していると批判された。編集会議などで、仲條さんは、諦めたような口調でよく言った。「林さんはアヴァンギャルドだから」。私自身にしてみれば「どこがアヴァンギャルドなんだろう?」という感じだったのだけれど。もちろん、『花椿』らしい価値観を共有しているフォトグラファーの筆頭のようなシンディ・パルマーノによるファッションのスタジオ撮影に、ロンドンで立ち会う時などは、そのセンスと現場の空気に圧倒される自分もいた。それでも、”日本人としてファッションを考える”という視点は、私にとって大事なものだった。
当時の編集部には上述のような空気があったので、『花椿』のなかでは、日本のユースカルチャーやストリートカルチャーを、特集など大きな規模で扱うことは、ご法度だった。それならば、アメリカの文化はどうなのか? と考え、それが1997年2月号の特集「ニューヨークのニューな部分」という企画になった。当時はMTVの登場とスケートボードカルチャーの興隆によって、西海岸の文化が輝いて見えた時代でもあった。新しいユースカルチャーが現れたけれど、前の世代はそこを視覚化できるビジュアル言語をもっていなかったから、必然的に若手がMTVの監督になっていった。そうした流れも後押しして、若者 が表現の主体になっていったのが当時の音楽シーンで、ミュージシャンのビースティ・ボーイズが、Tシャツを主体にしたストリート・ファッションのブランドX-Largeの経営を始めていた。そこに現れていたような、あらゆるカルチャーが一体化した流れは、とてもエキサイティングに思えた。
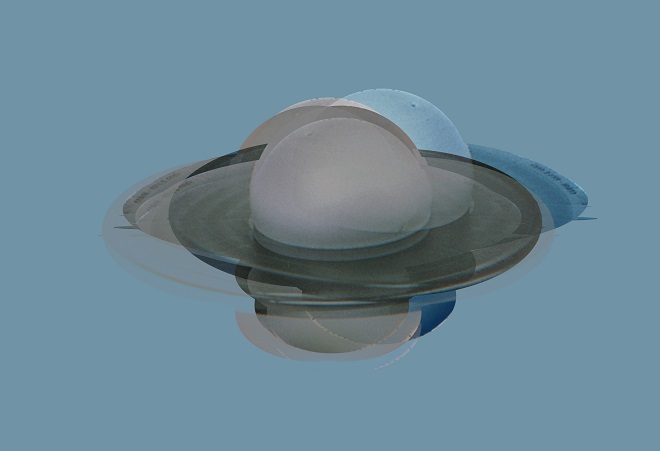
そう思って追いかけていると、ある日、X-Largeの女の子版のX-girlが登場する、というニュースを知った。こういう現象はすべて、パリコレのように、自分の生活に無関係としか思えないモードの世界とは違い、自分が着られる Tシャツ、というリアリティがあった。「文化も、生活全体もファッションとする」、という領域を超えて行くファッションという視座はモードの世界からかけ離れていたからこそ、モードを刷新していくには必要な視点だった。1997年にプレタポルテに参入したラグジュアリーブランドのルイ ヴィトンが2000年代、村上隆とコラボレーションしたことはファッション界に衝撃を与えたけれど、マーケットからくるアプローチだからこそ、このような領域の拡張は必然的な流れだったのだろう。現代では、先日急逝したヴァージル・アブローがIKEAの家具もデザインするなど、ファッションデザイナーの仕事がグローバルな展開であれば価格帯を問わず、かつ領域を超えていくことが、もはや当たり前のことになっている。
異世代との仕事のなかでみつけた、『拡張するファッション』への視点
異質だった私の興味関心は、 日々向かい風を受けながらも少しずつ、小企画の中に表れていった。最初のうちは、1995年4月号のソフィア・コッポラのインタビューペイジや、後藤繁雄さんの善悪対談でキム・ゴードンに登場してもらうといった編集行為や、小さなコラムでマイク・ミルズを紹介したり、WatchingコラムでHiromixにモッズの若者たちを撮影してもらったり。それが次第に、1997年2月号の「ニューヨークのニューな部分」のような、特集記事の規模まで膨らんで行った。ファッション撮影に関しても、2000年の表紙撮影のように、日本人の女の子をモデルにして、パリコレの新人デザイナーから撮影のために直接日本へ服を送ってもらうという企画に実現できたのは嬉しかった。ホンマタカシさんによる撮影現場は、長丁場な従来のファッション撮影の現場とは違い、数カットで撮影が終わってしまうという短時間の、ゆえに緊張感でいっぱいのスタジオ撮影だった。

戸田さんの質問にもどって、世代の違う編集部員や仲條さんの間に、一冊の雑誌をまとめる編集魂のようなものがあったのか? と考えると、それはたしかにあったと思う。ファッションを信じる精神であり、それは、変化や変化を予感させるものを信じる、ということだった。けれども、一人ひとりのなかで、ファッションの定義が異なっていた、ということも真実だった。
この夏、ロンドン留学中の最後にExpanded Fashion (≒拡張された領域でとらえられるべきファッション)のプラットフォームMODUSを2018年に立ち上げたゴールドスミスの教授、Ruby Hoetteに会った。彼女は「FashionはFashionsというべきで、複数形なのです」と言った。さまざまな定義の、概念のファッションがある。このことがもっと常識になっていくといいと私は思う。この視点は消費行為からはなれて、ファッションが思考の対象になった、と論じた2011年のわたしの著書『拡張するファッション』にも体現されていたと思うけれど、そもそもそうした意識は、世代の異なるADや編集者の間で、異なる考えを交わした編集会議やパリコレ体験から、自然に育っていった考えだったと思う。

人を信じる編集
もう一つ、特筆すべきことがある。『花椿』が、当時は月刊誌とはいえど、40数ページしかないA4の冊子なのに「雑誌」と自称する上で、あきらかに特徴といえたものは、「人を信じる編集」だった。メルカ・トレアントンのパリコレレポートは、『elle』や『Vogue』のパリコレレポートではない。メルカさんという一人の人が見た、判断した、感じた、考えた、パリコレレポートだった。「そこに人がいる」ということ。「その人を信じる」ということ。それは、「ワイン・アンド・キュイジーヌ」の増井和子さんであり、「東欧通信」の清恵子さんでありシネマのレポートをする宇田川幸洋さんやダニエル・エイマンであったりした。
この『花椿』流の編集に、私は多くを学んだ。仲條さんや平山さんが築いたこの花椿メソッドは、今も学ぶことができ、多分野に転用できる方法論だと思う。一人の人のなかにはかならず、複雑さや矛盾が内包されている。それは、マーケティングが先行するグローバリゼーションの時代に対抗し、消費されずに生きていくための確実な方法なのだ。人を切り口にすることによって、わかりやすさが要求される世界に対抗し、複雑さをとどめたまま、情報を伝えていくことができる。
平山さんが編集長の時代に培われた人脈には、『暮しの手帖』編集部を経てパリに渡り、フードライターになった増井和子さんや、パリのシネマ通であり人気の映画評論家山田宏一さん、『太陽 』編集長を経て20世紀パリのカルチャーをはじめとする評論で知られる海野弘さん、若くしてイタリアにわたってローマ人の歴史を綴る傍ら『花椿』にエッセイを書き続けた塩野七生さん、80年代ロンドンのミュージックシーンでデビューした「フランク・チキンズ」の法貴和子さんがいた。そうした華やかな人脈の原稿を享受する一方で、私はエレン・フライスやマイク・ミルズやスーザン・チャンチオロや清恵子さんを『花椿』に連れてきた。複数形のファッションズのなかでは、さまざまな概念が同居することができるのだ。
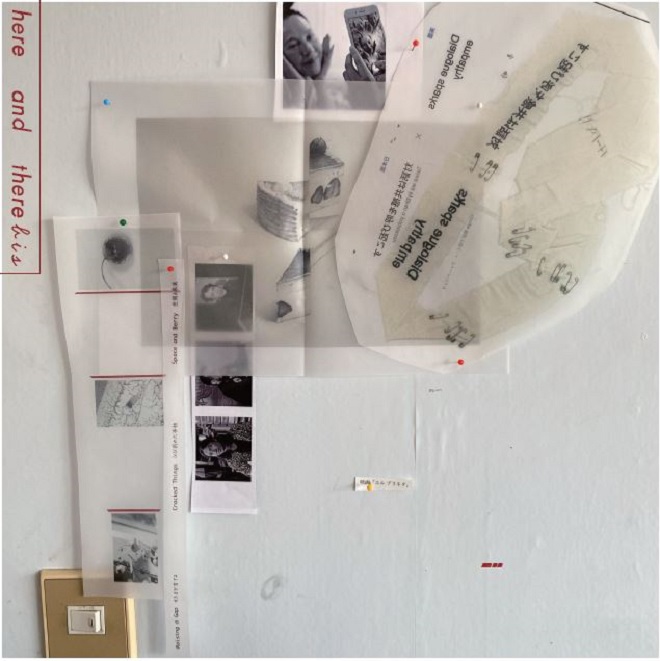
お知らせ
このたび、林央子さんが編集する雑誌『here and there』より『here and there bis 2022』が発行されます。アマリア・ウルマンが監督・脚本・主演を務めた映画『エル プラネタ』への想いを綴るようにして、アーティストがそれぞれのアートワークを寄稿したハンカチ文集。3月には東京都内でトークイベントも企画中とのこと。詳細は追ってお知らせいたします。
『here and there bis 2022』
仕様:大判ハンカチ(45・45cm 綿サテン カラー印刷 限定100枚)
参加アーティスト:田幡浩一、磯谷博史、haru.
アートディレクション:小池アイ子
定価:2,300円+消費税(税込2,350円)
取り扱い:東京都写真美術館内NADiffほか、セレクトショップにて販売

林 央子
編集者
1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)
http://nakakobooks.seesaa.net/
https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓
写真家
東京/京都在住
触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。
http://hosokuramayumi.com
















