
90s in Hanatsubaki
2022.04.12
第21回 最終章 物質文化を超えて。時代の変化のきざしを、ファッションから見つける その1
文/林 央子
写真/細倉真弓
編集長交代から5年。1998年の『花椿』は、その年32才になった私にとっても印象深い年輪になった。5月号からの「イン・ファッション」は、フリーになられた渡辺三津子さんにかわって私が担当することになった。打ち合わせや撮影は平山景子さんの存在感が変わらず圧倒的だったものの、夕方から仲條事務所を訪ねて、アシスタントの渋谷善雄さんと一緒に写真をセレクトし配置する徹夜のレイアウトは、写真をコピー機で拡大して切り抜いて置きながら配置をみていく、手工芸的な作業でもあって、楽しめた。
『花椿』が時代の先端を切り取ってみせる、というような心意気が現れたページだったから、毎月そのページを担うことはやはり楽しかった。この時期から「イン・ファッション」には、服や靴やバッグなどの物の紹介や、映画や書籍などの文化の紹介に加えて、ファッションにあらわれている時代精神をフランソワ・ベルトゥにイラストにしてもらう、というページを企画していた。98年の「イン・ファッション」でフランソワのイラストに添えられた文章と、絵の内容をあげてみると以下のようになる。「東洋思想、ニューエイジ会期の世紀末。エクササイズは、エアロビクスからヨーガへ」(4月号・座禅を組んだトレーニングウェア姿の人物のシルエット)。「緑の命から、年に一度の贈り物。生命の神秘と力、やさしさを植物は人間に届けます」(5月号・植木鉢で実をつけた植物に水をやる場面)。「パリの人気セレクトショップ、コレットの地下はウォーター・バー。どの水を選ぶ?」(7月号・2本のペットボトル)。「深い眠りの底で出会うものは? 心地よい睡眠は、現代人にとって一番の贅沢です」(9月号・シーツと枕の寝具を上から見たところ)。

この98年、5月号の特集は「Design Today」。仲條正義さんとパリへロケに出かけ、マーク・ボスウィックと撮影をした。モデルはNYから飛行機代を払って呼び寄せたスーザン・チャンチオロにも立ってもらったほか、マークの紹介で、パリでデビューしたてのブレスのデジレ・ハイスにスタジオに来てもらい、彼らのデビュー当時の新作を撮影させてもらった。マークと『花椿』はこの撮影が、初仕事だった。日本食レストランの夕食の席で、仲條さんがマークに納豆をすすめ、食通のマークがなんとも言えない顔をしたのを記憶している。デビューから10年目のマルタン・マルジェラが発表した平らな服、フラット・ガーメントが、モダンデザインのあり方を問う特集全体を牽引していた。1ページ目には、仲條さんが頼んでマークに漢字で書いてもらった「今日」という文字が使われた。
98年7月号はNYからマイク・ミルズをよんで京都の印象、「Impressions of Kyoto」という特集を組んだ。写真はホンマタカシさん。構想や人脈の関係づくりは私からのものだったけど、特集担当者は編集部の別なスタッフ で、という条件つきで編集長の小俣千宜さんが許可した企画だ。アイデアは共有し、仕事のわりふりは平均的に。つまり、アイデアを出さない人にも仕事のチャンスが与えられるように、という考え方は、『花椿』から一歩外に出て、ほかの雑誌編集部の常識から考えるとかなり特異なやり方だったけど、一般企業のなかの一つのセクションである『花椿』編集部ではこのやり方が、当然のことのように採用されていた。グローバリゼーションの一方で、日本らしさを味わえる街として、京都は2010年代から劇的に外国人観光客を増やすことになる。そうした現象があらわれる直前に、「外国人の目から見た」という視点を借りながら、伝統的な京都の景観の独特さを紹介する企画になっていた。
7月号の「Speed」ではオランダのファッションの最新動向について、『Purple』編集長の一人、オリヴィエ・ザムに寄稿してもらっていた。クチュールに転向したヴィクター&ロルフと、ヴィクター&ロルフのためにコンセプチュアルな靴をつくっていたフレディ・スティーヴンスや、『Purple』にコム デ ギャルソンのリプロダクションを発表していたパスカル・ガテンの活動を紹介するコラムだった。パリコレに通っていても、根底からその世界を覆すような新しい試みに出会うのは稀なことだ。その一つの潮流が当時は、オランダからくる実験的な試行錯誤の流れだったのだ。
たとえ小さなコラムであっても、自分たちの編集部目線で書かずに、フランス思想界の論客の一人としても認知のあったオリヴィエに言語化してもらうことで、ファッションという文化の層の厚みを伝えることを狙っていた。エレン・フライスにもオリヴィエ・ザムにも、パリコレ期間中、ベルヴィルの中華料理のレストランの大きな円卓で『Purple』関係者たちと食事をともにするときなどに、こうしたコラムへの執筆をしばしば依頼して、後日その原稿を紙面に紹介していった。

『花椿』では毎年春と秋の年2回、パリコレ特集を組んでいたけれど、この年の3月号のパリコレ特集から私が執筆することになった。3月号は私が一人で。その後9月号以降は、平山景子さんと私で6ページずつ分担して書くスタイルが出来上がった。 98年3月号のパリコレ特集は、前年10月に開催された98年春夏パリ・コレクションの報道だ。他に先駆けて早い情報を自負していた『花椿』だが、パリコレレポートに関しては、他の雑誌のレポートが出終わったころ、着る人がそのシーズンの服を考えるころにレポートが出た。「パリへ発つ前から、どよめきを起こしたのが『コム デ ギャルソンとマルジェラが同じ時期、同じ場所でショーをやるらしい』というニュースだった。」という書き出しで始まる私のレポートは、メルカ・トレアントンさんへの取材と自身が見たことで主に構成される平山さんのレポートとは違い、期間中(またはその前後)に見たもの、読んだ記事、取材した人の声など、ショーをとりまく外部の情報もふんだんに取り入れて構成した。
取材した声を引用した人はたとえばファッションデザイナー(ジェレミー・スコット)、ファッションジャーナリスト(平山景子、メルカ・トレアントン、ローレンス・ブナイム)、ファッション関係者(スティーブン・ジョーンズ/帽子デザイナー、ステファン・マレー/メーキャップデザイナー、マリア・ルイザ/ショップオーナー、マーク・ロペツ/ヘアクリエイター)などである。一週間程度の出張で、ショーも見た上で取材もして記事を書くため、その期間中の多忙さといったらなかった。とはいえ速報記事ではない分、執筆までの間に内容を熟慮する余裕はあった。媒体によっては発信するスピードを問われるメディアもあるため、体力的にもっとハードなジャーナリストはたくさんいたはずだけれど。
その中でも、25年後のいまも印象に残るコメントはこれだ。
「スティーブン・ジョーンズは『人種のミックスと、オーセンティックな異文化との出会い。そこに最も、新しいイメージが生まれる可能性を感じる』と語った。その言葉の裏には、今回のガリアーノでの経験がある。ショーの最初に登場した白いニットのロングドレスは、白人のモデルには誰にも似合わなかったが、アジア人のモデルが着たとたんにすばらしくピュアに引き立った。そういえば、97年の返還前に旅行した香港では、インド、マレーシア、中国、イギリスなどさまざまな人種が交差する高層ビル街に、一瞬未来の光景が見えた気がした。舞台はパリでも、パリ・コレクションはパリについてだけのものではない。このことをパリが見逃すはずはないだろう」
当時、ファッションにおける選択を人生の重要な要素のひとつと捉える人も多かった東京とは異なり、香港は、たとえばパリが発信する最新ファッションの潮流とは無縁な街という印象だった。けれども、いつまでそうあり続けるのだろう? という疑問を私は持っていた。自分らしい考察をぶつけたつもりで書いたこのテキストも、編集部で話題になったかといえばそういうこともなく、どちらかというと「変わったことを書くのね」という受け止めではなかったかと思う。その10年後、2008年に大きく報道されたニュースは20周年のショーの後、マルタン・マルジェラ自身が無言でメゾンを去ったことだった。90年代のクリエイティビティにわいたファッションの世界が、ひとつの終止符を打った、と多くの人が受け止めていた。その要因のひとつには、その10年のあいだにグローバリゼーションの波がファッションを直撃したことがあった。2000年代には、90年代にファッション都市と認識されていた街とは異なる消費の場所が、中国やアジアに出現していた。

当時、『花椿』チームとして一緒にパリコレに行っていた渡辺さんとの会話で、97年前後のパリコレウィーク中に、サンジェルマンにオープンしたルイ ヴィトンの新店舗のことを話したことも覚えている。渡辺さんは「そこで買い物している人がいるなと思って、よく見たらマーク・ジェイコブスだったの」と言った。その時の店舗の風景をうっすらと覚えている気がするので、私も彼女と一緒にマーク・ジェイコブスのいるヴィトンの店舗にいたのかもしれない。どこまで正しいのか、今はもう記憶は定かではない。でも確かなことは、そんな会話をしたすぐ後に、老舗バッグブランドのルイ ヴィトンが服飾に参入して、パリではどちらかというと軽視されていたアメリカ人デザイナーの一人であるにもかかわらず、気鋭のデザイナーとしてマーク・ジェイコブスを迎え入れたことが大々的に報道された、ということだ。こんなふうに、歴史を目撃したと思える実体験が、パリコレ取材に行っていた頃の収穫の一つといえるのかもしれない。マーク・ジェイコブスがルイ ヴィトンと契約してから、マーケティング主導の発想が、保守的だったモード界にどんどん取り入れられていった。その一つが、02年から始まった村上隆さんとのコラボレーションのような、アートの世界との共働だった。
08年から18年までの10年、マルジェラのみならずパリコレを拠点としていたさまざまなデザイナーがビジネスの路線変更やブランドのクローズを迫られた。私が『花椿』のためにレポートした最後は2000年だったと思うけれど、その前後に多数デビューしたフレッシュな若手デザイナーの一群にいた、たとえばヴェロニク ・ブランキーノやアン・ソフィー=バックなども、残念ながら活動に終止符をうったブランドだった。その一方で、アジアの購買力は増す一方だ。25年前にスティーブン・ジョーンズがガリアーノの舞台裏で実感したような、「もう一つのイメージ」、西洋文化にかならずしも主導されないファッションのイメージが増えていくのが当然といえる時代をいま、迎えていると思う 。そしてはからずも、インターネット上のSNSでファッションブランドの経営方針があちらこちらでバッシングされることも、90年代にはなかった ことだが、昨今の現実になってきている。
一見、経済力を背景に、購買者側に発言のパワーがあるように見えるし、発言権は中国などの非西洋文化圏にうつったかのようにも見える。けれどもそこでは、深い対話やイマジネーションを喚起するようなクリエーションは行われているとはいいがたいのではないだろうか。時代を牽引するような「新しいイメージ」が、ファッションの分野で、なかなか見えてこない、という歯痒さもある。当時のパリコレが打ち出したような大きなイメージに対抗する、大きな物語や大きなイメージが出現する時代ではなく、無数の多様なイメージや流れが出てくる時代になってきていると思えるのだが。
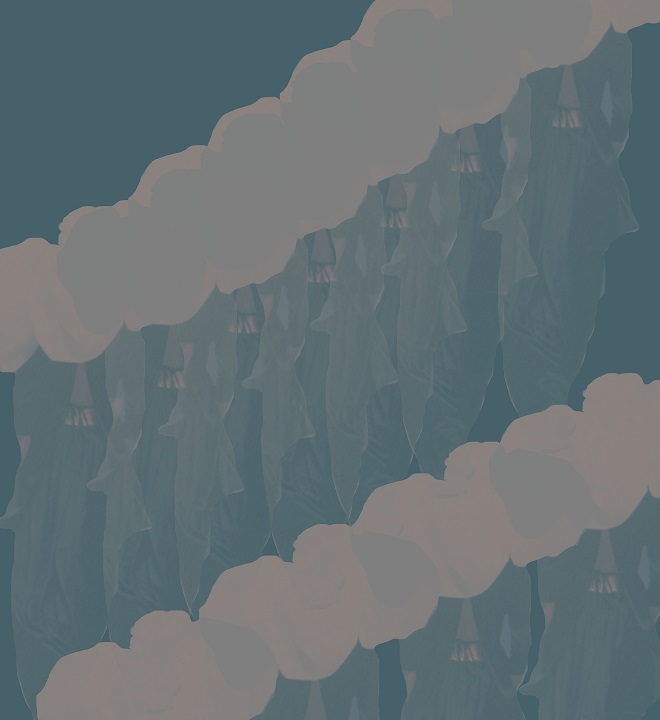
とはいえ、捨てる神あれば、拾う神あり。18年、クリエイティブなデザイナーたちが一旦ファッションというフィールドを離れることを余儀なくされたような情勢のなかで、逆にファッションを思想的に論じようという流れがヨーロッパで台頭し始めている。そのひとつに、ロンドンの美術大学、ゴールドスミスで「拡張されたデザインの実践」を教えるファッションの指導者、ルビー・ホエットがオランダの美大で教えるキャロライン・スティーブンソンと組んで立ち上げた、MODUSというプラットフォームがある。
Vol.18でも少し触れたように、美術史でロザリンド・クラウスが提唱した「拡張された彫刻」という概念を反映し、それをファッションというフィールドに置き換えて「Fashion in the expanded field」や「Expanded Fashion」などのキーワードからファッションにまつわる思考を拡げようとする動きがある 。ヨーロッパの美大でファッションを教える先生たちが主体となって、論文誌や年に一度の展覧会をつくっていこうとするMODUS は、18年にオランダで始まり、新規な動きのまた別の拠点であるオーストラリアの学者たちも共鳴している。その直後にロンドンに留学していた私は 21年に論文を書き始めてから、こうした流れの中心にいる若い学者たちに、次々に会っていくことになる。今までになかった動きを、これから自分たちでつくろうとしている彼女たちは総じていきいきとしていて、考え方は柔軟で、これからファッションの拡がりをつくることにワクワクしているように見えた。
ここまで書いて、私は編集部の戸田さんに、資料を自宅に送ってもらう依頼をして、それが着くのを待っていた。3週間待っても届かなかったので、執筆にのぞみたい前の週の週末に、「書籍化に間に合わなくなるので」と催促をした。その週末、偶然にも98年と08年に自分の手がけた編集仕事がInstagramに上がってきて、15年前と25年前の過去についてあらためて、雑誌という存在を通して考えることになった。
次回へつづく。

林 央子
編集者
1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)
http://nakakobooks.seesaa.net/
https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓
写真家
東京/京都在住
触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。
http://hosokuramayumi.com
















