
90s in Hanatsubaki
2022.03.04
第19回 マルタン・マルジェラと『花椿』の90年代 ―脱構築とは何か? その1
文/林 央子
写真/細倉真弓
人と違うことを恐れない編集
40数ページしかない月刊誌の『花椿』が雑誌の顔をするためには、世の中のほかの雑誌と同じテーマや人を取り上げていては、勝てないことを自覚した上で、「違うことをする」姿勢、人が選ばない選択肢を選ぶ姿勢があった。「人と違うことを恐れない」編集といえば、『花椿』らしいフォトグラファーを考えたときにまっ先に思い浮かぶ、シンディ・パルマーノとの仕事にも、その遺伝子があった。シンディを見つけてきたのは平山さんと仲條さんで、80年代半ばにロンドンで話題を呼んでいた二人の新人写真家がニック・ナイトと、シンディ・パルマーノだった。世間の人の多くはニック・ナイトに飛びついたけれど、『花椿』はシンディを選んだ、と平山さんに聞いたことがある。
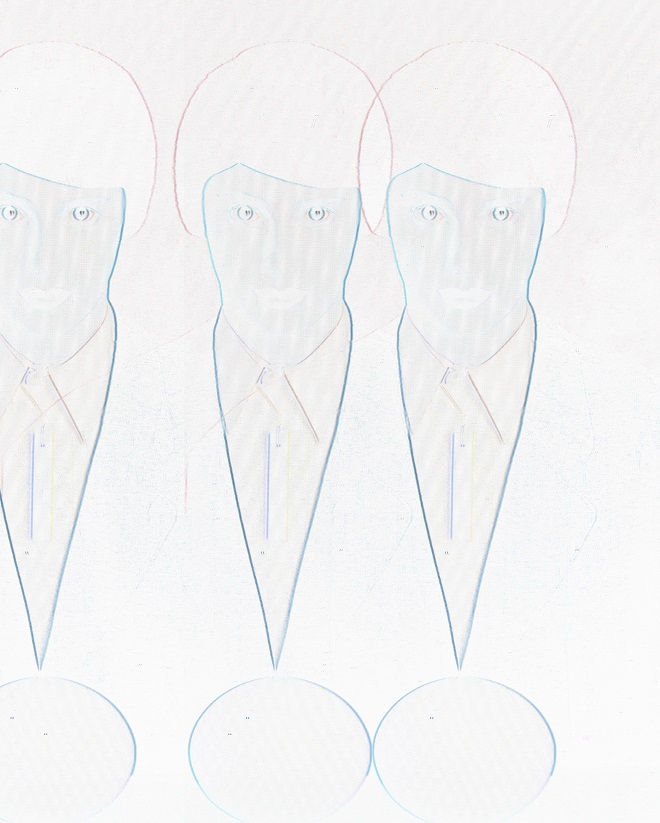
シンディは87年から88年にかけて『花椿』の表紙を撮影していたし、その後もパンクファッション特集(1993年11月号)、ヴィヴィアンウェストウッド特集(1993年1月号)など、『花椿』にとってのちにエポックメイキングとなるような特集は彼女が撮ることが多かったのだが、その彼女と雑誌が出会ったばかりのころに、シンディは未婚のまま出産することを選ぶことになった。通常はドキュメンタリー記事の掲載はしない『花椿』だが、若くしてロンドンで写真家という仕事をしながら、一人で子どもを生み、育てる決心をしたシンディのその挑戦、その生き方を、8ページの特集記事にしたことがあった(1988年7月号)。当時は『花椿』の若手エディターだった渡辺三津子さんがロンドンへとんで、出産ルポルタージュの記事を書いたのだ。そして当時編集長であった平山さんはその子の名付け親、ゴッドマザーになった。仕事が重なってくると、こうして家族ぐるみのような付き合いが、海外のクリエイターとの間でも生まれていくことが『花椿』のまわりではよくあった。このような記事を誌面に取り上げるところや、塩野七生さんやホーキ・カズコさんなどの海外でひとりで生きる日本人女性のエッセイを連載することの多かったところに『花椿』を貫く、フェミニズム的姿勢をみてとることもできるのではないかと思う。
入社したばかりのころは、女性モデルをファッションとからめて、静物画のコンポジションのようにスタティックに配して撮影し、新たな意外性の美を紡ぎ出すような表紙のイメージが、わたしにとっては憧れの的だったシンディ。そのうちに、パンクファッション特集でロンドンでのロケに連れて行ってもらえるチャンスが回ってくると、わたしはシンディのご自宅に平山さんたちと一緒にお邪魔する機会を得た。いつも、掲載紙の海外送付のため封筒に書いているその住所が、ロンドンの実際のストリートの名前で、その場所に彼らが住んでいることを目撃したことに、ふしぎな感動があった。撮影の現場ではとても厳しく、シンディは彼女自身がストリートキャスティングで声をかけて集めてきたモデルたちをも、彼女がイメージする構図に合わないと、差し障りのないような指示を与えながら、それとなく次々とカメラの視野から外して行った。30歳そこそこの女性が、ヘアメークやモデルなどスタッフが10名以上いるクリエイティブな場の中心になって指示を与え、イメージをつくっていく様子を見たのははじめてだった。日本人のフォトグラファーと仕事をするときは、細部のすみずみまで指示を出すアートディレクターの仲條さんも、シンディが撮影するファッション写真となると、現場では任せきりであることを知ったことも、驚きだった。

アーティスト気質のシンディからは自分からこれを撮りたいというプレゼンテーションもよくあって、それが実現したのが1990年4月号、5月号のドゴン族特集だった。アフリカのマリ共和国に単身で渡って撮ったドキュメンタリー写真は、対外的にも好評で、とある大手出版社から、写真集として出版しないかという打診の電話を受けたこともある。シンディは自分の仕事を本のかたちに定着させることにあまり興味がもてなかったようで、その話は流れてしまったけれども。『花椿』にいて、たくさんの才能豊かなフォトグラファーと仕事をする機会をいただいたけれど、本当にパワフルなクリエイターとして記憶に焼きついている存在は、やはりシンディだった。私がフリーになった後も、彼女に撮影をお願いしたいと思って2010年ごろに動向を尋ねてみると、「子どもが4人生まれて、もう写真を撮る生活から離れてしまったようだ」と人づてに聞いた。決して妥協せず、とことん納得がいくまで何時間かかっても撮影をやめないこともあったシンディは、作家的な気難しさもあって、『花椿』以外ではあまり、まとまった仕事の発表はないようだった。ともあれ、そんなシンディの思い出がつまったロンドンは、私が所属する前の80年代からずっと、『花椿』の編集において、新しい才能との出会いの場として重要な拠点だった。

新しさとストリートファッションの発信地、ロンドン
80年代から90年代初めにかけて、平山さんと仲條さんがしょっちゅう撮影にきていたその街は、ファッションの世界のなかでの位置付けを考えると、つねに新しさが出現する都市だった。古くは60年代のモッズファッションやミニスカート、70年代のパンクファッションもロンドンが発信地だった。80年に創刊された『i-D』や『The Face』といった音楽やユースカルチャーとファッションを扱う雑誌媒体が、老舗のファッション誌にはない新鮮なビジュアルを求めたこともあって、新しいモデルと、駆け出しのファッションフォトグラファーは大抵、ロンドンにいた。彼らのセンスの良さを嗅ぎつけて集まってくる感度の高い、新しい表現への実験に意欲的なスタイリスト、ヘアやメークのチームもロンドンで見つかった。90年代後半からグローバリゼーションが闊歩して見えにくくなった側面があるが、本来ファッションという場所は、センスの良さ、感性の鋭さで、個人が世界と勝負できるフィールドなのだ。ファッション写真家たちは、ロンドンで頭角を表すとパリに移住し、モードの首都パリで洗礼をうけて、名前を確固たるものにして、ニューヨークへ行く。世界的に名前が知られる人たちは大抵、そういう道をたどっていた。
そのロンドンに、『花椿』を離れて約20年後の2020年代初頭に、2年間住むことになったことは先に触れた。90年代当時から連綿と今にいたるまでファッションデザイナーを多数排出した美術大学、セント・マーティンズでアートヒストリーを背景にした展覧会学を学ぶことになったのだけれど、この時代においては、ロンドンがエッジーなファッションの発信地だという概念をもつのは、もはや難しかった。同じくセント・マーティンズの大学院で学んだ、ファッションとアートヒストリーを専門とする新進気鋭の学者イェッペ・ウゴリグに会って「歴史的にみてもロンドンは、モッズやパンクが登場した街だし『i-D』などの雑誌もあって、ストリートファッションの本拠地だったよね」という話をすると、「ロンドンのそうした側面をうっかり忘れていたよ、たしかにそうだよね」という反応だった。93年生まれ、北欧出身の彼にとっては、ロンドンも私たちよりは身近な都市で、日本人ほどには「ファッションの本拠地のなかでの、ロンドンと他の都市の違い」をあえて意識する機会は少ないのかもしれないと思った。

ロンドンとのつながりは『花椿』だけでなく、80年代には資生堂もダギー・フィールズというロンドンのクリエイターと契約して「パーキー・ジーン」という若い女性向けの化粧品キャンペーンを打ち出していた。資生堂のような化粧品会社が海外と接点を持つ上で、イギリスといえば王室文化、とならずに、ファッションやクラブシーンに近いクリエイターと契約を結んでいたということは、80年代の勢いのなかだからこその冒険だったかもしれないし、慧眼だったと思う。インターネットが文化を制覇する前の時代、こうした選択や決断は、現代よりずっと身軽だったのではないだろうか。
次回へつづく。

林 央子
編集者
1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)
http://nakakobooks.seesaa.net/
https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓
写真家
東京/京都在住
触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。
http://hosokuramayumi.com
















