
音楽と小説の両輪で言葉に向き合うクリープハイプ尾崎世界観さんとアーティストがものづくりについて語り合う対談企画の特別編。今回のゲストは詩人の暁方ミセイさん。暁方さんは1988年生まれの詩人で、2010年に現代詩手帖賞を受賞、翌年『ウイルスちゃん』という第一詩集を発表されました。宮沢賢治の作品を敬愛し、大学院では宮沢賢治の詩の研究と創作を行い、2018年に『紫雲天気、嗅ぎ回る 岩手歩行詩篇』を上梓されました 。今回は、『花椿』2021年秋冬号にも掲載の宮沢賢治の詩集『春と修羅』の序をテーマに二人が語り合いました。宮沢賢治が感じていた世界とはどんなものだったのか、なぜ賢治の詩は多くの若者に影響を与えているのか。
尾崎世界観(以下、尾崎) 自分が曲の歌詞を書くときは、先にメロディーを作ってそこに言葉を流し込むようなイメージです。言葉はものすごく量があるので、途方もない作業になりますよね? だから、使える言葉をあらかじめ減らして、その制限の中でやるほうが自分にとってはすごく心地いいんです。だから何もないところで詩を書けと言われたら、絶対に無理ですね。
暁方ミセイ(以下、暁方) 詩にもいろいろ種類があって、短歌や俳句など音の数が決まっている定型詩もありますよね。尾崎さん、短歌とかうまそうな気がします。
尾崎 前に雑誌で歌人の方と競作してくれと言われてやってみたことはあります。でも、半分くらい書いたときに別の歌人の方にどうですか?と見せたら、リズムがすごく悪いって言われて、少し傷つきました(笑)。ああ、歌人には、短歌のリズムがあるんだなと思って。だから、短歌というのは自分の中にはないリズムだなと思ったんです。
自分は音楽をやっていて、そのリズムの中でしか言葉が書けない。小説も結局そうなんだと思うのですが、同じリズムで書いている感じはありますね。逆にそれがないと道筋がわからなくなっちゃう気がします。今回、暁方さんの詩や宮沢賢治の詩を読んでみても、どうやって書くんだろうと思ったし、その前にどうやって読むんだろう? どう理解すればいいんだろうと思いました。自分の場合は、言葉を使う上で音という補助輪を使っているようなイメージで、でもそれも自分だという自覚はあるんですけど。うん。なんか自分が書く言葉とはまったく違う感覚があって、すごく不思議だったし、刺激的でしたね。
暁方 文学の中でも宮沢賢治ってすごく独特な存在だと思うんです。
尾崎 周りにいても、友達にはなれてないかもしれないです。一緒にいても別のところを見ていそうな気がして。きっとそこが魅力なんだと思うんですけど。なんだか同じ場所には立っていないというか。そっちへは降りていかないよって言われているような感じがしました。自分が触れている表現というのは、わりと何か自分の肉体を使って感じたものを言葉にしていくという感じで。でも賢治は感覚だけで肉体がないというか、意識だけでものを見ているようで、そこが面白いと思いました。
暁方 なるほど、そういうふうに感じられるんですね。確かに尾崎さんの書く小説もですし、歌もですが、絶対に自分は低い位置にいて、そこから書いてやるというすごい意気込みを私は感じます。そこがすごく好きで、ロックだなって思います。
宮沢賢治は、明治の後期くらい(1896年)に東北の恵まれたお家に生まれたんですね。当時の東北の農家は、暮らしが苦しい家が多くありました。そんな状況のなか、賢治は比較的裕福な家庭で育ちました。それに対する申し訳なさがあったのだと思います。
『春と修羅』の中で、自分のことを修羅と呼んでいますが 、修羅というのは仏教用語で、自分は人間以下の存在であると言っているんです。
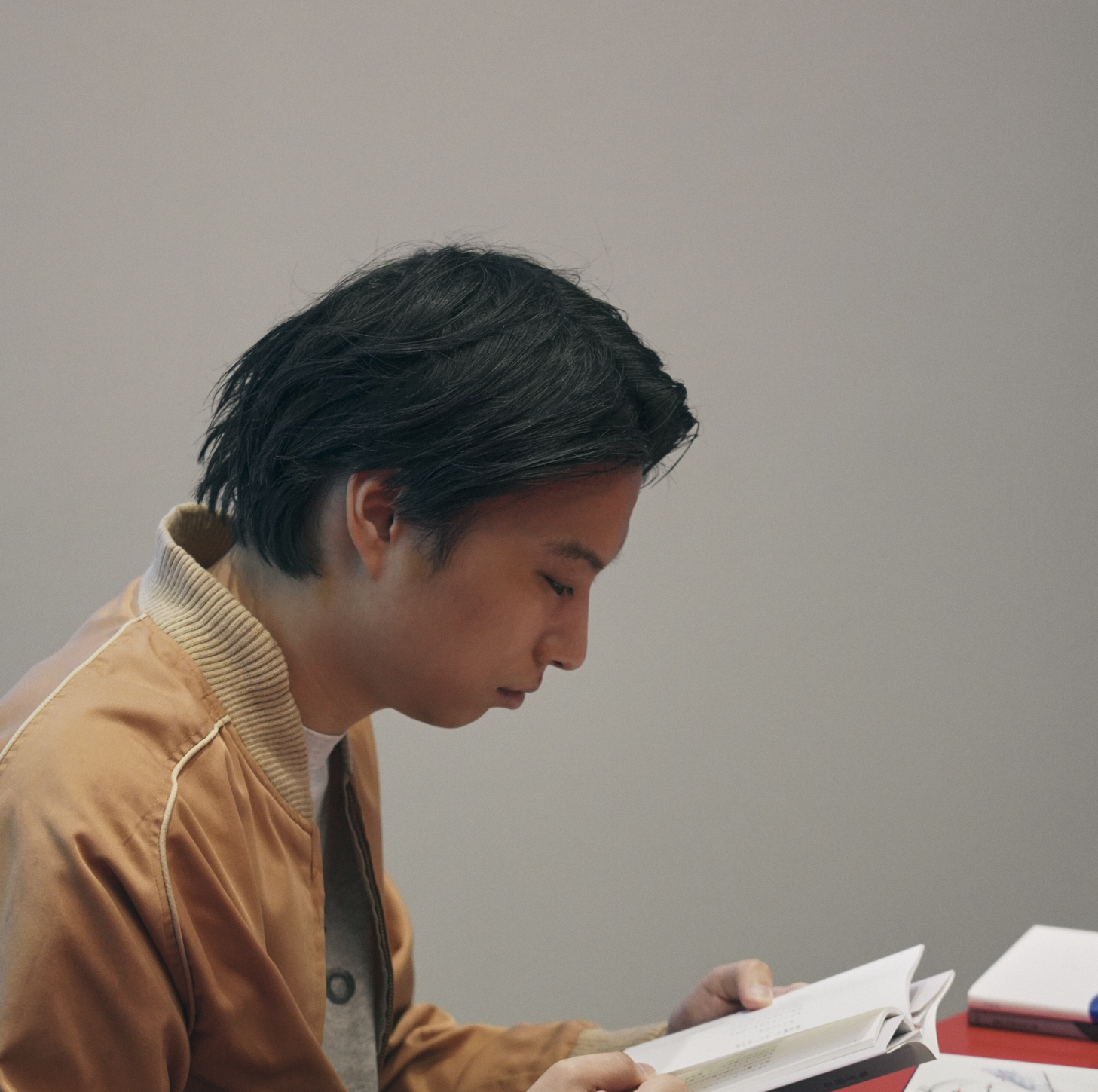
尾崎 修羅って、人間以下ということなんですね。
暁方 そうなんです。でも、高みから書いているようにも見えますよね。
その印象は、賢治の詩作のテーマである「心象スケッチ」という方法からくるのだと思います。賢治は、心のなかに現れ、連鎖し反応していくものを、ありのまま書くということを目指しました。それを突き詰めると、温もりみたいなものからは離れていくのかもしれません。
『春と修羅』の序の詩にはいくつかポイントがあると思うんですが、
わたくしという現象は
まずまっさきに、「現象」という言葉を使っている。例えば「存在」や「事実」ならば、単に私自身のことを指しますが、現象というのは、私だけではなく別の他者が必ず同時にあって、動的なものとしてそこに「起こる」ことです。要は、周りとの繋がりの中にこそ自分があるという感覚。
そして、これは
心象スケッチ
であるという宣言。心のありのままを写したものであるという宣言です。
けれどもこれら新生代沖積世の
巨大に明るい時間の集積のなかで
正しくうつされた筈のこれらのことばが
わづかその一点にも均しい明暗のうちに
(あるいは修羅の十億年)
すでにはやくもその組立や質を変じ
しかもわたくしも印刷者も
それを変らないとして感ずることは
傾向としてはあり得ます
というところは、自分は今このように心象スケッチを書いているけれど、正しく書いたつもりでも、感じた自分と書く自分の間には修羅の十億年にも等しい隔たりがあり、今の自分は瞬間瞬間、消え去って変わっていくよ、ということでしょうか。
他には、この仕事によって世界の見方や認識を変えようと思っていること、これは「第四次元」の芸術であるということが、この詩の主張しているものだと思います。私なりの解釈ですが(笑)。
尾崎さんが受け容れられないとおっしゃっているのは、ひょっとしたら賢治の宗教性なのかもしれません。賢治は、科学と宗教を一致させるということを言っていて。心象スケッチによって、それを試みていた面もあるので。
尾崎 なるほど。心象スケッチか、スケッチという感覚は自分にはないんですよね。何かを丁寧に写し取っていくというよりは、もっと肉体にぶつけていくというイメージです。
暁方 確かにそうですね。賢治は自分の書くものは「詩」ではなく「心象スケッチ」だと言っています。でも、考えてみると、心象、心に写るものをそのまま書くということは、文学としてはよくあることのように思えますし、きっと尾崎さんもやっていることなんだと思います。でも、そこで賢治は何が違うのかなと思うと、彼独特の四次元を念頭に置いた世界観が特異なのかもしれません。

10代で現実の生活がうまくいかなかったとき、理解できない言葉に惹かれた
尾崎 宮沢賢治が好きな人は、皆さん、暁方さんみたいな解釈をされているんですか?
暁方 いやあ、どうなんでしょうね(笑)。宮沢賢治が好きっていう人は、童話を好きな人の方が多いのではないかと思います。『春と修羅』の序というのは、読む人を門前払いするような間口の狭さがありますからね。でも、私は最初に賢治にのめりこんだのが、この詩なんです。
尾崎 こんなすごい詩を読んで、その奥に入っていこうと思えることが凄いですね。
暁方 ちょっと敷居が高いですよね。でも、中学生の私は、この詩に強く惹かれて賢治の世界に入りました。当時の私はとにかく世界に対して安心していたかったんです。学校でもあまりうまくいってなくて、親ともうまくいってなくて、どうしたもんかな〜という毎日で。でも、本を読むのは好きで、自分でものを書いたりするのも好きだった。そんな状態の時に、この詩を読んだんです。
「わたくしという現象は」という部分も、私は他のものたちと繋がっていて、ひとつの生態系の中に生きていると言っていると思いました。孤独でいいんだよって言われたような気がしたんです。みんな孤独なんだけど、同時に繋がっているという。
尾崎 そんな風に受け取られたんですね。
暁方 よっぽどせっぱ詰まっていたのだと思います(笑)。真剣に読むと難しいものでも、当時の自分は、言葉の中から勝手に情報を取り出して受け容れていたような。
尾崎 自分でもそうだったんですけど、10代の頃にうまくいかないときは、とにかく意味がわからないものに触れると、すごく安心していた記憶があります。理解できないものがすごく好きだったんですよ。なんというか、世界がちょっと拡張されていくというか、まだまだいけるという感覚があって。自分が追いつめられていくと、もう自分の身体しかスペースがないという感覚になって、ちょっとでも動いたらズレてしまう、落ちてしまう怖さがあって。そういうときに何か理解できないもの──僕の場合は写真だったんですが、ギャラリーでよく写真を見ていましたね。バイトしてライブハウスにお金を払って、またライブしてという繰り返しの生活をしていたときは、本当に写真ばかり見ていましたね。そういう理解できないものに救われていたし、暁方さんも、中学生の時のそういった時期だったからこそ、詩の奥に行けたのかもしれませんね。
暁方 わからないものがあることで安心するという感覚、すごくよくわかります。賢治の世界って、人間社会だけじゃなくって自然界とか宇宙とかそういうものまでひっくるめて同じ生態系の中にいる。私は、当時、人間社会で詰んでいたので。そこから抜け出すには2パターンあるって思っていたんです。さらに自分の中に引っ込むか、あるいは自分のいる場所を広げるか。
その自分のいる場所って、共同体ということだと思うのですが、家や学校の人間関係の中にしかなかったそれを、もっと広げたかったんです。もっとぐちゃぐちゃでいろんなものがある世界にいると実感することが、当時の自分にとってはすごく大事なことで、賢治の世界というのは、その共同体をずっと外まで広げてくれるものだったんです。なので私にはこれしかない!って一気にのめりこんじゃって。序から始まって『春と修羅』を全部読んで、他の詩も読んでいった感じですね。


──後編は近日公開します。お楽しみに!

尾崎世界観
ミュージシャン
バンド「クリープハイプ」のボーカル、ギター。独自の観察眼と言語感覚による表現は歌詞だけでなくエッセイや小説でも注目を集める。著書にエッセイ集『苦汁100%』『苦汁200%』、小説『祐介』(すべて文藝春秋)、エッセイ集『泣きたくなるほど嬉しい日々に』(KADOKAWA)などがある。2021年1月に発表された小説『母影』(新潮社)は、芥川賞にもノミネートされ話題となった。同年12月8日にはニューアルバム『夜にしがみついて、朝で溶かして』が発売。2022年4月に歌詞集『私語と』(河出書房新社)を刊行した。
2023年3月には幕張メッセ国際展示場・大阪城ホールというキャリア史上最大規模の会場にて、アリーナツアー 2023「本当なんてぶっ飛ばしてよ」を開催する。
http://www.creephyp.com

伊藤篤紀
映像作家/フォトグラファー
1994 生まれ。
制作会社にて映像制作を学んだ後に独立。2019 年よりフリーランスで映像のプロデュース、ディレクションを行う。主にファッションメディア、ブランドの映像を手がけ、また、フォトグラファーとしてキャンペーンビジュアルやポートレート撮影も行っている。Amazon Prime Video の番組「キコキカク」、VOGUE GIRL, ELLE など国内外複数のファッションメディア、UNIQLO、TOMO KOIZUMI × MARC JACOBS、Kudos などブランドの映像を担当。
http://www.atsukiito.com/

谷本 慧
ヘア&メイクアップ アーティスト
1986年生まれ。大阪出身。大阪の店舗を経て、上京後、原宿BRIDGEに7年間所属。2019年CITY LIGHTS A.I.R.に参加。サロンワークを軸に、広告、雑誌、TV、MV、CDジャケット等、音楽を中心としたヘアメイクを担当。
https://www.instagram.com/3104tanimoto/
https://satoshitanimoto.tumblr.com/

暁方ミセイ
詩人
神奈川県生まれ。2012年、詩集『ウイルスちゃん』(思潮社)で第17回中原中也賞、2018年に詩集『魔法の丘』(思潮社)で第9回鮎川信夫賞、2019年に詩集『紫雲天気、嗅ぎ回る 岩手歩行詩篇』(港の人)で第29回宮沢賢治奨励賞を受賞。最新詩集は、『青草と光線』(七月堂)。
撮影:伊藤篤紀
https://twitter.com/kumari_kko

上條桂子
ライター/編集者
雑誌でカルチャー、デザイン、アートについて編集執筆。展覧会の図録や書籍の編集も多く手がける。武蔵野美術大学非常勤講師。著書に『玩具とデザイン』(青幻舎)。2022年10月には編集を手がけた『「北欧デザイン」の考え方』(渡部千春著、誠文堂新光社)が発売。
https://twitter.com/keeeeeeei
https://www.instagram.com/keique/?hl=ja
















