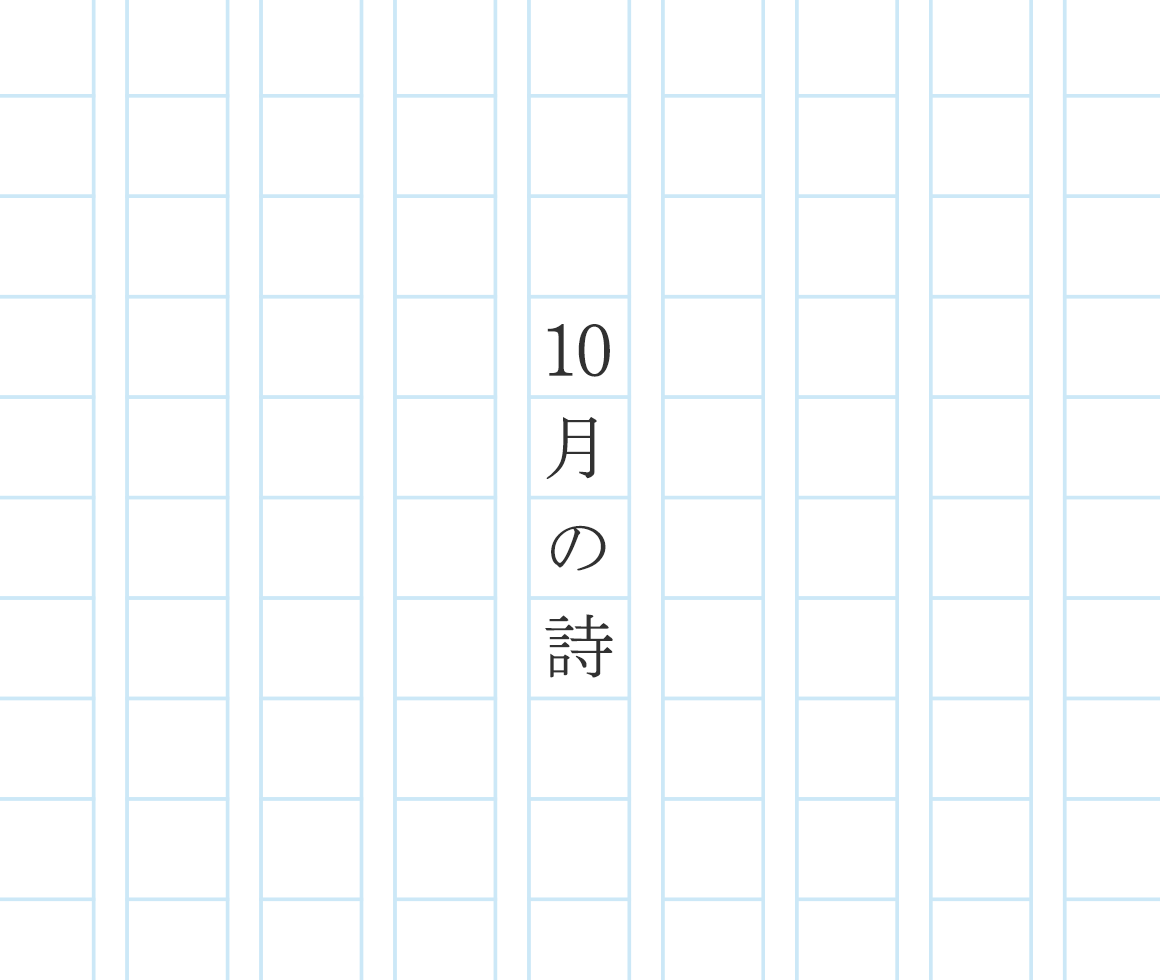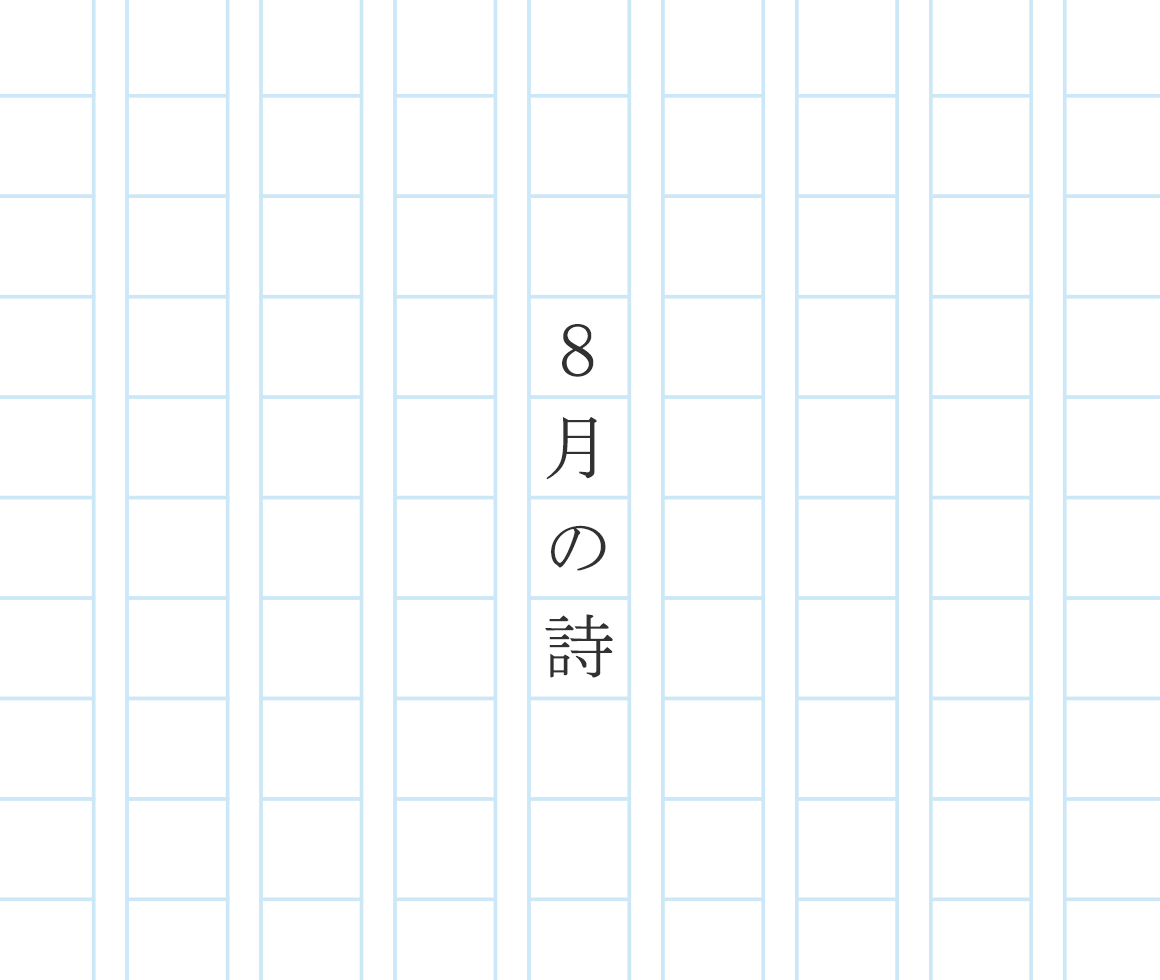染みついた雨音が聞こえる
君と会う日は
雨降りの事が多くて
駅の近くの喫茶店の
窓側の席に座り
マスタードのよく効いた
ハムと胡瓜のサンドイッチと
珈琲を飲みながら
雨音を聞いていた
摺りガラス越しの
通りを眺めながら
きっとどちらかが
余程 雨に好かれているのだろうと
よく話していた
君と会わなくなってから
信号が変わるのを待つ交差点で
夜中に目が覚めて水を飲む台所で
文庫本を読むのに腰かけた公園のベンチで
降っていないのに
雨音が聞こえる事があった
この間
海辺の町へ行き
夕方に海岸で
海を眺めていた
また雨音が聞こえだした
波の音と染みついた雨音が
混じりあう中を
レインコートを着た犬が歩いていく
雨音を聞きながら
閉じた君の目を
水平線みたいだなと思って
見ていたことがあった
選評/暁方ミセイ
堀口大學の『月下の一群』に収められている、「地平線」(マックス・ジャコブ作)という有名な詩があります。とても短くて、「彼女の白い腕が/私の地平線のすべてでした。」というたった二行の詩です。遠い地平線まで、私の世界が全て、彼女でいっぱいになってしまった。それはすでに過去になっていて、今はその美しい腕を思い出すだけ……。
平野さんの「水平線」は、この詩のオマージュかもしれません。「地平線」の性愛は「彼女」の肉体に対する甘えた感じがあって、どこか安らかであるのに対して、この詩はまるで「君」のまぶたに世界が覆われて、閉じこめられてしまったような感じがします。幻の雨音は、語り手にあとからあとから、世界と同じくらいに膨れ上がった、わからない「君」のことを囁きます。それはただ、語り手の孤独を縁取るのです。
「水平線」は、「閉じた君の目」の思い出でありながら、同時にキーワードとなっている雨が、一粒ずつ流れてつくったものでもあります。記憶の中で降っている雨は、目の前で海になり、遠い水平線まで続いているのです。そこが「地平線」にはない現実性というか、詩の全体に冷静な感じを与えていて、さらりとした終わり方もとても魅力的です。