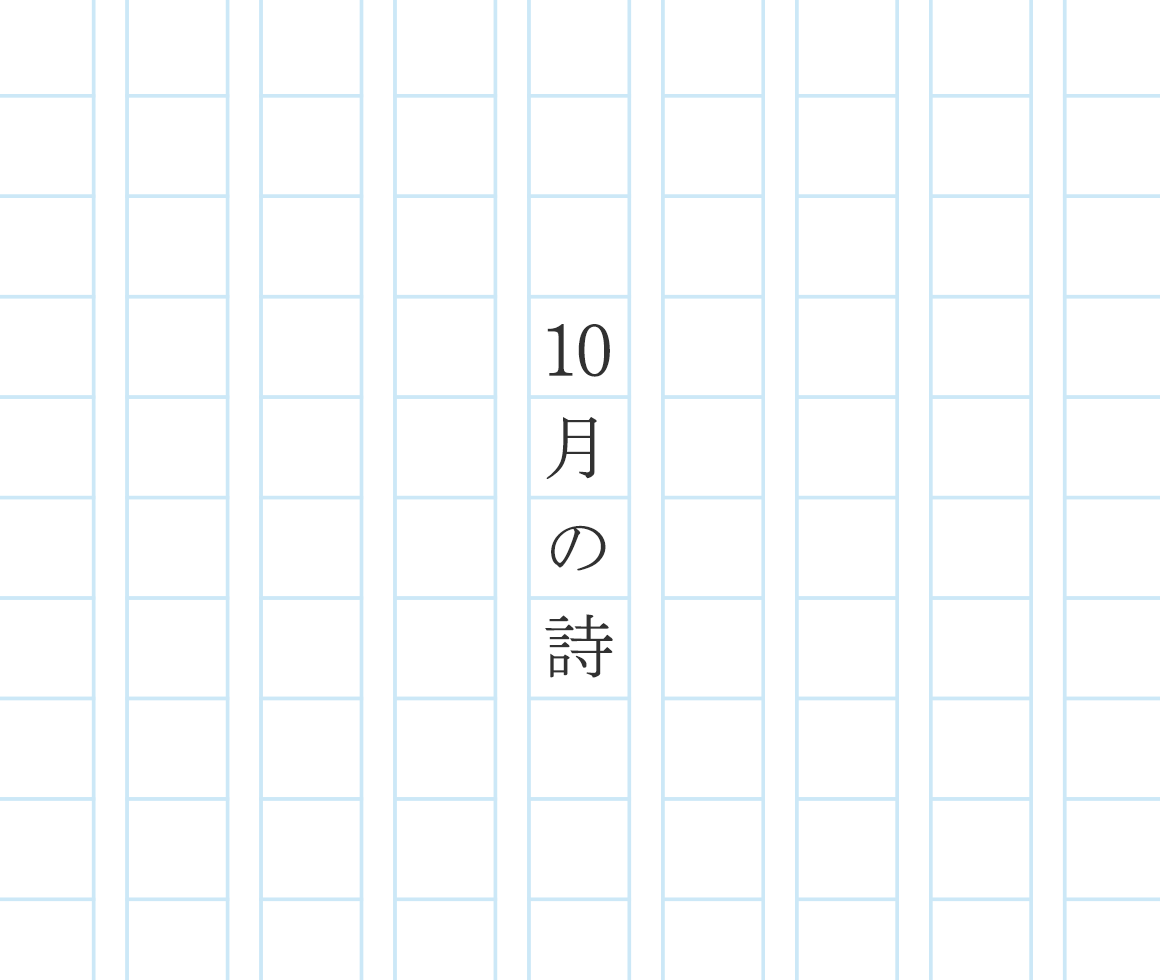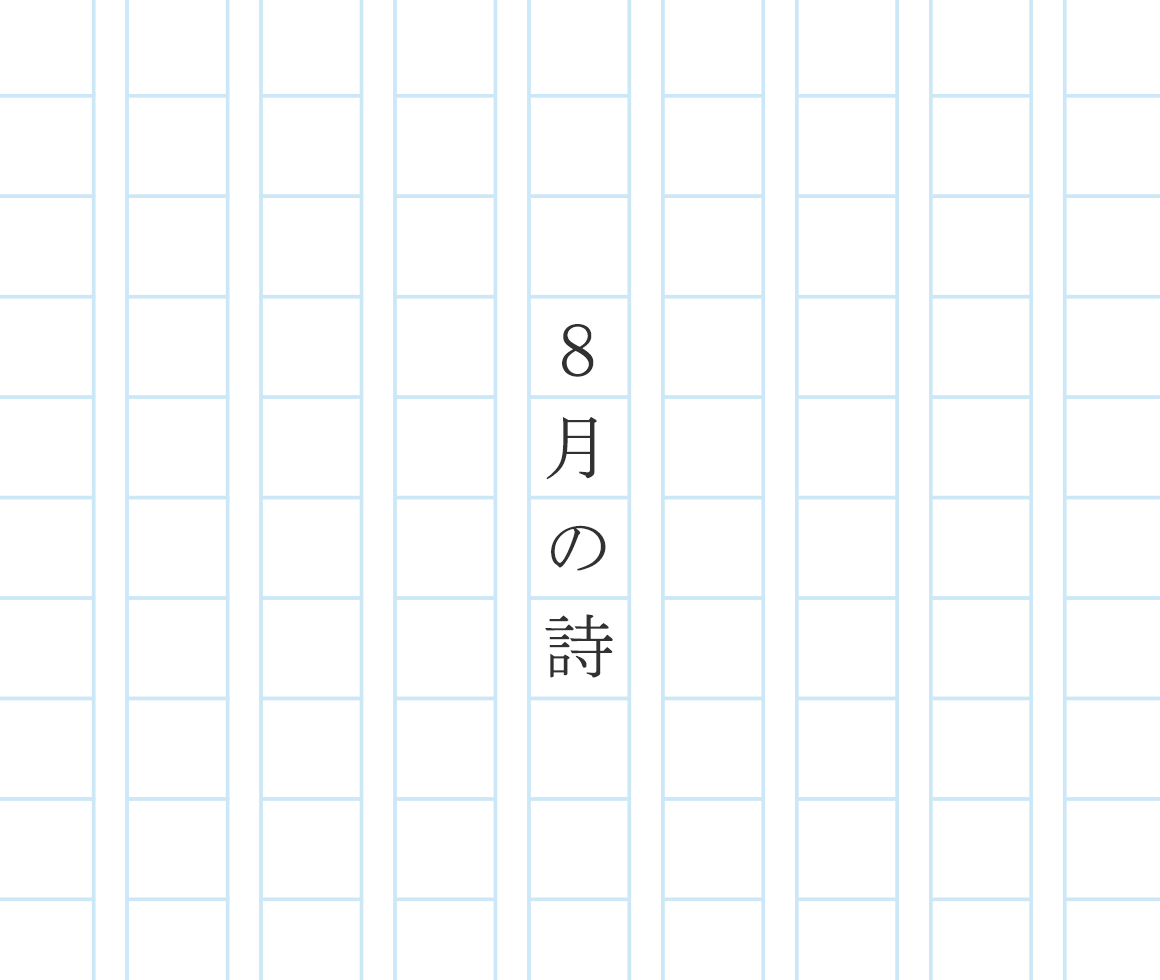犬の散歩に
犬を忘れてしまうとき
鎖に繋がれている透明なふるえを
濡れたタオルで包みあげる
夢を忘れ
朝はすみやかに行われて
火をつけた煙草
そっけない
返事
みたいだ
前に進むものと
後ろに進むものが
ある交差点の同じ信号を待っていて
祈るような
ながいあくびのあと
水浸しの食卓へ
お辞儀をする
ぎこちない
箸の持ち方を咎める人は
水面に反射する顔をみたことがなくて
鏡に関する言葉すら
発音することができなかった
水差しは
つねに明日のほうへ
傾いていたように思う
花瓶のなか
とくとくとそそがれる闇に
何を住まわせようか
わたしたち
部屋のすみにも
あたらしい泉があることを知り
折鶴を
もう一度
丁寧にひきのばす
対岸に手を振る無邪気さで
また
人を傷つけて
そうやって、わたしたち、
選評/大崎清夏
タイトルを和訳すると「百の朝」。散歩、交差点、鏡、花瓶といった言葉によって、いくつもの、それぞれの朝の風景を重ねるように描いた詩です。ひとりのひとが過ごしてきた「百の日々の朝」なのか、百人が過ごす「ある一日の朝」なのかはわかりません。それでも、とても爽やかな朝というよりは、「犬の散歩に/犬を忘れてしまうとき」のことをぼんやりと思いだすような、あるいは「ぎこちない/箸の持ち方を咎める人」を冷めた視線で見守るような、曇り空の朝の雰囲気が、詩の全体を満たしています。
私たちがほんとうはよく知っている、日々の大部分に相当する、平面的な気持ちの時間。寂しさや悲しみとも言い切れない、もっと薄くて、けれどもないことにはできない、「感情」とも名づけがたい心の動きに、この詩人は触れようとしているようです。
そんな平面的な気持ちをすこーしだけ優しく揺さぶってみるような第5連が、とてもいいなと思いました。「つねに明日のほうへ」傾いている水差しと、「闇」が「とくとくとそそがれる」花瓶。水差しと花瓶は、もしかしたら同じひとつの姿かたちなのかもしれません。生の微細な感触が、ていねいに掬いとられています。