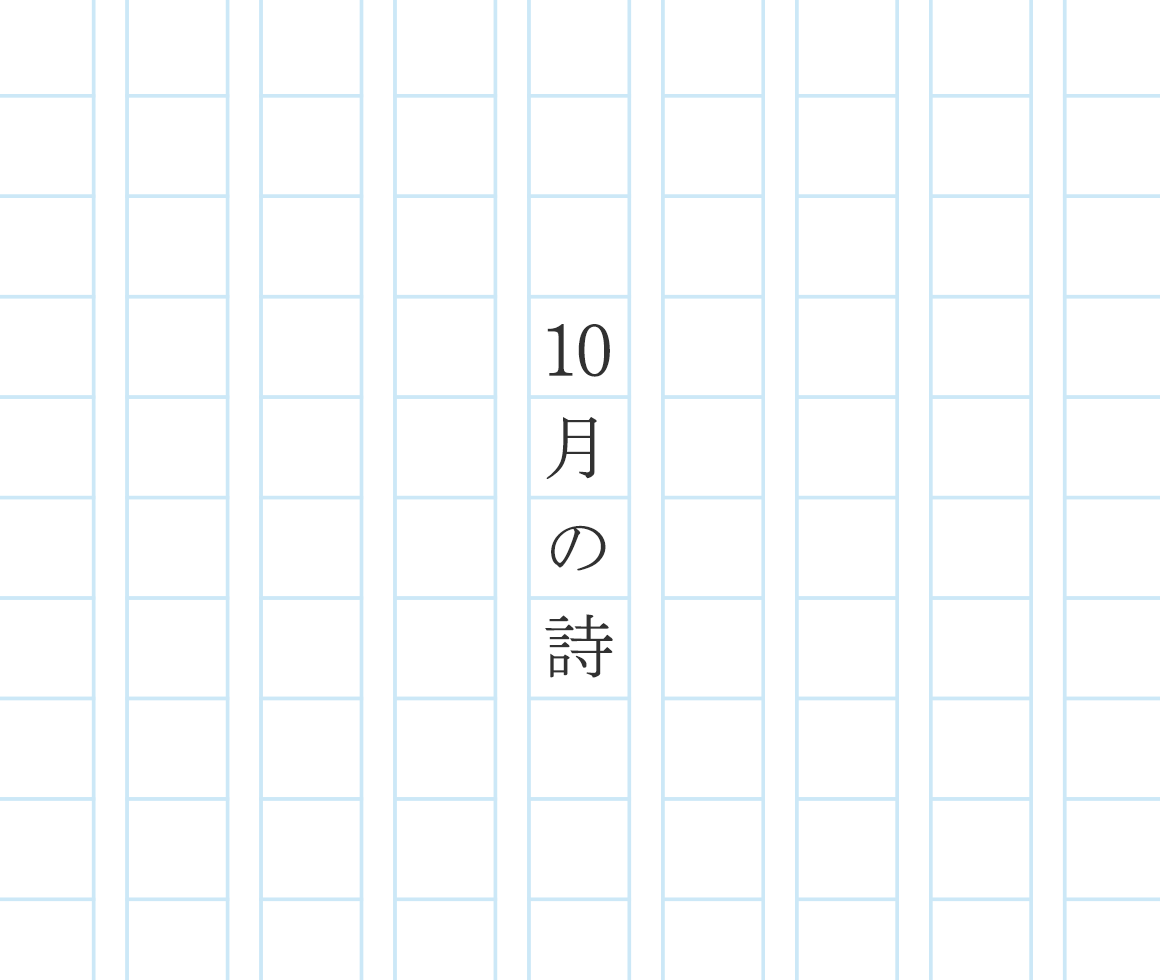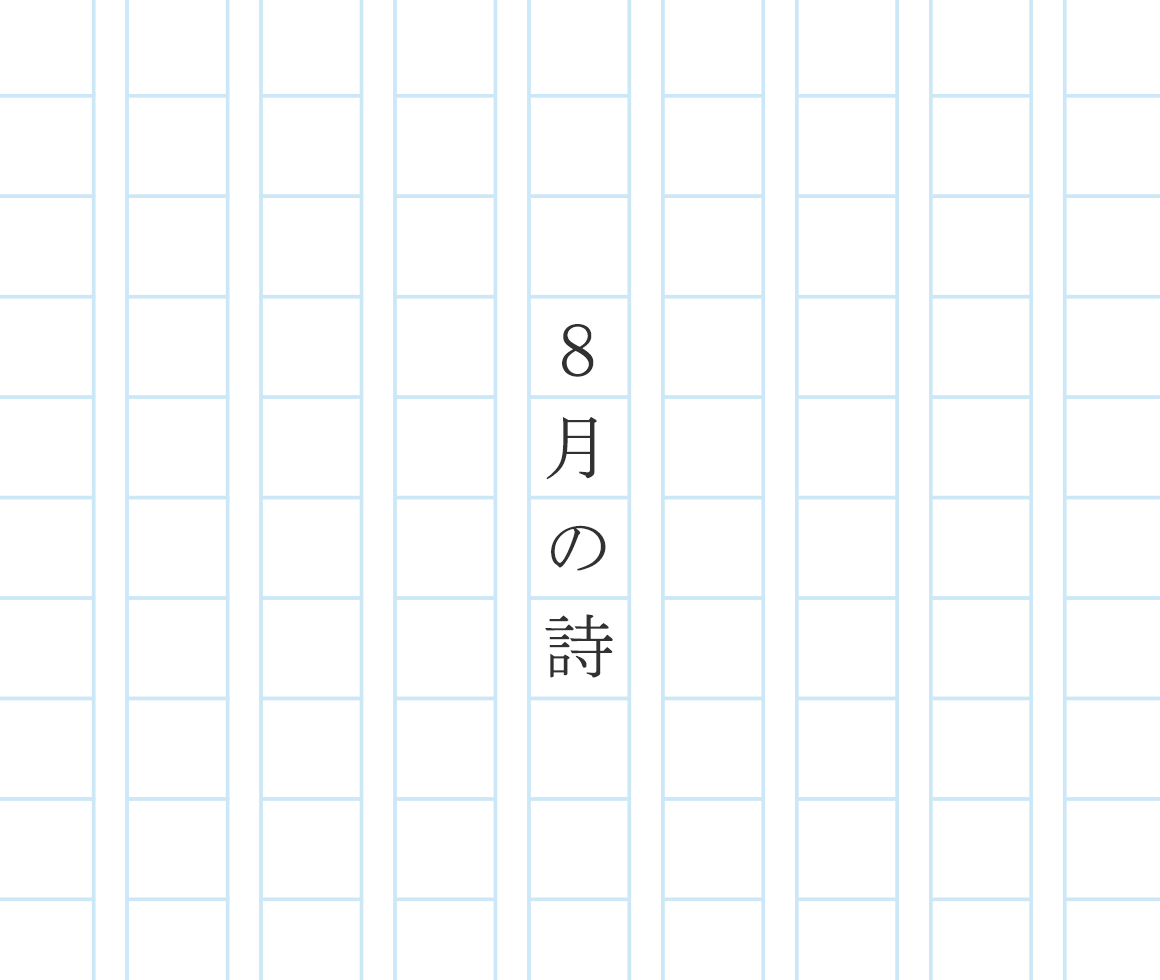蜘蛛が一匹、
狭いマンションの中に入り込んでいた
コーヒー飲んでもいい?
眉間の皺、すごいよ
いつまで仕事をやっているの?
もう、寝るよ
その蜘蛛は、
やたらに目の前を横切っては
話しかけてきているようだった
その蜘蛛は、
夜中、洗濯機を回した時に
慌てて出てきた
なるほど、洗濯機の下でいつも寝ているのだろう
その蜘蛛は、
時折、姿が見えなくなった
出て行ったのか
それとも洗濯機の下なのか
あるいはカーテンの影になったのか
その蜘蛛が、
ある日、窓の前で物思いに耽っていた
思うことはあったが、外に出してやった
これを機に、洗濯機の下を掃除しようと思った
しばらく寂しくなった
梅雨になり
雨の気配が近づいてきた頃
その蜘蛛は、また現れた
一体どこに通り道があるのか
平然と天井を歩きながら話しかけてきた
まだ仕事していたの?
洗濯機の下は、当分あのままにしておこう
選評/穂村弘
部屋の中で、小さな「蜘蛛」を見かけることがある。この作品では、そのような現実の体験と、心の中の解釈が微妙にズレながら、一つのハーモニーを作り出しているようだ。詩の舞台となる世界が、家族と同居している一軒家では成立しないだろう。一人暮らしの「狭いマンション」でないと駄目そうだ。それから、もちろん他の虫ではうまくない。「蜘蛛」という存在に特有の神出鬼没感がポイントなのだ。ベタな見方かもしれないが、この説得力と魅力の背景には、「夜中」に「洗濯機」を回すような生活感覚と、孤独感があるのだろう。「その蜘蛛」という言葉の繰り返しも、特別感とシンパシーを高める効果を上げている。名前をつけるほどではない関係性がいい。「パートナー」というタイトルが最善かどうかは検討の余地がありそうだ。