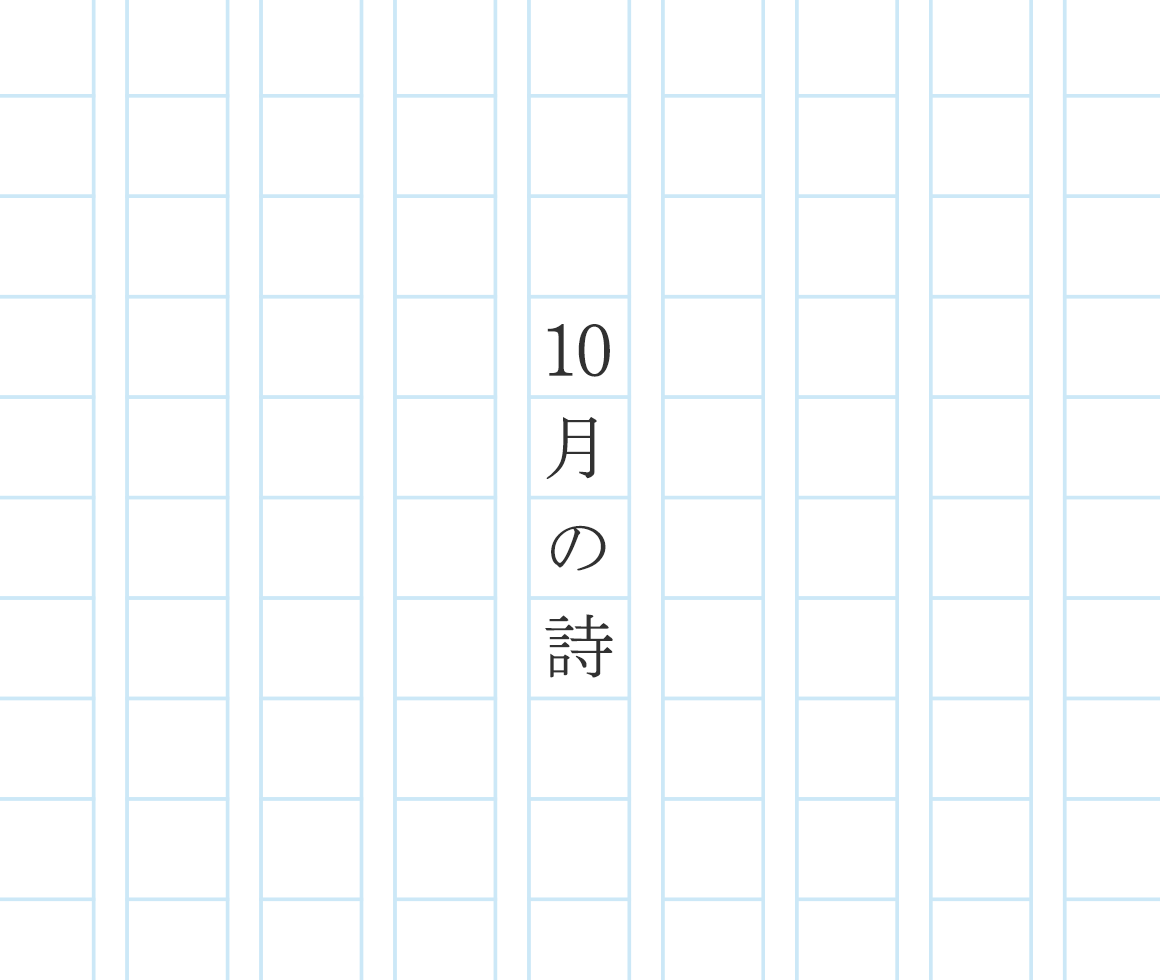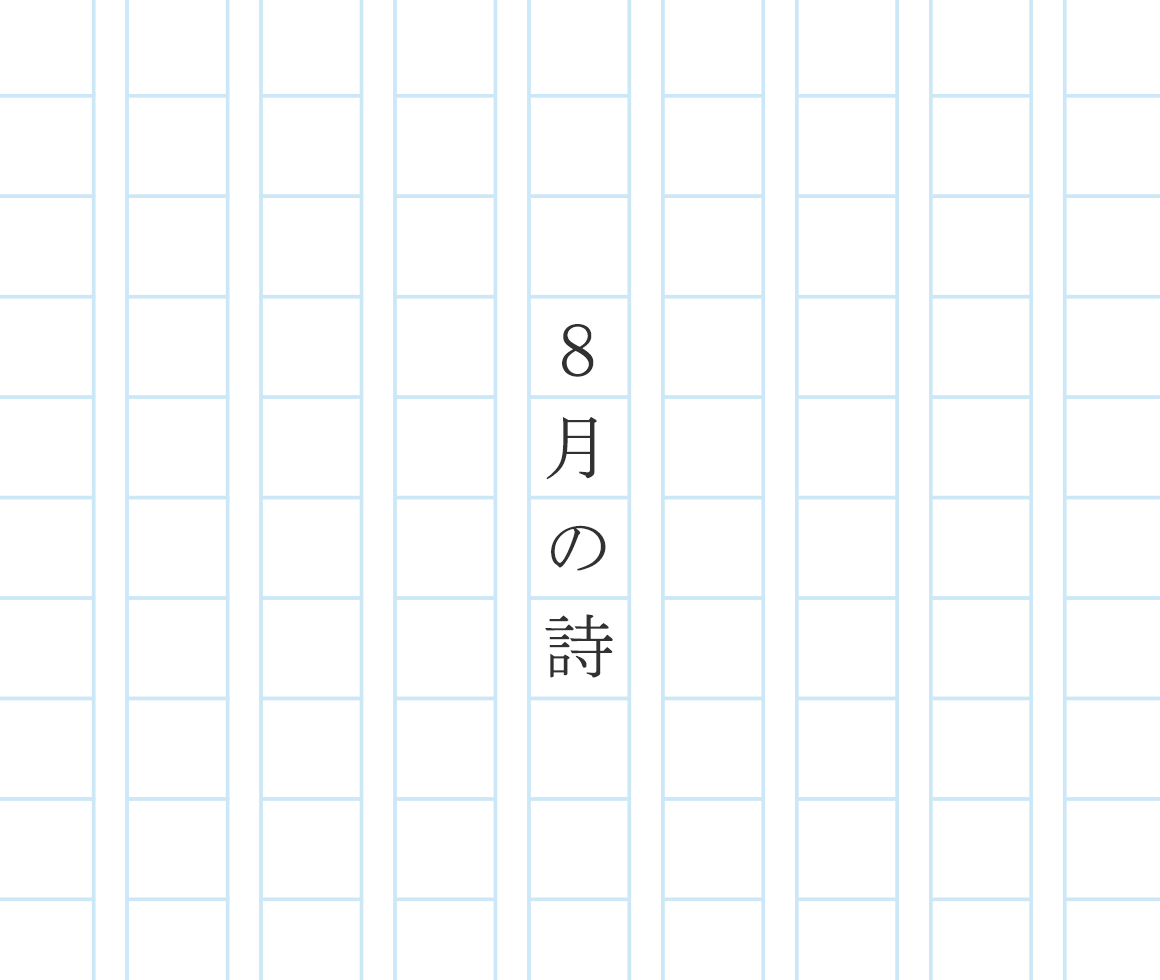生き延びたぶんの襟足を刈る
生き延びたぶんの髪の毛が床に落ちて
生き延びたぶんの重さが床に落ちる
これで生き延びられますか
と、両手に持った鏡が問う
これで生き延びられます。たぶん
やわらかな白が首に広がると、生き延びたぶんのわたしの産毛を剃るだけのような顔をしている剃刀が近づいてくる。ほらほら、ここで死んでしまえますよ、とけしかけて、わたしの首にふれる
けしかける剃刀が首にふれて、そのまま下りて、離れて、
またふれる
そうやって、何度もけしかけてくる
なんとかかんとかふん張っているところに
冷まされても、なおも熱いタオルが首に巻かれて、
今日も今日とて生き延びてしまった
自分の手の中の剃刀がわたしをけしかけていたことに気づいていたのだろうか、ご主人が「2か月くらい切ってなかったんだね」などと、わたしが生き延びていた時間をおおよそ言い当てたところで、たった今わたしが生き延びた5月の夕方に吹く風か、はたまた歩くわたしが吹かせている風か、そういう風を耳の下に受けながら駐車場まで歩く
はあ、今日も今日とて生き延びてしまったな
選評/大崎清夏
知らないうちに伸びてしまった髪の毛を切る、その切り捨てた分の重さをみて、どこか他人事のように「生き延びたぶん」の時間を観察している「わたし」。わたしたちの日常の中にうっすらと、でも確実に漂っている死の気配を、この詩はとても的確に漂わせている。それは人間が、たとえばこの理髪店のご主人が、ないことにして生きようとしている死の気配だと思う。
問いかけてくるのは鏡で、首にふれてくるのは剃刀で、理髪店のご主人の顔は見えない。そういう無機質なものや、熱をもった身体から切り離されて床に落ちた髪の毛や産毛のほうに「わたし」の実感は引き寄せられているのに、「なおも熱いタオルが首に巻かれて」、人間として生きるように仕立て上げられてしまう。
「なんとかかんとかふん張って」わたしたちは生きているけれど、なんのために生きているのか。生きてしまうことの受動性が迫ってくるとき、「死んでしまえますよ」という強迫=誘惑に、わたしたちはつい気をとられるのかもしれない。
結句の「はあ」で、この詩が維持してきた緊張感が、ちょっと抜けすぎてしまう気がした。欲を言えば、「はあ」に込めたものまで言葉で描ききってみせてほしい。この詩が描いている密やかな恐怖には、わたしも心当たりがあるから。