
90s in Hanatsubaki
2020.04.30
第12回 マイク・ミルズからスーザン・チャンチオロへ その3
文/林 央子
写真/細倉 真弓
キム・ゴードンやソフィア・コッポラという、雑誌のなかに頻繁に登場している人たちのコメントにはいつも気づきのヒントが隠されていたから、そういう人たちの記事をみつけるとやはり、すみずみまで読んだ。そうすると、その人がそのとき一番の興味がある人物は誰か、などの情報をしっかり見つけることができた。そういう情報を自分なりにつなげて想像のなかで人物関係図をつくっていて、マイク・ミルズとソフィア・コッポラとキム・ゴードンが互いに友人関係にあり、またマイク・ミルズがとても価値をおいている友人がアーロン・ローズであることなどもわかってきていた。私はもともと一人のひとの興味関心のあり方というのにもとても興味があった。一見バラバラのジャンルにいる人たち、ミュージシャンとアーティストと小説家などであっても、その人の興味ある人物として見てみると、彼らの共通項がすけてみえたりもする。みんなが普段から目にしている雑誌やCDを情報源にすれば、気になる人の最新の、時にはパーソナルな情報までしっかり把握できるし、それを見つけるのは自分だけの宝探しのような気がして、雑誌を読むことが大好きだった。記事本文も読んでいたけれど、インタビュアーがその人に聞いて直接記した情報がそのまま出てくるような、キャプション的な小さな文字の情報のほうに、わたしにとっては大事なメッセージがあることが多かった。
だから、自分が書くキャプションのような短い原稿も、スーザンという人物を知る上でヒントがたくさん隠れたものにしたい、と思って書いていたと思う。もともと長く書けるような場所ではないから、書き手の印象や情感をこめるような余地はない。それでも、取材させてもらった人から出てきた貴重な情報を、私の主観でまげることなく、なるべくその人の口から出た言葉そのままに、ピンで留めるようなものにしておきたい。そう思っていた。また、スーザンからもらったプレス資料に書かれている言葉もすべて読んで、参考にした。
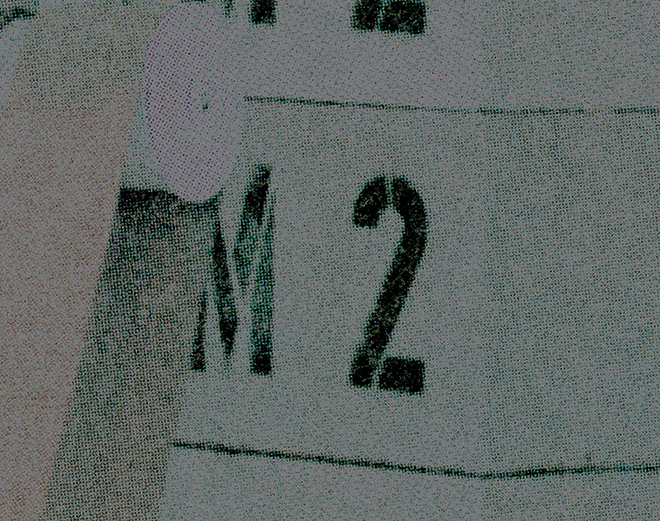
それにしても、「美大では絵画と彫刻を専攻?」「水着やランニング・クローズからのインスピレーション?」「抽象的、構造的で脱構築的?」それらの言葉の意味は、出会って20年以上がすぎる今となってはとてもよく理解できるものだが、ふつうに新進ファッションデザイナーを取材したときに出てくる言葉とはずいぶん、違っていた。その違いに出会ったときに、自分が理解できる情報だけをピックアップして発信してしまうことも出来ない事はない。けれども、「キャプション情報は宝の地図」だと思っている私は、なるべくヒントになるような言葉は端的に記しておきたいと思っていた。ただ、その時わたしが彼女の言葉からわたしがうかべた感情は、この短い原稿からはみえてこないはずだ。
その後5年間、2000年前後までスーザンが展開したRUN コレクションを夢中になって取材した私は、スーザンのインタビューを何度もさせてもらったけれど、毎回取材のあとにのこるものは大きな「?」なのだった。前回の「?」を胸に抱きながら、また次の取材に足を伸ばす。その活動を続けてきて、その後2000年頃にスーザンがRUNコレクションを一旦停止する決断をしたとき。私も資生堂をはなれて自分で『here and there』という個人的な出版物を立ち上げようとしていた。その創刊号には、それまで取材してきたスーザンの、「?」に導かれるようにして重ねた取材をつなげて、まとめて記すインタビュー原稿をつくってのせた。
(September 1996~January 2001)
<ファーストコレクション、1996年春夏。ソーホーのアンドレア・ローゼン・ギャラリーで/ニューイングランド生まれ/兄弟はいない/8歳のころから、枕カバーを切って、腕と袖をつくり、ドレスに仕立てていた/11歳のころからバービー人形のドレスをつくる/パーソンズで美術史とファッションを専攻。ペインティングもする/ハンドメイド/過去に、バーナデット・コーポレーションとのコラボレーション/RUN:逃げること/「ファッションデザイナー」とは?/何でもある時代。いろいろなジャンルから、なぜファッションを選んだのか/ここニューヨークで、毎日見ているものは?/時代の動きとの関連/フレキシブルvs ストロング/ヨーロッパ/自分の美をみつける/ファッション・ワールドと自分を保こと/インディヴィジュアル/信念/運動は好き?>
彼女のアトリエは、チャイナタウンのビルの隙間、中国人のおじいさんが居眠りしている細い通路を、身体の向きを変えながらやっと通り過ぎて、ガタガタいいながらすすむ古い鉄製のエレベーター(ときどき扉が開いて見えるのは、今世紀とは思えない縫製工場の一場面。ジェフ・ウォールの作品で有名な、あのアジアの工場シーンが浮かぶが、この目で見た現実の迫力には負ける)が、やっともちあげた「6N」のフロアにあった。スーザンはアーティストのリタ・アッカーマンとこのフロアをシェアしている。
1996年9月 ニューヨーク
「一回目のショーは、路上のファッションショー。2回目は屋外の駐車場をつかってショーをしました。空っぽの空間が美しいと思ったんです。車や飛行機など、スピードが早く動いているものに強くひかれます。私の服には、いろいろな要素が入っています。新しいものから古いものまで、すべて。デニムスカートのような既成の服を、自分でつくりかえることもします。シェイプをつくって、人の体の上にのせる、という行為が好きです」
「ずっとスポーツをしていました。中学・高校時代はランナーでした。スキーも、水泳も、エクササイズもします。ニューヨークでは毎朝、バッテリー・パークでジョギングをしています。自分をある限度までプッシュする、というスポーツの行為が好きなんです。また“人間の動き”という点において、スポーツも美とつながってくると思います。スポーツウエアのデザインにも美しいものがたくさんありますし、インスパイヤされることもあります」
「彫刻、絵、ドローイング、そのすべてに均しく興味がありました。かつてはドローイングだけに絞ることも考えたのですが、いつのまにか、本能的にファッションを選んでいました。毎日かならず、ドローイングやコラージュをしています。そこから服へ、考えを発展させていきます。これはずっと続けている作業で、これからも続けていくと思います。グラフィックをとても愛しているのです」
「でも、この秋に行う3回目のコレクション『RUN3』では動きのある表現をしたくなったので、ショーをせずに映画でプレゼンテーションすることにしました。いつも、自分の内側から出てくるものを正直に“表現”にします。それしか道はないと思っています」
「ニューヨークは恐ろしいほど、情報が集まってくる街。自分らしさを守りながら、自分の力を出していくためには、リラックスできる方法を学ぶことも重要です。そうでないと、自分が壊されてしまう。極端に強い意見をもっている人がたくさんいるので、この街でサバイバルしていると、どうしてもハードな感情を抱いてしまいがちです。だから、柔らかさや優しさは、自分で築くしかないのです。毎日毎日、リラックスして自分らしくいよう、といいきかせながら、全進していくのです」
「私が信じているのは、自分を表現するためには、たくさんのメディアをもつべきだということ。ひとつに限定しないで、つねにいろいろな方向に行ける状態に自分をもっていくこと。それは、今という時代のクリエイティビティーのありかたの鍵だと思います」

この原稿の途中で引用したキャプション的な原稿は『花椿』の誌面のために書いたもの。一方こちらは、その後何度も取材を重ねた彼女とのやりとりを、薄い一冊の本を書くような気持で5年後に、その取材ごとの印象ややりとりをまとめ、自分なりのスタイルで書き綴ったものの一部だ。当時、何度もニューヨークまで出張できたわけではないから、その時たった一回ずつ行なったアトリエでの打ち合わせと、取材当日に聞いたことをミックスさせて後日、書いたものだ。スーザンの言葉は取材者である自分の言葉や質問で遮らず、そのままに引用符でまとめる。けれども取材に行く前に自分が考えていたことは、取材ノートにあった言葉の羅列をそのまま冒頭に抜き書きして、記した。
キャプションのような原稿も、これだけ長く記した原稿も、どういう媒体にどういう形で情報を発信して届けていくか、という書き手の意識によってかき分けられるものだ。もちろん後者のほうが、その人物をよく知っているという経験知があるから、出会頭に発信できる情報とは質も量もかわってくるのだが。

この特集は私にとって、その頃一番つくりたい企画であり、そんなストーリを『花椿』の特集にすることは、生まれて初めて実現できた快挙だった。『花椿』にとってもニューヨークでのロケは、初めてのことで、現場では毎日、モデルの着替えや食事、実費精算などに気を配りつつ、スタッフの中で最年少でもあった私は日々、文字通り走り回っていたのだった。
アトリエでの出会いから数日後、『花椿』特集この時最後の撮影が、スーザンの場面だった。その日、スーザンはびっくりすることを私に言った。「取材のお礼に洋服をあなたにプレゼントをしたいけど、何がいいかしら?」
スーザンからのこの申し出は本当に驚きだった。いつもこのような申し出は、私にではなく、私の近くにいた、業界ではよく知られた存在の上司や仲條さんに、向けられていたからだ。なぜこの人は私に価値を置いてくれるのだろう? という純粋な驚きで頭をいっぱいにしながら、アトリエで見た彼女のアバンギャルドな服を思い出し、いちばん自分が生活のなかで着れそうな服を思い出して「デニムスカートが欲しい」と言った。日本に帰ってしばらくしたら、本当にその服が送られてきた。2度しか会っていないのに、サイズは私にぴったりだった。
その後20年以上にわたり交流が続くことになったスーザン・チャンチオロとの出会いはそれほど印象的で、わたしはいつまでも忘れないだろうと思う。そして印象的な出会いというものは、いつも自分がその相手を見つけにいくというよりは、相手が自分を見つけてくれるということもあるものだ、と思い知ったのである。

林 央子
編集者
1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)
http://nakakobooks.seesaa.net/
https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓
写真家
東京/京都在住
触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。
http://hosokuramayumi.com
















