
都築さんの「密談」(1988年 8月号)でも紹介されたアルフレッド・バーンバウムさんは、90年代の『花椿』のテキストを語る上でとても重要な存在だ。彼は89年4月号から91年12月号までの3年間、「KOKORO」という<外国人の目線から見た、なんとも変わった国、日本>についてのエッセイを編集部の依頼によって執筆していた(筆名はスペンサー・イスフリー)。来日まもない外国人が見る「フシギでオモシロイ日本」についての声をあつめたNHK BS1の日曜夜の人気番組『COOL JAPAN~発掘!かっこいいニッポン〜』は2006年春に放送開始し現在も放映が続いているが、その先駆的なエッセイともとらえることができる。
この「KOKORO」はアルフレッドさんの後にリービ英雄、ケイト・クリッペンスティーン、レスリー・ポロックなどさまざまな方に単発もしくは連載で執筆を依頼し、93年3月号まで続いた。当時は毎年、1月号もしくは4月号で誌面をリニューアル、連載を見直していたから5年間続いたというのは、『花椿』のなかでも長寿の読み物の一つになった、ということだ。
「KOKORO」をアルフレッドさんが書いていたころは平山景子さんが担当し、リービ氏以降は私が担当する読み物になった。90年代半ばになるとアルフレッドさんは東京を拠点にしながらも、タイやミャンマーによく旅するようになったため、その活動を反映した「アジア・スープ」という連載を執筆していただいた(96年1月号〜98年12月号)のだが、今回はその前段でもあったアルフレッドさんによる「KOKORO」の連載を中心にご紹介したい。
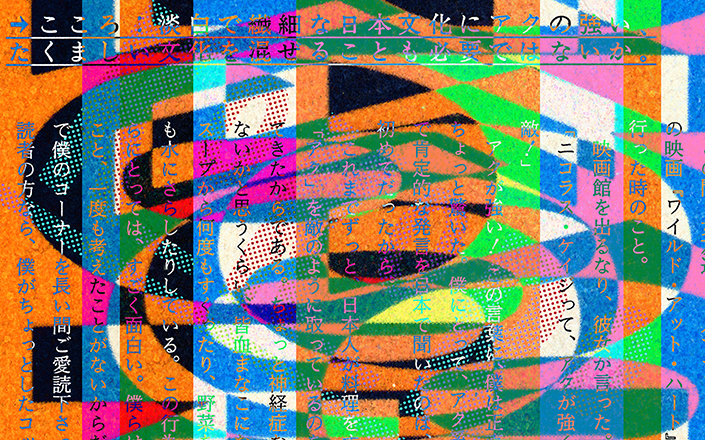
よく記憶しているのは、「KOKORO」の連載を担当していた当時の編集長、平山さんが私にアルフレッドさんを紹介するときに、こう話していたこと。「アルフレッドさんは、村上春樹の小説を英語に訳した人なの。時々アルフレッドさんの訳のほうが日本語の小説より良いという人もいるくらい、彼の翻訳には定評があるのよ」
80年代にアルフレッドさんの翻訳によって英語になった村上春樹さんの本には、 『1973年のピンボール』"Pinball, 1973" (80年作品 85年翻訳)、『風の歌を聴け』"Hear the Wind Sing" (79年作品 87年翻訳)、『羊をめぐる冒険』"A Wild Sheep Chase" (82年作品 89年翻訳)、『ノルウェイの森』"Norwegian Wood" (
87年作品 89年翻訳)などがある。90年代には『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』"Hard-Boiled Wonderland and the End of the World"や『ダンス・ダンス・ダンス』"Dance Dance Dance"をアルフレッドさんが訳した。
アルフレッドさんはアメリカ人だが、子供時代を日本で長く過ごしたようだ。ミャンマーをはじめいろいろな国にフットワーク軽く移動しているけれど、活動の拠点として日本で費やした時間はかなり長いはず。『花椿』のエッセイ「KOKORO」のなかでも、日本語の上手すぎる外国人は日本では好かれないということを自身の体験をもとにユーモアたっぷりに書かれているが、実際に会話をかわしてみるとこちらが腰を抜かさんばかりに彼の日本語は流暢だ。
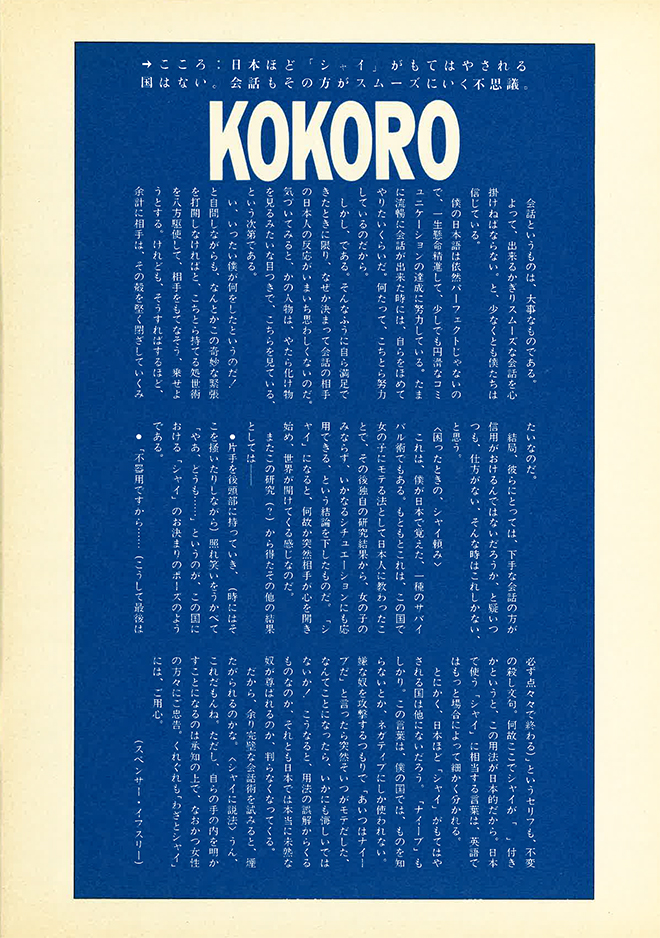
アルフレッドさんが綴った日本は、面白く、おかしく、奇妙で、外国人に不慣れで、愛すべき、独特なカルチャーの国。そのような、<外から見た日本>についての言説を、誰よりも当の日本人である私たちが面白がるという感覚は、90年代前夜から初期に顕著になってきたものであるように、今振り返ると思えてくる。
2000年代、東京で地下鉄に乗ると、英語だけではないさまざまな言語を話す観光客にたくさん出会うけれど当時は、おそらく京都をのぞけば、日本といえばわざわざ外国人が「観光」をしに来る場所ではなくて、ビジネスなどで仕方なく滞在する外国人が広尾の周辺にいるくらいだった。そのなかで日本固有の文化を面白がろうという視点をもっているアルフレッドさんのような人はごく一部。翻訳というお仕事を通して、昔のではなく同時代の、日本人の感性を紹介された功績は大きい。村上春樹の小説の英語訳というのはもちろん、現代の日本文化の世界にむけての紹介という側面からも非常に多くを貢献されたことに誰も異論はないだろうし、この連載の前回にご紹介した都築響一さんの出版物を英語に訳すのも、ほとんどアルフレッドさんが手がけられている。

アルフレッドさんの「KOKORO」の連載はわたしが編集部に入って一年後から始まった。「密談」は入社したその年の連載だったので、まだ勝手もわからないまま終わってしまった印象だが、わたしにとっては『花椿』でのさまざまな体験が味わいを増していく日々に併走してくれていたのが「KOKORO」の連載だったという意識がある。
わたしは今でも台所に立って料理をしていると、自ら料理の達人であり、異文化に通じていることから各国の料理の流儀を引き合いに出しつつ、その国の国民性を語ることもできてしまうアルフレッドさんが「KOKORO」の91年3月号で書いた、“日本人はなぜ<灰汁(アク)>を、親の敵のようにすくうのだろう?”という主旨のエッセイを思い出す。そして、料理のたびに律儀に「スープが透明になるまでアクをすくわなければ!」という脅迫観念から解放され、ちょっとホッとするのだ。それはとても小さなことかもしれないけれど30年間、日々欠かせない料理のなかの小さなプロセスを「まあ、別に目くじらたてて徹底することじゃないんだな」と気づかせてくれたことのありがたさには、元々ずぼらな私は計り知れない恩恵を受けていると思う。

またこの30年間、さまざまな地域にできた美術館や芸術祭に導かれるようにして地方に旅行することが増えたり、瀬戸内海の直島が外国人観光客の好む旅先になったりしたことで、日本人も日本国内の旅先について興味をもつようになったことは大きな変化だ。けれども「KOKORO」において、日本の地方都市をヨーロッパにあてはめると金沢はベルギーで、福岡はスペイン、仙台はフィンランド、和歌山はポルトガル……といった論調のエッセイ(90年7月号)を読んだときも、その発想力に膝をうったものだ。最近こそ脱都会志向があらわれ、地方の良さを見直そうという動きは盛んになっているものの、まだまだ都会志向だった90年代のはじめに、日本のさまざまな地域の良さを別な角度から眺めてみようという提案が、彼のような都市生活者からなされたことは、とても新鮮だったことを記憶している。

アルフレッドさんのエッセイが、30年たった今でもとても興味深く読めるのは、彼個人のなかの日本体験が、血となり肉となっているから。そしてもちろん、アルフレッドさんの様々な旅先での経験がいろいろな風味のダシとなって、アルフレッドさんだけが書けるユーモアいっぱいのスープになっているからだと思う。
アルフレッドさんを筆頭にして、都築さんの「密談」最終回に登場した編集者のレオナルド・コレンさんや、『花椿』のアート欄で長く毎月コラムを執筆していたヴァルデマー・ヤヌスシャックさんなど、『花椿』の誌面の裏側には、日本とかかわりの深い人たちがたくさん、有形無形にかかわっていた。コレンさんはアメリカ人、ヤヌスシャックさんはイギリス人だが、おふたりとも日本人の奥様がいらっしゃると伺っていた。こうした方たちの日本への興味がまずあって、『花椿』の限りのある誌面に、質の高い情報があつまってきていたからこそ、「冊子」ではなく「雑誌」という存在感を保てたのだろう。

連載を担当していたころ度々うかがったアルフレッドさんの、外苑前のワタリウムの裏手くらいの、コンクリート製のマンションの小振りな一室で、エスプレッソを淹れながら執筆しているアルフレッドさんのたたずまいを思い出す。インテリアはすべてDIYで壁は黄色く塗られ、ユニットバスは取り外されてシャワーに変換されていた。自ら手直ししたその部屋は、いかにも『Elle Deco』で見かけそうな洒落た空間になっていた。R不動産が登場するずっと前、日本で「リノベーションをした粋な部屋に住む」ことはごく一部の特殊な才能(?)の持ち主にしか実現できない夢のような憧れだった。
似たような話題でいえば、ベルリンの壁がくずれたのが1989年。東ドイツの空き物件に不法占拠して住まう「スクウォッティング」の居住スタイルを知ったのもこの頃だったけれど、それは日本の住宅事情においては到底、不可能なことだと感じられた。わたしたちは、日本という島国だからか、勝手に諦めていたり、権利がないと思い込んでいることがたくさんある。そのあきらめていることの根っこには「自由」とか「尊厳」とでもいうべきものがある気がしていた。でもそれは、本当は手に入るものなんだよ、目をこらせば見つけることができるんだよというメッセージを、アルフレッドさんのように日本を血肉化しているけれど、同時に日本を外から見る目ももった人が、発してくれていた。それがアルフレッドさんの書く「KOKORO」の根底にながれる、わたしたちへのメッセージだったような気がしている。

林 央子
編集者
1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)
http://nakakobooks.seesaa.net/
https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓
写真家
東京/京都在住
触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。
http://hosokuramayumi.com
















