
この連載「90s in Hanatsubaki」の執筆がはじまったとき、私は編集部にお願いをした。「過去の合本を見直すことはできますか?」。合本というのは1年分の『花椿』をまとめて一冊の本にしたもの。私が編集部にいたころは、編集部員1人に1冊ずつ、自分が仕事した年の合本が支給されていた。『花椿』はうすい冊子なので、一年分束ねてはじめて、一冊の本のようになる。過去の記事を参照するために、合本は頻繁に手にとるものだった。
こうして2018年秋から資生堂本社のある銀座に足を運びながら、『花椿』のバックナンバーを読み直す日々が始まった。私は会社員のころいつも、新橋駅から職場に通っていた。銀座という華やかな街の、後ろ姿から徐々に近づいていくような道のりが気に入っていた。だから今回合本を見るために通うようになったときも、この道のりを選んだ。現在、編集部が入っている建物は、銀座7丁目の本社ビル。この建物は私が社員でいた90年代頃とは外観が変わって、周囲の華やかさと釣り合うように、とても綺麗に装飾されている。当時の『花椿』編集部は、本社ビルの近くにある別の建物に入っていたのだが、現編集部はそのころの仕事場より、ずっと綺麗な空間に変わっている。もっとも私は、編集部にお邪魔するのではなく、編集部が用意してくれた会議室に入っていき、一人で作業をする。
久しぶりに再会した『花椿』合本のなかでも最初に手にとったのは、私が入社した年の1988年の合本だった。自分が希望した『花椿』の仕事ができることになったとわかり、実際に銀座で編集の仕事がはじまると、いつもワクワクした気持ちで眺めていた『花椿』。久しぶりに懐かしく開いたその合本でひきこまれたのは、都築響一さんが88年4月号から一年間連載された「密談」という対談ページだった。

この対談は私が担当したわけではなかった。入社したての私が担当したのはごく限られたページだけで、あとは皆さんのお手伝いだったから。都築さんのページは、のちに編集長になって93年4月号から紙質を変え、デザインをリニューアルさせた小俣千宜さんが担当していた。けれども、都築さんを対談連載に招いたのは当時の編集長、平山景子さんだったと思う。都築さんは平山さんとよく交流されていて、編集部にも頻繁に、海外のアーティストなどのお友達をつれて遊びにみえていた。私はそんなときにお茶を出ししたりしてご挨拶するだけだったが、分け隔てのない都築さんは新米の私にも、フランクに話をしてくださった。
都築さんといえば、若者の一人暮らしの部屋をポートレートのように撮影された分厚い写真集、名著『TOKYO STYLE』を出版されるのが93年。「密談」を連載されていた88年当時はちょうど、『ブルータス』や『ポパイ』に書かれるライターのお仕事から、現代美術の全集『ArT RANDOM』を京都書院から出されるなどの、ご自身の出版企画にシフトしていかれる時期ではなかっただろうか。「密談」を再読して改めて痛感したのは、都築さんの編集者としてのセンスの鋭さ。そして、90年代を目前にしたその頃、写真も扱う雑誌という情報メディアにおいて、本来は黒子のように表に出ない「編集」という行為が、「表現」になり出した時代、まさにそのころの時代性というものである。

この「密談」を『花椿』からぬきだして一冊の本にしたら、88年という時代の先端を走っていた人たちの意識を、ヒリヒリと手にとるように知ることができるだろう。書籍の編集者からしたら、「これでは薄すぎる」のかもしれないけれど、私の感覚からしたら、そのくらい価値のある読み物だと思っている。ある月は、四国の宇和島に引っ越される直前の、大竹伸朗さんが出てくる(88年6月号)。ある月は、現代陶芸から現代美術に転じたギャラリスト、ギャラリー小柳の小柳敦子さんが出てくる(88年7月号 当時は現代陶芸中心のギャラリーの若き女性画廊主、と紹介されている)。ある月は、その後『花椿』で重要なエッセイストになっていくアルフレッド・バーンバウムさんが出てくる(88年8月号)。アルフレッドさんは村上春樹さんの小説を英語に訳したことでも知られる翻訳家であり、また料理の達人でもあり、たくさんの旅やプロジェクトを手がけてきた多彩な人だ。
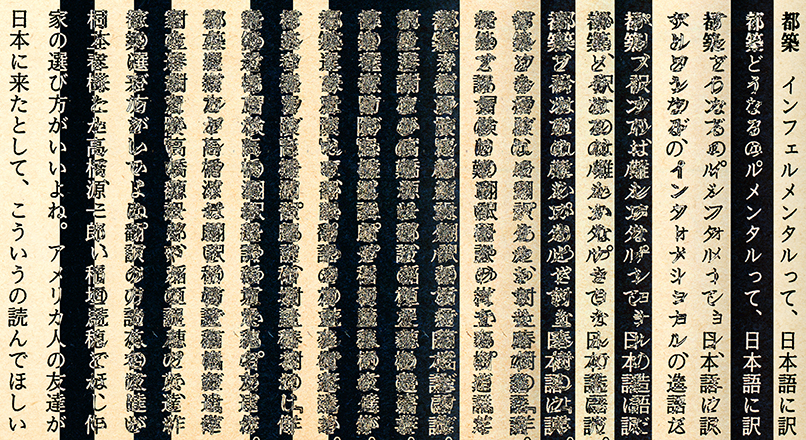
この連載の初回は『花椿』の側で出会いを設定した、スタイリスト安部みちるさんと都築さんの対談(88年4月号)。安部さんと都築さんは、この誌面が初対面だったと聞いている。安部さんは当時、もっとも先端的なイメージのあるスタイリスト。スポーツがわりにディスコ通い(「第三倉庫だとファッション屋さんが多くていやだから、トゥーリアやJトリップバー」)、朝はティップネスでエアロビクス、という話題がでるかと思えば、10年以上お茶のお稽古に傾倒していて、いまのマンションでは茶室を作れないことが悩み、などの話が繰り出される。お茶、歌舞伎などの日本の伝統的な文化に傾倒していることや、京都の一保堂の炒り番茶が大好きで、よく行く旅先は奈良や河合寛次郎記念館そして日本の高野山の宿坊、という話をされている。
当時は、インターネットはまだ普及していない時代だ。東京でカタカナ職業についた人の間では、海外の人との個人的な交流や外国の雑誌を通して、さまざまな異国の都市の情報が行き交っていた。それらは誰もが手にいれられるものではなかったからこそ、人より一足早く知っているという「情報に到達する速度の差」が生まれ、「価値」はその人独自のルートで手にした情報からつくられた。そして、つねに新しい感覚をもとめている人たちは、自らの刺激を、海外最先端の都市から届く情報にはじまって日本の伝統芸能まで、幅広い世界から素早く、自由気ままに選びとっていた。それがあたらしい時代を生きる女性のイメージであり、幅広い選択肢を取り揃えた生活こそ、最先端だと思われていた。渋谷に現在のLoftのもとになる「シブヤ西武ロフト館」がオープンしたのが87年冬。まさに90年代が花開く直前のこの頃から、「あらゆるものを取り揃えること」こそがあたらしく、都会的で画期的だと迎えられていた。

この連載「密談」は、都築さんがパーソナルに交流している人々と、毎晩飲みながら話しているようなプライベートな雰囲気の会話を、誌面のために公開してほしい、という主旨の企画だった。もちろん編集部の感覚による人選も、なかにはあったかもしれないが、ほとんどはその後の都築さんのお仕事にもつながっていったお友達ばかり、とお見受けしている。都築さんだからこそ出会われ、その後も親しく交流された方々だ。それは日本全国の人が、名前や顔を知っているような人々ではないかもしれないが、それぞれのその後のお仕事の活躍ぶりが分かっている今となっては、とても豪華な顔ぶれだ。とはいえ、掲載当時のタイミングでは「知る人ぞ知る」という存在の面々だったことは、間違いないだろう。当時の言葉で言えば、都築さんも都築さんが対談に招いた人も「カタカナ職業の、ギョーカイの人々」ということになるだろう。90年代直前に、都会でそういった仕事につく一部の人々の、アンテナの鋭さや時代を先取りする感覚が、この連載にはとてもよく表現されていたと思う。
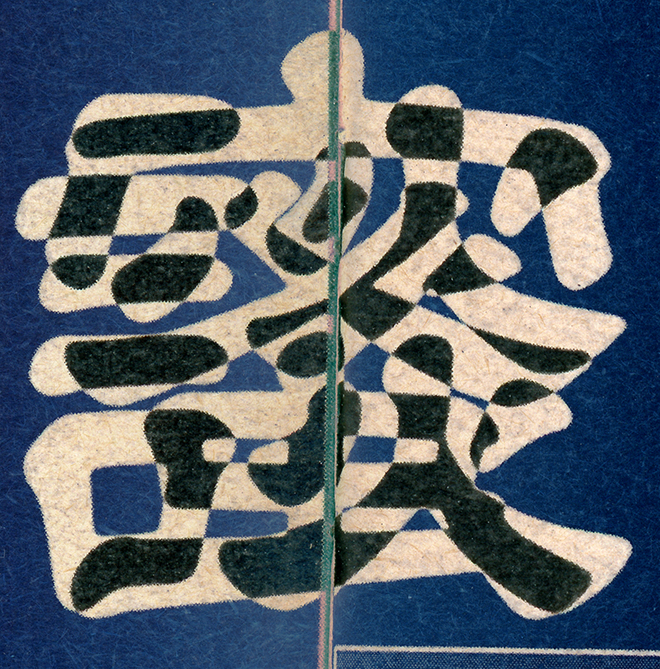
まだ編集部に入ったばかりの私が深く知ることではないが、当時編集部の中では、この連載に対して、異なる意見があるようだった。というのも「プライベートな会話」には、事前の下調べやリサーチは本来、必要ではない。その日出会ったその時の気分や関心事が、会話の内容に反映されていく。そうした機微をすくいとってこそ、より貴重な記事になる、という考え方がある。都築さんの「密談」の会話は、こういった観点からつくられているからこそ、とてもリアリティがあるし、30年たった今においてもその場を貫いた問題意識はより、切実なものになっていることに気づく。つまりプライベートな感覚で親密な相手との会話がふつふつと沸き上がる沸点の水面にあるものをしっかりキャッチした都築さんの「密談」は、とても早い時期に、的確に、さまざまな現代的な問題を提起されていたと思うのだ。
一方で、「今日のあなたの気分ではなくて、あなたの専門分野の情報を深く掘り下げて語って下さい」という考え方もある。編集部の中に異なる意見があった、というのは、このような異なる考え方が「雑」の部分として編集部内で共存していたということだ。「今日の気分」のような語りがずっと続いていること自体に意味を見出せない、それは深みがなく浅い話だと思う人もいた、ということ。けれども私はそうした見方には、同意出来ない。もしその上澄みのもとをさぐっていけば、氷山の下の塊のように、大きな本質につきあたる可能性がある。現在の私は、そう考えている。
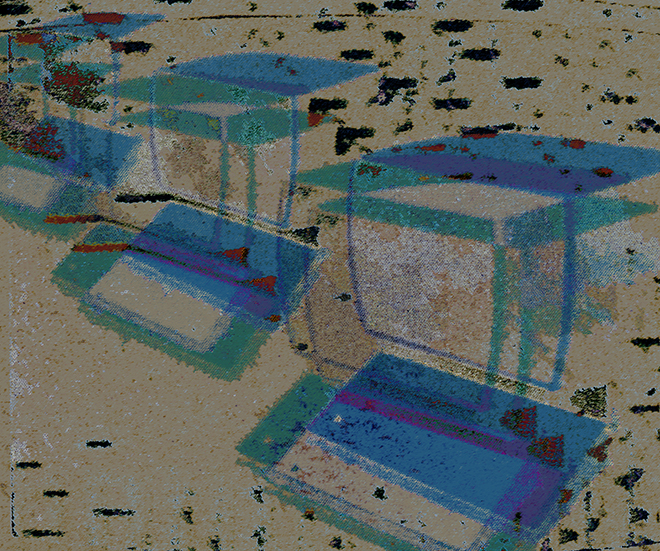
この論点をつきつめていくと、こういうことだ。プライベートな会話が、新聞などに書かれている公的な言論に比べると貴重なものではない、という考えに私は反対で、親密な信頼関係のもとに交わされる会話にこそ本質が宿る、と思っている。だからこそ、今私が個人的に編集している個人雑誌『here and there』では同時代を生きる人たちと個人的で親密な対話から生まれたやりとりを保管しているような意識で編集しているのだ。
30年前のあのころ、都築さんがお友達をよんで『花椿』の誌上で展開してくださった貴重な話題———30年後の今も驚くほど、重要な問題ばかり——をここで、ざっと見ていこう。
「伝統っていうのは、アバンギャルドだと思うの。因習とは違って」
「東京にいると、つい仕事の電話をしたり。でも高野山では部屋に電話なんてないから、シャットアウトって感じ。(略)清まる思いがする。」(安部みちる談)
「坂本九が『スキヤキソング』でヒットチャートの1位になったのは、もう20年以上も前だけど、日本人が日本語で作詞作曲して歌って、全米ナンバーワンというのは、もう奇跡だよね。今、機材も情報も発達して、誰でも簡単に外国に行けるようになって、簡単にヒットチャートにのれそうじゃない。でも、できないってところがおもしろい。やっぱり、テクニックじゃなくて思いが世の中を変えて行くという、一つの例だと思う」
「自分の描く線と全く同じものは世界にない。どんなに似た人がいても同じ顔の人は一人もいない。これ、神様が暗黙のうちに人間のオリジナリティーを教えていると思うの。(略)だから、俺はこの世の中をまだまだ信じていられるんだ」(大竹伸朗談)
「作る人、売る人、買う人。この3人がいて初めて成り立つんだと思うのね。」
「バリ島のウブドという村なんて、『朝、窓のこっち側にいた牛が夕方にはあっち側へ行ってた』というほかには何にも景色の変わらないようなところなの。自然の調和があって、一日中眺めていても飽きない。やはり、自然の中の静物、鳥とか、花とか、私も含めて、神々によって生かされているのだ。『神に感謝』っていう言葉が素直に言えた。東京にいたらそんなこと絶対、考えられない」
(小柳敦子談)
「大学のころ、建築の勉強をしてて途中でやめたのは、新しいものを作るより今あるものを改造するとか保存する方が意味があると思ったから。廃墟的なところに魅力を感じるんだ」
「僕の翻訳の仕方は、まず頭のスクリーンに状況を描いてみて、英米人ならどういうだろうと考える。いったん崩してから組み替えるという方法をとっているから、時間はかかるけど自然な英語になると思うよ」
「今まで英語で紹介された日本文学は、あまりにも暗くてしめっぽい谷崎潤一郎的な世界だから(笑)。それだけじゃないぞ、こういうのもあるよって伝えたい」(アルフレッド・バーンバウム談)
地方と都市、欧米と日本、前衛と伝統、ジャンルを超えた表現、東京にいても手に入らないもの。さまざまなゲストが、自分の問題意識として語るそれらのことは、2020年を目前にした現在の私たちが抱く問題意識と驚くほど似ている。都築響一さんは96年に刊行された『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』で木村伊兵衛賞を受賞された。その後も定期的にユニークな本を出版され続け、個人メールマガジンを発行されるなど出版の新たなあり方に果敢に挑戦されている。その勇敢な編集姿勢は、都築さんが93年に出版された初めての写真集『TOKYO STYLE』のあとがきに記されたテキスト『坐して半畳、寝て一畳』に集約されているのではないだろうか。敬意を持って引用させていただきたい。
「いままでたくさんのメディアが、日本の住まいについて語ってきた。けれどもそのほとんどすべては、実際に住んでる僕たちにとってはなんのリアリティも持たない。単なるレディメイド・イメージにすぎない。「和風」という商品名にすぎない。
本書はテクノロジーも、ポストモダンもワビサビも関係ない単なる普通の東京人がいったいどんな空間に暮らしているのかを、日本を外から眺めている人たちにある程度きちんとしたかたちで紹介するおそらくはじめての試みである。
家賃を何十万円も払えない人々がどんなふうに快適な毎日を送っているのかを、僕はテクノロジーと茶室や石庭がごちゃごちゃに混ざったイメージ・オヴ・ジャパンがはびこるなかに情報として投げ込んでみたかった。」
(都築響一『TOKYO STYLE』あとがき「坐して半畳、寝て一畳」より引用)
誰も伝えないなら、自分が伝える場をつくろう。そういう姿勢を編集者になりたてのころの私は、都築さんのような先輩編集者を見ながら、感じ取っていたのではなかっただろうか。30年前の『花椿』を開いて、そんなことを思った。

林 央子
編集者
1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)
http://nakakobooks.seesaa.net/
https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓
写真家
東京/京都在住
触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。
http://hosokuramayumi.com
















