
90s in Hanatsubaki
2021.12.16
第16回 『花椿』とは何だったか? その1:探究心がひらく雑誌
文/林 央子
写真/細倉真弓
2021年10月、秋晴れの日の午後に、銀座7丁目から汐留にうつったという資生堂花椿編集部に出かけていった。帰国後、はじめての連載打ち合わせのためだ。現役編集者の戸田さんと私が、それぞれこれまでの連載を読み直し、気になることなどをまとめ、打ち合わせにのぞんでいた。私は1988年入社。戸田さんはファッション業界紙『WWDジャパン』を経て2012年に入社、お互いがそれぞれが関わった、あるいは関わっている『花椿』というものの姿を言葉にしようという思いを、やりとりしていた。気がついたら日が沈んで、夕方になっていた。この打ち合わせに二人が費やした時間を支えていた思い、それが『花椿』の正体である気がした。

「『花椿』とは何か?」。現役編集者だったころの私の頭には、いつもその問いがあった。企業の発信する媒体であり、売り上げを問われるわけではない『花椿』は、その発信行為に企業が価値を見出すということが存在理由だ。前身の『資生堂月報』『資生堂グラフ』から数えて100年続く媒体の歴史のなかで、その灯火が消えかけたときが幾度となくあったことは、私の実体験でも知っている。企業の中でそれをつくる一人一人が、その意義を自問自答しながら作る媒体。『花椿』の編集行為は、自らの価値を自分たちでつくり続けることでもあった。
1966年から『花椿』のデザインに携わるグラフィックデザイナーの一人であり(この頃は複数のアートディレクターが制作に関わっていた)、1982年から2011年までただ一人でアートディレクターをつとめた方に、仲條正義さんがいた。じつは、この原稿を書いた直後に私は仲條さんの突然の訃報を耳にしたのだが、その仲條さんは、『花椿』といえばMr Nakajo、というように多くの人に愛された、媒体の精神を象徴する存在だった。私が1988年に入社したときから2001年に退社するまでもずっと、『花椿』は仲條さんが40ページ強の誌面の細部まで目を光らせている媒体で、それほど長い年月、一人のつくり手が、ファッションにも精通したアートディレクターとして深くかかわったという歴史を背負った出版物は、類を見ない。
今年のはじめに、その仲條さんの作品集が出版されたことで、仲條さん人気が巷で盛り上がっている、と打ち合わせで聞いていた。その稀有な活動歴が知られれば、より広い世代に仲條さんの功績が受け入れられるだろうことは、想像に固くない。とはいうものの、雑誌のデザインはグラフィックデザイナーやアートディレクターが一人でつくるものではなく、編集部との丁々発止によって生まれるものでもある。当時の編集部の空気を回顧することで、見えてくるものは何だろうか?

私と『花椿』の関わりを、時系列で見ていこう。1988年に資生堂に入社し、『花椿』編集部に入った私に最初に与えられた仕事は、資生堂の企業方針を取材して外の世界に向けて紹介するとても短いコラムや、化粧品の新製品カタログなどだった。そのほかに、当時編集長だった平山景子さんが担当していたファッション要素の強いBeautyページの撮影には入社当初から参加していて、素顔のモデルが瞬く間に、ファッションとヘアメークでドラマティックに変身していくさまをつぶさに見ていたし、『花椿』の精神を体現しているといえそうな「イン・ファッション」の、撮影前のスタイリストとの打ち合わせには毎回参加していた。編集長や先輩編集者がさばくファッションページに、まぶしい憧れをもってみていた。
そして『花椿』のファッションといえば、春夏と秋冬の年二回のプレタポルテのファッションショーをレポートする、コレクション特集がある。創刊直後はパリのジャン・パトゥ社との提携で流行情報を紹介していたが、時代を経て、70年代にはパリに住むファッション・ジャーナリストだったメルカ・トレアントンさんに寄稿いただくスタイルになっていた。私の入社から5年後の1993年春、編集長だった平山さんがファッション・ディレクターに、それまで副編集長だった小俣千宜さんが編集長に交代した。それにともなって、まずは先輩編集者でその後『VOGUE JAPAN』の編集長になる渡辺三津子さんが、その後私自身も1993年10月からパリコレに取材に行くようになった。渡辺さんがフリーになった90年代後半からは私が「イン・ファッション」ページと表紙の撮影も担当するようになっていった。このような変動にともない、パリコレレポートを、私が一人で書いた号もあった(1998年3月号)。編集長でいる間は平山さんが自らレポートを書くことはなかったが、編集長の立場から変わって、ファッション・ディレクターとしての関わりになっていった93年 からは、平山さんも執筆という形で『花椿』に関与することになり、1998年9月号からは平山さんと私がそれぞれ6ページずつ、合計12ページの特集を分担するシステムが出来上がって行った。そういった経緯もあり、この時代は、『花椿』の姿が変遷するなかで、異世代と異文化の声が、薄い『花椿』の冊子にあつく集約されていた時期だといえるだろう。
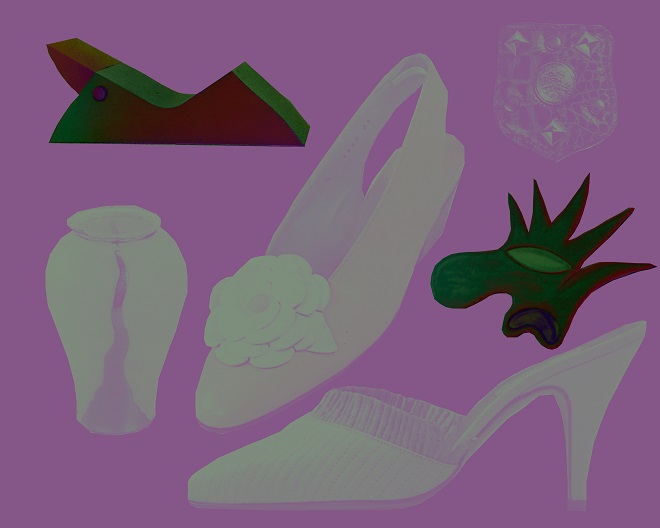
その後、私自身が社内での『花椿』をめぐる政治的な状況に疲れ、会社を離れたのが2001年。当時のファッションの動向に目を移せば、アナ・ウィンターのUS版『VOGUE』が先陣をきって、ファッションショーのWeb配信を始めたのが2000年だった。打ち合わせの前日に映画館でみていた作品『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』でマルタン・マルジェラがいみじくも語ったように、ファッションが変貌していく変化のはじまりの、きっかけがファッションショーのweb配信だった。それはファッションの現場のエネルギーが失われ、ファッションデザイナーたちがこれまでとは違うニーズを求められるようになる何かの始まりであり、おおきな変節点だったのだ。 90年代の服作りにおいても、メディアとのコミュニケーションにおいても、ファッションを脱構築する実験的な行為を重ねたマルタン・マルジェラは2008年、20周年のファッションショーの日に、誰にも告げずにメゾンを去った。その行為によってさらにマルジェラは神話化され、その謎めいた存在が伝説となったのだ。
その前年の2007年に発行された「The Last Magazine 世界の最先端マガジンアンソロジー」という本は、アメリカの広告代理店に勤務していたデヴィッド・レナードが「我々が雑誌だと思っているものは、今にも消えようとしている」という導入文とともに、絶滅寸前の雑誌文化の輝きを放つ媒体として、インディペンデント雑誌のアンソロジーを編んだものだった。その本の出版当初はまだ、彼の予言にそれほど真実味を抱けないでいた私も、月日がたつうちに、『流行通信』(2007年)『スタジオボイス』(2009年)『ハイ・ファッション』(2010年)などの休刊が現実になり、雑誌が消滅する時代という言葉を実体験することになった。
その『The Last Magazine』には私の個人雑誌『here and there』も紹介された。私にとっての恋人のような存在だった『花椿』の編集部を離れた失意の日々のなかで、「では、本当に自分がしたいことは何だろう?」という思いから、友達のエレン・フライスが『Purple』でやっているような自由な編集の実験をしたい、とつくり始めたこの媒体は、私にとっての自由で個人的な部活の時間のようなもの。そのかたわらで『SPUR』や『Ginza』などのファッション誌のアート欄でライターの仕事をしていた。このような商業雑誌の編集に携わることで、あらためて『花椿』とはなんだったかということを考える視点を得た気がする。そしてそのことが、今、このコラムを執筆するモチベーションともなっている。

もう一方で、『花椿』全体としての流れはどうだったかというと、戸田さんの分析と、質問はこうだった。『花椿』は従来、美しい生活文化の創造と、女性の教養を高めることを目標に、一般女性にむけて1937年に発行された。バックナンバーを見ていくと、インターネットのない時代、日本女性のニーズにあわせて媒体の姿は変わって行った。60年代、70年代には日本が海外の情報に開かれていった様子を『花椿』からたどることができる。80年代に入ると、発信対象を高感度層に絞りこんでいき、90年代には、よりファッション面で研ぎ澄まされていった。清恵子さんが連載した「東欧通信」(1994年4月号から1996年12月号まで連載)のように、世界の果てまで果敢に出かけていくような、一人の女性の姿をおいかけたり、アジア映画を定期的に特集したり、一般的な欧米主義から一線を画す掘り下げの深い記事も多かった。『花椿』を通して知る90年代は、「ファッションが文化になっていった時代」といえるのではないか。そして、今も「『花椿』が大好き」という読者層は、この時代、90年代の『花椿』体験を指していると思われる。戸田さんはこうも言った。「そんな『花椿』をつくっていた当時の編集部では、世の中の趨勢とは一線を画した、編集者一人ひとりが共有している『花椿』魂のようなものがあったのでしょうか?」
その大きな問いを前にして、記憶をたぐっていこうとしたとき、きっかけの扉をくれたのは戸田さんの「イン・ファッション」ページの見出しの言葉への指摘だった。80年代から『花椿』ではじまったこのコラムには”イン・ファッション ライバルは知らない” という言葉がページの端に踊っていた。この見出しはつまり「あなたのライバルが、まだ知らないような最先端の情報は、ここにある。他とは違う、際立った私になるための、とっておきがここにある」という、メッセージだったのだろう。
まだスマホが普及していないころ、雑誌から得る情報が自分の価値を高めてくれると多くの人が信じていた時代のことである。私の『花椿』編集者時代の体験のなかでも、このページにまつわる仕事や、紙の雑誌という、今は文化のなかで主役の座を退いてしまったかのようなメディアにまつわる思い出は、背骨にあたるような存在といえる。その記憶をゆっくりと紐解いていきたい。
次回につづく。

林 央子
編集者
1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)
http://nakakobooks.seesaa.net/
https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓
写真家
東京/京都在住
触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。
http://hosokuramayumi.com
















