
90s in Hanatsubaki
2021.09.30
第14回 ロンドン留学ノート その2 意外なところで『花椿』と出会う
文/林 央子
写真/細倉真弓
ティム・インゴルドの著作をもとにした方法論の論文をゾロ目の日、3月3日に提出してからは、今いる大学院の学部であるExhibition Studies(展覧会研究)らしいテーマに移っていった。次の課題は、自分が足を運んだことはないけれど、歴史的に重要だと思う展覧会について一つ選んで評論をする、というもの。この課題で書こうと思った展覧会を選ぶことは、たいして難しくはなかった。2011年にフランクフルトの美術館MMKで開催された「Not in Fashion」展。スーザン・チャンチオロやBLESSといったファッションのつくり手、アンダース・エドストロームやマーク・ボスウィックというったファッションフォトグラファーが参加していて、他にもメゾン マルタン マルジェラやコム デ ギャルソン、ウォルフガング・ティルマンスなどといった顔ぶれが参加していた。展覧会を見にフランクフルトまで行こう、とまでは至らなかったけれど、カタログは買っていた。「Not in Fashion」展の前の年にマーク・ボスウィックがRizzoli社から出した写真集と、展覧会名がまったく同じ名前だったことが印象的だった。
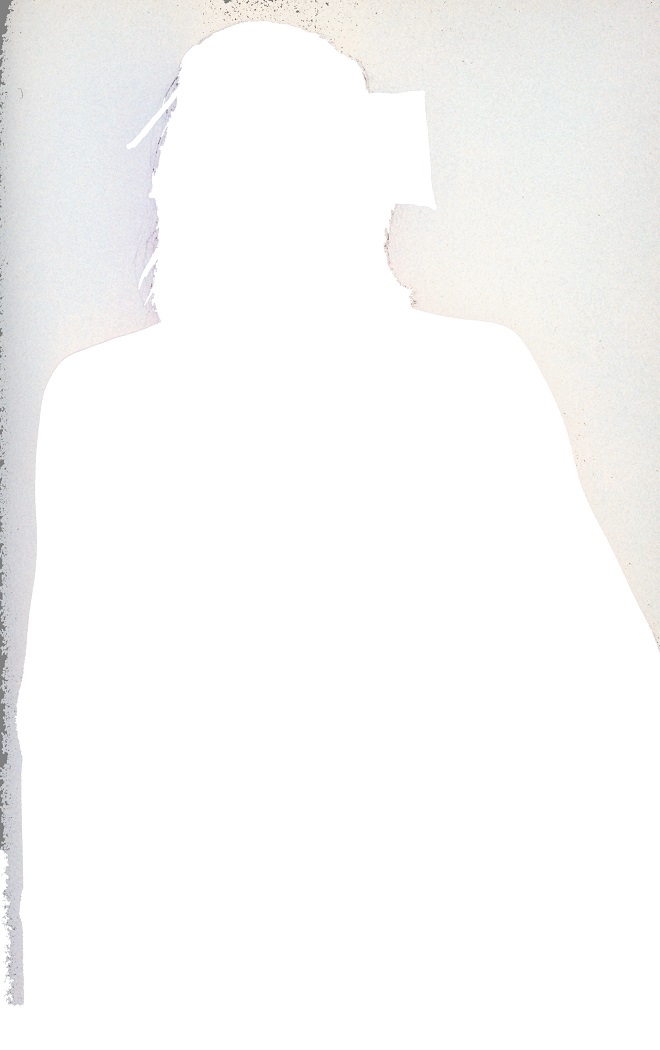
時間がたってから90年代という時代を振り返ってみると、私がもっているこの年代のファッション写真を扱ったいくつかの写真集は、編集の偏りがつよすぎてあまり納得ができない気がしていた。けれどもこの展覧会カタログは、そうした偏りを感じず、自分が体験してよく知っている気がする90年代のファッション写真の流れが俯瞰されているな、と思える内容だった。開催から何年かたってもときどき、当時からファッションとそれをとりまく世界のつくり手として関わっていた私の友人たちは、この展覧会のことを話題にしていた。2010年代後半になって、コム デ ギャルソンやマルタン マルジェラの活動を回顧する展覧会が開催される流れになって、あらためて考察すると、1990年代のファッションの面白さは、個々の活動というよりむしろ、いろいろなデザイナーや写真家たちがあちらでも、こちらでも、同じような顔ぶれが一緒に活躍しているという仲間感、サークル感だったと思う、という文脈で。2000年代以降、ファッションのグローバル化が進むと、かつてのようなつながりの感覚は消えて、個別にそれぞれの活動がある、というように分断されてしまったけれど、90年代の面白さは、あのつながりの感覚にあった、としばしば友人たちと話し合っていた。

「Not in Fashion」展のコンセプトはまさに、このような、90年代のファッション界にあった、なんとも言えないつながりの感覚を提示することにあった。現代アートの美術館で開催されたファッション写真の展覧会として、当時『i-D』や『The Face』、『Purple』などの印刷媒体に発表された写真を美術館空間に合わせて、作品として展示したのだ。
論文を書くために当時のキュレーターのソフィー・ヴァン・オルファースに取材すると、意外な事実につきあたった。この展覧会が開催された年は、金融街フランクフルトにできた現代アートの美術館の20周年にあたる年で、さまざまなアートのコレクションを保有する美術館の、現代写真のコレクションをリサーチして新たな観点からの写真についての展覧会が企画されていた。それに関わるチャンスが、新米キュレーターだった彼女に訪れた、というのだ。当時の写真部門のリーダーは、アート作品のほかにもたとえば、当時エイズの蔓延についてなどへの社会的主張をこめて制作されていたベネトンの広告写真を美術館のコレクションとして購入するなど、意欲的にコレクションの枠を広げていたらしい。
その写真コレクションを見て彼女が衝撃を受けたのは、荒木経惟さんの作品だったそうだ。美術館の保有しているアラーキーのコレクションのほとんどが、大量の印刷物だった。写真家のオリジナルプリントではなく、雑誌などの印刷物となった物としての写真の放つ魅力というものに、それらを見た彼女は、目を開かれた。そこから着想したのが、90年代にファッション誌上に最初にあらわれた写真を展覧会にする、という「Not in Fashion」展の発想だった。

私たちが日本にいて、「こんな展覧会があるらしいよ」と噂していた、そんな注目の展覧会が、じつは日本の写真文化や雑誌文化に触発されたものだったとは。展覧会の企画に 関しても彼女は日本の写真家にも興味があったのだけれど、つながりがなく、声をかける機会が得られなかったと説明していた。そんなことを色々話すうちに、またびっくりする話題がでてきた。今はキュレーター職を離れ、フランスの田舎の一軒家を親から受け継いで、子どもを育てる生活をしているという彼女とskypeで話をしていたとき、私は日本で買った展覧会のカタログを開いていた。すると彼女は、「このカタログは、『花椿』のデザインにインスピレーションを受けたの。家に一冊あったから」と言った。展覧会カタログはおもて表紙、裏表紙ともに観音開きになっていて、たしかに、『花椿』は私が在籍していた1993年にデザインリニューアルをした際、表紙を一枚折りたたんで広げられる観音表紙の仕様になっていたのだった。
観音表紙は複数の写真を掲載できて、表紙の情報量を増やす効果がある。当時の『花椿』は表紙撮影のために海外ロケを行っていたので、そのロケの舞台裏を見せるようなショットを折りたたみ箇所に掲載していた。このカタログにおいては、主要な展覧会イメージを一点にしぼらず、グループ展のなかから複数の写真を表紙に掲載できるメリットがあっただろう。
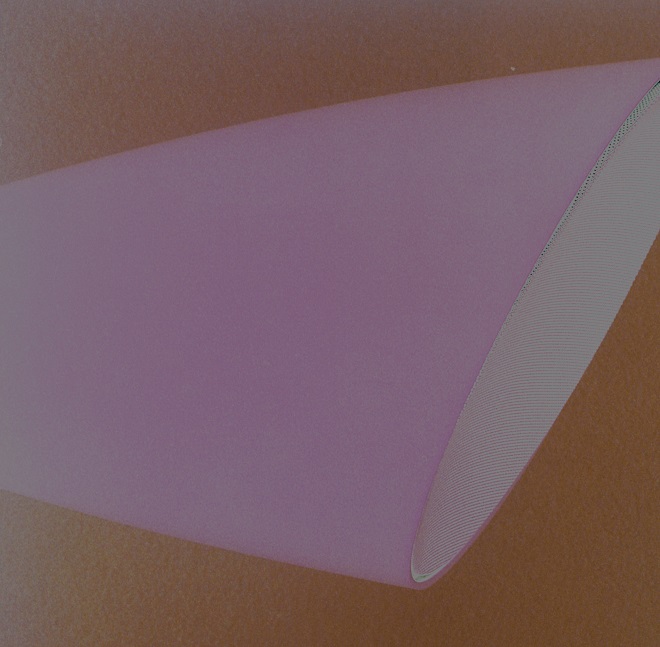
ほかにも、一般的なファッション誌にはグロッシーな上質紙が選択されることが多いけれど、『花椿』は再生紙のようなザラっとした紙を使っていた。それでも、写真の再現性にはこだわりながら。そこにも彼女は目を留めていて、カタログも『花椿』同様マットな紙を選択したのだという。彼女の当時のパートナーがフォトグラファーのマウリシオ・ギジェンで、わたしは『Purple』のエレンを通して、彼の写真を『花椿』に掲載したことがあった。そんなことが理由で、90年代の『花椿』が彼女の目にふれていたのかもしれない。
20年以上前に自分がしていたことが、いろいろな経緯を経てたどりついた今いるこの場所、そしてこの取材によって、繋がった。過去と今が接続された、不思議な瞬間だった。
次回につづく。
前回の第13回はこちらからどうぞ。
https://hanatsubaki.shiseido.com/jp/ninetys/13305/

林 央子
編集者
1988年に資生堂に入社以来、2001年に退社するまで、花椿編集室に所属。入社時の名物編集長、平山景子さんやアートディレクターの仲條正義さんから編集のいろはを学ぶ。古き良き資生堂宣伝部の自由な雰囲気や、銀座という独特な風土の中で国内外のクリエイターと交友を深めた。フリーランスになってからは雑誌などに執筆するかたわら、個人雑誌『here and there』を立ち上げる。2019年から2年間、ロンドンで生活し美大セントラル・セント・マーティンズで展覧会研究に着手。著書に『つくる理由』(2021年)、『拡張するファッション』(2011年、のちに同名の展覧会になって水戸芸術館現代美術センター、丸亀市猪熊源一郎現代美術館へ巡回)ほか。『here and there』 最新号のvol.15は7月1日発売。本連載をまとめた書籍は近日刊行予定。(Amazon.co.jpにて予約受付中)。(画・小林エリカ)
http://nakakobooks.seesaa.net/
https://hereandtheremagazine.com/

細倉 真弓
写真家
東京/京都在住
触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。写真集に「NEW SKIN」(2020年、MACK)、「Jubilee」(2017年、artbeat publishers)、「transparency is the new mystery」(2016年、MACK)など。
http://hosokuramayumi.com
















