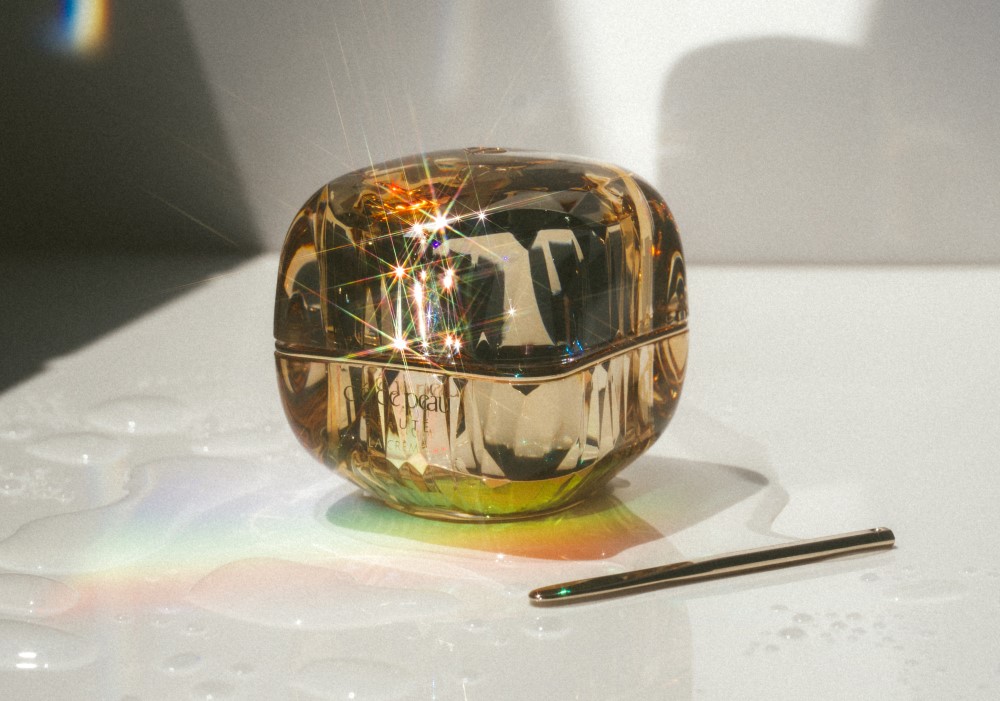東京にいくときはたいてい銀座に泊まる。
仕事の打ち合わせが昼からの日は、銀座の大通りを赤いビルディングを目指して歩く。着いたら、奥のエスカレーターで上の階へ。壁紙は薔薇色。薔薇といっても赤も白も黄もあるけれど、私の薔薇色のイメージはアンティークローズのにぶいピンク色だ。「銀座本店サロン・ド・カフェ」の壁紙はまさに私のイメージ通りの薔薇色をしている。
カフェに入ると絨毯で足音が消える。ぴしりとスーツを着た年配の給仕さんが、私の荷物とコートを受け取り、座るときは椅子を引いてくれる。白いテーブルクロスには皺ひとつなく、小さな花瓶の水は澄んでいる。紙ナプキンはしゅっと立ち、砂糖壺はぴかぴか。ハンドバッグを持っていたら、銀色の鞄かけをテーブルにつけてハンドバッグをかけてくれる。鞄かけには花椿のマークが刻まれている。

初めてサロン・ド・カフェにいったのは、小説家デビューした十二年前だ。授賞式に来てくれた友人たちと待ち合わせをした。私は本や書類の入った大きな鞄を肩にかけていて、給仕さんは鞄を受け取ってくれたが銀の鞄かけにはかけてくれなかった。友人やまわりの席の女性たちの鞄かけを見て羨ましくなった。あれは財布とハンカチとちょっとした化粧品しか入らなそうな小さなバッグのためにある金具なのだ。それ以来、仕事の場へいくときも原稿や本を入れる鞄とは別に、小さなバッグを持つようになった。
ストロベリーパフェを注文する。ハーブティーも一緒に。木の箱がテーブルに置かれ、九種類のハーブを嗅いで選ぶことができる。飲む間にパフェがやってくる。資生堂のパフェはまずグラスのかたちがいい。口がひろく、下のほうでちょっとくびれていて、優雅で品のある女性のようだ。そのグラスの縁に苺がならび、パフェが冠をいただいているように見える。私はこっそり淑女パフェと呼んでいる。朝一番にこのパフェを食べると、一日淑女のように振る舞える気がする。
帰りはエレベーター。給仕さんは、私が乗るまで扉が閉まらないようにボタンを押していてくれる。
京都に住む私にとって東京は仕事の街だ。ときには嫌なこともある。サロン・ド・カフェでの行き届いたサービスは、自分は大切にされるべき存在なのだという自信をくれる。それがたとえ金銭によるものだとしても、働き、自分の贅沢のためにお金を使えることは素晴らしいと思える。あの空間がずっとありますようにと祈りながら仕事へと向かう。


千早茜
作家
1979年生まれ。幼少期をザンビアで過ごす。立命館大学卒業。2008年小説すばる新人賞を受賞した『魚神(いおがみ)』でデビュー。同作で泉鏡花文学賞受賞。13年『あとかた』で島清恋愛文学賞受賞、直木賞候補。14年『男ともだち』が直木賞候補、吉川英治文学新人賞候補となる。他の著書に『クローゼット』『からまる』『西洋菓子店プティ・フール』『神様の暇つぶし』『さんかく』など、尾崎世界観との共著に『犬も食わない』、エッセイ集に『わるい食べもの』がある。最新刊は『透明な夜の香り』。Photo: 文藝春秋
https://twitter.com/chihacenti