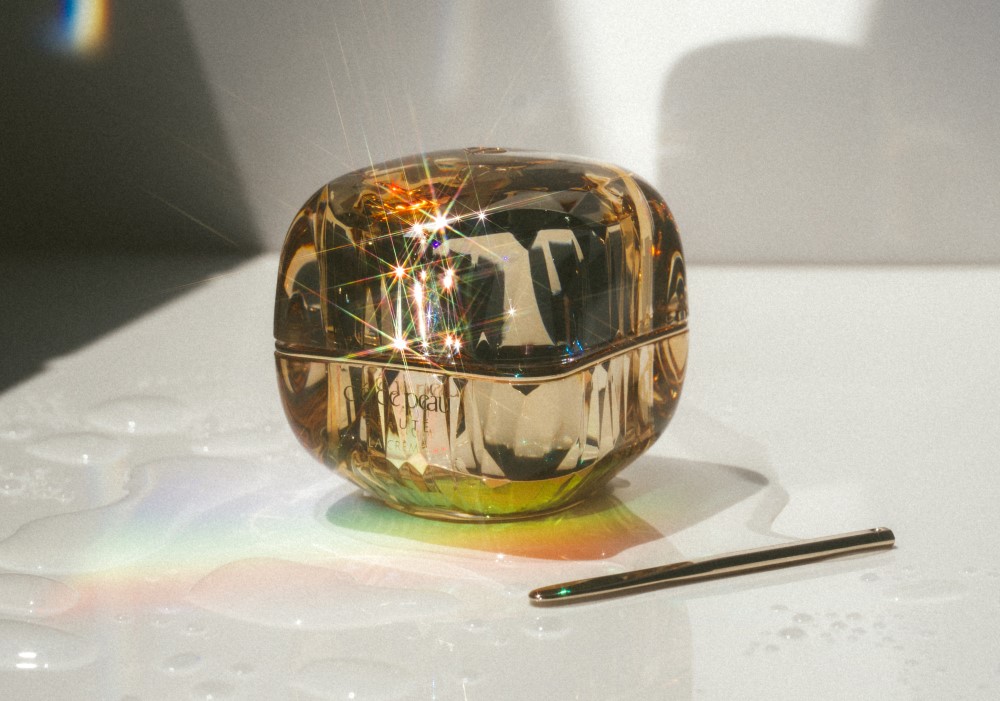これまで会ったことのない人間に出会った時、
さらにその人が「美しさ」という部門で、これまでに出会ったことのない人間だった時、心と目がクギ付けなる。また同じ人間のはずなのに、別の生き物のような気がしてくる。
「美人」の初体験といったらいいのか、それは21歳のころだった。面白いのが初対面ではなく、以前にも会ったはずの人だったこと。その時の印象は、「色白でかわいらしい人だな」くらいだった。それから半年後に会った時、わたしは震えた。
見た目でまずわかるのは、少しスリムになっていたことと、センスが磨かれていたこと。何か生まれ変わったみたいに思えた。何かが変化していた。その「何か」が、美しさの秘密かもしれなかった。恋をしたのかもしれなかったし、彼女自身の「何か」革命がおこったのか。
究極の美人ではない、不思議な不思議な人だった。
この世のものとは思えない、風貌と風格が漂っていて、ただそばにいることが、架空の世界に思えた。うちに泊まりに来て隣に寝ていても、一緒にご飯を食べていても、その場だけ、その時間だけ、別の世界だった。
その彼女はいつも、花椿マークの入った八角形の白い缶を持っていた。それは傷だらけで凹みもあって、長いこと愛用しているのがわかるものだった。その中には彼女の大切な金の糸、切手、押し花、レースが入っていた。蓋をあけると甘いいい香りがした。わたしはその缶の中身が、もとはビスケットだとはつゆ知らず、彼女の美しさによく似合う香りだなあと思っていた。
その後、初めてこのビスケットを頂いた時、ビスケットの焼印とツヤの美しさを眺めた。バターの風味と、どこか懐かしいような、フランス・モンサンミッシェルの伝統菓子のガレットクッキーにも似ている、濃厚でサクサクと軽く甘い味。昭和初期から作られているという。ということは、戦争の最中の作れぬ時代も経ての、大ロングセラーだ。きっと昔はたいそう高級で貴重だっただろうバター。その歴史とともに、ありがたく頂こうと思いながらビスケットを食べ切ってしまうと、白い缶が、あの甘いいい香りと一緒に残ったのだった。
さて、またその美人の話に戻る。
彼女はしょっちゅう「美しい」という言葉を放っていた。川面の光を見ては「美しい」と。ピアノの旋律を「美しい」と。わたしの瞳も「美しい」と褒めてくれた。植物を愛でてはまた「美しい」という。「美しいものが大好きなの」とその彼女はよく言っていた。
彼女にはしばらく会っていない。
幽霊だったのか、本当に幻だったのかもしれないと今でも思うが、今は2人の子供のお母さんをしているらしい。いつか会いたいと思いながら、いつか自然に会える気がしている。あの美しい花椿のロゴマークと白いビスケット缶を見ると、その美しい人を想わずにいられないのだ。

ひがしちか
デザイナー
日傘作家。1981年長崎生まれ。手描きの絵や刺繍を一本一本施す一点物の日傘をつくる作家として「Coci la elle」を主宰。絵を描いて生きる覚悟、生み出すものへの責任、美しく強烈なビジュアルへの執着、日常への愛情が表現の原動力。清澄白河にアトリエと併設された本店がある。絵にまつわるプロジェクト「meme」でも活動中。