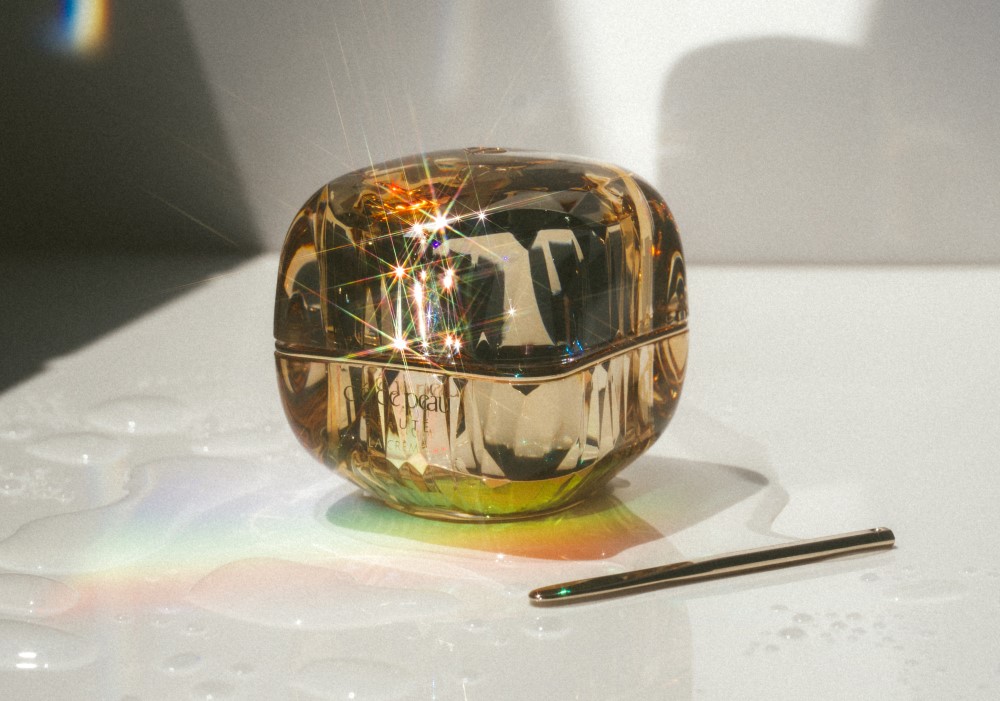メイク魂に火をつけろ
「メイク魂に火をつけろ。」、その挑発的なコピーが化粧品のために謳われたのは約20年前の1997年、当時私は高校生になったばかりの頃。メイクって闘いなんだ、CMを見てそう思った。
女が可愛く、綺麗に、艶やかに、つまり男にモテるためにするものだった化粧やおしゃれは事実私の思春期あたりから進む方向が明らかに違っていった。眉は細く高く、アイラインは強く跳ね上がり、まつげは幾重にも重なり、アルミホイルを細かくちぎったようなラメで女の子たちの目元は人体にはもともとない光を放つようになった。もちろん各々の志向する文化によってそれは異なる。前述したのは主に、ギャルメイクと言われたものの成り行きである。その当時はほかにもオリーブ少女と言われるような文化系女子もいて、さらに「メイク魂に火をつけ」られた主なターゲット層は、多分もう少しだけ上の世代の、すでに社会で活躍中の大人の女性だったと思う。
それでも私たち女は確かにあの時けしかけられたのだ。魂に火をつけるというこれ以上ないくらいハードボイルドな文言で、自己表現としてメイクに挑むというあり方を高々と提案された。
未だにあの頃のギャルメイクってなんだったの、と男性に聞かれることがある。「だってあんなの行き過ぎてて、全然男をそそらないじゃない」
20年も前、男をそそるメイクを捨てちゃっていいじゃない、と資生堂は挑発した、と私は勝手に思っている。20年経った今、私たちが昔より選べることは増えた。女らしさとしてのメイクやおしゃれをしないことは、変なことではなくなった。女っぽさを敢えてのアイテムとして身に纏うという上級の遊び方も覚えた。今はもう、メイクに魂も着火も要らない、そんな肩肘張ることはしなくていいのかも。とても心地いい世界だ、「メイク魂に火をつけろ。」と高らかに叫ばれた20年前よりはきっと。
私にとって、かつての女にとって、メイクは戦闘服だった。男をそそる闘いではない、この世界で自分を、どうにもならない自分自身を、これまたどうにもならない女という容れ物としての体から逃れられないこの自己を、容れ物としてしか見ない世界で、表現することを諦めない闘いだ。さて闘いは終わったのかどうか? このコピーを目にした時に、やっぱりまだまだ疼くような勇気を感じる私自身が、いまの私にとっての答えと言える。アイラインを引くたびに魂に火をつけて、確かめる。今日が昨日よりは少し、自由かどうか。

鳥飼茜
漫画家
1981年生まれ。2004年デビュー。主な作品に、『先生の白い嘘』(講談社)、『地獄のガールフレンド』(祥伝社)など。2018年9月から、初めての日記エッセイ『漫画みたいな恋ください』(筑摩書房)、鉛筆描きの短編集『前略、前進の君』(小学館)など3カ月連続で作品を刊行。ツイッターはこちら→@torikaiakane
[profile photo/Fumi Nagasaka]
https://twitter.com/torikaiakane