犬は、夕陽を見ても、なつかしいとは思わない。そう思えるのは人間だけだ。なぜなら犬は、つねに自然に包まれている存在だから。人間だけが、自然から離れてしまったのだ――。石川・能登で暮らす漆工藝作家・赤木明登さんの著書『二十一世紀民藝』(美術出版社)は、そんな前提から始まり、ではいま、現代のものづくりが失ってしまった「本質」とは何か、それを取り戻すにはどうしたらよいかについて、思索と実践をめぐらせる。
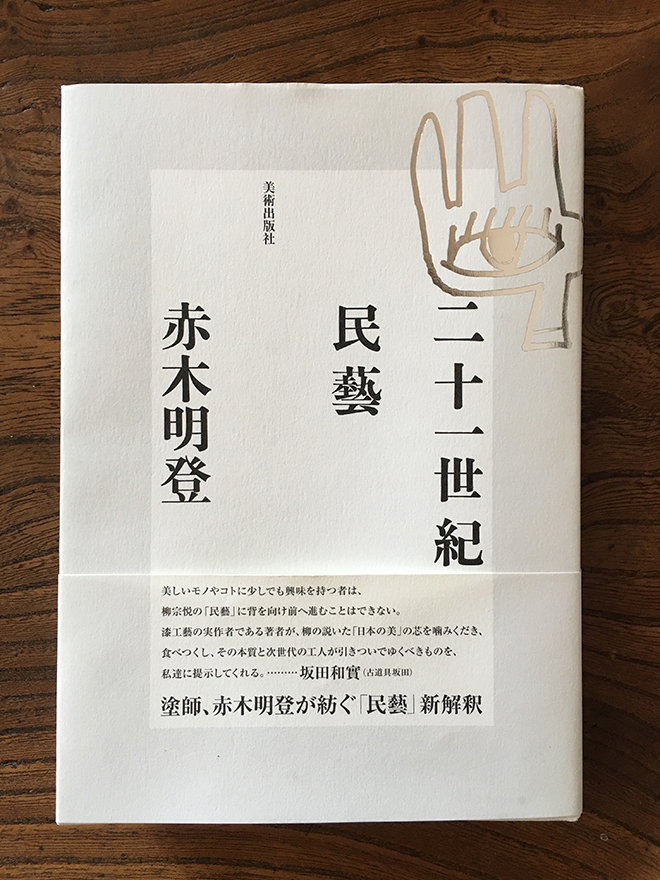
桃山期・江戸期の漆椀、漆器づくりの工程、漆という素材、古物の「写し」、先人たちの死、工藝界と自身の活動の時代的整理、芭蕉の俳句、滋賀の杜氏、岩手のどぶろくと干し肉、イタリアワインの醸造家、茸採り、数多の鮨店。著者はこうした自らの体験を、民藝運動の提唱者・柳宗悦が遺した言葉に重ねながら、その意味するところを問うていく。
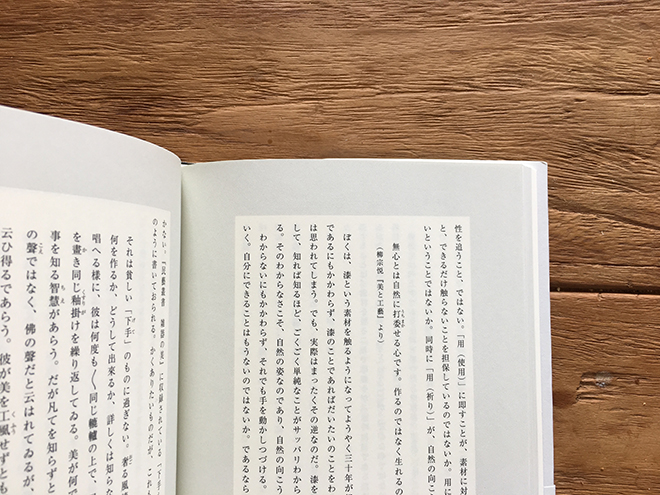


日々の制作も同じなのだろう、自らの手元で生まれた経験から、何らかの確信に至ろうとする足取りは、迂回し、蛇行し、行きつ戻りつし、立ち止まり、ためらい、悩む。けれども、結末ではなく過程の反復と蓄積にこそ実感が宿るのだろうし、受け手としては、こう言ってよければ、そのような軌跡に愉楽をも感じてしまうのだ。そして、柳宗悦も、自然も、明言しない「暗示」の内に、著者は、ある確からしさの輪郭を結び始める。そのとき読者は、大いなる太古への遡行と、ゆらぎ続ける現生の一瞬間という、矛盾した二つの同一を、垣間見る。
ぼくの内なる自然と、素材という自然を重ね合わせることである。(中略)その刹那に、自然の向こう側にある何か大きなものとの接続を感じる。そこが「美しいもの」が生まれる場所である(本書より)
もっとも著者は、「何か大きなもの」――本書では「浄土」「他力」「信仰の世界」といった言葉でも語られるけれども――へ身を預けることに、抵抗があることを隠さない。預けてしまえば、自分という存在がなくとも構わなくなってしまうからだ。確かに、例えば仏教的無常観とは、(自分という存在も含めて)すべてがはかなく移ろいゆくことだと、一般には了解されている。けれども無常とは、そうして移ろいゆく様を見ている「私」を、むしろ積極的に肯定しているのだと、私は思う。そのような存在の一部として、人は、個別性を持つ人は、居場所を与えられているのではないか。
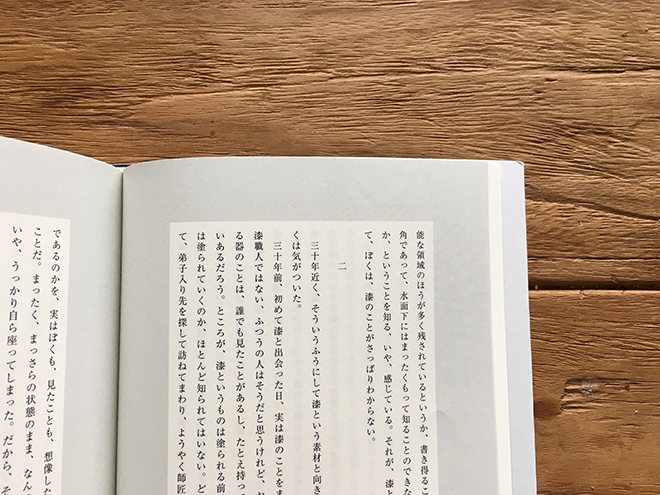
輪島塗の飯椀を能登の山中で拾い、四半世紀かけてその「写し」を一万個以上つくり続けているというくだりに、目が留まる。作者は制作のなか、やがて、「器が、ぼくを利用し、かってにどんどん増えて」いるのではないかという思いを抱く。そこには自我や、人間中心的な考えを越えたものが、実感としてある。このとき個人とは、「天に祈り、地に繋がる」無数の点のひとつでしかない。けれども、一個の点という存在があるからこそ、無数という全体があり得るのだ。夕陽を見てなつかしいと思うことは、「大きなもの」への帰属を物語っている。

岡澤 浩太郎
編集者
1977年生まれ、編集者。『スタジオ・ボイス』編集部などを経て2009年よりフリー。2018年、一人出版社「八燿堂」開始。19年、東京から長野に移住。興味は、藝術の起源、森との生活。文化的・環境的・地域経済的に持続可能な出版活動を目指している。
https://www.mahora-book.com/
















