
今年10月に開催されたTOKYO ART BOOK FAIR 2017。そこで行った『花椿』主催、スペシャル・トークショーの内容をご紹介します! パート1のゲストは、アートディレクターの仲條正義さん、澁谷克彦さん、そして文筆家の山崎まどかさんです。2017年に創刊80周年を迎えた『花椿』のこれまでとこれからをアートディレクションの側面から、紐解いていきます。
『花椿』の始まりと『花椿』メソッド
花椿 1937年創刊の『花椿』は、資生堂の企業文化誌としてビューティーやカルチャー、ファッションなどさまざまな情報をお届けしてまいりましたが、その大きな特徴はグラフィカルな誌面にあるということで多くの皆さまからご評価をいただいてきました。本日ご登壇いただく仲條さんにはその80年の中の半分以上、40年以上にわたって花椿のアートディレクションを手掛けていただきました。そして、澁谷克彦さんは2012年から仲條さんのバトンを受けて、今回最新号の『花椿』2017年冬号までアートディレターを務めていただいています。また本日皆さまにお配りしています『花椿』2017年冬号の中にポケットがありまして、その中に花椿文庫が入っております。それはこの80年分の『花椿』を山崎まどかさんに全部ご覧いただいて、独自の視点で切り取って編集していただいた特別な冊子です。本日は『花椿』をつくってくださった二人のアートディレクターと、そして『花椿』を読者の立場で80年分ご覧いただいた山崎まどかさんの三人で、『花椿』のグラフィックについて楽しくお話ししていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。
山崎 私は今年の春から資生堂に通い詰めて、保存されている『花椿』のバックナンバーをすべて見せてもらって、改めて『花椿』がもっている独特の美意識や歴史と言いますかレガシーをひしひしと感じました。私は高校生のときから『花椿』を読んでいたのですが、当時は本当にアヴァンギャルドでエッジィで、かつエレガントな雑誌という印象があったのですが、今見てもビジュアルやエディトリアルデザインが本当に刺激的だなと思いました。今日はその美意識のファウンダーとも言える、立役者のお二人、仲條さんと、そして伝統を守りながら新しい誌面をつくっている澁谷さんに直に誌面づくりのお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
仲條/澁谷 よろしくお願いします。
仲條 僕は40年で、澁谷さんは大体10年ぐらい?
澁谷 いえいえ、5年か6年ぐらいです。
仲條 それを一緒に話すっていうのは……ちょっとね(笑)。
山崎 (笑)。80年の媒体の歴史の中で一人の方がアートディレクター(以降、AD)を40年間務めることは滅多にないですよね、すごいことだと思います。
仲條 こんなに長く、よく任せてくれましたね。私は今年で84歳なんですが、最初22歳で資生堂に入って、3年で辞めちゃったんです。宣伝部に配属されたんですけどあんまり怠慢だったもので、辞めたほうがいいんじゃないかと思ってね。辞めて何年か経ってから『花椿』の当時の編集長、山田勝巳さん、私より少し上の方で雑誌をお好きな方でね、彼が仲條君ちょっと手伝ってくれよと言うものだから受けてみたというのが始まりです。最初の4年ほどは他のスタッフもいたんですが、そのうち大勢でやると面倒くさいと思って私一人で勝手にやるようになったんですよ。資生堂という会社はわりと懐の深いところがあって、当時は高度成長期ということもあって、まあどんどん予算も増えるし部数も増えるしで、お金をべらぼうにかけるようになった。出張も頻繁に、それも外国に長く滞在してうまいもん食って帰る(笑)。それが癖になっちゃってずーっと辞めもしないで40年もやらさせていただいたんです。
山崎 とても贅沢なお話ですね。いろんな場所に行ったりという経験も貴重ですね。
仲條 はい。まあ今と違って「情報」が新鮮で面白い時代だったんですね。今はもう何をやったって見たことあるとか、そんなの持ってるとか、そういう時代になっちゃったからメディアが刺激をもつということがあまりわからないかもしれないけれど、昔は何をやってもわりとみんな面白がってくれたんですよ。日本とロンドン、ニューヨークの文化の違い、そういうものが際立ってましたから、何をやっても絵になるし、まあ楽なもんでしたよ、ふふふ。今は純粋なメディアというのがどんどんなくなっちゃったということなのかなぁ。
山崎 今は情報が溢れていてもう刺激がないとおっしゃいましたが、『花椿』の誌面は今見てもとても際立っていて、ユニークで、私は読みながら改めてこのエッセンスを盗みたいと思いました。パリやロンドンの記事は他の雑誌にもあるけれど、『花椿』には独特の写真の使い方や視点というのがあって。それは本当に新鮮だと思いました。そういう発想はいったいどこから来てると思われますか? やっぱり仲條さんの頭の中?(笑)
仲條 あのね、僕というよりも当時のスタッフで写真専門の方がいたんですよ。その方々が薦めてくれる写真家がアヴァンギャルドな人ばっかりで、一般に評価されてる人たちとは違う人だった。そういう人たちが「今はこれだろ」という助言をくれましたから、今となっては僕なんかよりもそういう方々の鋭いことばが思い出されますよ。
山崎 たとえばどのような助言ですか?
仲條 「あの人はおしまいじゃない?」とかね。
山崎/澁谷 (苦笑)。
仲條 そんな具合なものだから、僕はすでに世の中で評価されている人や物はつまらないと思ってました。だから僕は横尾忠則さんを起用したりしてたんだけど、横尾さんを起用することはそれはそれで挑戦だったんですよ。
山崎 そうなんですか。かなり早い時期の誌面で横尾さんが手掛けた「ラブすごろく」というすごいアヴァンギャルドで素敵なページがあったのですが、そんなにリスキーだったんですか?
仲條 横尾さんの作風は資生堂らしくないと言われていたんです。
山崎 そうなんですね。だからこそ敢えて『花椿』が起用したということですか?
仲條 そうですね。当時は本当にちょっと危険な感じがしましたからね。
澁谷 やっぱり資生堂の宣伝物は写真家やアーティストのタッチを選ぶところがありますね。たとえば『花椿』でお願いしていた荒木(経惟)さんにいわゆる“化粧品広告”みたいな写真はお願いできない。荒木さんはもっと女性の本質的なところに焦点をあてていく方だから、化粧品広告の表面的な美しさにはあまり興味をもたれないと思うんです。仲條さんはまだ名前が出ていない新進の方をよく起用されていましたが、僕は広告写真とは異なる魅力をもった方に依頼するということを意識していました。女性の本質を捉える方に、花椿流に撮っていただくという感じです。
仲條 それを実現できたのはいいんじゃないですか。雑誌というのはイラストレーションや絵画のメディアではありませんから、見かけはやっぱり写真なんです。イラストではあんまり情報にならない。そうするとカメラマンというのは、ちょっと変わってる人がいい。そういう人はADの言うことは聞かないけども、面白いのは面白い。と言いつつ僕はなるべくこちらの言うことを聞いてくれそうな人に頼んでましたけどね(笑)。
山崎 こないだ写真家のホンマタカシさんにお会いしたら、『花椿』の仕事は大変だったとおっしゃっていました。
仲條 嘘つけぇ~。彼ほど言うこと聞かない写真家はあんまりいなかった(笑)。まぁ時々はいましたけどね。でも付き合ううちにだんだんと親しくなって、そうするとこっちの気持ちをわかってくれたりね。
澁谷 そうですね。例えば荒木さんくらいベテランの方になると資生堂はこういう感じ、というのを考えてくださって、ご自分のアーティスティックな部分を資生堂のトーンに合わせてくれるんですよ。そこから「荒木さん、もっとエロを引き出してください」とアートディレクションをする。彼の中の抑えようとする部分をもう一度引き戻すというか、それも資生堂というフィルターの中で引き戻すという、そんな作業ですね。必ずしもADだからといってすべてを指示するわけじゃなくて、魚を放流するように自由に泳いでもらった中から少しずつ流れる、泳いでいく場所を決めていくような感覚です。それはこういうエディトリアルデザインの中では特に大切だと思うんですね。広告はある程度事前に決めておかないとリスクがありますので。
山崎 そうですね。でもすべてが自由というわけではなくて、根底に資生堂的な美意識というのはありますよね、やっぱり。
澁谷 おそらくそういうところを通してカメラマンの方たちに仕事していただくと、彼らも新しい面を発見できたり、今までできなかったことができると喜んでくださる。彼らに喜んでもらえるといい仕事ができたなという実感がもてて、次につながりますね。

編集とアートディレクター
仲條 大体当時の雑誌にはADなんて役割はなかったの。カメラマンが撮ってきたものをレイアウトする人がいればよかった。そんな時代だったから、最初の頃は編集者がレイアウトしてたんですよ。
澁谷 そうですか。僕がADを担当している間は編集者がレイアウトすることはなかったです。記事ページのラフのようなものはありましたが。というのも、『花椿』の編集者は基本的には資生堂の社員なんです。秘書部や商品開発部など、そういう会社の他部署から社内異動で配属される。ですから基本的に生き馬の目を抜く編集者という感じは少なくて、どちらかというと“資生堂”に軸足を置きながら編集をすることで編集室が出来上がっている。その編集室の雰囲気が巷の雑誌の編集部とは違うんじゃないかなと思います。媒体によっては編集がAD的な役割を担うところもあるので、雑誌によってその辺の関係性は違うようです。
仲條 やはり力の違いなんだよ。スタイリストが立場として強かったり偉いとなると、スタイリストが先導役になる。
山崎 そうですね。でもやはり『花椿』はADの力がとても大きく反映されている雑誌という気がします。
澁谷 多分、任されていますよね。
山崎 そう、“仲條ワールド”、“澁谷ワールド”みたいなものがある。
仲條 こっちが年取っちゃうとだんだん編集室の若い人は言いづらくなってね。もう独裁で、わしの言うこと聞け! みたいなことになってましたね。
澁谷 それはいいことなんですか?
仲條 や、わかんない(笑)。
澁谷 あははは。
山崎 客観的にですが、結果としてはよかったと思います。
仲條 大体雑誌づくりはそんなに大勢でやるもんじゃないですよ、ビルを建てるわけじゃないんだから。すごく物事がわかる人が一人で仕切ったほうがいい。できる人は文章もわかるのよ。全部わかるんだよ。絵も写真もわかる。そういう人が往々にしているわけよ。
山崎 すべてを見通せる人が。
仲條 うん、未来も。
山崎 未来もですか。でもわかります、そういうADは文章も写真もファッションのこともすごくわかっている。たとえばアレクセイ・ブロドヴィッチであるとか、やはりすべての美意識をもっている人がいることは雑誌にとってはとても意義深いことなのではと思います。
仲條 そんなに強い巨人じゃなくてもいいんですよ、読む人は一般の人なんだから。もちろん一般の人で鋭い感性をもっている人もいるけれど、仕事としてはプロではないという意味です。雑誌に携わる人はそういう人よりも少し上の感性をもってればいいだけだから。だから気楽なもんだと思ってなかったら僕はこんなに続けてなかっただろうね。
山崎 なるほど。そういう風に仲條さんが自由にされていたからこそ、『花椿』の独自の方向性が築かれたのかなと思います。
仲條 まあ一人だから、あの手この手でいろいろ考えなきゃいけないところはあったけどね。

思い出の特集をいくつか その1
山崎 1987年5月号は「MIAMI BEACH BOYS&GIRLS」という特集です。すごく素敵な写真が連なる特集ですが、どのような思い出がありますか?
仲條 マイアミ……かっこいいねぇ。これは写真家の三浦憲治さんとの初めての仕事だったんだけど、一緒にマイアミに行ってね。
山崎 贅沢ですよね、今ではちょっと考えられない。
仲條 モデルはみんな素人の人たちで、バレエダンサーの女の子やバーに居た男の子とかで。
山崎 その感じがすごくいいですよね、用意された感じじゃない。すごく開放的でかわいくて明るくて。素敵だなと思います。
仲條 うん。洋服はイギリスのスタイリストにやってもらったの。クラシックな50年代っぽいスタイリングでね。
山崎 そういう多国籍な感じがありますね。マイアミといってみんながふつうに思い浮かべるようなマイアミ映えする素敵なファッションじゃないところがすごくいい。
仲條 これがふつうのきれいなモデルさんだったらつまんないよ。気候もよかったし、まあ楽しかったよね。
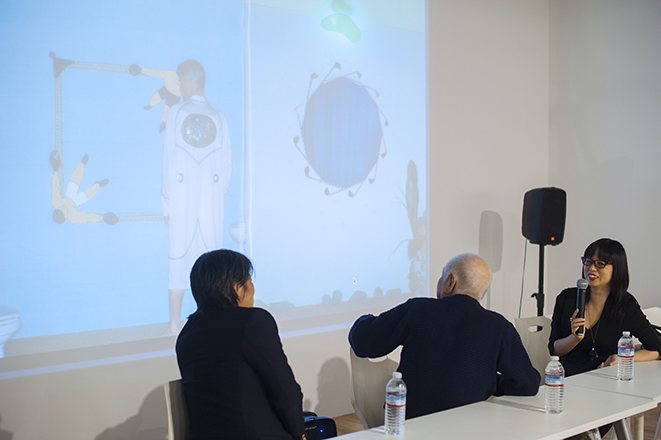
山崎 次は85年ですね。
仲條 この頃の表紙はシンディ・パロマーノに1年間か半年続けて撮ってもらっていて。僕は惚れ込むとその人とばかり組むんですよ。だからこの表紙以外にも誌面でチョコレートの特集などいろいろ一緒にしましたね。
山崎 パロマーノさんのポートフォリオ的な写真のタッチによってアーティストの世界観がすごく伝わるものになってますよね。
仲條 やっぱりすごい人でしたよね。
山崎 85年11月号は架空のホテルをつくり上げる「HAPPY HOTEL」という特集ですね。当時の『花椿』ですごいと思うのは、世界観を一からすべてつくってしまうという点です。これもそういうコンセプトだったんですか? とても印象的です。
仲條 そうですね。模型でホテルをつくりました。
山崎 模型でホテルをつくるというと今だとウェス・アンダーソンの映画『グランド・ブダペスト・ホテル』を思い浮かべますが、その意味でもこの特集はすごく早いですね。
仲條 ちょっとレトロな感じもするでしょう。
山崎 そうですね、ちょっとレトロです。
仲條 わりとそういうのが好きなんですよ。
山崎 でもレトロな中に当時のアヴァンギャルドっぽいファッションがありますね。
仲條 このときのスタイルのテーマがスポーツだったんです。電球がバスケットボールのかごに入っているところとか、カウンターの手前の野球のスコアボードなんかもその名残。
山崎 本当にこういうホテルがあったら素敵ですよね。
仲條 スタイリングは安部みちるさんという方が手掛けたの。
山崎 このゴングもつくられたんですか?
仲條 これもつくった。
山崎 すごい、これは撮影終了後どこに行ってしまったんですか?
仲條 これはね、カメラマンの小暮徹の家にある。
澁谷 今ないかもしれないですよ、引っ越されたから。
仲條 いや持って行ったと思うよ。違うかな。
















