
尾崎世界観さんとアーティストが対話する企画。今回は、資生堂ギャラリーで開催中の展覧会「万物資生|中村裕太は、資生堂と を調合する」の美術家・中村裕太さんと対談します。前編では資生堂の歴史を紐解きながら、今和次郎や赤瀬川原平と資生堂の歴史資料が「調合」された「万物資生」の考え方に触れました。後半では、中村さんの作品へのアプローチや歴史との向き合い方、そして「資料」の取り入れ方について話は広がりました。
展覧会概要はこちらから
過去の創作物を「資料」として扱い、 見つめ直すことで見えてくる世界。
──150年分の歴史を振り返るというかなり情報量の多い展示でしたが、まずはご覧になっていかがでしたか?
尾崎世界観
いままでで一番濃密な展覧会でしたね。情報量は多いけれど、一つひとつの作品を見ながら文章をすべて読んでいくことでだんだんとわかってくる。歴史を絡めた作品へのアプローチということも含めて、すごく面白い経験でした。
自分の作品は、自分自身を前面に押し出したものが多いので、今回の展示に対してすごく視野の広さを感じました。中村さんご自身の作品はすごく控えめで、他の作品や過去の資料はしっかり並べてありますよね。そういう感覚を、自分も見習いたいと思いました。つい、どうしても過去の創作物を超えたい、負けたくないという思いが強くなってしまうので。だから、今日会場で中村さんの作品がいろいろな作品と並んだ様子を観客として見たときに、すごく得るものがありました。中村さんの作品がいろいろな資料の中にあることで、そこに穴が開いて空気がよく通るような感じがしました。
資料だけではどうしても勉強しているみたいになってしまう。そこに隙間ができて、すごくアクセントが利いていると感じました。
中村裕太
粘土の質感もあるのかもしれません。僕がものを考えるときは、紙に文字や絵を書いたりすることもあるのですが、粘土を捏ねていることが多くて。粘土を捏ねていると、すごくクリエイティブになれる瞬間があるんです。言語ではなく本能的な部分が刺激されるような。粘土って、ぐっと押したらその部分の形が変わっていくし、ひと晩置いてみたら全然質感が変わっていたり。すごく可塑性が高いというか。そういう変質する物体を扱うことは、自分の表現において重要なことですね。
尾崎
粘土には独特な感覚がありますよね。そして、手で触るということも重要な気がします。歴史資料というのは揺るぎないものだと思いますが、そういうものに対して変化する素材を使うというのが興味深いです。そして、自分の手触りそのものを見せていると、展示を見ていて感じました。この展示以外の作品制作でも、「資料」を参考にされることはありますか?
中村
結構あります。いろいろなバリエーションがありますが、過去の資料や文献を見ながらインスパイアを受けて作品をつくっていく感じです。歴史的にこうだと言われている事象や作品の見方、評価ってあるじゃないですか。確かにある文献にはそう書かれているのかもしれないけど、他の資料をいろいろ紐解いていくと「本当にそうなのかな」と疑念が湧いてくる瞬間があるんです。もう1回調べ直したり、粘土で起こし直したりしてみると、その物事の違う側面が見えてくるようなところがあって。だから、歴史的なものをもう1回再構成していくというのを、この数年の作品ではやっています。だから自分の作品を前面に押し出すスタイルではなくて、自分が抱いた疑念や不思議に思うことを粘土と文献を使いながら、自分で確認作業をしているような感じです。
尾崎
面白いですね。歴史をちょっといじっていくような。
中村
学生時代はずっと陶芸をやっていたのですが、陶器の作品って本当に山ほどあって、自分でつくらなくてもいいなと思っていた時期があるんです。でも、陶器のことを知りたい、所有したいという思いはある。明治時代に来日した動物学者のエドワード・モースという人がいるのですが、その人は日本の陶器を5000点ほど蒐集し、現在はボストン美術館に収蔵されています。僕にはそうしたコレクションは作れないけど、かつて陶器が作られていた場所の近くの川や海岸を歩いていると陶片が落ちている。自分で作品をつくらなくてもいいと思っていたのですが、拾うという行為にもクリエイティブが担保されているんだと思えた。そのときはモースの文献と自分が拾った陶片を組み合わせて作品をつくったりしていました。


尾崎
拾う行為がクリエイティブ。確かにそうですね。そういう意味で言うと、資料を集めることは拾う行為とも言えますよね。作品制作をする際、今ある条件自体を疑ってみるということは大事ですよね。資料もそうだし、締切りもそう。そうした条件に対して粘土のようなもので、本当にそうなのか?という疑問を混ぜ込んでいくというか。
中村
そうですね。条件を疑うということは諦めではなく、必然のような気もします。先ほども言いましたが、やっぱり自力だけでものをつくっている感覚ってあんまりなくて、すごく他力的なんです。そうした手つきは今和次郎や赤瀬川原平さんにも感じます。
尾崎
今回の展示を見て、資料という感覚がすごくいいと思いました。何でも資料と言えるじゃないですか。自分の好きなものでも、これは資料だと思えば、何でも仕事に結びついてくるし、愛着が湧く。それは自分にはない感覚だったので、すごくいいものを得た気がします。資料はどうやって探していますか?
中村
買うものもあれば、拾うものもあっていろいろですが、骨董品のようにすでに価値のあるものにはあまり興味がないんです。散歩をしていて、気になったものを拾うのが基本ですかね。それを続けていくと、同じようなものが他のまちにも落ちていたりすることがあって。そんな感じで、モノや文献との出会いからシナプスみたいに繋がって、それこそ展覧会になったりすることもあるんです。だから、ダルマを集めるぞって言って集めるようなことはしませんね。
尾崎
いくつかの偶然が重なって手を伸ばすけれど、手を伸ばしても捕まえられるかどうかわからない。やっぱり面白いですね。資料だと思えば、ある意味、上からいけるということですよね(笑)。
中村
そうなんです(笑)。嫌いなものも資料として考えれば、見ることができる。また、資料が資料を呼ぶというか、そうした資料たちと巡り合わさっていく感じがありますね。釣りみたいな感じで釣り糸をちょんちょんいじってもダメで、そういうときはひたすら待つ。そういう意味で、資料を寝かせるというのもよくやります。買ったり拾ったりしても、すぐに作品づくりに着手はしない。例えば陶片は拾ってきたとき、すごく汚れているんですね。拾った瞬間ってすごくテンションが上がるんですが、それを一回疑って寝かせる。その後、頃合いを見て陶片とお風呂に一緒に入って、陶片をブラシで磨くと思ってもみなかった柄が現れたりするんです。
尾崎
拾われてきてから、中村さんと一緒にお風呂に入るまでにある程度時間がある。
中村
はい。磨いてみると、思いもよらない印が後ろに押してあったりして。同じものと何度も出会う、出会い直すような感じです。
尾崎
同じモノ、本や資料に出会い直すという感覚は、すごく素敵ですね。これは悪い意味ではなく、歴史資料というと過去のモノで、現在は当時の役目を終えていて、距離がある感じがします。でも、そういった資料も見方によって変わって見えるということが、今回の展示でよくわかりました。
中村
もうこの世にはいない方の作品や資料と、自分がつくった作品を一緒に展示するのって、ある意味すごく怖いというか、過去の資料や作品に受け容れてもらえないんじゃないかという恐れがありました。でも、僕の勝手な思いではありますが、赤瀬川さんの作品の上に自分の作品を置いたとき、「あ、いいかも」と思えたんです。それが僕にとってこの展覧会の大事なポイントで、その瞬間に出会えたことが、大きな発見でしたね。



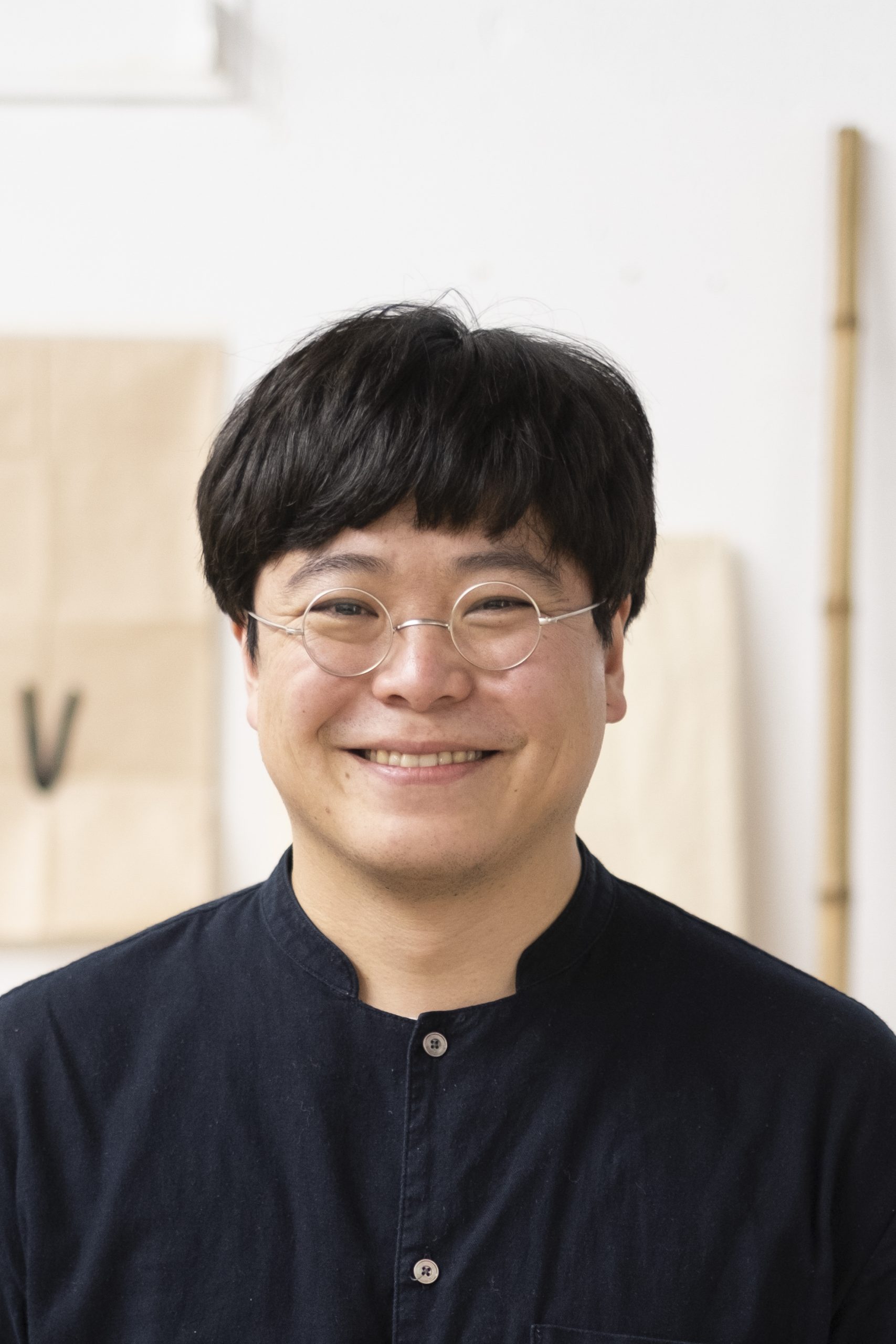
中村裕太
1983年東京生まれ、京都在住。2011年京都精華大学博士後期課程修了。博士(芸術)。京都精華大学芸術学部特任講師。
〈民俗と建築にまつわる工芸〉という視点から陶磁器、タイルなどの学術研究と作品制作を行なう。近年の展示に「第20回シドニー・ビエンナーレ」(2016年)、「あいちトリエンナーレ」(2016年)、「柳まつり小柳まつり」(ギャラリー小柳、2017年)、「MAMリサーチ007:走泥社—現代陶芸のはじまりに」(森美術館、2019年)、「ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ?」(京都国立近代美術館、2020年)、「丸い柿、干した柿」(高松市美術館、2021年)。著書に『アウト・オブ・民藝』(共著、誠光社、2019年)。
会期:2022年2月26日(土)~5月29日(日)
会場:資生堂ギャラリー
住所:東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビルB1
開館時間:平日11:00~19:00、日・祝11:00~18:00
定休日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合も休み)
TEL:03-3572-3901
詳しくはこちら→資生堂ギャラリー公式サイト

尾崎世界観
ミュージシャン
バンド「クリープハイプ」のボーカル、ギター。独自の観察眼と言語感覚による表現は歌詞だけでなくエッセイや小説でも注目を集める。著書にエッセイ集『苦汁100%』『苦汁200%』、小説『祐介』(すべて文藝春秋)、エッセイ集『泣きたくなるほど嬉しい日々に』(KADOKAWA)などがある。2021年1月に発表された小説『母影』(新潮社)は、芥川賞にもノミネートされ話題となった。同年12月8日にはニューアルバム『夜にしがみついて、朝で溶かして』が発売。2022年4月に歌詞集『私語と』(河出書房新社)を刊行した。
2023年3月には幕張メッセ国際展示場・大阪城ホールというキャリア史上最大規模の会場にて、アリーナツアー 2023「本当なんてぶっ飛ばしてよ」を開催する。
http://www.creephyp.com

山添雄彦
フォトグラファー
1963年 大阪生まれ
80年代後半よりスタジオ勤務の傍ら関西のアンダーグラウンドシーンを撮影する。
1991年 渡仏、STUDIO ZERO PARIS に勤務。
1995-1999年 JEAN-BAPTISTE MONDINOに師事。
2000年 独立。2005年 帰国。
お好み焼きを焼くのが好き。
http://yamazoetakehiko.com/

谷本 慧
ヘア&メイクアップ アーティスト
1986年生まれ。大阪出身。大阪の店舗を経て、上京後、原宿BRIDGEに7年間所属。2019年CITY LIGHTS A.I.R.に参加。サロンワークを軸に、広告、雑誌、TV、MV、CDジャケット等、音楽を中心としたヘアメイクを担当。
https://www.instagram.com/3104tanimoto/
https://satoshitanimoto.tumblr.com/

上條桂子
ライター/編集者
雑誌でカルチャー、デザイン、アートについて編集執筆。展覧会の図録や書籍の編集も多く手がける。武蔵野美術大学非常勤講師。著書に『玩具とデザイン』(青幻舎)。2022年10月には編集を手がけた『「北欧デザイン」の考え方』(渡部千春著、誠文堂新光社)が発売。
https://twitter.com/keeeeeeei
https://www.instagram.com/keique/?hl=ja
















