
福村なずながほとんど化粧をしなくなったのは三十一歳のときで、きっかけは、当時の恋人の一言だった。
その日はお昼前に待ち合わせて、昼ごはんを食べて、スタジアムで野球のデイゲームを見て、そのあとカラオケかボウリングをして、夕食を食べるという盛りだくさんのデート内容を、ずいぶん前に決めていた。ランチの店は決めていなかったけれど、夕食のレストランはイタリア料理店を予約していた。なずなのほうが先に着いた。しばらくしてから恋人があらわれて、なずなを見るや、化粧濃くない? と笑って言った。なんか夜っぽい感じがする、と続けた。
なずなは猛烈に恥ずかしくなり、何も言わずに駅のトイレにいき、水道でバシャバシャと顔を洗った。クレンジングシートを持っていなかったので、ウェットティッシュでさらに顔をこすった。ほぼ素顔で戻ると、なずなが気分を害したと思いこんだらしく、「さっきのはどう見ても夜の顔だったよ」「野球にいくんだからあんなに盛らなくても」と彼は言い訳のようにくり返し、なずなは恥ずかしいを通り越して腹立たしくなり、でも、それを気取られたくなくて、「ちょっと気合い入れすぎちゃった」と言って笑ってみせた。
それももう十年も前の話になる。その恋人とは半年と少し交際して別れた。その日のことなど恋人は忘れていただろうが、交際しているあいだなずなはずっと覚えていて、化粧に細心の注意を払った。濃いとか夜の顔だとか、二度と言われたくなかった。別れたのは化粧問題が原因とはまったく関係なく、ぶつかることが多くなって、きみとは先のことが考えられないと相手が言い、それで別れることになった。なずなも同じように思っていたが、そんなふうに言うのは相手に失礼な気がして言わなかっただけだったから、別れて安堵した。その後、化粧をすること自体がいやになってしまった。
なずなの母親はメイクアップアーティストだった。もともとは化粧品専門店で働いていたらしい。それもなずなが生まれるよりも前の話で、なずながものごころついたときは、母はメイクアップアーティストとして、先輩アーティストについて修業していた。なずなが小学校に入学した年、母親はひとり立ちして働くようになった。テレビや雑誌に出る人たちに化粧をほどこすのが母の仕事だとなずなは知っていて、そんな母をかっこいいと思っていたから、多忙な母が不在がちで、母より料理の下手な父親と夕食をとることや、父が残業や出張でいないときは祖母の住まいにいくことに、不満を感じたことはなかった。
中学に上がると、雑誌の片隅や映画のエンドロールに母の名前を見つけることが多くなり、尊敬の気持ちはますます高まった。高校に上がると、こっそりメイクをしている同級生もいたけれど、なずなはグロスすらも使わなかった。母のようにはうまくメイクをする自信がなかった。
高校を卒業したとき、母がなずなにメイクレッスンをしてくれた。基礎化粧品と必要最低限のメイク用品を買いにいき、自宅のリビングで、母はなずなに数パターンのメイクをしてくれた。ナチュラルメイクの場合は下地を塗る前に化粧水をたっぷり肌にしみこませてマッサージすること、やさしい顔つきにしたい場合は眉のアーチをやわらかく、シャープな印象にしたいときは眉山をくっきりと、その場合はこのあたりに眉山を作ること……といった母のレクチャーになずなは興奮した。母の言うことは論理的で、シェーディングやシャドウの入れかたに至っては数学的で、「こうすると目がぱっちり見える」「こうすると鼻筋がすっとする」と、言われたとおりに自分の顔つきが変わるのに、いちいち驚いた。
その日から、出かける用事があるときは臨機応変な化粧をするようになった。大学やアルバイトにいくときはナチュラルメイク、飲み会や合コンのときははなやかなメイク、ライブやイベントに参加するときは崩れにくいメイクと、母のレクチャーをもとに、工夫して顔の感じを変えるのはおもしろかったし、メイク道具を揃えていくのもたのしかった。
学生時代に編集プロダクションでアルバイトをしていたなずなは、卒業後、フリーランスのライターになった。最初は、その編集プロダクションをつうじて、依頼があれば、グルメでもファッションでも、どんな種類の記事でも書いた。アルバイト時代と変わらない収入しかなかったが、ちょうどそのころウェブメディアが台頭してきて、じょじょにウェブマガジンでの仕事が増えはじめ、卒業して三年もたつころにはかなりの忙しさになった。二十五歳のときに家を出てひとり暮らしをはじめた。
取材先によってなずなはメイクを変え、在宅仕事のときも、朝起きれば日課のようにメイクをした。幾度か恋をして、片想いのまま終わったり、数年の交際後に破局したり、結婚を考えたのに相手が海外転勤になって自然消滅したりした。
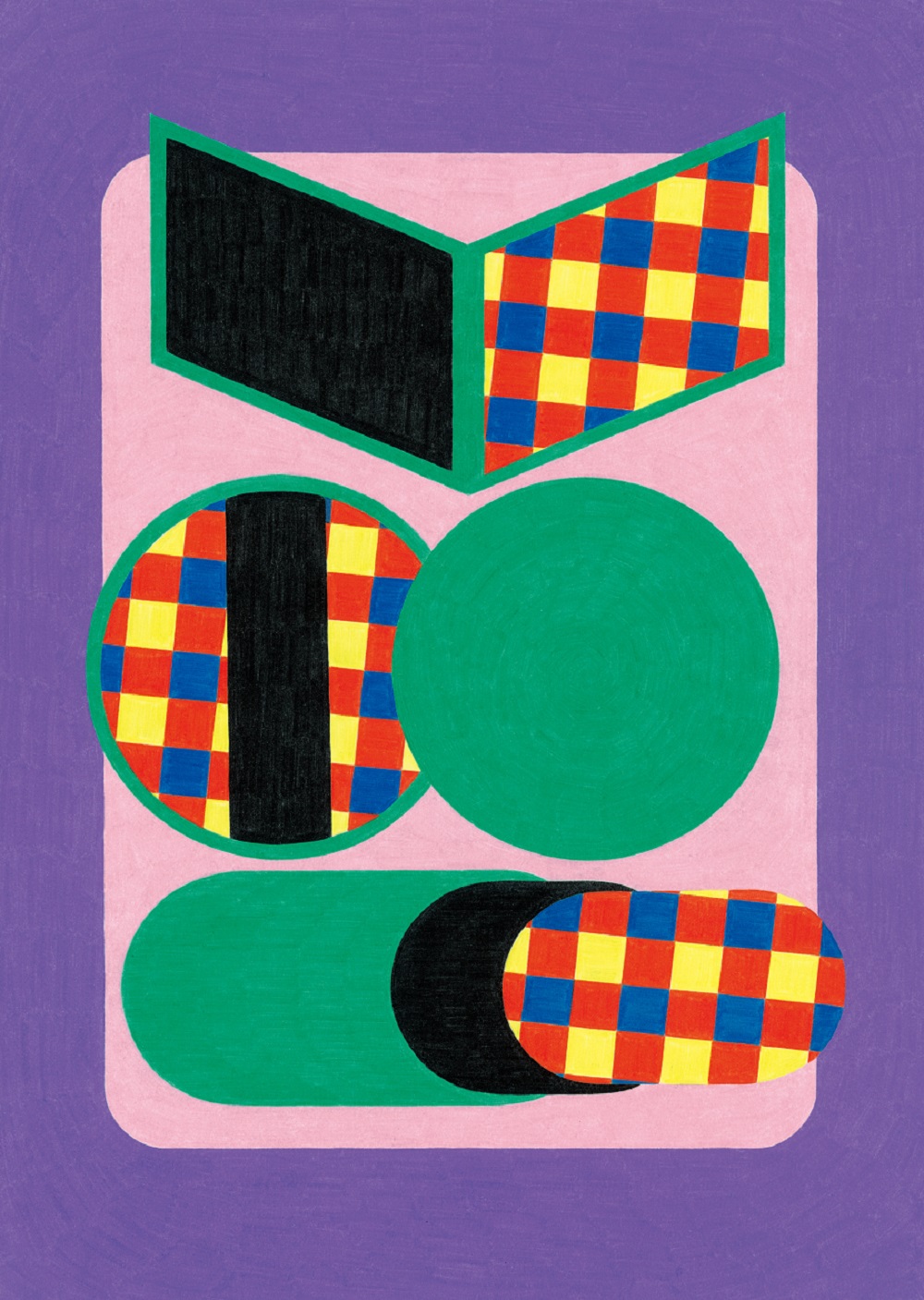
そして三十一歳のときの、「化粧濃くない?」発言だった。それまで恋人にも友だちにもそんなことは言われたことがなかった。その恋人を、今までつきあっただれよりも好きというわけでもなく、別れたのだって約半年と早かったのに、彼の言葉と、その言葉で受けた衝撃をなずなが忘れることはなかった。
化粧ってなんなんだろうと、三十一歳のなずなは考えた。こうすれば柔和な顔立ちに見える、こうすればシャープな印象になると母は教えてくれて、たしかにそれはそのとおりなのだけれど、それって他人からこう見られたいという気持ちがあるってことじゃないか。でも、私は私で、こう見られるも、ああ見られるも、ないじゃないか。こう見られたいって気持ちの根っこには、好かれたいとか、きれいだと思われたいといった、見栄や媚びがあるからじゃないの?
そんなふうに考えはじめると、なずなはとたんに化粧をするのがいやになった。ずっと誇りに思っていた母の仕事さえも、うとましく思えた。女性が、他人から―多くの場合男性から、どう見えるか考えている仕事。シミやくすみを隠すことで、老いや疲れを見せないようにする仕事。でも、女性たちだって疲れるし老いるし、肌はくすむしたるんでいく。それでいいじゃないか。なぜごまかす必要がある。まるで黒に挟まれた白いコマがぜんぶ黒に変わっていくみたいに、なずなは化粧のいっさいを否定したくなった。
家で仕事をするときはノーメイク、取材時は日焼け止めだけ。一か月もすると、化粧をしない気安さにあっという間に慣れた。三十代の半ばから、なずなの仕事は軌道に乗ってますます忙しくなり、化粧をするための時間をとるという考えも、霧散した。
ときどき呼ばれる友だちの結婚式には、さすがにファンデーションを塗るが、アイラインも入れないしマスカラも使わない。友人の紹介で、初対面の人と食事にいくことになってもノーメイクで出かけた。初対面の人に会うのに化粧をしないのは相手に失礼だと、以前どこかで聞いたことがあったが、それにすらもなずなは心中で反発していた。
実家に帰るのは年末年始くらいになった。還暦を過ぎてなお現役で働いているなずなの母は、化粧をしなくなった娘を見ても何も言わないが、なんとなくかわいそうな目で自分を見ているとなずなは感じる。流行の変化が激しい業界にあって、母が今も働いていることは立派だと素直に思うが、しかし家でも化粧をしている母に違和感も覚えるようになってしまった。六十五歳で定年退職し、シルバー人材センターに登録して週に一、二度アルバイトをしているという父親は、なずなが化粧をしなくなったことにも気づかない様子で、早く嫁にいったらどうかと時代錯誤なことを言い続け、それもなずなを辟易させる。
そうこうするうち、新型コロナウイルスの感染拡大により、パンデミックが宣言され、日本ではほぼ全員がマスクをするようになった。なずなの取材はすべてオンラインになり、家から出ない日々が続いた。七十歳になったら仕事を引退すると母は言っている。人と接近しなければならないメイクアップの仕事も減っていると、電話口で母は話した。引退して、コロナがおさまったら、おとうさんと悠々自適に旅行でもするわと言っている。
パンデミックのさなか、友人主催のオンライン飲み会で知り合った男性となずなはしたしくなり、緊急事態宣言が発出されるとオンラインでおしゃべりし、解除されると飲みに出かけるようになった。化粧をしたほうがいいかどうか、なずなが少しでも迷ったりせず素顔でデートに出かけられたのは、たぶんマスク生活のおかげだろう。世のなかの多くの人が、アイメイクだけか、化粧をまったくしなくなるか、どちらかになっている。そして、会食や飲み会が激減し、それまでよく会っていた人と疎遠になることが多いなかで、なずなと彼、小岩井覚は反比例するようにしたしくなり、たがいの素顔よりマスクをした顔のほうがなじみ深いながら、結婚することを決めた。
それみたことか、となずなは心のどこかで勝ち誇ったように思った。化粧で見栄えよい顔を作らなくても好きになってもらうことはできる。彼の家に泊まった翌朝も、短い旅行に出かけても、あせって化粧をすることもないし、いっしょに暮らすようになっても、素顔でいることに躊躇しないでいい。
行動制限がだいぶゆるくなってから、それぞれの家族とともに会食をし、マスク不要になるらしいという話があちこちで聞かれるようになって、なずなたちは話し合った末に結婚式を挙げることにした。出会いのきっかけになった友人たちを招きたかったし、三年ほどのパンデミックで、全国、あるいは全世界で多くの結婚式が中止になったり延期になったりした、そのリベンジの気持ちもあった。
マスク着用は個人の判断に委ねると政府が発表してから二か月後、なずなと覚は規模の大きくないホテルで結婚式とパーティをおこなうことになった。ドレスとスーツはホテルでレンタルすることにした。花嫁の髪のセットとメイクアップもホテルの無料サービスがあったけれど、なずなの母が、どうか自分にやらせてほしい、それを引退前の最後の仕事にしたいと言うので、なずなは母にまかせることにした。
当日の朝、母に化粧をしてもらってから、父と母とタクシーでホテルに向かうことに決め、結婚式前日、なずなは実家に帰った。実家のリビングも食堂も、元なずなの部屋も、段ボール箱や色あせたトランクや、紐で縛られた雑誌類が雑然と置かれていて、お正月に帰ったときよりごたついている。
おばあちゃんのおうちを処分することにしたの、と夕食の席で母が言った。なずなが子どものころ、父と母が多忙なときに、よく預けられた祖母の家は、この家から電車とバスを乗り継いで四十分ほどの都下にある。五年前、祖母が九十五歳で大往生を遂げたあと、処分する決心がつかないと、母の妹が主張し、そのままになっていた。しかしながらパンデミックのさなか、妹夫婦は田舎暮らしがしたくなったと、大分の、露天風呂付きの一軒家に引っ越しを決めた。それで母とそのきょうだいたちは、処分することを決め、祖母の家に通ってはそれぞれ引き取りたいものを分けているのだという。今度あなたが帰ってくるときにはきちんと片づいてるから安心しなさいな、と母は笑う。
風呂に入り、荷物置き場と化したような元自室のベッドに寄りかかり、なずなは覚とLINEで明日の打ち合わせをする。ふと寄りかかってしまった雑誌類の束が倒れ、縛っていた紐がほどけて床に古い雑誌やアルバムが散らばる。LINEのやりとりを終えて、なんでこんなものを引き取ったのかと、なずなはため息をつきながらそれらを縛りなおすために積み上げていく。
見覚えのある雑誌に目が留まる。表紙の色あせた古い雑誌類は、祖母の家の本棚で見たことがある。羽子板を持って向かい合う晴れ着姿の女性、飛行機の前に佇むツーピース姿の女性、水着姿で砂浜に寝そべる女性……、子どものころにこれらの表紙を見たときは、昔っぽいとしか思わなかったが、大人になった今見ると、なんと新鮮でかっこいいデザインだろうと驚いてしまう。なずなは何気なく一冊を手に取り、開く。
正しいマッサーヂの方法。ヒロインのメーキャップ。あれ肌の化粧。赫ら顔を直す手當は。ぱらぱらと薄いページをめくり、ほかの一冊を手に取る。秋の美容・日やけ直しと匂い。流行と私たち。懸賞・私の髪型・発表。旅先での美容について……。目次の文字を読むうちに、なずなはいつしか若かりし日の祖母の心持ちになる。戦中戦後と贅沢を知らずに思春期を過ごし、結婚し、子を産み、家事と育児に追われ、四十歳になる前に夫を亡くし、子どもたちを育てるためにがむしゃらに働いて、帰ってきては家事と育児にあいかわらず追われ、そんな日々のなか、自分のための雑誌を手に入れ、読む時間を作るのは唯一の贅沢だったかもしれない。子どもたちが寝入ったしずけさのなか、ていねいにお茶を淹れ、文字を追い、うつくしい女性たちの写真を眺め、はやりの化粧法を見ながら素顔に指を這わせてみる。肌の手入れをする時間も満足にとれないけれど、写真と文字が教えるマッサージ方法は頭にたたきこむ。日本茶の香ばしいにおいとページをめくるかすかな音が聞こえてきそうだった。
まだ祖母でもなかった祖母は、きっとこの雑誌をめくっているときは母ですらない、ただの自分自身だったろう。夫を亡くし、再婚することもなくひとりで子どもたちを育てた祖母にとって、化粧はだれかのためにするものではなかった。だれかに見せるためのものでもないし、好かれるためのものでもない。自分自身でいるための、背筋を伸ばして立つための、明日に向かって歩くための、支えみたいなものだった。そんな母を見て育ったから、なずなの母は化粧を仕事に選んだのではないか。若かり
し日の母もこれらの雑誌を読んでいたのかもしれない。そうだ、だから捨てられなかったのだ。
三十一歳の私にそう教えたい、なずなは思う。化粧が濃いと言われたとき、あんたのための化粧ではないと言い返せばいいのだと言ってやりたい。恥じる必要もない、水で洗い流す必要もないと言ってやりたい。自分というものがまだわかっていなくて、だから他人の言葉にあんなに動揺した、自信のない私に、そう言ってやりたい。
それはもうかなわないから、せめて明日、きっちり化粧をしてもらおう。どんなふうにしようかしらと母はきっと言うだろう。やっぱりやさしい感じ? はなやかで強い印象がいいかしら。スタイリッシュなのもすてきよね。史上最高に私らしくしてくださいと、だから明日私は言おう。
なずなはひとりうなずき、雑誌をきれいに重ねていく。お肌に悪いから今日は早く寝なさいよ、と、階下から母の声がし、はーいとなずなは大きく答える。
1967年神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。1990年「幸福な遊戯」で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。96年『まどろむ夜のUFO』で野間文芸新人賞、2005年『対岸の彼女』で直木賞を受賞。その後も「ロック母」(川端康成文学賞)『八日目の蝉』(中央公論文芸賞)『ツリーハウス』(伊藤整文学賞)『紙の月』(柴田錬三郎賞)『かなたの子』(泉鏡花文学賞)と受賞作多数。小説のほかに旅のエッセイや書評集も手がけ、文芸賞の選考委員も務める。最新刊は食をテーマにした短編集『ゆうべの食卓』。
*HANATSUBAKI STORY「史上最高に私」は『花椿』2023年号資生堂チェインストア100周年特別版に掲載しています。
スペシャルトークイベント 角田光代×穂村弘「小説と短歌 ことばと想像のあいだにあるもの」のダイジェスト版動画(約22分)
















