
画像処理が巧みになってからというもの、幽霊たちにはさぞかし住みにくい世の中になっただろう。いるようにも、いないようにも、加工できてしまう。ちょっとしたことなら手軽に繕えてしまう。しかもわりときれいに仕上がるから、時には心地よいとすら思って、特に疑問を持たずに納得してしまう。ということは、しかし、目に見える世界の格好がよければ、それで事が済んでしまう度合いが増えたということだ。だけど体裁のいいビジュアルは、ノイズを見えなくしている。聞こえのいいメッセージが腹の底を隠すように、こざっぱりと漂白された現実こそ、かえっておそろしいものはない。見えないものは現実の懐を深くする。

東京都写真美術館でタイの映画・美術作家、アピチャッポン・ウィーラセタクンの個展『亡霊たち』が開催されている。彼は映画『ブンミおじさんの森』で2010年のカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したほか、2012年には現代美術の重要な国際展のひとつとされる『ドクメンタ』に出展するなど、すでに国際的評価の高い作家だ。


その作品のテーマは、おおよそ次のように言っていいだろう。記憶、残像、余韻、夢、眠り、過去と歴史、地方に伝わる伝説や神話、幻想、幻影、精霊、幽霊、妖怪、死者……つまりはどれも、目に見えないものだ。目に見えないけれど、かつて目の前にあったもの。確かに存在していたけれど、消えてしまったもの。そうしたものが層になって堆積しているのが、彼の現実なのだろう。そして、彼にとっての作品とは、それらが消えてしまう前に描かれた、スケッチのようなものなのだろう。本展の図録で彼はこう語っている。
ぼくは朝、目を覚ましていそいそと夢を書きとめる。夜のあいだ自分はいったい誰だったのか、突き止めてみたいのだ。
たとえば《灰》という作品では、彼の日常に登場する親密な人々や風景がモンタージュされていき、淡い色彩と、鳥のさえずりなどの背景音によって、やさしい追憶へと結晶していく。それは、彼の見た光景であることは間違いないけれど、映像のやわらかいヴェールにひとつひとつ包まれることで、「彼の」という人称が、ぼやけて、ほどかれていく。《サクダ(ルソー)》に至っては、メランコリックなギターの音色を背に、男の独白は空気のなかに霞んでいき、「僕の体は僕のものではない」といった感覚にまでおよんでいく。記憶や、死者や、精霊と一緒に、自分もいつか消えてしまうことを、そして大きなものの一部になってしまうことを、彼は知っているのだ。

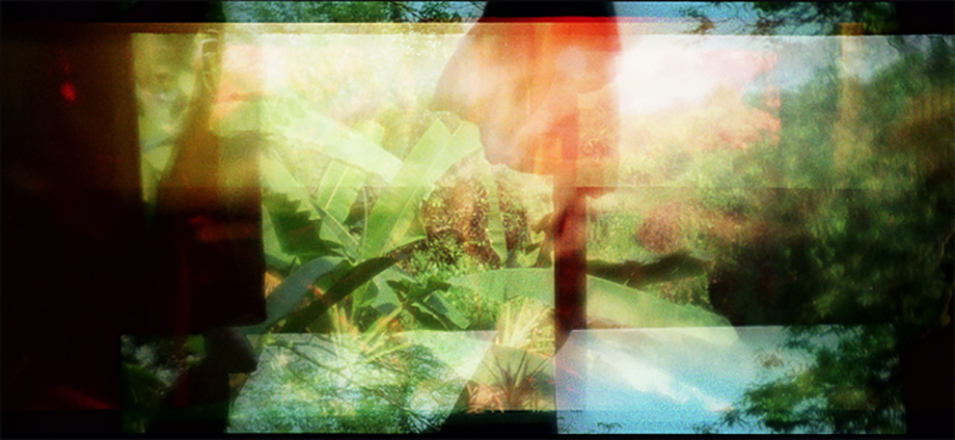
もうひとつの特徴が、ユーモアのようなファンタジーを仕掛けていることだ。たとえば《花火(アーカイヴス)》では、闇夜にたたずむ老齢の男女が、花火の閃光によって白骨の彫刻に姿を変えたりする。実は舞台となる寺院の開祖は赤狩りにあっていて、彫刻は政府の抑圧への抵抗を表しているそうだが、彼はインタビューでも、母国の軍政の腐敗や暴力への明らかな嫌悪を吐露していたりして、かなり社会的な意識を持っていることがわかる。ただ、そうした感情や思想は、直接ではなく、ある種のファンタジーを通して表されている。それこそ創作に許された武器であることを、彼は知っているのだ。

目に見えるものと、見えないものや消えてしまったものの、両方に、彼の世界はまたがっている。現実と非現実、現在と過去、生と死、といったことの、どちらがいい/悪いと判断すること自体を越えて、両方の要素を包み込む、調和した世界。それは本展の、光と闇にまたがる空間構成にも、子宮のような映画館の暗がりと、白光に包まれた美術館やギャラリーのホワイトキューブの、両方にまたがる彼の創作自体にも、よく表れている。どちらにもまたがって、どちらでもあるというのは、本当に幽霊のようだし、そんな彼の、現代における意味は、冒頭に記したとおりである。かくして幽霊はよみがえったのだ。
COVER PHOTO:《窓》1999年 シングルチャンネル・ヴィデオ SDデジタル、カラー、サイレント 11分56秒 東京都写真美術館蔵
関連リンク

岡澤 浩太郎
編集者
1977年生まれ、編集者。『スタジオ・ボイス』編集部などを経て2009年よりフリー。2018年、一人出版社「八燿堂」開始。19年、東京から長野に移住。興味は、藝術の起源、森との生活。文化的・環境的・地域経済的に持続可能な出版活動を目指している。
https://www.mahora-book.com/
















